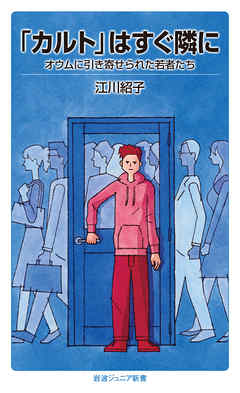あらすじ
家族や友人などの繋がりをすべて断ち切って、オウムに入信し、凶悪な事件に手を染めていった若者達。一連の事件がどうして起きたのか、彼らは特別な人達だったのか。オウムを長年取材してきた著者が、若い世代に向けて事実を伝えるとともに、カルト集団に人生を奪われない生き方を示す。巻末に年表を付し、当時の社会も見える化した。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
オウムに入信し、凶悪事件を起こしてしまう人達はなぜそうなってしまったのか。そもそもオウムがどうしてこんなに力を持つことになったのか。時代の背景から、どんな人でもそうなってしまう可能性があることなど、とても、分かりやすく詳しく書かれていた。宗教に全く関心がない私だが、もしかしたらなにかをきっかけにカルトに関わってしまう事もあるのかと怖くなった。裁判でみんなが口を揃えて言っていた「疑問や違和感を持った時に、自分を信じればよかった。それを見逃し続けることで、自分では何も考えないで言われたことを行うようになっていた。」マインドコントロールは恐ろしいことだが、実は今でも会社や学校や部活や仲間うち、そんなコミュニティでも同じようなことがどこかで起こっていると思うと、カルトと紙一重なのだ。
Posted by ブクログ
「カルト」はすぐ隣に
オウムに引き寄せられた若者たち
江川紹子氏による作品。
2019年6月20日第1刷発行。
江川紹子・・1958年8月4日東京都生まれ。
千葉県立船橋高等学校を経て、早稲田大学政治経済学部卒。
神奈川新聞社の社会部記者を経て、フリージャーナリストになる。
新宗教、災害、冤罪のほか、若者に悩みや生き方の問題に取り組む。
1995年一連のオウム真理教報道で菊池寛賞を受賞。
本書は岩波ジュニア新書ということで小学校高学年、中学生、高校生向けに分かりやすく書かれている。
もちろん当時を振り返るのに本書は有効なので、社会人にもおすすめだ。
1995年はターニングポイントと言える。
オウム真理教事件の前後で日本社会は明らかに変わった。
新宗教も含めた宗教団体の力は衰え続ける一方になった。
葬儀も簡素なものに変わりつつある。
直葬というものまで世の中で浸透してきた。
そのように大きく変化したきっかけは突き詰めるとオウム事件ではないだろうか。
この事件の事を深く知る事は重要だ。
(宗教団体の力が衰えたとは言っても、カルト的なモノが無くなったわけではない。日本会議のような政治団体のカルト性が近年際だつ)
オウム真理教で死刑になった最高幹部達も詳細をよくよく知れば哀れとしか言いようがない。
彼らもまた犠牲者なのだと思う。
どれだけ多くの人の人生を狂わせたのか。
著者の江川紹子氏も当時オウム真理教に暗殺されかけた(宮崎県)
小林よしのり氏もオウムを批判した為に暗殺団を送り込まれた。
別にカルトや宗教だけに限らないだろうけれども、
ファンと言える著者やオピニオンリーダー、発信する内容をチェックするインフルエンサーなど誰もがいることと思う。
その際には複数の、少なくともセカンドオピニオンを持つべきであろう。
特定のコンサルに盲信するような態度は誤りであると考えるべきだ。
人間は弱い存在なので放っておくと自分にとって都合の良い「見たい現実」ばかり見てしまうものだ。
定期的に自分と異なる立場の論者の発信する内容を全て肯定しなくて良いけれども、読む、見る習慣はつけた方が良い。
印象に残った点を紹介していきたい。
死刑囚が受けるべき刑罰は、死刑の執行のみなので、
逃げ出したりしないよう身柄拘束はされていても、禁固刑や懲役刑を受けた受刑囚とは違って刑務所には行きません。
拘置所は主に、裁判が確定する前の人たちが収容される場所ですが、
死刑囚は刑が確定した後も拘置所に留まり、そこで執行されます。
死刑執行ができる拘置所は、全国に七ヵ所あります。
麻原の生い立ち
制服も、他の生徒のお下がりを着ていました。
週末も、自宅に帰ることなく寮に残り、両親が学校を訪ねてくることはありませんでした。
そうした家庭事情の反動か、彼は子供の頃から金に対する執着が強かったようです。
「金持ちにならにゃあ」が口癖。
就学奨励費などは使わずにせっせと貯め、同級生に金品をせびることがしばしばありました。
そうして卒業時には300万円もの貯金をしていたといいます。
ワンマンな親分肌で、人の上に立ちたい欲求も強かったようです。
小学部5年の時に、児童会の会長に立候補しました。
寮でおやつに出るお菓子を、同級生や下級生に献上させて貯めておき、自分に投票するように言って配る、買収工作まがいのことまでやりましたが、落選しました。
彼は激しく落胆し、先生が妨害したせいだ、と言って責めたのです。
中学部の時にも生徒会長に立候補しました。
この時は、泣いてみんなに訴えたのですが、やはり駄目でした。
この時も、智津夫は落選にひどくがっかりしていたそうです。
怖いので面と向かって逆らわないけれど、投票の秘密が守られる選挙では、彼には入れたくないというのが、同級生や下級生たちの本音でした。
けれども一般信者は、自分が何を作っているのか知らされていませんでした。
何か危ないものだと感じたり、部品の形状から「銃かもしれない」と察したりした人はいましたが、なぜそんな物を作るのか、深く考えてはいませんでした。
上からの指示は、すべて修行と心得て、疑問を抱いたりあれこれ詮索したりせずに、黙って従うことが教団の中では当たり前になっていたからです。
教団側も、秘密保持のために、違法行為については一般信者に詳細を教えませんでした。
いったい、これからの日本はどうなるのだろう。
そんな不安が人々に芽生えてきたこの時期、爆発的にヒットした本が2つありました。
1973年3月に出版された小松左京のSF小説「日本沈没」(光文社)と同年11月に出版された五島勉の「ノストラダムスの大予言」(祥伝社)です。
「ノストラダムスの大予言」は1974年のベストセラー第2位となりました。
ちなみに、1位はアメリカの小説「かもめのジョナサン」(リチャード・バック、新潮社)
でした。他のかもめのように、単に餌をとるために飛ぶのではなく、より速くより高く飛ぶことを極めようとするかもめの物語です。
ただ漫然と生きるのではなく、よりよく生きたいと願い、生きる意味や自分らしい生き方を探している若者たちは、この本に共感しました。
後にオウム真理教に入信し、教団ナンバー2となる村井秀夫もその一人です。
彼は、オウムに入ることを親に反対された時に、この本を渡し、「読んでください。僕の気持ちはこの本の中にあるから」と言ったそうです。
オカルト情報は口コミでも広まりました。全国各地の学校では「こっくりさん」占いが一種の降霊術としてブームとなり、失神したり心を病む子供も出ました。
そんな中、書籍「ノストラダムスの大予言」は、その後も売れ続け、累計で250万部にもなりました。
続編も次々に出され、いずれも数十万部から
100万部の売り上げがありました。このシリーズは、20世紀末の日本人、とりわけ子供や若者たちの意識に少なからぬ影響を与えました。
人は誰かのために役に立ちたい、という気持ちが大なり小なりあります。
信者たちは、自らが「解脱悟り」を得るだけでなく、多くの人々を救う為の教祖の「救済計画」を手伝うことになると信じて、修行や活動に打ち込みました。
「救済」は自分の生きがいを求め、生き方に迷う若者たちを教団に吸い寄せる力にもなったのです。
最も重要なことは、自分のアタマで考えることだと思います。
もし皆さんがそれと知らずにカルト関連の人にかかわったとしても、彼らの発する言葉に注意深く耳を傾けていれば、必ず違和感を覚える点があるはずです。
その感覚を大切にして欲しいのです。
そして、その違和感がなんなのか、その正体をご自身で考えてみて欲しいのです。
宗教団体なのだから、学歴を偏重しがちな世俗とは違うはず、と思いきや、オウムの中も、かなりの学歴社会でした。
麻原に重用され、教団幹部となった
人たちの中には、有名大学出身者が何人もいます。
信者たちが出身大学ごとに「◯◯大、歌います!」と宣言して、オウムの歌を歌ったりもしました。
特に東大出身者は一目置かれ「オウム真理教東大生グループ」の名前で、本も出しています。
これは、東大進学を夢見ながら果たせなかった麻原のコンプレックスの裏返しでもあるのかもしれません。
「最終解脱者」であり、戒律を超えた存在と自らを位置づけていた麻原は、高い世界に導く儀式と称してしばしば若い女性の性をむさぼっていました。
麻原は妻との間に二男四女をもうけましたが、気に入った女性信者を側室にし、少なくとも3人の女性との間で合計6人の子供が生まれています。
女性信者は、人の命を奪うような凶悪犯罪にかかわることは稀でしたが、その代わりに性や若さや容姿を教祖や教団に奉仕させられていたのでした。
広瀬(健一)は、逮捕後に拘置所の中で生理学や心理学などいろいろな分野の本をたくさん読み、当時の「(神秘)体験」は「人が葛藤状態にある時に、
脳内神経伝達物質が活性過剰な状態で起こる幻覚的現象」と理解するようになりました。
実は、ヨガや伝統仏教の修行者でも、この種の超常体験をしている人はたくさんいます。
伝統仏教では、そうした「体験」は修行の妨げになる幻想や幻覚として、惑わされないように戒められます。
ところがオウムでは「神秘体験」として肯定的にとらえるばかりでなく、教義の正しさや教祖のエネルギーの力を証明するものだと教えていました。
「体験」をきっかけにオウムにのめり込む人は、自ら体感しているので、親や教師など周りの大人たちがいくら意見をしても、教団の言うことが真実であるように思ってしまいます。
教団は、信者を獲得し、心を呪縛するのに、「体験」の効果を最大限に利用しました。
(出家信者は)食事は一日一回。教祖一家は焼き肉や寿司、メロンなどを自由に食べていましたし、一部幹部はファミリーレストランにも出入りしていましたが、広瀬を含めて多くの信者は教団から支給される
「オウム食」と呼ばれる味の単調な食物だけを食べていました。
こんな風に疑問や違和感を自分自身で抑えつけ、教義の世界だけでモノを考えてしまうのが、オウムのようなカルトの心の支配の特徴です。
スタンレー・ミルグラムというアメリカの心理学者が書いた
「服従の心理」(河出文庫)
↓
ナチスドイツのユダヤ人虐殺(ホロコースト)にかかわった人たちは、家庭ではよい夫だったり息子だったりする人たちでした。
老人、子供まで殺害したベトナム戦争でのソンミ村虐殺事件にかかわった米兵もそうです。
この戦争では、韓国軍による村民虐殺も報告されています。
日頃はごく普通の市民なのに、このように一定の条件下では、指導者の指示に従って、通常は考えられないような残酷なことをやってしまうことがあります。
日本軍が戦時中、中国・南京を攻略した際に、
少なからぬ非戦闘員の殺害、略奪などを起こした南京事件も同様の事が言えるかもしれません。
ミルグラムの実験で、権威の存在、組織のシステムに
よって、こうした残虐行為にかかわってしまう人間の心理が浮き彫りになりました。
林郁夫は、別の信者の裁判に証人として呼ばれた際、この本を読んだ感想を次のように述べています。
「私もナチのことは知っている。小さい時に、(ナチについて書いている)本を読んでいて吐き気がして、どうして人間ってこんな残酷なことまでできるんだ、と思った。ほかにも、(アメリカの水爆実験で被爆した)
第五福竜丸のことや原爆のこと、人種差別のことなどを読みました。
そういう被害を与えた人たちは特殊な人たちであり、自分は(彼らと違って)
良心に従って行動できると思っていた。
でもそうじゃない。
単に、過去の残虐な行為を(知識として)知っているだけでは抑止力にならない」
人間の心は、特異な環境に置かれれば、残酷な行為もしてしまう弱さを持っているのでしょう。
誠実で真面目な人柄や、頭のよさや知識の量、
社会経験の豊富さで、その弱さを補えるとは限りません。
自分にもそういう心の弱さがあると自覚して、このような特異な環境に陥らないように努めるしかないのかもしれません。
さらに、テレビの人気バラエティ番組が麻原をスタジオに呼び、好きなように語らせました。
「ビートたけしのTVタックル」(テレビ朝日系)でのビートたけしとの対談で麻原は「私に代わって、オウム真理教の教祖をやってもらってもいいんじゃ ないですかね」と相手を持ち上げ、たけしも「おもしろいよなあ、麻原さんて」
と応じました。
「とんねるずの生でダラダラいかせて!!」(日本テレビ系)では「麻原彰晃の青春人生相談」と銘打って、若者の悩みに答える企画も行われていました。
そうした番組で、麻原は「ちょっと変わっているけど、精神世界に詳しく、悩みにやさしく答えてくれるおもしろいおじさん」を演じてお茶の間に浸透していきました。
「朝まで生テレビ!」(テレビ朝日系)では、麻原以下オウムの幹部と、別の新興宗教団体の関係者を生出演させ、対決を演出。
相手方は教祖が出演しなかったこともあり、オウム側の独壇場となりました。
これを見て、オウムに関心を持ち、入信してしまった若者もいます。
こうしたメディアや知識人は、人々のオウムに対する警戒心を解き、広める役割を果たしてしまったと言えます。
メディアは、このような脅しに屈せず、きちんと適切な取材をして報じることが大切で、そういう点でもオウムの事件は大きな教訓を残しました。
オウムで事件を起こした人たちの証言や手記を見れば分かるように、カルトのメンバーは元々は社会のルールや人権を損なうような人たちではありません。
それが、カルトに心を支配されると、無意識のうちに、アタマの中の思考回路がそっくり、カルト式回路に変えられてしまいます。
それを「マインド・コントロール」と呼びます。
体を拘束し、薬物や拷問によって無理やり新たな価値観を注入する「洗脳」とは異なり、「マインド・コントロール」は意思に反した強制的なものとは言えないことが多く、当人はコントロールされているとは気づきません。
カルトから身を守るうえでは、特定の団体を「カルトか、カルトでないか」という二分法で考え、その結論を待って判断するというのは、得策ではありません。
それより一つの価値観に固執し、それまでの人間関係を壊したり、社会の規範から逸脱する行動をとったり、人の権利を損なうような傾向のある場合はマインドコントロールを疑い、カルト性が高いのではないかと、よくよく注意し、距離を置いた方がいいと思います。
カルトは、どの時代や社会にも現れます。
カルトは、宗教には限りません。過激派など政治的な集団やマルチ商法といった経済的な集団の中にも、カルト性の高い所があります。
人間は、生まれから死ぬまで、ずっと順中満帆というわけにはいきません。
人間関係に悩んだり、努力が報われなかったり、選択に迷ったりします。
病気をする、事故に遭う、父母や友人が亡くなる、恋人と別れる、友達と深刻な喧嘩をする、受験に失敗する、職を失う・・・
こうした予想外の出来事に見舞われることもあります。
そんな時、人はカルトに巻き込まれやすい、と言います。
救いの手がさしのべられ、素晴らしい解決法を示されたように思うと、ついつい信じたくなるからです。