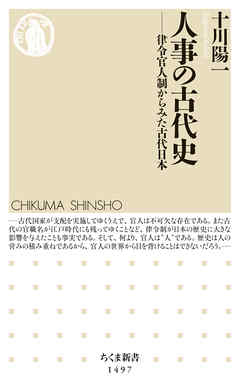あらすじ
古代日本において、国家を運営するうえで律令官人制という仕組みがつくられ、緻密な評価システムに基いて天皇を中心とする官人統治がなされた。そして政治が動き出し、官人の差配も変化し、報復左遷や飼い殺しのようにみえる人事もまかりとおるようになったのだ。では、その実態はどのようなものだったのか? 人が人を管理する上で起きる様々な問題を取り上げ、古代日本の新たな一面に光をあてる。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
古代日本における律令官人制について、その成立から奈良時代での確立過程、平安時代における変容までをたどり、律令官人の勤務・評価の実態を明らかにする内容。散位という地位に着目することで古代国家の特質にも迫る点があり興味深かった。
Posted by ブクログ
律令官人制についての一般向けの書籍(新書)は野村忠夫『古代官僚の世界』以来でしょうか。基本的な制度の説明や政治動向の記述が多いのですが、官人制の構造は複雑なため、これを欠いては一般向けとは言えない難しいものになるでしょう。大変読みやすく、面白かったです。
第1章「国家と人事のしくみ」は、ウジとカバネ、位階と官職、官位相当、考選、四等官、蔭位、出身など律令国家の支配機構について概説し、ところどころ補足的に奈良時代前中期の政治動向を説明しています。第2章「官職に就けない官人 散位の世界」は、散位という存在やその国家による管理、家政機関の帳内・資人について述べられています。帳内・資人について、一般を対象とした新書でこんなにも詳細に説明されているのは初めて見て感動しました(笑) 第3章「政争のあとさき」は、官人の刑罰や特権、奈良時代後半の政治動向について述べています。このなかで著者は解官のことを「散位に落とす」と呼び、処分の一種として機能したと論じています。第4章「平安京と官人制の転換」は、平安時代前中期の政治動向とそれによる官人制の変質について概説しています。律令官人制は衰退するのではなく形を変えつつも日本の社会(地方を含めて)定着・浸透していく過程を展望しています。
私は学生・院生の頃に律令官人制をテーマにして研究していたことがあり、初めて活字化(査読付き雑誌に論文が掲載)された論文は、帳内・資人の採用規定についてのものでした。今は研究から遠ざかってしまいましたが、あの頃の研究に対する熱意と憧れ、歴史研究の面白さをこの本は思い出させてくれました。著者の他の論考もぜひ読んでみたいと思います。
Posted by ブクログ
今までイマイチちゃんと理解しきれていなかった位階と官職について、それぞれの違いや相互の関わり方などが噛み砕いて解説してあって、とても分かりやすかった。日本史で習ったあれこれが、あちこちに繫がって非常に面白い。
その他散位や地方行政にも触れられていたのも良かった。
これの女子版も是非書いてほしい。
Posted by ブクログ
<目次>
プロローグ
第1章 国家と人事のしくみ
第2章 官職に就けない官人~散位の世界
第3章 政争のあとさき
第4章 平安京と官人制の転換
エピローグ
<内容>
「人事」と銘打っているが、律令制全般をうまくまとめてくれている。ちょうどこのあたりの授業をしていたので、タイムリーであった。実例も多く、わかりやすい記述だったと思う。
Posted by ブクログ
律令国家の中核を成す太政官等二官八省の組織機構や位階制度について、制度史にはこれまであまり興味が持てず断片的な知識しかなかったので、一度きちんと勉強したいとの考えから、本書を手に取った。
日本では、官人個人にまず位階を与え、それに対応する官職に任命させる、官位相当というシステムであったが、律令制の母国である隋唐とは異なるものであったこと、出土木簡によって明らかになってきた勤務評定の具体像、前代の氏族秩序と官人制との関係、功績や処分によるキャリアへの影響、ポスト不足のため位を持っていても官職にない「散位」の意味合い、位置付け、処遇、官人の地方における実態といった多岐のトピックが取り上げられている。
また、時代の推移に伴い、官位自体も無実化するものがあったり、業務遂行の方法の簡略化や大内裏の官司が縮小するといった実態も述べられている。
一部理解が難しいところはあるが、本書により、律令国家における官人の実相がだいぶ分かるようになった。
ただ、官人の待遇、給与に関して、身分給の食封や位禄、職務給の季禄に関する紹介はされているのだが、それによりどの程度の生活ができるものだったのか、その点についてイメージが持てるような項目が欲しかった。