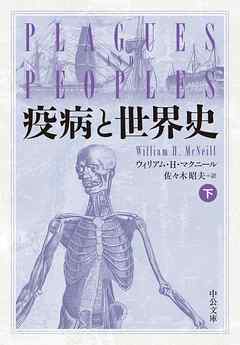あらすじ
かつてヨーロッパを死の恐怖にさらしたペストやコレラの大流行など、
歴史の裏に潜んでいた「疫病」に焦点をあて、独自の史観で現代までの歴史を見直す名著。
紀元1200年以降の疫病と世界史。
「中国における疫病」を付す。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
人類の歴史は、人間が他の人間に寄生する「マクロ規制」と、目に見えぬウイルスや微生物が人間に寄生する「ミクロ寄生」により規定されてきたといえる。科学技術が大いに進歩した現代においても、人類はこの規定の枠外から出ることがない。
本書は2つの寄生のうち特に「ミクロ寄生」に焦点を当てている。例えばスペイン人の南米征服に疫病が決定的な影響を持っていたことは広く知られているが、ではスペイン人はいつこの疫病を克服したのであろうか?このような考察を繰り広げていくと人類と感染症の壮大な歴史が浮かび上がり、歴史が転回する重大な局面を創出していたことが理解できる。
刊行されたのが1985年であるから、今から40年前の著作である。その頃に比べると疾病に対する人類の理解や対処も長足の進歩を遂げている。しかし、この2つの寄生の枠組みは、今後の人類の歴史を規定し続けるのだろうと思わせる説得性がある。改めて味読したい。
Posted by ブクログ
下巻は時代の下降とともに人口変化などのデータが増えてきて、より説得力が増す。と同時に、歴史上の出来事における疫病の与えた影響の大きさが感じられる。1500年代の新大陸に起きた出来事は圧巻の筆致。あっけなく侵略されてしまったのは、そういうことも要因だったのかと。
今の時代に生きるありがたみを強く覚えた。
Posted by ブクログ
下巻の半ばから、ようやく(期待していた)本題。
何故、かくも少数のスペイン人に、アステカとインカという二つの大帝国が征服されたのか。
確かに、スペイン人がやってきて疫病が大流行して膨大な死者が出、且つスペイン人は疫病の被害を受けない。それなら、人口が激減して軍のみならず国家も社会も崩壊するし、「神の恩寵を受けているとしか思えない」スペイン人への抵抗は物理的にも精神的にもできなくなるな。そりゃあ、キリスト教に改宗するわけだ。ようやく理解できた。
そして、「悪疫によって引き起こされた一般大衆の憎悪と恐怖の感情は、激越な形をとってほしいままに表現された。特に貧者の富者に対する長い間抑えられてきた怨恨が、しばしば表面化して爆発した。こうして各地に起こった暴動と私邸の略奪は、社会組織を重大な試練に直面させる事となった」
この一説は、新型コロナウイルスからの黒人暴動を予言した形となってしまった。残念である。合衆国がこの試練を乗り越えんことを祈りつつ。
それにしても、「マクロ寄生」という概念(一般に言うところの分業化と権力)は必要だったのか未だに酔うわからんが。
Posted by ブクログ
感染症が土着化すると、人口減少への圧力が減少、人口増へ
民間の習俗は、疫病を防止することも助長することもあった。モンゴルの、モルモットは先祖かもしれないから狩らないようにする慣習はペスト菌との接触を遠ざけた(が、その慣習がなかった漢民族がかかった)
タミル人の、水は毎日組み、室内で長期間そのままにしないという慣習は、居住区域からボウフラの生息域を遠ざけ、マラリアやデング熱対策となった
一方、イエメンの回教寺院の沐浴場では、病原体をもった生物が共有され、清めるどころか感染を拡大させた
マラリアに罹った動きが鈍くなるとさらに蚊に刺されやすくなり、動きを鈍くするマラリア原虫が生存に有利になる。蚊帳を使うことでそのような淘汰圧が消え、症状が軽くなる。
医者の仕事は心理上の問題だった。高い金を自信満々の専門家に払った、何かやった、ベストを尽くした、と思えることが救い。どうしたら良いのかという判断責任からも逃れられる。
人痘種痘は、アジアの民間療法として11世紀くらいから行われていた。
戦争では長らく戦闘死よりも病死が多かったが、日露戦争での日本の病死は戦闘死の4分の1だった。考えうる疫病の予防接種を全員にしていたから。以後列強はこれに倣った。
マラリアの原因となるマラリア原虫は、ヒトとカを行ったりする中で生存する。そのため、そのサイクルを絶てば絶滅する。
蚊を減らす:殺虫剤、天敵導入、不妊種導入
蚊と人との接触を減らす:虫除けスプレー、蚊帳、水たまりの除去(住環境・習慣の変化)、牛などの別の吸血先の確保【!!!】
ミクロ寄生(微生物の感染)/マクロ寄生(支配者による収奪)のバランス
Posted by ブクログ
疫病の発生過程の説明にまず驚かされた。初期の人間は、生態系の中に組み込まれており、自然な疫病による人口統制がなされていた。しかし、狩猟や農耕を始めることによって生態系を壊し、ミクロな病原菌の生態系をも壊すことによって細菌の繁殖力を増強することによって都市病等の病気にかかるようになっていった。このように自業自得的な過程があったということに非常に驚いた。
そして、このように周期的に訪れる疫病からの死の恐怖が、キリスト教を発展させていった。というのが面白かった。キリスト教では死は幸福であり、ほかの宗教では不幸であるというはっきりとした違いを再確認させられた。
また、このような疫病が数々の戦争の原因となったり、勝敗を決する要因となったりしていることに驚かされた。さらに、戦争の原因となっているにもかかわらず、その戦争の衛生部隊によって衛生観念が広まっていったという逆説的なことにも驚かされた。
最後に筆者が述べていた、「過去に何があったかだけでなく、未来には何があるのかを考えようとするときには常に、感染症の果たす役割を無視することは決してできない。創意と知識と組織がいかに進歩しようとも、規制する形の生物の侵入に対して人類がきわめて脆弱な存在であるという事実は覆い隠せるものではない。人類の出現以前から存在した感染症は人類と同じだけ生き続けるに違いない。」という文章は、この先も真実であり続けるだろうと思った。技術が発展するにつれて菌の繁殖力が強まっているという背景にはこのようなものがあるのだろうと考えさせられ、技術の発展も一概に良いことといえないのではないかと思った。
Posted by ブクログ
上巻より読み応えあり。
インカやアステカが滅亡してしまったのはヨーロッパ人の軍事力が高かったからと思っていたけど、ほとんどが未経験の疫病によるところと知って、そのスケールの大きさになんとも言えない気持ちになる。
現在も北センチネル島をはじめ未開の部族といわれる人々との交流が制限されていることに納得がいった。ちょっと会っただけで一族全滅の可能性があるなんて恐ろしいし、なんとなくいろんな病気になったり予防接種をしてきたお陰で健康でいられることにしみじみとありがたみを感じる。
あまり語られてこなかったけど、疫病は歴史を大きく変えるのだなと実感。コロナもその流れの一部なんだなぁ。
Posted by ブクログ
第四章は、中世ヨーロッパで黒死病と恐れられたペストがユーラシアの草原に棲む齧歯類から広がっていくことを示す。第五章は、大航海時代にアメリカの新大陸に渡ったヨーロッパ人が、免疫系の整っていなかった現地のインディオに与えた影響を論じている。ジャレド・ダイアモンドが「銃・病原菌・鉄」で著述しているように、旧世界と新世界の遭遇で疫病の果たす役割の大きさが非常に良く分かった。
第六章は近代的な医療技術の発展で人類が次第に疫病を制御できるようになった経緯にふれる。ただ、人類が「寄生する形の生物の侵入に対して人類が極めて脆弱な存在である」点は変わらない。
Posted by ブクログ
ダイヤモンドの銃病原菌鉄を大分前に読んで感動したが、疫病を中心に書いている本書のスペイン人が中南米に勝った一連の疫学的作用はこっちの方が俄然分かりやすいし、説得力がある。想像力が豊かだし、本当にそうだったんだろうなと言う凄まじい説得力がある。その上、結びに書いてあるこれからのインフルエンザを中心とした未知の疫病による未来の災厄は本当に恐ろしいし、逃れざる現実なんだなと新型コロナを前に恐怖と共に説得力を持つ。地球温暖化も含めて色々な事が今後も起きていくのだろうし、そう言う時の備えに対し、国や世界全体として備えが必要だと強く思った。
Posted by ブクログ
疫病・感染症との関わりという視点でみたマクニール先生の世界史講義。下巻は、モンゴル帝国の勃興から、近現代(1950年代)ころまでを扱っている。
上巻よりも時代が下ってきているせいか、具体的なエピソードが多くなり、マクニール先生の筆も迫力を増している。世界史の大きな転換点には、いつも疫病との闘いがあったということが、この本を読むとよくわかる。インカ帝国・アステカ帝国の征服、アメリカ大陸に渡ったピルグリム・ファーザーズたちが「新世界」で領土を広げていくときにも、その背景には疫病が介在していた。
特に、これは歴史の皮肉であり、同時に大変興味深いと感じるのは、そうした疫病に対する耐性(免疫の有無)が時として、在来の宗教も抱き込んで統治の方法(征服の方法)に、狡猾に利用されたということである。もしも、白人征服者たちが、アメリカ大陸に辿り着いた時、逆にアメリカ大陸在来の疫病にやられていたとしたら、現在の人種問題はどうなっていただろうかと考えてしまう。「歴史にifは無い」と言われ、もしも、、などと考えるのは野暮であることは承知ではあるが、根深い人種差別の歴史を考えるとき、そして社会を分断するほどの暴動を目の当たりにするとき、ふとそんなことを夢想したくなる。
ところで、この本は、山川の「世界史」を学んでいるだけではわからなかった歴史の裏側を見せてくれるのも大変に面白い。たとえば、西ヨーロッパの知識人たちの共通語であったラテン語が衰退し古語となってしまった原因は、この古代語を自由に操れるまでに習得した聖職者や教師たちがペストに罹って大勢死亡したことで加速したとか、「イギリス発汗熱」という疫病が蔓延する中で、ルターとツヴィングリが「これ以上ここで話していると俺たち感染してしまう!」と言って、突然逃げ出したために、ルター派とカルヴァン派が分裂したままになってしまったとか、コレラ菌の入ったビーカーの溶液を飲み干した医者の話とか、このほかにも目から鱗な話が散りばめられていて興味が尽きない。
だが、この本に惹かれるのはこのような面白さだけではない。マクニール教授の社会に対する温かい眼差しと、来たるべき社会に対する卓抜した眼差しに息を呑むためである。
マクニール教授はいう。「これは甚だ不愉快な可能性として考えられることは、敵国の民衆を行動不能に陥らせることを目指して生物学の研究が進められた挙げ句、高致死性の感染症の病原菌を敵地にばらまくようなことが行われ、それが世界の一部、いや恐らくは全土にわたる疫学的惨禍を引き起こすかもしれないということである。」と。昨今のコロナウィルスの発端がいかなるものかは明らかではないが、仮に俗に言われるように、武漢の生物学研究所から漏れた(あるいは撒かれた)ものであるとするならば、マクニールは未来における感染症の世界的蔓延を「予言」していたことになる。
続けて彼は「現在のところ、また近い未来にあっても、人類は地球という惑星がいまだかつて経験したことのない巨大な生態的大変動のさなかにある。だから、遠くない過去におけると同様、ごく近い未来に予想されるものは、決して安定などではなく、ミクロ寄生とマクロ寄生の間の現存するバランスに生じる、一連の激しい変化と突発的な動揺にほかならない。(中略)未来には何があるのかを考えようとするときには常に、感染症の果たす役割を無視することは決してできない。創意と知識と組織がいかに進歩しようとも、寄生する形の生物の侵入に対して人類がきわめて脆弱な存在であるという事実は、覆い隠せるものではない。」といい、未来への警鐘を鳴らしている。
上巻のレビューの冒頭に述べたとおり、本書は何気なく手にした本であったが、期せずして、私たちの歩んできた歴史と未来に対する深い視座を与えられ、これからも時を経て読み返したい一冊となった。
Posted by ブクログ
「ペスト」を読んだので、感染症の認知度とか、予防・免疫について、どこまで分かってた時代なのか知りたくて読みました。難しかったですが、面白かったです。戦争と感染症が、お互いに人口の割合を自然操作しているものってところが凄いなと思いました。人の意思とは、世界の意思から逸脱できないなんだなと。神様信じてないけど、世界の意思は感じました。
Posted by ブクログ
感染症の観点からみた世界史
関連リンクの「感染症の歴史」について先駆的に叙述したもの
同著者による『世界史』と同じく
ひとつの確固たる視点から人類の歴史を概観している優れた歴史書だが
未開の分野で先立つものの少なさからか
説明がばらけすぎていて読みにくいところがあり中途半端
疫病の場合は人間の歴史と異なり
対象がとても理性的で個々人のわずかなうごき差が混沌しないため
歴史数寄にとって興味を削ぐのかもしれない
Posted by ブクログ
下巻では3つの章に分かれていて、紀元前1200年から1500年まで、1500年から1700年まで、最後は1700年以降の医学の発達に伴う生態的な影響について述べられています。世界史の教科書を紐解くと殆んどと言っていいほど疫病についての記述がありません。唯一、14世紀にユーラシア大陸全体に流行した黒死病(ペスト)の影響があるだけのようです。しかし、この本を読むと、疫病がいかに人類史に影響を与えてきたかが分かります。
紀元前から人類を苦しめてきた疫病は、ペストに代表されるように、風土病として長らくその土地に留まってきたのですが、ユーラシア大陸でのモンゴル帝国の侵略により、遠くの土地まで拡がってしまいました。その土地の遊牧民の部族は、ペスト菌を保菌している齧歯類(ネズミなど)に対する、感染の危険に対処する方法を昔からの掟を備えていて、疫学的にみても有効な方法でした。…よそから入ってきた連中が地方的な「迷信」として守ろうとしなかったとき、初めてペストが人間的な問題になりました。と著者が書いているように、その土地の慣習は何らかの理由があることを忘れてはいけないのです。
カミュの小説、「ペスト」を思い出しましたが、…完全な健康を保っている人物が二十四時間も経たないうちに悲惨な死を遂げてしまう…事態は、神も仏もない当に不条理な世界です。新大陸でスペイン人などが、インディオ社会や、それまで栄えてきた帝国を滅亡に追いやったのも天然痘などの感染症がきっかけでした。こうした疫病が目に見えない微生物の仕業だとは分からない、当時の人々の精神状態がいかに不安に苛まれるか想像の枠を超えてしまいます。日本でも飢饉などに加え疫病が流行った時代には仏像の建立が成されたのも合点がいきます。
公衆衛生の概念が発達してきた1700年以降の疫病対策は人口増加をもたらし、都市の発展を促しました。また20世紀の初頭には、予防接種を制度とするなどして、軍隊で発生してきた疫病による死者を戦死者より少なくする組織的な取り組みで成果を上げていきます。
こうして今日、私たちは衛生概念の行き過ぎた社会で暮らしています。腸内細菌のバランス云々がクローズアップされる所以です。感染症の制圧ということでは人類が勝利したかに見えるのは多分錯覚に過ぎないのでしょう。マクニール氏が最後に述べているように…寄生する形の生物の浸入に対して人類がきわめて脆弱な存在であるという事実は、覆い隠せるものでない。…ということです。交通網の発達した現代では地球上で感染症の発生、特にパンデミックはいつ起こってもおかしくないということを忘れてはいけないのを肝に銘じました。
Posted by ブクログ
こんなすごい本が、この金額で読めるってすごい。
不条理な、救いのない大量の死が神さえも駆逐する。
高校生のころ、歴史を勉強していたときに、急に強くなったり滅びたりする権力の原因が全然分からなかったけれど、確かに疫病という視点はなかなかなかった。
とてもいい本であったが、日本語訳がときどき???なところがあって、読むのに根気がいる。
Posted by ブクログ
(上巻より続く)
本筋は、
人類は病原体によるミクロ寄生と、他の肉食動物、つまり同じ人類、のちには征服者、支配者によるマクロ寄生のはざまで、つかの間の無事を保っている存在だ、
ということですかね?
確かに、人類誕生以来の疫病との戦いを読んでいると、
食物連鎖のヒエラルキーの頂点にいるのは、
人間ではなく病原体、という気がしてくる。
余談ながら一番の衝撃は、
インドのカースト制が、
異なった免疫をもつ民族を支配下に入れた際に
相互に安全な距離を保つために、
接触をタブーとしたことに起因するという解説。
もはや都市伝説?
Posted by ブクログ
下巻は、モンゴル帝国~現代までが対象である。
文化という人類共通の遺産のおかげで、「宿主」たる人間が食べられるパイ自体も大きくなったし、寄生体に対しても強気の姿勢を示せるようになった。
そもそも宿主-寄生体モデルは、両者に対して働くポピュレーション抑制機能である。だとすれば、文明の名のもとに既存の寄生体を弱体化させた人間のポピュレーションが増加するのは必然である。
だが、生態系が使える資源は限られている。それに、宿主-寄生体モデル自体がなくなったわけではない。では「宿主」たる人間はどうするか。マクロ寄生体のしっぺ返し、すなわち戦争による口減らしをするかもしれない。あるいは、ミクロ寄生体によるしっぺ返し、すなわち未知の病原菌によるパンデミックが起こるかもしれない(例:インフルエンザ)。両者を併せた、生物テロを起こすかもしれない。
もちろん、「宿主」が自制できれば、それにこしたことはないだろう。相当困難だろうが...。
Posted by ブクログ
下巻はモンゴル進出以降の疫病の歴史。黒死病と言われたヨーロッパのペスト禍。この間を含めローマ帝国最盛期からルネッサンス期まで、ヨーロッパの人口は殆ど増加しなかった。そして、新大陸到達におけるインディオの低免疫によるユーラシア・アフリカの疫病禍。絶望的ともいえる人口の減少は数百年かけて奥地の小部族をも全滅させた。
終盤は天然痘。いわゆる種痘免疫法は、古来よりアジアの庶民風俗として定着していたらしい。その技術が英国をはじめとする欧州の王室を救った。また戦死は、従来ほとんど疫病の感染が原因であった。しかし日露戦争における日本兵の集団混合接種により人類史上初めて相手方の攻撃が主因になった。
人類史においては鉄器、大砲、疫病が人口減少に寄与した物であるらしい。(「鉄・銃・病原菌」という本がある)ガンや心臓病が克服されても、人類は疫病とだけは付き合っていかざるを得ないと著者は語る。他生物には人類こそが最大の疫病であろう。
Posted by ブクログ
上より面白かったけどやっぱり読むのにめちゃくちゃ時間がかかっちゃった
昔は田舎=結納金とかの決まり事が多くて早くに結婚できなかった(お金が充分稼げるようになるまで)
都会=田舎のような制約が無いので若いうちから結婚できる
だったから都会の人口がどんどん増えていく
っていうのが今と真逆でびっくり…
どこの国や地域とは明記されてなかったけど、日本でもそうだったのかな??
新旧世界と疫病はかなり興味があるので面白かったです またこういう系の本読みたいな
Posted by ブクログ
普通に読むと飽きてくるので、この本と 医学の歴史を併読してみた。2冊の索引の共通項目から 逆引き 読みをしてみたら、理解度が高まった
特に 結核、腺ペスト、天然痘、ペスト、マラリア、梅毒が 出てきた時が この本のポイントだと思った
時系列に整理しながら読むと面白いかも
Posted by ブクログ
世界史は疫病が動かす。「銃・病原菌・鉄」より何十年も前の卓見。見えない、理屈がわからないものへの恐怖がどれだけの影響を及ぼすか、放射線科学を知らない人の振る舞いを見れば現代でもよくわかる。現代医療の恩恵を受けた常識で判断せず、未知の恐怖で世界史を理解すること。