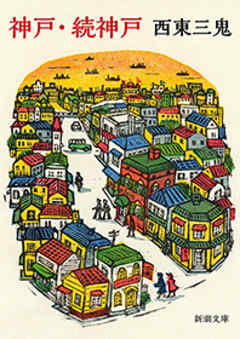あらすじ
第二次大戦下、神戸トーアロードの奇妙なホテル。“東京の何もかも”から脱走した私はここに滞在した。エジプト人、白系ロシヤ人など、外国人たちが居据わり、ドイツ潜水艦の水兵が女性目当てに訪れる。死と隣り合わせながらも祝祭的だった日々。港町神戸にしか存在しなかったコスモポリタニズムが、新興俳句の鬼才の魂と化学反応を起こして生まれた、魔術のような二篇。(解説・森見登美彦)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
『神戸・続神戸』は、新興俳句運動の中心人物のひとりであった俳人・西東三鬼が物した随筆である。太平洋戦争末期、三鬼が下宿していた神戸のホテルにおいて、住人たちが繰り広げていた狂騒的な日常を描いたものだ。
三鬼自身も戦時下で反戦的な俳句を詠んだとして検挙された経験もある人物だが、『神戸・続神戸』に出てくる人物たちは、それに輪をかけた曲者ぞろいである。どこからともなく貴重な食肉を仕入れてくるエジプト人や、体ひとつで渡世している娼婦たち。ロシアの老婆は日本娘をドイツ兵に売りさばき、台湾の青年はバナナの密輸入に精を出す。男たちは闇物資を、女たちは体を売り、特攻や結核や空襲でゴロゴロと死んでゆく。
このカオスのようなホテルはほどなく空襲で全焼し、前後して住人も死んだり消息不明になってしまう。このような社会の底辺の、いわば非国民たちの存在が公式に記録されるはずもないから、彼らが生きていた証は三鬼が書いたこの本の中にしかない。だが、三鬼が語る彼らの「生」の、なんとリアルなことだろう。なまなかな小説などには出せない凄みが、この随筆にはある。歴史には決して残ることのない、名もなき庶民たちの生の記録がここにある。
彼らの境遇の悲惨さは、ほとんど戦場ルポルタージュの様相を呈しているが、一方で奇妙な明るさにも満ちているから不思議だ。日本全土が軍事色に染まってゆく中、自らが異端者であるという事実は、彼らを萎縮させるどころか、矜持の源泉でさえあったようである。三鬼を含め、彼らはみな生まれついてのアウトサイダーであった。日章旗でも旭日旗でもなく、ただ独立不覊だけが、彼らの掲げる旗であった。
Posted by ブクログ
戦中・戦後の神戸に棲む、ふてぶてしいまでに逞しく生き抜いていく人たち。そんな人たちや当時の神戸の様子を、俳人らしい目線で描かれた作品です。著者当人の言によると「フィクションではない」とのこと。
登場人物達は、今の真面目な日本人にはちょっと想像も付かない人たちだと思います。今の時代だと絶対に受け入れられない人たちだけど、私は嫌いじゃない。
私は神戸で青春時代を過ごしたので、開戦して1年が経とうというのに、大音量のジャズが聞こえてくるバーがあったくだりを読んで、神戸のお役所嫌いや、自由を何よりも尊び、他者に干渉しない気質はこの頃すでにあったのだなと、懐かしく思い出しました。
Posted by ブクログ
第二次世界大戦中の神戸、アパートを兼ねたホテルに主人公は住む。そのまわりには日本人だけでなくエジプト、ロシア、台湾、朝鮮、ドイツなど様々な出自の怪しい人々が蠢く。
戦時中だけに物資や食べ物は不足し、住むところに困ったり、体を売ったり、病気で死んだり、という悲惨な状況である。にも関わらず、生々しさがなく別世界の寓話のような仕上がりになっている。
解説で森見登美彦氏が、三鬼とは天狗の異名だという逸話を取り上げ、著者の書きぶりを「フワリと宙に浮かんで人間たちの営みを俯瞰しているようでありながら、俗世で生きる彼らへの愛情ゆえに見捨てて飛び去ってしまうこともできない」と書いている。「千一夜物語」とも書かれていて、自分がぼんやり感じたことを見事に言語化してくれたこの解説にも★5つをつけたいと思った。
Posted by ブクログ
この頃、生きて明日を迎える事がどれだけ大変だったかがよく分かった。個性豊かで人間味たっぷりの隣人たちがバタバタと死んでいくのはショックだが、それでも人々の毎日は続いていく。あまり感傷的にならずに記しているところが良かった。
この時代を生きている人にとって死とはどういう感覚だったのだろう。空襲で亡くなった描写は現場の様子が目に浮かぶようだった。生きたい人たちの元にも、暴力的な死が一瞬でやってくるのが怖い。
女たちがどんな風に神戸の街を生きていたか、考えるのも辛い。困窮の末に辿り着いた人もいれば、モラルの崩壊した人もいて、実情は分からない。でも戦争がなければこんな事にはなっていないだろう。
どれも興味深い話ばかりだったが、白井氏との謎のドライブの話は特に面白かった。
『続神戸』は戦争末期や戦後の重い話も多く、この混乱した時代をなんとか生きなければならなかった人たちを思うと悲痛な気持ちになる。
弾圧のために創作を諦めざるを得なかった俳人たちが再び作品作りに打ち込めるようになったのはよかった。食べるのに困るその時も俳句のために集まる、その情熱にグッときた。すべてを諦めたであろう数年間がどれだけ酷なものだったかが分かる。
貴重な話ばかりだった。
Posted by ブクログ
何の情報で知ったのだったか、私の好きな作家さんが何人も絶賛してたので、読んでみることにしました。
西東三鬼は俳人で、新興俳句系の句誌を創刊したりしてた。
でも、俳人になる前は歯科医師、その後貿易会社役員など経歴が面白い。
戦時中、京大俳句事件で執筆活動停止処分され、妻子を東京に置いて単身神戸に移住。
これはその神戸の頃の回顧録的な作品。
今まで、映画やドラマや小説で知っている戦争中の苦しさ、貧しさ、暗さ、悲壮感...
その重さで戦争モノは敬遠しがちな私ですが、著者の淡々としていて、ユーモアあふれる文章にぐいぐい引き込まれてしまいました。
しかも生活していたアパートとホテルの間のような止宿人たちの個性豊かな面々との交流が味わい深くて良かった。
本当にこれは戦時中の話なのかと思うほど、外国人もうろうろしてるし、のんびりした感じがあるんだよね。子どもとか出てこないし、大人の世界。
不思議な魅力にあふれてました。
で、解説が森見登美彦氏で満足度上がりました。
Posted by ブクログ
戦中戦後の神戸の猥雑な空気や人間模様が、淡々とした距離感と味わいで描かれ素晴らしい。私にとってこんな文章が書きたいと思うお手本のよう。場所柄時代柄の各国の人の交錯が梨木香歩の「村田エフェンデイ滞土録」を思わせる。一人一人の無名の人の持つ大きなドラマをさらりと書くセンスと腕前に感嘆。神戸の民衆史としても興味深い。
Posted by ブクログ
戦中、戦後を強かに生きた人々の喜怒哀楽が描かれているが、ちょっと不思議な読後感がある。コスモポリタンや自由を愛した人々というと何かが違う。国家の庇護を受けないが、その代わり国家の命令にも従わない。望むと望まざるとに関わらずそういう境涯へと至った人々が力強く生きていく様を、ほとんど心理描写を交えずに断片的に投げ出すように描いていく。この愛すべき人々との交わりに何かしらの感興や心の動きがあって俳人はこの散文を書いたのだか、生涯を損耗させるほど打ち込んだ俳句ではどうだったのか。俳句という器では任が重かったのか。虚子の花鳥風月では描けなかった経験だと思う。ただこれに催された感情の動きを何とか俳句という形式で表現したいという想いにも駆られて三鬼は新たな道の模索を始めたのではないか。単に戦後の解放ということだけではないと思う。また新興俳句の単なる復活ではない道を模索するのは本書で描かれた経験があったからではないか。桑原武夫の第二芸術論に対する反発もあったのだろうか。俳句を断念した静塔を説得する件は、静塔が軍隊において味わったその人生経験を基として新たな俳句の創造を共にしたいとの想いに沿ったものだったのだはないか。三鬼の戦後の句を読んでみたくなる書き物である。
Posted by ブクログ
自動車旅行の話が好き。
どのキャラも濃いが、時代と場所が濃いのである。
二階の部屋に舞い込んでくる人々をとりなしていく、三鬼の寛容さと淡泊さが面白い。
Posted by ブクログ
戦時中の日常風景が描かれていて、
どんなことでもなんとか商売に繋げようとする人はいるもんだとか
女を武器にして生き延びる逞しさであるとか
学習としての戦争とはまた違った一面から
当時の様子を知ることができた。
書きぶりから
案外楽しんでいたんだなと思ってしまいそうになるが
そう思いかけたところで出てくる
死の描写に現実を思い知らされる気分だった。
Posted by ブクログ
戦前戦後の日本人、特に女性はほんとにたくましい。生命力がすごい。パワーがページから溢れてくるようです。神戸の雰囲気も、いかにもな感じ。いろんなことがあったんだなあ、としみじみ感じました。今よりずっとダイバーシティが身近で、グローバリズムも相当。こんな社会で生きてた人は強かっただろうな。
Posted by ブクログ
こんなタイトルだけど、観光案内ではありませぬ。
「まったくよくいうよ」私が友だちならそんな風にツッコミたくなるような語り口。
サラリと、時に厳しさや悲しみさえ、ユーモラスな空気で運んでくる。
彩り豊かな人々と世界。
あの困難な時代が、なんとおおらかで「生き生き」と描かれていることか。
そして、そこにある現実を思うとき、つっと何かが胸に留まる。
人々の足音と息遣いが聞こえるようだった。
Posted by ブクログ
人にすすめられて読みました。で、びっくり!
これは面白い。何はともあれ、神戸の本好きは必読(?)かも。神戸の空襲を挟んで数年間のトアロード、実録です。イヤ、すごい!
Posted by ブクログ
お世話になっている古本屋さんからオススメして頂いた一冊。
著者の作品は初読みとなりましたが、著者が俳人だからなのだろうが味わったことのない文体に惹き込まれてしまいました。
タイトルにある神戸は私の地元からほど近く、何度か私の地元の地名が出てきたり、知っている地名や通りが一層親近感を与えてくれたとはいえ、時は太平洋戦争の前後のストーリー。
ストーリーというよりは日記に近い感じと言ったほうが表現としては近い気がします。
登場する人物も個性豊かであり、それぞれの魅力が詰まっていますが、やはり本作の醍醐味は文体だと思います。
日本語って奥が深いなぁ…
改めて実感しました。
説明
内容紹介
「おすすめ文庫王国2020」年間最優秀文庫編集者賞受賞!
(本作品刊行により)
森見登美彦氏、賛嘆!
「戦時下の神戸に、幻のように出現する『千一夜物語』の世界」
高野秀行氏、賛嘆!
「私の理想とする、内容が面白い、文章がうまい、ユーモアがある、の3点をパーフェクトに満たした名著」
穂村 弘氏、賛嘆!
「アウトサイダーの輝きという点において、この作品は阿佐田哲也の『麻雀放浪記』 と並ぶ傑作だと思う」(「週刊文春」2019年8月1日号「私の読書日記」より)
南條竹則氏、賛嘆!
「文句なしに面白い。金子光晴などとはまた異なる、軽やかなコスモポリタニズムを感じる」
東山彰良氏、賛嘆!
「港町に仮寓することが自由と同義だった時代の、これは神戸という街が見せる人生の幻影だ」
瀧羽麻子氏、賛嘆!
「今とはまるで違う景色と、今はもういない人々の、鮮烈な存在感にただ圧倒される」
谷津矢車氏、賛嘆!
「戦中のわずかなひと時、神戸に現れた奇跡のアジール。この怪しげな輝きは一体何だろう」
葉真中顕氏、賛嘆!
「なんと楽しく恐ろしい読書体験だろうか。ユーモアと自由という人の精神の最も尊い輝きの隙間から、ときおり戦争という人の最も愚かな行為がぬっと顔を出すのだ」
永嶋恵美氏、賛嘆!
「読み手を問答無用で現実から引き剥がして、異界の夜に放り込む、そんな物語。唯一の欠点は、文庫一冊で終わっていること。西東三鬼をあの世から呼び戻して続きを書いてもらいたい」
いまみちともたか氏、賛嘆!
「柔らかな反骨がしなっている」
語り継がれる名作、ここに復活──。
「神戸」の文章を読むとき、私は「まるで人の良い天狗が書いたようだ」と感じる。(略)フワリと宙に浮かんで人間たちの営みを俯瞰しているようでありながら、俗世で生きる彼等への愛情ゆえに見捨てて飛び去ってしまうこともできない。(森見登美彦「解説」より)
第二次大戦下、神戸トーアロードの奇妙なホテル。東京から脱走した私はここに滞在した。エジプト人、白系ロシヤ人、トルコタタール夫婦……外国人たちが居据わり、ドイツの潜水艦や貨物船の乗組員が、缶詰持参で女性目当てに訪れる。死と隣り合わせながらも祝祭的だった日々。港町神戸にしか存在しなかったコスモポリタニズムが、新興俳句の鬼才の魂と化学反応を起こして生まれた、魔術のような二篇。
昭和十七年の冬、私は単身、東京の何もかもから脱走した。そしてある日の夕方、神戸の坂道を下りていた。街の背後の山へ吹き上げて来る海風は寒かったが、私は私自身の東京の歴史から解放されたことで、胸ふくらむ思いであった。その晩のうちに是非、手頃なアパートを探さねばならない。東京の経験では、バーに行けば必ずアパート住いの女がいる筈である。私は外套の襟を立てて、ゆっくり坂を下りて行った。その前を、どこの横町から出て来たのか、バーに働いていそうな女が寒そうに急いでいた。私は猟犬のように彼女を尾行した。彼女は果して三宮駅の近くのバーへはいったので、私もそのままバーへはいって行った。そして一時間の後には、アパートを兼ねたホテルを、その女から教わったのである。/それは奇妙なホテルであった。(「第一話 奇妙なエジプト人の話」より)
内容(「BOOK」データベースより)
第二次大戦下、神戸トーアロードの奇妙なホテル。“東京の何もかも”から脱走した私はここに滞在した。エジプト人、白系ロシヤ人など、外国人たちが居据わり、ドイツ潜水艦の水兵が女性目当てに訪れる。死と隣り合わせながらも祝祭的だった日々。港町神戸にしか存在しなかったコスモポリタニズムが、新興俳句の鬼才の魂と化学反応を起こして生まれた、魔術のような二篇。
著者について
西東三鬼(さいとう・さんき)(1900-1962)
岡山県生れ。日本歯科医専卒業後、シンガポールにて歯科医院を開業。帰国後、33歳で俳句を始め、新興俳句運動に力を注ぐ。「水枕ガバリと寒い海がある」の句で知られる。1940(昭和15)年、いわゆる「京大俳句事件」で検挙される。'42年に神戸に転居。終戦後に現代俳句協会を創設。一時、雑誌「俳句」の編集長も務めた。句集に『旗』『夜の桃』『変身』など。自伝的作品『神戸・続神戸・俳愚伝』でも高い評価を得る。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
西東/三鬼
1900‐1962。岡山県生れ。日本歯科医専卒業後、シンガポールにて歯科医院を開業。帰国後、33歳で俳句を始め、新興俳句運動に力を注ぐ。1940(昭和15)年、いわゆる「京大俳句事件」で検挙される。’42年に神戸に転居。終戦後に現代俳句協会を創設。一時、雑誌「俳句」の編集長も務めた。句集の他、自伝的作品『神戸・続神戸・俳愚伝』でも高い評価を得る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
Posted by ブクログ
高野秀行さん絶賛の本書。
なるほど高野さんと同じ匂いのするユーモアが感じられて読んでいて楽しい。
そのユーモアはよりお洒落な感じで、考え方も変わっていて面白い。
くすっと笑える軽快な文体ながら、第二次大戦真っ只中のノンフィクションで、戦時中の日本人の日常と国際都市だった神戸の不思議さと、いろいろ考えさせられる作品。特に「続神戸」は戦争と戦後のどろりとしたものが急に迫ってきてハッとさせられる箇所が多かった。
この頃のしたたかな日本人といまの日本人、なんだか全く別の国の人間な気がしてしまうな。
Posted by ブクログ
戦時下の神戸を描いたエッセイのような私小説のような一冊です。
空襲や物資の不足があり悲惨な状況ではあるのでしょうが、登場人物はみなどこかしたたかで自分が大切にするものに従って生きており、哀れみを以て接するのも何か違うなと思います。当時の人々には当時の人々の人生があったのでしょう。ユーモアを持って飄々と暮らす西東三鬼や周囲の人々の人間らしさからか、遠い昔のことであるのが嘘のように思え、背表紙に「魔術のような二篇」と書かれているのもわかる気がしました。
Posted by ブクログ
小説かと思ったらエッセイ!これ全部事実なのか。
なんと情緒溢れる作品だろう。
舞台が神戸ということもあり、あのあたりでのエピソードかと思うと感慨深くなります。
確かに古い文体なんですが決して古臭さは感じないキレのある文章。
軽い口当たりで書いてるけど決して軟弱ではない文章。
これは隠れた名作ではないでしょうか。
Posted by ブクログ
太平洋戦時下の神戸を舞台にした奇書。
太平洋戦争さ中、神戸トーアロードにある朱色に塗られたホテル。そこには様々な国籍の人々と、娼婦でもあるバーのマダムたちが下宿人として住んでいた。東京を逃れこのホテルに移り住んだ俳人・西東三鬼が描く、ちょっと不思議な人間模様。
西東三鬼は新興俳句運動の中心人物の一人として、戦意高揚の俳句作成や使う季語すら国から推奨される時代に、厭戦や反戦の俳句を次々と掲載したことから、治安維持法に基づく言論弾圧事件(京大俳句事件)に連座、検挙された人。
そんな人物が描く戦中の神戸のホテルの住民は「エジプトのホラ男爵・マジット・エルバ氏」「通俗小説のヒロインの様な娼婦・波子」「比類なき掃除好きの台湾人・基隆」「悲運の美人看護婦・葉子」「お大師様を信仰する広東人・王」など多彩で、どこか”魔都”と呼ばれた頃の上海の様で、ひたすらに妖しく、どこか奇妙な明るさがあり、また自由でコスモポリタンな雰囲気があります。
解説は森見登美彦さんで『千一夜物語』を引き合いに出していますが、確かにそんな感じもあります。
この本の中で三鬼は「頑強に事実だけを羅列していた」と書いています。あの戦争のさなかにこのような異世界があった事も一つの驚きです。古めかしいと言って良い文体だと思いますが、佳い意味で味があります。
「続神戸」は名の如く「神戸」の続編。
戦後まもなく、アメリカ統治下の神戸と俳句の世界に戻ろうとする自身の姿が描かれます。
”妖しさ”が薄れた分、魅力は減ったかな。
Posted by ブクログ
戦時下の神戸の下宿屋のようなホテル。さまざまな国の人たちがいて、それぞれの想い強い気持ちがあって、戦争に縛られているなか一生懸命生きている。それを俯瞰に見ている著者の文章が面白かった。解説で人生は近いと悲劇、遠いと喜劇、とあって、面白いと思ったのはそういうことなんだなと思った。続編の戦後編はツライ理不尽な…と悲しくなった。
Posted by ブクログ
まず書いておかなければならないのは、俳人よりも歌人を重視したいと、要らぬ偏見を持っている。寺山のせいだ。
情けないことだが「水枕ガバリと寒い海がある」しか聞いたことがなく、その句を聞いても、作者に注目したことがなかった。
が、神戸の、しかもトアロードといえば足穂のだなっ! と鼻息を激しくし、いわばミーハー的に読んだのだ。反省。
しかし足穂の生年が1900-1977。
西東三鬼の生年が1900-1962。お、すごい、ニアミス有り得るかも……?
ただし足穂の神戸時代はおそらく二十歳まで。
かたや西東三鬼の神戸時代は四十代。
合わないではないか。
しかし、神戸のコスモポリタニズム・ダンディズム・モダニズム・エキゾチシズム・コズモポリタニズム・ボヘミアニズムは、きっと時代を超えるのだ。
通じるものを感じた。
33歳で俳句を始めたという、若干の遅さも、また。
ひとまず「物づくし」という言葉がある。
それを派生させて「人づくし」という言葉を作れば、西東三鬼。
(足穂は「物づくし」の遥か彼方にあって思想をもオブジェ化する「オブジェづくし」だろう)
本書は雑誌「俳句」昭和29-31年、「天狼」昭和34年への寄稿。
つまり終戦10年熟成して、ようやく戦中戦後について発表できたものなのではないか。
西東三鬼ほどのコスモポリタン・ダンディスト・モダニズスト・エキゾチシズト・コズモポリタン・ボヘミアンにおいてすら、戦禍が過酷だったのではないか、と思う。
太宰や安吾を連想するが、その列に並べてもよさそうだ。
ところで本書で光るのは、やはり語学。
相手の言葉がわかるからこそ、壁を作らない……といえば2020年現在の「分断ー批判ー流行り」に迎合しすぎだろうか。
いやいや、外国語で思考を複眼化することは、かつてでも今でも、外国でも日本でも、戦時下でも平和な世でも、「跳び出す力」になるのだ。
この力を持っていたからこそ、作者は、日本人ー外国人ー売春ー惚れた腫れたという重さ、に、ユーモアー哄笑ー含み笑いの軽さ、を追記できた。
いわば太宰にも安吾にもできなかった、性的人間としての別側面を、文学史の壁画に描いてくれた。唯一無二。
それは祝祭のイメージ。読書中、映画「アンダーグラウンド」の音楽を流していた。
神戸つながりで時代を前後して、谷崎潤一郎、久坂葉子、中島らものヘル・ハウス、村上春樹の思春期、を連想してもよさそうだ。
また渡辺温「ああ華族様だよと私は嘘を吐くのであった」をも。
→《チャブ屋(チャブや)は、1860年代から1930年代の日本において、日本在住の外国人や、外国船の船乗りを相手にした「あいまい宿」の俗称。「横浜独自の売春宿」といわれることもあるが、函館や神戸など他の港町にも存在していた。また、食事やダンス、社交など買春以外の目的で遊びに来る客もおり、必ずしも「売春宿」とは言い切れない。》
以上のごときごった煮を、
《この「神戸」の登場人物の大方は、戦争前後に死んでしまうのだが、これは私が特に死んだ人のことばかりを書こうとしたのではない。ひとりでにそうなってしまったのである。何故そうなったかは私には判らない。ただ一つ判っていることは、私がこれらの死者を心中で愛していることだ。》
とまとめてしまえる、抒情と老獪が同時に屹立するところに、西東三鬼の魅力を、読む。
Posted by ブクログ
神戸市内の本屋で平積みになっていました。
帯の「森見登美彦氏賞賛」につられて買いました。
知った地名
第二次世界大戦末から戦後まで
とても興味深く読みました
そうか、こんな人たちがこんなホテルでひっそりと命をつないでいたんだ
何と「濃い」人たち!
ひとり一人が小説の主人公のようです
もちろん著者もすごい!
私の母はこの頃、この近くに住んでいたんですよねえ
≪ ひっそりと 自由を我らに 叫びつつ ≫
Posted by ブクログ
あの時代、みんながみんな「お国のため」モードじゃなかったのだということがわかってよかった。
どれだけ上手く騙したり煽ったりしても、全員を暗示にかけることは、絶対にできない。
Posted by ブクログ
この人の文体は、下手くそな浅田次郎と洗練されていない森見登美彦を併せたような印象なのです。でもたまらなく惹かれる。
歯科医で俳人の著者。戦時下に東京から神戸にやってきて、移り住んだのは多国籍の長期滞在者がいる世にも怪しげなホテル。
インテリなのにプライドをまったく感じません。しかもお人好し。ホテルを出て購入した家に人がなだれ込んでもそのまんま。便所が詰まれば糞まみれになって掃除する。
いずれの話も飄々としていて、かつ無理に人を笑わせようとしていないから、余計に可笑しい。しかも切ない。
彼が当時を共に過ごした人たちはみんなどうしているのか。あらためて、戦争はしちゃいけないと思う。
Posted by ブクログ
小さい頃から通い慣れた街が、戦時中から戦後はこんな様子だったとは
食糧もなく、自由もなく、空襲に怯える日々の中でも、外国の人たちと心は自由に生きていた著者。
戦争の中の現実の生活。
おもしろく描かれているけどつらいな
Posted by ブクログ
劇団太陽族「神戸世界ホテル」の原作だということで読んだ。俳人西東三鬼が書いたノンフィクション自伝小説だ。彼自身も治安維持法で京都で収監されていたそうだが、そんな暗さや怯えはなく、脳天気でありながらもその密度は濃く、戦中戦後を生きている。とっても不思議な人だ。
Posted by ブクログ
第二次大戦下、神戸トーアロードの奇妙なホテル。“東京の何もかも”から脱走した私はここに滞在した。エジプト人、白系ロシヤ人など、外国人たちが居据わり、ドイツ潜水艦の水兵が女性目当てに訪れる。死と隣り合わせながらも祝祭的だった日々。港町神戸にしか存在しなかったコスモポリタニズムが、新興俳句の鬼才の魂と化学反応を起こして生まれた、魔術のような二編。
多少脚色はあるにせよ、すごい時代にすごい生き方をしている人たちが描かれていて、うわあという感じ。神戸という港町ならではの空気なのかもしれないけど、誰に従うこともなく、のびのびと自由に、まるで天狗のように駆け回るエネルギーあふれた登場人物たちに感嘆してばかりでした。筆者本人も大変な生活だったはずなのに、つらさや深刻さを敢えて削ってからりとした文章にしているところもすごい。今の時代には、逆にこういう醒めたような中に熱い芯の通った、凄みのある話を書ける人はいないような気がしている。
Posted by ブクログ
筆者の暮らすホテルにまつわる人々を冷静に眺め、ユーモアを交えて淡々と。
物語性が強いわけではないが、戦時下の神戸のふつうのーいや、ちょっと変わった暮らしぶりをサクっと描いている。
折々、筆者の情け深いところ、優しいところに触れられる文があり読んでいて気持ち良い。
敗戦前後の話なだけあって正直描かれる事象は暗かったり悲しかったりするのだが、なんというか全体を通して軽い。貧乏しようと人が死ねど軽い。今風に言うと、筆者が“ネアカ”が滲み出ているとおもう。
戦時の市井の様子がわかる文章は興味深く面白い。
Posted by ブクログ
現実のお話なのが、虚構であるのか?きっと大変なはずであろう戦中の生活を描いてあるのに悲壮感はあまり漂わない。むしろ色めき、艶のある世界に見える。
Posted by ブクログ
不思議な軽みに満ちた小説。俳句雑誌に連載されたそうだが、軽みといえば漱石の「猫」も俳句雑誌ホトトギスに連載されたものだった。短詩の極地たる俳句の雑誌に散文を書くとこんなふうになってしまうのかもしれない。 いわく軽み。いわく写生。
昭和十八年の戦時下神戸で、著者が「小谷氏」に引き合わされて一緒に釣りなどしているエピソードが個人的には興味深い。井上靖の「闘牛」のモデルといわれた辣腕のイベント仕掛け人である。数年前サトウサンペイさんから聞いたことがあるが、大丸宣伝部にいた彼を引き抜いて新聞に漫画を連載させたのが小谷氏だったそうだ。神戸という土地の不思議さを思う。