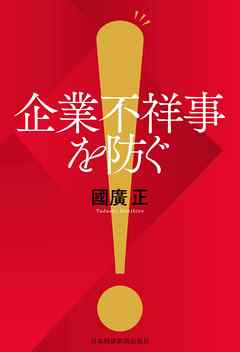あらすじ
コンプライアンスは、「過剰規制」から「ものがたり」へ
“規則を厳守”するからうまくいかない! 「コンプラ疲れ」を脱する3つのカギ
日本経済新聞社「2018年 企業が選ぶ弁護士ランキング」(危機管理分野) 1位!
企業不祥事が起こるたびに「コンプライアンス」が叫ばれる。しかし、実際には多くの企業で過剰規制による「コンプラ疲れ」が生じており、不祥事防止の役に立っていない。
コーポレートガバナンスの観点から社外取締役の義務化も進められている。しかし、ガバナンス先進企業と言われた東芝の不正会計事件から分かるように、「形だけ」のコーポレートガバナンスに不祥事防止の効果はない。
そこでこの本では、できるだけ多くの実例をあげて、「なぜ、企業不祥事はなくならないのか」「なぜ、そのコンプライアンスやコーポレートガバナンスは機能しないのか」を根本にまで遡って明らかにする。ここでは、「ストーリーの欠如」と「場の空気(同調圧力)」がキーワードになる。
その上で、「では、どうすればよいのか」ということを、危機管理の現場対応や社外役員としての活動といった筆者の実務経験に基づいて具体的に提言する。ここでは、「多様性」「インテグリティ(誠実性)」「空気読まない力」がキーワードになる。
この本のタイトルは、「企業不祥事を防ぐ」というシンプルなものだ。書かれているのはすべて実例(筆者の実体験も多く取り入れている)とそれに基づく考察だ。「机の上で考えた理論」は書いてない。
この本が、読者に「オモシロかった」と言われて、「やらされ感のコンプライアンス」から「元気の出るコンプライアンス」への橋渡しになることを願っている。
――「はじめに」より抜粋
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
不祥事が起こるたびにコンプライアンス強化が叫ばれ、対策も打たれるが再発防止に役立っていない。何故なのか?日弁連の第三者委員会ガイドラインを作った著者が考察する。ちなみにこの第三者委員会の評価委員会があることを本書で初めて知ってネットで興味深く読んだ。
久保利弁護士や著者らが舌鋒鋭くダメな第三者委員会を評価していて非常に示唆に富む。
本書に戻って、コンプライアンスの仕組みがワークせずに企業不祥事が再発するのは、再発防止のための余りに詳細なチェックリストによって現場が疲弊し結果としてコンプライアンス施策への「やらされ感」から形骸化するからだという。ならばどうすべきか?について、例えば企業トップが宣言する血の通ったコンプライアンスストーリーが必要だと説く。物語があるコンプライアンスは「面白い」が故に多くの社員に浸透すると言うのだ。
それから「日本企業に特有」の不祥事要因についても考察する。過剰品質やDX化への遅れ、同質性の空気圧について考察し、多様性と異文化の許容にその解の一つを見出している。更に、昨今のコンプライアンスリスクの真の恐ろしさはレピュテーションリスクであるとして、企業を取り巻くステークホルダーの多様化とその価値の置き所やSNSが一般化した環境でのコンダクトリスクについても考察する。多様化したステークホルダーの価値観や正義感に対応するためには、従来の細かなチェックリスト方式によるコンプライアンスは無力であり、プリンシプルベースでダイナミックに対応できるリスクベースアプローチが必要とする。
では、企業は(我々は)何に依拠してコンプライアンスや企業ガバナンスを推進するのか?は難しい。何故ならそれらを個別に定義することは、プリンシプルベースに反してしまうからである。著者は依拠すべきところを「インテグリティ=誠実さ」であるべきとする。もっともインテグリティを定義することはそれに言及したドラッガーも「難しい」としていて、逆にインテグリティが欠如する人の例を挙げてインテグリティを浮き彫りにしようとする。曰く①人の強みではなく、弱みにフォーカスする者、②皮肉屋、③「何が正しいか」よりも「誰が正しいか」に興味を持つ者、④真摯さよりも頭脳を重視する者、⑤有能な部下を恐れる者、⑥自らの仕事に高い基準を定めない者、を挙げて「真摯さに欠ける者は、如何に知識があり、才気があり、仕事ができようとも、組織を腐敗させる」としている。日本の人事評価に欠けているところを如実に指摘していると思う。多くの経営者や政治家達はインテグリティに反する目線で評価され、トップに上り詰めていないか、ひいてはその仕組みが日本の閉そく感を生み出していないか顧みる必要があろう。
ここから論点はコーポレートガバナンスに至り、全般統制のモデルであるCOSOERMにまで言及しながら話が進む。末尾に環境対策と環境系NGOとのコミュニケーションについて書かれていて、NGOを鬱陶しがらずに対話と改善のPDCAを回し続けることこそが企業のガバナンスに直結するとあり、企業統治の過去と課題、現在の立ち位置、変わらなければならない今とこれからを俯瞰することができて非常に勉強になった。
Posted by ブクログ
びっくりするくらいの、驚きの名著!
弁護士の著書ということで無味乾燥で四角四面の教科書的な内容かと思いきや、これが真逆。ここまで日本の組織…日本企業の現場の状況、実際の行動原理を踏まえた"血の通った"リスクマネジメント論、ガバナンス論もないと思われます。
広く一般向けの本ではないですが、企業でその領域の業務を担当している日本人の必読書ですね、これは。
Posted by ブクログ
弁護士として胸熱な1冊でした。
細かい法律知識ではなく弁護士としての感性(正義感・バランス感覚・スピリット)をきちんと仕事にしている。ひとつのロールモデルである。
ものがたり(ストーリー)のあるコンプライアンス
※楠木健『ストーリーとしての競争戦略-優れた戦略の条件』
「赤信号みんなで渡れば怖くない」
性善説/性悪説ではなく性弱説
安全の「制度的保障」
制度に抜け穴ができると,制度全体の信用性を失わせる。データの流用や偽装は安全を確保するための制度に対する信頼性を根本から突き崩す。
日本企業は属人的な摺り合わせ型の発想から脱却できず,客観的データによる「見える化」をベースにした品質保証に移行できなかった。
「盗む不正」と「ごまかしの不正」
ノー・トレランス
企業不祥事の本質はレピュテーション・リスク
「負のスパイラル」により企業価値が毀損した状態。
企業価値を創り出しているのは,株主・投資家・消費者・取引先・従業員・監督官庁・マスコミといったステークホルダーの企業に対するレピュテーションである。
レピュテーションは,「企業の行為やそれに言及する情報をもとに与えられる,あらゆるステークホルダーによる評価の集積」である。
「法令遵守」という発想でレピュテーション・リスク管理はできない。
コンダクトリスク
・明確な法令違反の事案は比較的少数だが「全体・集団」として見ると不当性が明らかになり,ステークホルダーの強い怒りを招く。
・「業界の常識」が「世間の非常識」となっている。
・顧客本位ではなく,会社本位である。
・行き過ぎた収益重視が背景にある。
ルールベースとプリンシプルベース
リスクベース・アプローチ
「厳密にやってまちがえるより,おおむね正しいほうがよい。」(マーヴィン・キング 元イングランド銀行総裁)
フォワードルッキングな想像力
3つの防衛線
①事業部門による自律的管理
②リスク管理部門による支援と牽制
③内部監査部門による検証
小さな不正には動かぬ証拠があるが,大きな不正には兆候しかない
インテグリティ
「経営管理者にとって決定的に重要なものは,教育やスキルではない。それは真摯さ(インテグリティ)である。」(ドラッカー『現代の経営 下』P.262)
「真摯さ(インテグリティ)に欠ける者は,いかに知識があり,才気があり,仕事ができようとも,組織を腐敗させる」(上Pp.218-219)
定義は難しいが,
①企業が急激に変化するビジネス環境に対応するための「羅針盤」となり,企業の持続的成長の基礎となるもので,
②「何のために企業はあるのか」「企業としてどうありたいのか」という「働く意味」と密接に関係し,
③「結果として」企業のコンプライアンス・リスク管理につながる。
寺師正俊「レピュテーションリスク(評判リスク)ー概念整理とマネジメントの方向性」SJRMリスクレビュー6
ガバナンスの基本はチェック&バランスによる規律
空気読まない力
社外役員の役割は,いざというときに社長に「ノー」を突きつけることにある。
Bad News First/Fast
危機管理の本質
①正確な状況把握
②明快な決断
③ブレることのない断固とした対応
今の時代,不祥事を隠し通すことは不可能だ。
「企業という組織の中で不祥事を「なかったこと」にするのは,「部屋の中にいるゾウを見るな」というに等しい。」
「報道を防されないこと」ではなく「報道を1回で終わらせ,連続報道を防ぐこと」
ステークホルダーは,「経営幹部が不都合な事実を認識していたにもかかわらず開示しなかった」という「不作為」を「隠蔽」と評価する。
ステークホルダーの信頼回復のために必要なこと
①不祥事の事実関係を明らかにし,
②不祥事をもたらした原因(root cause)を解明し,
③その原因を除去するための再発防止策を実行する
④①~③のプロセスをきちんと説明する
「ボヤで騒げ!」
ボヤでどんなに騒いでも大火事になることはない。
NGOが求めているのは,満点の答案ではない。対話とそれに基づく改善行動,つまり「対話をしながら考え,行動していく姿勢」と「PDAでの対応」というダイナミックなプロセスである。
「概ね正しい」ことを良しとする(百点主義ではない)七十点対応。
Posted by ブクログ
最後の『企業不祥事を防ぐにはお仕着せの規則や制度ではなく、一人一人の働く意識しかない』という最後の言葉が印象的で、過去に実際に起きた不祥事や実例もとても面白かった。
コンプライアンスというと当然守らなければいけないものだが、形骸化したり「ごまかしの不正」のように明確な意思なくリスクを犯してしまうような事例が度々報道される。
日本独特の文化や空気感に流されたり、過度な規則や制度で形骸化してしまい、自分でも気が付かないうちにレピュテーション・リスクを犯してしまうことのないように、コンプライアンスに対する意識を変えていかなければいけないと感じた。
山一證券を題材にした「しんがり」は読んでみたいので、早速購入した。
Posted by ブクログ
世の中のコンプライアンス論を一掃する「現実感」と「希望」
日頃聞く法律家の論とは全く違う、人間の血の通った法社会論
さすが著名弁護士 ヒトの動機 ①正義 ②カネ
日本の組織は責任者不在
同質性と空気(無責任の体系東大政治学者)
決断に基づく悪事より性質が悪い→反省なしヒトラーと太平洋戦争
コンプラ疲れ コンプラのためのコンプラ
広く世のためヒトのための仕組み化
危機管理には「決断する胆力」70点でも決断を優先 不作為は✕
←ダメなのは①隠蔽②都合の良い情報③不決断
Posted by ブクログ
この本の最後に書かれていた「企業不祥事を防ぐには一人ひとりの働く意識しかない」という言葉が心に残った。企業は他種多様な外部のステークホルダーに囲まれた存在で、企業価値はレピュテーションの集積で形成されている。だからこそ、働く一人ひとりが倫理観を持ち、その総和として誠実な組織を創り上げることが大切なんだと思う。
品質不正だけではなく
品質不正についての本を探していたが、本書は前半だけで、どちらかというとコンプライアンス、企業のありかた、等を弁護士目線で説明されている内容でした。
著者の経歴を見るべきでした。
第三者委員会等の設置を考えている人にはお勧め鴨