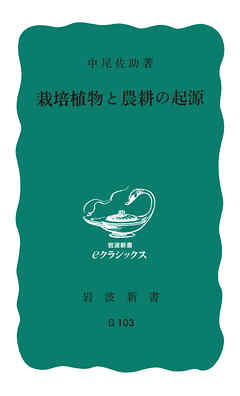あらすじ
野生時代のものとは全く違った存在となってしまった今日のムギやイネは、私たちの祖先の手で何千年もかかって改良に改良を重ねられてきた。イネをはじめ、ムギ、イモ、バナナ、雑穀、マメ、茶など人間生活と切り離すことのできない栽培植物の起源を追求して、アジアの奥地やヒマラヤ地域、南太平洋の全域を探査した貴重な記録。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
初版は1966年1月なので、かなり昔の本です。
でも、書かれていることは大昔の栽培植物と農耕の起源ですから、古くても問題ないです。
私が手にしたのは、2024年4月発行の第67刷でした。
果物の中では、バナナが一番たくさん作られていること、
小麦や米などの穀類は野生種には多年草のものもあるけれども、栽培植物になったのはすべて一年草であること、
小麦と米を比較すると、米のほうが美味しいので、どちらも栽培できる地域では米が主流になることなど、いろいろとおもしろい知識を得ることができました。
人類の文化のおおもとは農耕なのだから、農耕の起源を知ることはアジアの文化、アフリカの文化、ヨーロッパの文化などを理解するのに一助になると思いました。
Posted by ブクログ
宮崎駿さんと鈴木敏夫さんが、この本を読んだと見て読んでみた。
50年以上前の本で、今は新しい知見が出てきているのかもしれないが、
古代文明発生以前からの植物と人の文化を描いていて、とてもワクワクしながら読み進めることが出来た。
身の回りにある植物の背景や歴史を感じることが出来、日常の楽しみが増えた
Posted by ブクログ
農耕からホモサピエンスの文明が大きく発展したことはよく知られている。しかしながら、どのようにして主食となる作物を作ってきたかは知らなかった。
さまざまな試行錯誤と努力と観察があって初めてこれらのことは成し遂げられたのだろうと思う。そう思うと、いくつかの農耕の起源が実に尊いことに気がつく。
小麦などを主食とする人以外が多いということにも驚いた。
Posted by ブクログ
バナナやサトウキビは食べやすいように品種改良をされてきた。
農耕の方法についても工夫がされてきて今に至っている。
米は小麦よりも人類には受け入れられやすい。
マコモはワイルドライス。
Posted by ブクログ
「イネ作」など、出版年相当に言葉遣いが古いのは致し方ない。イネの移植栽培についてなど、自分がごく当たり前と思っていること、勝手に思い込んでいることが、他の文化と照らし合わせることで実は違っていたことに気付かされた。一度読み終わっても、また読みたくなる。
Posted by ブクログ
農学部生たるもの、中尾佐助大先生の著作ぐらいは読んどかなきゃ、ということで大学3回生のときに読みました。
イネ、ムギ、マメ、イモ、その他雑穀、茶などの私たちの食生活に欠かせない栽培植物について、現地調査や遺伝学的な解析から民俗学、文化的な考察を交えながらその起源を追求した傑作。
中学や高校の地図帳に載っている、根菜農耕文化(南アジア熱帯;イモ、バナナ)、サバンナ農耕文化(アフリカ・北部インド;雑穀、ゴマ、マメ)、地中海農耕文化(トルコ東部;ムギ、えんどう豆等)、新大陸農耕文化(メキシコ;トウモロコシ、カボチャ、ジャガイモ)という4つの独立した起源から農耕が伝わっていく中で形成されたそれぞれの文化(農耕文化複合)があるという説を初めて説いた本です。
そして、根菜、サバンナ、地中海の3つの農耕文化複合とイネ(稲作)や茶といったアジア特有の作物と風土がフレンドされて「照葉樹林文化」(東アジア;イネ、茶、桑(絹))が形成されていると説明しています。
単に農耕の起源を追うのではなく、栽培作物を栽培したり利用する中で衣食住の文化的な面にも多く触れられてるのでいろんな視点から楽しめます。生物学的な部分は、出版されてから技術が進歩しているので専門的な方には不満かもしれません。また、生物学に疎い人でも、その部分を読み飛ばせば十分読めます。
意外にも栄養バランスがいいのはサバンナ農耕文化だったり、日本などの照葉樹林文化に人々はイネが伝わるまでは山岳民族だったなどが面白い発見でした。
Posted by ブクログ
本書は我々が日頃食べている穀物などのルーツがどこか?ということを探るという内容である。日頃我々は、意識せず、米を食べ、バナナを食べたりするわけだ が、今、口にしている植物で野生種はないということ。ほとんどが数千年の歳月をかけて人類が選抜し、育ててきた栽培種であることにまず驚く。生活の知恵が 栽培植物には詰まっているのである。こうした育種の伝統は当然、その遺伝子に蓄積されており、この種を保存するということにももちろん意味がある。出版が古いため、昨今の話題の遺伝子改良食品には触れられていない。
Posted by ブクログ
しばらく前に金曜ロードショーの『もののけ姫』を観て、改めてその世界観やら今に通じるところとかをいろいろと考えさせられて、もののけ姫の考察的なサイトを読み漁っていたところで辿り着いた本。もののけ姫やトトロは照葉樹林文化論に基づいているとかで、そういう太古の森の話かなと思って読み始めてみると全然違った。野生植物から良い品種を選び出し、それをどのように栽培植物化して改良していったか、それがどれだけ文明発展の重要な基礎になったかということがエリア別・品種別に述べられている。読み進める中で、昔感じた素朴な疑問も思い出した。中1の歴史の授業では、「弥生時代に大陸から稲作が伝来した」と習ったけど、あんな水田なんていう複雑なものを最初に考え出した人すごすぎるだろと思った記憶がある。当然いきなり水田で栽培したわけではなく、湿地に自生する野生の稲を採集し、良い品種を選んで栽培・改良した結果が日本に伝来したと言われる稲作の姿ということらしい。読んでみると当たり前のようにも感じるけど、そこには長い年月をかけた数え切れない試行錯誤があったことだろう。そこには人類の歴史の基礎となる劇的な進歩があったのだと思い知らされる一冊だった。
Posted by ブクログ
文化(カルチャー)はその名前の通り、耕す事というのが、この本を読むと実感します。人類の英知をかけて、いかに人間が栽培しやすく、より多くの収穫が得られるように長い年月をかけて品種改良をしてきたかが良く分かります。
Posted by ブクログ
文化"culture"の元の意味は耕す"cultivate"から来ているという指摘は言われてみれば目から鱗。なるほど、農業"agriculture"はまさにカルチャーそのものってわけだ。マクニールの『世界史』が紀元前における農耕文化の発展に対してやたらとページを割いていたのも今となってはよくわかる。農耕文化とは技術や儀礼だけでなく、栽培植物の品種それ自体も含まれるというのはその通りだと思う。僕らが日々食べているご飯も何万年もの改良の跡が刻まれているわけで、美味しく食べられるってのは一つの歴史的行為なんだ。
Posted by ブクログ
歴史上での記述と近代までの農耕の世界分布を、農耕文化複合の概念によって合理的に説明している。
世界の農耕文化の時代を超えた全体像や、文明の初期段階における農業の発展が原始国家の形成に対し果たした役割などを具体的にイメージできるようになった。
少し読み難い日本語で書かれていることと、新大陸原産の作物が殆どおまけ程度にしか触れられていなかったのが残念。発行が1966年なので現在の定説とは違う点もあるかもしれない。
Posted by ブクログ
世界の農耕文化を根菜農耕文化、照葉樹林文化、サバンナ農耕文化、地中海農耕文化、新大陸農耕文化に分け、それぞれの農業の形態の特徴や、栽培植物とその伝搬ルートについて説明する。
・根菜栽培植物が石斧があれば金属や土器がなくても成り立つ。BC1000年頃にアフリカ東岸に到着して西へ広がり、バンツー族が発展して勢力を拡大する要因となった。ブタとニワトリを家畜化した。
・照葉樹林文化の中心は、中国西南部のロロ系民族(イ族等)の地帯。
・サバンナ農耕文化は雑穀、果菜類、油料作物が特徴。マメは煮て柔らかくする必要があり、土器の発明以降に食用になったと考えられる。
・地中海気候地帯は野生の一年生植物が多かった。冬作物。古代オリエントの灌漑農業、ギリシアとローマのドライファーミング(乾地農業、二圃式)による第二次革命、ゲルマン系民族の三圃式による第三次革命、輪栽式などの第四次革命と発展した。ウシ、ヒツジ、ヤギ、ウマ、ロバを家畜化した。
・ジャガイモを凍結乾燥加工できたことから、アンデス文化が余剰を蓄積、輸送でき、高度の文化への発達の基礎となった。
図の説明が多かったので関心をもって読み始めたが、農業に関する知識に欠けるため、難儀した部分が少なくなかった。
Posted by ブクログ
照葉樹林文化は、ヒマラヤから日本まで連なり、共通の自然資源利用形態を基盤とする文化。こういう人と自然の関わりを反映した文化っておもしろい。もっと詳しく書いてあったら良かった。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
野生時代のものとは全く違った存在となってしまった今日のムギやイネは、私たちの祖先の手で何千年もかかって改良に改良を重ねられてきた。
イネをはじめ、ムギ、イモ、バナナ、雑穀、マメ、茶など人間生活と切り離すことのできない栽培植物の起源を追求して、アジアの奥地やヒマラヤ地域、南太平洋の全域を探査した貴重な記録。
[ 目次 ]
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
栽培植物と農耕を通して人間は文明を発展させたわけですが、豊かな食糧事情が必ずしも文明を発展させるわけではないということがわかり、新たな発見をさせてくれた本書です。
Posted by ブクログ
農耕文化の歴史を全世界的視野でまとめ,その発生と伝播の過程を描き出そうという意欲的な試み.旧世界での農耕における作物や栽培様式のバリエーションについての幅広い検討から,旧世界の農耕文化の潮流を大きく3つ,根栽農耕文化,サバンナ農耕文化,地中海農耕文化に分類した.それらの発生・伝播過程と相互の関係をまず再構築した.次に,旧世界と新大陸の農耕文化の成立過程を比較検討することによって,新大陸の農耕文化が,旧世界のそれと類似の過程を辿って,独立に成立してきたということを指摘する.
Posted by ブクログ
人類の文化のなかで大きな位置を占めてきた、植物の栽培および農耕の歴史について解説している本です。
著者は、世界の農耕文化を四つの系統に分類しています。東南アジアを中心とする「根菜農耕文化」では、バナナとイモの栽培が中心となってきました。その北部にひろがる温帯の地域における「照葉樹林文化」では、クズや茶が、またアフリカなどの「サバンナ農耕文化」では雑穀やマメが、そして「地中海農耕文化」では麦の栽培がおこなわれてきたと著者は述べて、それぞれの農耕文化の起源について論じています。このほか、日本を含むひろい地域において重要とされてきた稲の栽培についての章と、新大陸の農耕文化について論じた章もあります。
人類の農耕文化の諸相について解説している本ですが、「あとがき」には「農業の起源と発達の歴史は、二〇世紀までの人類の歴史の中心的事実であった」と述べられており、農耕文化という視点から、人類の文化史の大きな展開をめぐるスケールの大きな議論が展開されています。
Posted by ブクログ
アグリカルチャーがカルチャーの一環であるとする著者が、各地を回って調べたもの。
農耕文化単一起源説を否定し、起源地はアフリカ、中近東、メキシコ、東南アジアの四系統であると唱える。
さらに、メソポタミアで発生した農耕文化は、それ以前に東から来たとする説を紹介する。
文章はわかりやすく、面白い。
Posted by ブクログ
戦史を学ぶときに見落とされがちなのが、農耕の進化だ。よく出来た本ならば兵站についても語られることはあるが、それでもその時代の生産能力、収穫時期、保存技術が語られることは少ない。
まずは人類の農耕は如何にして発展してきたのか、というところから学ぼうと本書を手に取ったが、期待からはややずれていた。
本書は、野生植物が栽培植物として育てられるようになるまでをたどる歴史本であり、その視線の先はほぼ紀元前にある。
進化の概念が明らかになるのは近世まで待たなければならなかったが、配合の技術は紀元前どころか、人類の誕生とともにあった。
バナナ、イモ、クズ、アワ、ヒエ、ムギ、トウモロコシ。それぞれの農耕文化における代表的な主食を、その原種の生息地と遺伝子情報から伝搬経路をたどり、同種の農耕文化を規定する。という繰り返しが基本的な流れ。それ以上の総括や考察があるわけではなく、面白味に欠ける。
そもそも倍数体や多年性植物、条播や禾本科なんて言葉が注釈なく使われるあたり、読み手は限定されているのかもしれない。
本書単体で楽しめる人は少ないだろうが、食と文化の結びつき、地域別の発展速度の違いや宗教との結びつきなんて面白そうなことを考えるには、本書のような探求の積み重ねこそが必要となるだろう。
Posted by ブクログ
バナナが優良な栽培に適した果物、と著作された頃は、まだ、バナナはそれなりに高価だったかも?
と、思うので(両親の発言やちびまる子ちゃんを思い出して、なんとなく)
そうすると、バナナは確かに安く売られるようになって、安定的な栽培化に成功したのかな?と思う。
こうゆうの、学生のころに読みたかったな
Posted by ブクログ
いつぞや、宮崎駿監督が進めてたから読んでみた。 初版が60年代の本なので、多少、現在の考えとずれがあるかも知れないが、日本の農耕が、中国、東南アジアというよりも、根元はシルクロード伝いで雑穀型の農耕文化を受けてきたというのは、なるほどと思うところがあった。
Posted by ブクログ
読みにくかったです。まず読み進めるのに苦労しました。ですが、内容はその労力に見合う魅力的な内容でした。照葉樹林文化というのは初めて聞いたのですが、なるほど、農業環境が文化を育てていくという考えは納得できます。その文化圏での共通点なども大変興味深かったです。また、日本に入ってきたのは稲より芋が先というのは衝撃でした。いろいろな意味でもう一度読み直したいです。
Posted by ブクログ
本書が執筆された1966年から、生物学は大きな進歩を遂げていて、本書もその観点からすると不満を感じてしまう。
ただし本書には「民俗学的農耕文明史」といった側面があり、その意味では十分に現代的な価値もある本。
新書という体裁・読者層の制約から参考文献などの記述は敢えて外したとのこと。それはそれで妥当なことと思う。ただ、それならば文献に当たらなければ当否の判断できない記述をもう少し減らして、より民俗学的視点を強調した構成にした方が面白かったかとは思う。
目次:
1. 栽培植物とは何か
2. 根栽農耕文化 - バナナ・イモ
3. 照葉樹林文化 - クズ・チャ
4. サバンナ農耕文化 - 雑穀・マメ
5. イネのはじまり - 10億の食糧
6. 地中海農耕文化 - ムギ・エンドウ
7. 新大陸の農耕文化 - ジャガイモ・トーモロコシ
Posted by ブクログ
1966年初版の古い本です。
この本には、遺伝育種学、栽培植物学の立場から、人類がどうやって
栽培植物というものを獲得したかの仮説が書かれています。
大学生の時にこの本のp146〜p148のくだりに、えらい感動しました。
内容を適当に端折りながら書き出すと
ーーーーーーーーーーーーー
原始採集経済の人々が大草原に入り込み、
野生の種の採集と狩りをしキャンプをするようになる。
すると、キャンプの周囲には窒素を濃縮した排せつ物がまき散らされる。
そのことが、大草原の中に島のように土壌の異なる場所を作り出す。
この人間が新しく作り出した環境の中に入り込んで育つ植物は
普通の野生植物とは異なる植物となる。
具体的には、突然変異によって適応を遂げた植物群が生じたのである。
簡単に言うと、野草から雑草へと進化したのだ。
さらにこの雑草群の中にムギ類の野生種が入り込むと
もう農業に非常に近いものとなる。
このようにムギ類は、野生から雑草へ、そして栽培植物へと
変わってきたのだ。
特に注目すべきは、野生から雑草へと変化したときには、
農業はまだ始まる以前のことなのに、植物の品種改良ともいえる
遺伝的な変化が起こっていたことだ。
こうして、人間が土地を耕すことを 植物の側から準備して待っていたのだ。
ーーーーーーーーーーーーー
最後の結びは、多分に詩的なとらえ方ですが、人間は本当に自然と
つながって進化してきたのだと感動したくだりです。