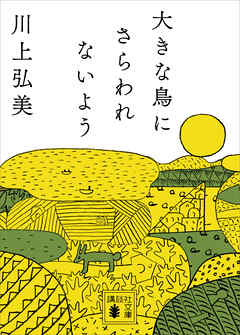あらすじ
遠い未来、衰退の危機を認めた人類は、「母」のもと、それぞれの集団どうしを隔離する生活を選ぶ。異なる集団の人間が交雑することにより、新しい遺伝子を持ち、進化する可能性がある人間の誕生に賭け―。かすかな希望を信じる人間の行く末を、さまざまな語りであらわす「新しい神話」。泉鏡花文学賞受賞作はるか先を静かに見通し、慈しみ深く描いた未来の人類史
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
圧倒的な空想と人類観
淡々とした(神話的とも評される)書き口で遠き日の人類を描く どちらかと言うとマクロな情景の描き方、読点の使い方(間のとり方)、情報の開示の仕方が魅力的
世界観 世界観 世界観
「ねえ、人は、どこから来たの」p.20
Posted by ブクログ
この本の良かったところは、人間と観測者、そして大きな母という生み出す者によって物語が紡がれている点だと思う。みんな人間を愛し、憎んでいるところが本当に人間らしくて好きだ
Posted by ブクログ
ブッカー賞候補作。
どこかの世界を描いているわけでもなく、神話のような世界。
設定も人同士ではなく、異なる遺伝子同士で交雑させた子どもたちが描かれている世界
これを映像にしたら、人の姿をしているかもわからないし、想像力がフル稼働させられてしまう1冊。
Posted by ブクログ
とてもよかった:
世紀末的な世界観を著者らしい静かで優しく描いていた。
緩やかに終わりへと向かっていく中での人々の思いが見事に描かれていた。
時折のぞかせる筆者の生物学への専門的な知識が作品のクオリティを見事に押しあげている。
個人的に、「愛」という短編が印象に残った。
「研究所」という独特な環境の中で、男の子の一途な恋慕の感情が、とても新鮮に映った。
また読み返したいです。
Posted by ブクログ
冒頭の一話目、遠い未来の日本を舞台にした幻想的な短編……としみじみ読んだところが、先へ進むにつれて世界は様相を何度も変え、最終的にSF的神話体系となってぐるりと巡る。眩暈がするような読書体験だった。
人類はいつか必ず滅ぶだろう。私たちは必ず死に絶えるだろう。その先にあるのが絶望だけなのか、その過程にこそ救いがあるのではないか。
祈りに満ちた眼差しが全編に染み通っていて、背表紙の「新しい神話」の評もなるほど、と。
聖書に所縁のあるような人名もところどころに見受けられ、個人的には福音書のようにも感じられた。
エリ、エリ、レマ、サバクタニ。その過程にこそ神の慈愛は注がれていた。
Posted by ブクログ
これは何度も美味しい小説ですね。
一読目
世界観とか想像するのに忙しすぎて脳内パニック。すごい世界観、驚いた、このサイズの本にこんなスケールの話が収まるの?しかもこの柔らかな雰囲気のSFって、何が何だか、、ぶっ飛ばされました。
もう一回読んで、三読目くらいからようやく文章楽しめるのかな、、、
いやぁすごかった、こんなみたことも聞いたこともない世界観だけど解像度高く情景が想像できてしまった、なんちゅう文章力。
Posted by ブクログ
短編集かと思って読み始めたら、とても不思議な世界に遭遇したような感覚で引き込まれて読み進めた。独特のふんわりした中にも鋭い感性が溢れた文章で、最初はきつねにつままれたような感覚で読んだが、
最後まで読み、解説を読んだら作者の深い人間感というか世界観に感銘を受けた。
Posted by ブクログ
小さなエピソードがモザイクみたいに重なって、最後には一枚の大きな絵が浮かび上がってくるような構成がすごくよかった。
物語が円を描くようなつくりになってて、読み終わったあとにもう一回最初から読みたい、と自然に思えた。
自然に生まれたわけじゃない人間や、クローン、母という存在に管理される世界。現代の延長線にありそうなテーマを通して、自分たちの価値観や常識がどれだけ不安定なものなのかを突きつけられる感じがした。
そもそも「人間を人間たらしめる条件」ってなんなんだ、と立ち止まって考えさせられる作品だった。
Posted by ブクログ
物語の中の時間単位が大きすぎると思わせるほど、割と近い将来の出来事なのかもしれない。視点の違うエピソードを繋ぎ合わせることで徐々に世界の様相や成り立ちが見えていく感覚は、未来のことでありながら歴史書を読み解いていくそれとも似ている。
色んな登場人物がいるけど、読者はこの世界でいう「見守り」の立場に近いところに置かれているような感じかな?
感情が最小限まで削ぎ落とされた先にある、戦争も平和もないグロテスクな秩序。人工知能の一つにチャッピーと愛称をつけて呼び始めた今、僕らはどのフェーズにいるんだろう。
Posted by ブクログ
好き嫌いが別れそうな本だったけど、私は好き。人類が滅亡の危機に晒されながらも、なんとかその命を絶やさないよう、いろんな策を考え行動する様を描いてるところは、手塚治虫の火の鳥に似てるな〜と思った。
Posted by ブクログ
自分の中で、その本に対する感想がまとまらない時は、気持ちが自分の中でまとまるまで、その本のレビューや解説を見ないことにしている。
この本も、読んでいる間中ずっとふわふわした非日常感を感じたり、常識の通じない異国に来てしまったような心許なさを感じたりした。
でもそれが嫌な気持ちではない、というのが不思議なところ。
短編の語り手たちの多くが身の回りの世界をよく理解できてない感覚と、読み手である自分が、この物語をうまく掴めていない感覚がすごくリンクする。
二回読み返した、お気に入りの本になりそう。
Posted by ブクログ
やわらかな言葉で終わりゆく世界が静かに描かれおり、気づいたらこの不穏で、不思議な、滅びゆく世界に深く没入している自分に気づき....うっかり数日で読破。
読みながら国立科学博物館の展示の一つである宇宙や地球や人のなりたち・進化をアニメーションで映した「地球史ナビゲーター」の映像がリンクし頭の中をくるくる駆け巡る。
あの暗い部屋でゆるやかに繰り返される宇宙と世界と人の物語をぐるぐる・ぼんやり観た時の感覚とこの本の読後感が非常に似ていた。
私たちはなに?
私たちはどこからどこへ?
愛とは?
人とは?
そんな答えのない問いを繰り返しながら我々は結局、愛して憎んで闘ってを輪廻の如く繰り返し続け今日も少しずつ終わりへ向かって歩みを進めているのかもしれない。
川上弘美の作品は真鶴が今の所1番お気に入りだけれどこれもなかなかどうして素敵です。
Posted by ブクログ
最初は世界観に慣れず「??」と
なりながら読み進めていたが
徐々に見えてくる世界観や
短編集?と思ってたら絶妙にリンクしてるお話で
どんどん引き込まれていきました。
一文ずつ短く淡々と描かれているのが
滅びゆく世界観を表してるようで
どこか怖さがありつつ、優しい温かさも感じた。
人類滅亡の話なのに
読み終わったあと、
これは希望のお話なのだと感じた。
叶わないと諦めてもなおも希望を抱き
小さな祈りを捧げる、そんなお話。
祈りは人が生きている限り続くんですね。
Posted by ブクログ
大きな「鳥」にさらわれないよう、「」この中に、なんでもいい他の言葉をいれてみたら…。
「さらわれないように。」と何度も言われるほどに、人間は弱く儚い生き物で、心とは何かにさらわれることのように思える。さらっていくものは何か…。
Posted by ブクログ
絶滅寸前になった人類が母の監視の元、いくつかの共同体に分かれて過ごす日々を切り取った終末SFの連作短編集。冒頭から語り口調が素晴らしく、その文体だけで斜陽となって滅びに向かう人類の愚かさへの絶望と絶え間ない悠久の孤独を感じてしまう。
一つ一つの短編はどれも緩い繋がりとなっており、世界観を共有しながらも読み味が少しずつ違うのが面白い。特に目立った事件や大きな出来事が起きるというわけではないのだが、その背景に挟まる断片的な情報の不穏さが素晴らしく、設定面は若干フワフワした部分がありながらも、クローンや人工知能といった設定は惜しみなく使っており、そこから察するディストピアな世界観がたまらなく美しい。愛と憎しみ。滅びと再生。絶望と希望、と人類の抱えた問題を表裏一体としながら紡がれたサーガは円環へと閉じていく。傑作。
Posted by ブクログ
人類は急激に減りつつあった。そして地球上の誰も人類の衰退を止める術を持っていない… 現存の人間ではもうだめだと考えた人間が 人間を進化させ違う人類をつくりだす計画をたてた。
今 私たちがいるこの世界は『運命』という章で〝わたし〟が語っているどのフェーズにあるのだろうかと考えた。
もう既に私の体内に何かが常駐しているのだろうか…
もう人類が地球生態系の最上位者ではなくなるのも時間の問題なんだろうか…
この先人類はどれだけ同じ事を繰り返していくのだろうか…
読み始めてからしばらくして 始めの『形見』だけ毛色が違うなぁと思ったが その理由は最後まで読んでからわかる。 解説にもあったが この中には始まりと終わりの両方があったのだ。
川上弘美さん。私は初読でしたがとても新鮮でした。
Posted by ブクログ
「滅びゆく世界を慈しみ深く描いた未来の神話」と文庫の帯にはあって、いい得て妙だと思いました。
語り手を変えながら物語が続くのですが、私は途中、このディストピア物語が一体どこまで続くのか、不安になりました。それでも巧みな書きぶりで、どんどん読み進むことができ、最後2つの物語で、全体の枠組みを開示してくれます。
とはいえ、明るいものではありません。「あなたたち、いつかこの世界にいたあなたたち人間よ。どうかあなたたちが、みずからを救うことができますように。」このレマの祈りは、この小説を読む私たちに向けられたものでしょう。
そしてそれでも今の人類は滅んでいく。「エリのつくった町のことを、レマはまた思う。町の中を流れる川で、小さな新しい人々は湯浴みをする。白いガーゼのうすものをはおり、女たちと子供たちが、石だたみを踏んで川まで歩いてゆく。ときおり、川を小舟で下ってゆく男女がいる。新しい場所で、新しい物語をつくるために。」人間からではない遺伝子でつくられる小さな人間たち。そのコミュニティから離れて、新しい場所を求める小さな人間が、希望として語られます。
新しい物語。それは愛や憎しみ、神や神話、排除の話ではないのでしょう。ここで安易には、著者から語られないということでしょうが、いつかその物語を読みたいと思います。
Posted by ブクログ
人とは何か、どんな姿をしていても人間なのか、そもそも人間と決めることに意味はあるのかわからなくなっていく。そして人間は生きていく意味があるのか。
変に賢いからそういうふうに考える。小鳥のようにただ子孫を残すなどの純粋なもので満たされているほうが幸せかもしれない。ディストピアともユートピアとも読める不思議な本だった。
Posted by ブクログ
気持ち悪さがあるが、すぐにそれ以上にそれを上回るその気持ち良さ。よく分からない世界をどんどん読み進められるけど、もう少し理解したいので再読する。
Posted by ブクログ
読んでいるうちに、自分が今いる世界を信じられなくなってきてしまった。わたしが今いるのは、何回目の世界で、誰によって創られたもので、わたしを見守る上位的存在はいるのか…。影響されやすい性格なのでそんなことを考えてしまう。
破滅の道をたどるというのに人はなぜ、人を憎み、争い、それでも愛すのか。人間というものを考えるときに根本となるものをテーマにしてると思う。読みながら、こんなに人間の営みを俯瞰して見ることができて、このディストピアのシステムを構想し、お話の中で機能させることができた川上弘美はなんて頭がいいのだろうと何度も唸った。そりゃブッカー賞候補にも上がるなあ。
人間は愚かな存在だけど、それでも。
Posted by ブクログ
人為的に作られた環境で人はどう生きていくのか。繋がりがあるようなないような集落が衰退したり生命維持方法が進化したりするディストピア。
時系列を理解するのにちょっと苦労しましたがそれもまたこの作品の良さなのかと感じました。
SFをこのタッチで表現できる稀有な作家さん。2回読んでもまだまだ理解できないけど素晴らしい魅力を持った作品です。
2025年の国際ブッカー賞最終候補ノミネート作品。こちらは 残念ながら受賞には至りませんでしたが受賞作のBanu Mushtaqさんの『Heart Lamp』もできれば読んでみたいです。
Posted by ブクログ
読み出してしばらくこの本の世界観がつかめなかった。そういった説明が少ない。でも、作者の中にきっちりとした世界ができてるとは感じられた。
この話が言うように、人間はくだらないことを続けている。遠い将来、人間はどうなるのだろう? クローンが生まれるのか? 新人類は出てくるのか?
Posted by ブクログ
未来、人類は絶滅衰退から逃れるために新たな遺伝子を持ち、進化と循環を繰り返す道を選んだ。作られた新しい人類の世界、新しい人類の暮らしの物語。
一般的なSFとは違う読み心地で、とにかく静かなお話。
進化のスピードはとんでもなく速いのに、人間たちは怒鳴りもせず取り乱しもせず、どこか淡々としていておだやかで。そのギャップが薄ら怖い。
作中の人間の生活ぶり、進化や衰退の過程はテクノロジーや環境のもう引き返せない変化が静かに進んでいる現実と、そのことに気付いているのに気付かないふりをして日常生活を送っている私達の姿が重なって見えて、今を生きる私達に差し迫った危機への警鐘のようにも感じた。
Posted by ブクログ
神話かな?
人間とAIとクローンと原始生物の話
ファンタジーのようだけど 考えさせられる内容でした
短編集みたいだけどぐるーとまわって あぁ~この事だったんたと 話がつながり面白かったです
Posted by ブクログ
未来の人類の話。どのくらい未来なのか分からない。
不思議な話だった。読み進めていくとメビウスの輪のように最初に戻ってくる感じ。
川上さんはどうやってこんな物語を思いつくのか不思議だ。
Posted by ブクログ
登場者たちの語りのなかに人類衰退への諦めが滲み出ており、読んでいて寂しく悲しい気持ちになりました。手塚治虫さんの火の鳥のような世界観。状況描写が少ないので、状況がよくわからないまま読み進めることになりますが、終盤では明らかにされていきます。
Posted by ブクログ
読み終わった。
とっても とっても時間がかかった。
丁寧に読んだ。
怖くなったり悲しくなったり、諦めや失望が大きくて 少しの希望はすぐになくなったり
とにかく悲しくなる。未来から投げ込まれた本なの? どうすることもできないの?