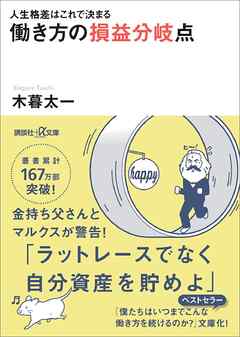あらすじ
ベストセラー『僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか?』がついに文庫化され、会社に左右されない自分資産を積み上げる実践法がさらに追加されました。ビジネス書作家として累計167万部の発行部数を誇る著者が、経済学の原理と自身の体験をもとに解決策を提案。『資本論』のマルクスや「金持ち父さん」が教えてくれるショッキングな社会のルールを知ることから、幸せな働き方への変革は始まります。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
大学生や新社会人、会社員の働き方に疑問を持っている全ての人々に薦めたい良書。
「しんどい働き方」から抜け出す方法や「豊かな働き方」をするために必要なことを論じる前に、マルクス資本論から見た私たちが今いる資本主義経済の構造・仕組み、私たちの給料がなぜその金額なのか、価値と使用価値、利益とは何か、労働者の運命、など重要かつ根本的な部分から説明してくれるため、この一冊を読み込むだけで社会の仕組みや会社員という存在、給料の仕組みなど一通りのことが分かるようになると思う。以下重要だなと思ったこと。
1.二種類の給料の決まり方
①必要経費方式→伝統的な日系企業
②利益分け前方式(成果報酬式)→外資系金融や歩合制の会社
2.二つの価値
①価値→それを作るのにかかった手間の積み重ね
②使用価値→それを使ってどれだけ役に立つか
3.ビジネスから利益が生まれるのは商品を生産する過程で労働による「剰余価値」が生まれるから。モノを仕入れて販売し、その差額分が利益になるというわけではない。
4.二種類の労働者の労働
①必要労働(給料分の価値を生む労働)
②剰余労働(企業の利益である剰余価値を生み出す労働)
→絶対的剰余価値(剰余労働の長さを増やすことで得た価値)
→相対的剰余価値(必要労働時間が減り、相対的に剰余労働時間が増えることで生まれる価値)
→特別剰余価値(生産性が高まり同じ時間内で他社よりも多くのものを作れるようになるが売値は変わらない。社会的価値と個別的価値の差額分)
5.「労働の使用価値」より「労働力の価値」を先に高める
6.「自己内利益」を増やす働き方をする
①世間相場よりもストレスを感じない仕事を選ぶ
②まず「積み上げ」によって土台を作り、その土台の上でジャンプする
③労働力を「消費」するのではなく「投資」する
④長期的な資産を作る仕事を選ぶ
⑤過去からの「積み上げ」ができる仕事(職種)を選ぶ
⑥変化のスピードが遅い業界・職種をあえて選ぶ
⑦賞味期限が長く、身につけるのが大変で、高い使用価値のある知識・経験をコツコツ積み上げる
⑧PLだけでなく、BSも考えて働く(=BS思考)
7.「資産を作る仕事を、今日はどれだけやったか?」を毎日自分自身に問う
Posted by ブクログ
▪️用語
価値: 商品を作るのにかかった費用
使用価値: 商品を使うことで得られるメリット
▪️給料の本質
2種類の給与体系がある
・必要経費方式: 働いていくために必要なお金を支給する
・利益分前方式: 儲けた分で給料がきまる
労働力を商品だと考えると、必要経費方式では「価値」に依存して給料がきまるので、「使用価値」(=売上実績など)では決まらない
▪️資本主義経済の仕組み
会社は利益を出すために活動するが、利益は商品の価値が材料の価値よりも大きくなることで「剰余価値」として発生する。
その剰余価値には以下の3種類ある
・絶対的剰余価値:
労働者をたくさん働かせることで得られる剰余価値(例: 3時間多く働かせたが、その分を回復させるのに1時間分の時間で足りれば、2時間分の剰余価値が得られる)
・相対的剰余価値
生活費が下がることで、働いていくために必要なお金が下がり、支給する給料も下げられる
・特別剰余価値
イノベーションや、自社だけが知っている効率的なやり方でコストを削減すること
▪️資本主義で生きる労働者の運命
企業が利益を上げるために労働者が発明したイノベーションで、(労働者の)生活費が下がれば、給料の基準も下がってしまう(給料が必要経費方式なため)
他社との差別化を図るためにイノベーションを出してもコモディティ化してしまうので、利益創出のためにイノベーションを出し続けるしかない(でも、そうすると生活費が下がり給料も下がる)
▪️高い賃金を払ってもらうための条件
給料を高くするには労働力の「価値」を高めることが重要。
でも、多くの人は「使用価値」を高めることに注力している。使用価値を高めることの具体例は残業することや、売上成績を上げること。
それでも給料は上がるが、一時的なものになってしまう。
▪️自己内利益を高める方法
自己内利益は以下の式だが、QoLのようなもの
自己内利益 = 年収・昇格による満足感 - 生きていくための必要経費
高給だけど、それを上回る激務・プレッシャーだとQoLは低くなる
【満足感を変えずに必要経費を下げる方法】
他の人と比べて精神的苦痛を感じにくい仕事をすること。
必要経費の中には気晴らしをするためのお金も考慮されていて(会社によるが)、精神的苦痛が少なければ気晴らしする必要がなくなるため。
【必要経費を変えずに満足感を上げる方法】
労働力の価値を高めることです。つまり、他の人が真似しにくい能力を身につける、ということです。
こうすることで、自分の必要経費はそのままでも年収を上げられたり、昇格できたりする(そんなに簡単な話でもない気はするが。。。)
ただ、変化の早い業界では身につけた能力がすぐに使えなくなるかもしれないし、スキルの内容によっては賞味期限が短いものもあるので、できるだけ長いもので身につけられるとよい(例として、会計の知識、営業のスキルなどが挙げられる)
労働力の価値を高める取り組みは数年から10年単位での積み上げが必要で、日々の生活の中で労働力を「消費」するのではなく価値を高めるために「投資」することが大切とのこと。
本著の中にあったメッセージとして
「PLだけではなく、BSも考えて働く」
がありました。
PLが目先の利益を、BSが高められた労働量を表しているのだと解釈してます。
Posted by ブクログ
資本主義経済のなかで生きる企業は、みんな元来『ブラック』衝撃的な一文だが、そうなのだろう。何故働いても楽にならないのか、日々しんどい働き方を続けてる全ての人に。