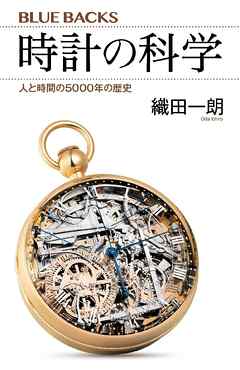あらすじ
人類が「時間」の存在に気付いたのは、いまから5000年以上も前のことです。太陽の動き利用した「日時計」から始まり、周期を人工的につくりだす「機械時計」の誕生、精度に革命を起こした「クオーツ時計」、そして時間の概念を変えた「原子時計」まで、時代の最先端技術がつぎ込まれた時計の歴史を余すところなく解説します。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
人類が時を測るためにつくった時計の歴史を紹介。
前半は日時計・水時計・火時計・砂時計などいろいろな昔の時計の紹介。
中盤あたりから駆動のエネルギーにゼンマイが登場し、そこから脱進機構のメカニズムの説明と時間信号源(振り子など)の紹介がメインになっていく。最後はデジタル時計の登場から電波時計の説明などの後、時間を定義する原子時計を紹介して終わる。
一冊読むと時計史がわかるかなりいい本。
Posted by ブクログ
時計の歴史を、その技術的な発展から書かれています。古代から太陽や水といった自然を利用し、そこからどのようにして時の概念を生み出したのか。その後しばらくは正確さとの戦いであったこと。そして次に小型化としての腕時計の時代。デジタルの時代へと。正確さは究極にまで進化し、一般人には不要なレベルにまで達するも、その真価が新しい時の概念を生み出したこと。時計に対する人々の歴史。それを読んでいると、人類の発展の歴史そのものが、ここに凝縮されていることを感じます。
Posted by ブクログ
1日は24時間で、1時間は60分で、1分は60秒。ずーーーっと当たり前
のこととして疑問を持たずに生きて来た。でも、最初に時間という
概念を思いついた人がいるんだよね。改めて考えると凄いわ。
太陽の動きによって、木や岩の影の長さや方向が変わるのを見て、
時間の存在に気がついたのだそうだ。そこから人類は「時間」を
知ろうとする努力を積み重ねて来た。
本書は人類が「時間」に出会ってから、それを知るために時計を
作った歴史のお話である。
面白いわぁ。特に古代の時計の話の数々は魅力的。日時計から始まっ
て、水時計、火時計、砂時計、花時計など。どれも試行錯誤しながら
改良を加えて、より正確な時刻を知ろうとしている。
天文学と深い結びつきのある時計だが、天文台と一緒になった中国・
北宋時代の水運儀象台は高さ12mになる巨大な水時計だったらしい。
本書では写真が掲載されているが、これは本物が見てみたい。
そして、花時計。今まで花壇の上を針が回るのが花時計だと思って
いたんだが、これは違うそうだ。本当の花時計は開花時間の異なっ
た数種類の花を植えて時間を知るものだった。
こういう花時計。どこかにないかな。時刻の正確さは抜きにして、
花の咲く時間で時を知るなんてロマンティックじゃないか。
昔々の目覚まし時計は時間精度が低くて、目覚まし時計呼べるよう
なものではなかったとかも面白い。
時代が進むごとに時計は小型化と正確性が求められるようになり、
腕時計も時代と共に進化していく。
今では携帯用端末を時計として使っている人が多いのか、腕時計
をしている人も少なくなった。でも、凄いんだよ、腕時計。
手首に着けられるサイズなのに、小さな小さな部品がいっぱいに
詰まっていて、しかも正確に時間を刻んでくれるんだから。
各章の間には「時」と「時計」に関するコラムもあり、知らないこと
ばかりが多くて勉強にもなった。
尚、1日が24時間なのは十二進法や六十進法を多用していたシュメール
人がバビロニアで文明を開化させたかららしい。
どれだけいろんなものを発明してるんだよ、シュメール人。天才の
集団か。
本書の表紙カバーの写真は、マリー・アントワネットが金に糸目をつ
けずに天才時計師アブラアン-ルイ・ブレゲ作らせた時計なのだが、
これ、復刻版があるんだよね。展示用で販売の予定はないようだ。
欲しいけれど、ブレゲの時計だから市販されたとしても高価過ぎて
買えないだろうな。シクシク…。
Posted by ブクログ
身近な機械ながら、具体的な構造について全然知らないため、読んでみた。
最初の章では「時間の発見」として、過去の文明が時間をどのように認識していたか、どのように取り扱っていたかを説明し、そのあとに「機械式時計の発明」「腕時計の誕生」「クオーツ、デジタル時計」について、発明の経緯や発明当時の時代背景と一緒に説明があり、非常に興味深く読むことが出来た。
また、著者が時計の販売店の出身ということもあり、戦後以降の各メーカー毎の発明やその販売路線など、細かい部分の分析があり、面白かった。
クオーツ時計の基本的な仕組みは知っていたが、実際に実用化するためには様々な工夫が必要だったことを知り、壁掛けのクオーツ時計を見ながら「こんなに安くていいのか」とも思ったりした。
Posted by ブクログ
時計の技術的な進歩が社会を変えていく様が面白かったです。時計の構造の説明がいちいち細かくそれはそれで面白いのですが、技術革新により異業種からの参入があったり、質の担保への要請からの規格化や監査があったり、技術を独占しようとするも代替技術が現れて廃れたり、行きすぎた質の追及が市場で受けなかったり、ビジネス本としても面白いです。
Posted by ブクログ
古代の時計から始まり、機械式時計、クオーツ時計、原子時計、光格子とけいまで、様々な時計の開発の歴史が書いてある本。
いろいろな時計職人の逸話なども入っているのがおもしろい。
ブルーバックスなので、科学的・工学的なアプローチが深く、そのあたりを知りたいひと向け。
うるう秒の現在の国際間での討議状況については他の文献に書いてなかったので参考になった。
Posted by ブクログ
日時計から機械式時計、クォーツ、光格子時計まで。時計の歴史は科学の歩みそのものですね。
ミニ四駆でお馴染みのボールベアリングってクロノメーター開発時に導入されたものだったんですね。
Posted by ブクログ
献本でいただいた 生きていくうえで誰もが関わることを避けられない時間 それを正確に計測し、自分の手で掴もうとした人間の軌跡が詰まった一冊 後半部分はかなり専門的な内容であったが、全体的に興味を引く内容となっており面白かった 個人的に第一章の古代の話が好き(レビュー遅くなってすみませんでした)
Posted by ブクログ
「時間」の存在に気づいた約5000年前から、
人と時計の悠久の歴史が始まる。
日時計・水時計・砂時計・火時計・・・そして機械式時計へ。
「神」のものであった「時間」は「人」のもとへ。
それは、生活・宗教・政治のために。
金属加工・合成の技術の向上・・・振り子やゼンマイの発明、
大量生産。
更には、電池、電子技術の発展からのクオーツやデジタル。
そして原子時計と、精巧さ、正確さが追求され・・・未来へ。
時計の仕組みがわかりやすい図と
丁寧に綴られる文章には好感が持てました。
また、索引と参考資料もわかりやすいし、コラムも楽しい。
日本人の技術の素晴らしさにも気づかされました。
読み進めるうちに、時計の博物館へ行って、
実物を見てみたくなりました。
Posted by ブクログ
内容は興味深い。
時間の発見から、時計の進歩、原子時計が出来るに至って、時間だけでなくいろんな概念が変わらざるを得ない。
自然の「時間」との誤差が大きな問題になっていることとか面白いんだ。
だが、肝心の技術面のところが、図も説明も素人には全く判りづらくって、寧ろキーワード拾ってネットで調べる方が判るってくらいで。
どういう人を狙っての本なんだろう。
Posted by ブクログ
機械式時計に興味を持ち、読んでみた。人間と時間との関わり・自然を利用した日時計の時代から、最新の原子時計まで、時間・時計と人類の歩みを順に追って行けるような感じ。
第1章 時間の発見
第2章 機械式時計の発明
第3章 腕時計の誕生
第4章 電子技術で誕生したクオーツ、デジタル時計
第5章 超高精度時計と未来
・東向島にあるセイコーミュージアムに行った事がある。第1章は、そこでの展示をなぞっているような感じ。
・人類最古の時計である日時計、そこから水時計、火時計、砂時計、花時計。どれも自然のものを利用して時間を得ていた。現在のように手軽に正確な時刻が得られるのは、実は当たり前ではなかった。遊女が客の時間管理に線香時計を使っていたとか、当時のエピソードがちょくちょく出てきて面白い。
・機械式時計の仕組みの説明は、文章メインなせいでわかりづらかった。
・和時計のガラパゴス感。不定時法と定時法。もし不定時法がもう少し続いていれば、日本が時計業界の覇権を握っていたかも?
・原子時計のような高精度の時計が一体何の役に立つんだろうと思っていたが、やっとわかった。GPSで位置を割り出すためには正確な時刻情報が必要だ。原子時計よりも更に精密な光格子時計では、時空の歪みまで検出できるようになる。