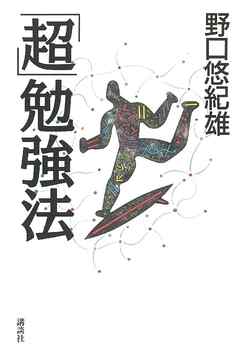あらすじ
勉強は、実は楽しい。「基礎から一歩一歩着実に」というこれまでの学習法を行っているかぎり、成績はあがらない。誰もが取り組め、めざましい成果が得られる画期的ノウハウと具体的方法を野口悠紀雄教授があますところなく公開。【「超」勉強法の主要ポイント】基本三原則:1.面白いことを勉強する。2.全体から理解する。3.8割までやる。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
読み易く、参考になる。基礎からも大事であるが、まずは全体を見通す為にとりあえず進みきる。ということも非常に大事である。外国語は耳から覚える。文章で記憶。数学も暗記である等、具体例が挙げられており良い。1995年出版の作品であるが現在でも通じると感じる。
Posted by ブクログ
高校時代に読んでおきたかった.これまでの勉強の常識をひっくり返す本である.
いろいろとすごすぎて内容をよく覚えていない.時間がもったいないがもう一度読むことにしよう.
Posted by ブクログ
英語、国語、数学、暗記の4分野に分け、筆者が自分なりの原則に基づいて推奨する勉強法を紹介しています。自分のものと重なる部分が多く、「うんうん」と頷きながら読める本でした。
特に英語の教科書丸暗記は、英語だけでなく外国語を勉強する上で必ず力になるし、パラシュート法も勉強の効率を上げるのにとても良い方法だと思います。
Posted by ブクログ
効率よく学習するヒントが得られる本。
この本はずっと家に置いてあったので、おそらく20数年前に読んだのだろう。背表紙は見ていたが、内容はすっかり忘れていた。もっとも、その後に『「超」文章法』など、野口氏の他の著作は読んでいたので、「わかりやすく書く技術」など、共通する部分は実践していた。本書の一部は身に付いていたということだ。
勉強法が書かれた本は、たいていあまり面白くない。「努力せよ」、「やる気を出せ」、「ゴールを想像せよ」という精神論に重きを置いたものも少なくない。たしかに、努力は重要だ。そして、努力が必要なことは、たいていの人はすでに知っている。
知りたいのは、どのように努力するかだ。
つまり、勉強のノウハウである。
「勉強」の本は、主に学生向けだと思われるかもしれない。しかし、この本は学生だけでなく、社会人も視野に入れて書かれている。その部分を引用しよう。
この本は、受験や学校の勉強のためのものではない。あらゆる知的活動の基礎となる学習行動一般について、有用なノウハウを含むと考えている。(p19)
学習することは、年齢にかかわらず重要だ。だからといって、やみくもにやっていては、効率が悪い。どうせなら効率よく学習したいと思うのが人情だろう。勉強のノウハウ、効率よく学習するヒントを得たいのなら、本書は一読する価値がある。
野口氏の本は、通り一遍のことを書いていないので、飽きさせない。わかりやすい文章で、読みやすいことも利点だ。
最後に、この本で基本となっている勉強法の三原則を下記に挙げておこう。
【「超」勉強法の基本三原則】
第一原則:面白いことを勉強する
勉強は楽しい/勉強を楽しいものに変えよう/知識があれば興味が深まる
第二原則:全体から理解する
一歩一歩進む必要があるか?/「鳥の目」法/重要な点を把握する
第三原則:八割原則
八割までをやる/基礎を八割理解したら応用に進む
Posted by ブクログ
古い本だが、読んでみた。勉強法においてなるほどと思う人はみんな暗記の重要性と勉強の効率を言っている。
勉強には暗記が必要であるのは受験を通して理解している。大学受験に効率的な勉強法を確立しておけば良かったなぁ〜と今にして思うが手遅れですわ。
Posted by ブクログ
本当に次々とノウハウ本を作るものである。
勉強法というものは、やはり重要なものであると思う。
勉強の方法は、わかっているようでわからないことが実状であろう。
どのように勉強するかは、
個人にあった一番やりやすい勉強法
を見つけることが必要であろう。
「どのようにして勉強すべきかという方法論は、
系統的に教えない。」
勉強ができないのは、能力が低いからでなく、
勉強のやり方に問題がある。
「学力」と「得点力」は別のものである。
「何歳になっても勉強はできる。
勉強を始めるのに、遅すぎることはない。
人間は何歳になっても、
学習によって進歩する動物なのである。」
「投資」としての勉強ではなく、
「消費」としての勉強である。
基本原則
①おもしろいことを勉強する。
好奇心が満たされるとき、誰でも楽しいと思う。
理解が深まると喜びを感じる。
勉強とは、本来楽しいものである。
楽しくなければ、楽しくなるように
学ぶ方法を変えることである。
教材も自分で選んで、楽しく勉強する。
ある程度知っていることについて
新しい情報が得られると興味をだく。
興味と知識は連鎖的に広がる。
②全体から理解する。
基礎は退屈で難しいものだ。
全体を把握し、それに基づいて部分を
理解をしようとする方法が大切。
上から見ればよく見えるし、
各部分は他の部分との関連において理解しやすい。
そこから「重要な点」を把握する。
「幹と枝葉の区別」能力を高める。
学力とは、重要なことに集中できる能力である。
③8割わかったら先に進む。
勉強も試験でも同じであるが、まず8割までやる。
残りの2割が難しい。
少なくとも、努力に見合った成果が得られない。
しかし、8割までは中断せずに行うことが大切である。
8割やったら、とりあえず進め。
高いところにのぼれば、2割が自然に理解できる場合が多い。
④目標が意欲を生む
勉強とは、目標と現在の状態との差を埋めるものである。
目標もイメージを伴った具体的なものに。
イメージが具体的であれば、望めば実現する。
各論の方法論
英語;教科書丸暗記法
学校での英語の勉強は、英語を分解し(=分解法)
日本語と関連つけて学習しようとするところに問題がある。
言葉をそのまま全体として受け入れる。
全部を記憶すれば、英語の成績は上がる。
①部分部分ではなく、全文を連続して覚えるほうが容易。
②ある箇所を思い出せば、あとは自動的に思い出せる。
③単語は一つ一つを無理して覚えなくても
文章を暗記すれば自動的に覚えられる。
④個々の単語をバラバラに覚えようとしても、
覚えられるものではない。
⑤英単語が日本語の単語に1対1に対応しない。
⑥分解法は、英語をリズムで覚えないので、聞き取れない。
⑦分解法は、英語的表現ができない。
英語的表現は、沢山の文章を読むことによってしか獲得できない。
受験英語は、教科書丸暗記で十分である。
出題者は、教科書の範囲を逸脱した問題を出すと
批判されるので、慎重になっている。
国語;字数把握の重要性
(1)文章の構造は、3部構成(序論;本論;結論)である。
序論;問題提起、問題の限定化、背景説明、先行研究のサーベイ
本論;
従来の考え方の批判、対立意見の紹介、
仮定の明示、分析、実証、批判
留保条件、客観的分析から主観的判断
結論;序論で提起した問題についての答え
(2)早く正確に読むには、
文章の最初と最後をまず読むことである。
全容把握→通読→拾い読み
全体を把握していると、部分は理解しやすい。
(3)文章の書き方
人を感動させる文章を書く必要はない。
相手に読みやすい文章を書く。
①1文1意主義をとる。「が」を使わない。
②ねじれをなくす。主語が入れ替わる。
重複表現。修飾関係をはっきりさせる。
(4)受験国語
短文(1500字程度)の文章を精読する。
150字程度の文章を書く。
数学;パラシュート法;受験数学は暗記だ。
当面の問題に集中して、解き方を習熟する。
できるだけ早く全課程を勉強する。
基礎を完全にマスターしてから
進んでならぬという固定観念は捨てる。
基礎がわからないから理解できないのではなく、
興味がわからないから理解しようとする意欲がわかない。
基礎概念や定理の意味は使うことによってわかることが多い。
基礎概念や定理の意味は、理由がわからなくても、
とにかく使い方を丸暗記する。
使っているうちにわかることがある。
受験数学は自分で考えて解くより
解き方を覚えてしまった法がよい。
ただし計算力はつけよ。
暗記術
記憶しようとするならば、
まず対象に注意を向け、興味を持つ。
理解することによって記憶する。
脳の記憶容量は、使えば使うほど大きくなる。
覚えられないのではなく、思い出せないことが多い。
①共通属性法;共通する属性でくくる。
②寄生法;よく知っているものに寄生させる。
③ストりー法;因果関係でストーリーを作る。
受験勉強
受験勉強は特殊である。
①問題が与えられている。
②正解がある。
③出題範囲が決まっている。
④知的な文章がでる。
⑤時間内に解く。
受験勉強は暗記だといわれる。
自分で解法を見いだして解いていては、
時間がかかりすぎる。
受験勉強は、絶対評価ではなく、相対評価である。
そのため、選別できる問題でなければならない。
入試問題が難しいのは、誰にとっても同じである。
しかし、難しすぎて誰も解けなければ、選別できない。
努力すれば解けるようになっている。採点するために曖昧では困る。
客観的基準がいる。
しかし、受験勉強によって、本来の知的活動に阻害される。
問題が与えられているから、
「問題を探す能力」がなおざりにされる。
「なにが重要か」を見抜く能力も問われない。
Posted by ブクログ
■超勉強法
第一原則:面白いことを勉強する。
第二原則:全体から理解する
第三原則:八割原則
◎八割までやる、残り二割は難しい。
◎基礎を八割理解したら応用に進む
Posted by ブクログ
文章の書き方など、大変参考になった。
1.一つの文で、複数の内容を述べない
曖昧接続の「が」を絶対に使わない。
2.主語述語のねじれをなくす。
3.修飾関係をはっきりさせる。
目次
序章 勉強はノウハウ
第1章 「超」勉強法の基本三原則
第2章 英語の「超」勉強法
第3章 国語の「超」勉強法
第4章 数学の「超」勉強法
第5章 「超」暗記法
第6章 「超」受験法
第7章 勉強の「超」ヒント集
終章 未来への教育
Posted by ブクログ
この本は高校生、大学生の時に何十回も読み返しては参考にしていた本だ。
自分に大きく影響を与えた本に間違いない。
しかし、英語の丸暗記法にはあまり賛成できない部分も多く、国語の部分の記述も物足りない感は否めない。
その他の部分でも、今となっては当たり前のことも多い。
(自分の経験では、まずは文法を頭の中に入れて、それで文章を文法的に解説するようにする。この本では分解法と言われて批判されているが、
正確に読むということを考えれば、とても有効な方法だと思う。そのあと、総合的な文法問題集を解き、繰り返し、同時にAll in oneのようなCD付きで重要単語を含んだ
文章を文法的に読んでいけば、少なくともNHKラジオ講座を聞き取れるリスニング力と簡単な文章が書けるようになるライティング力が着くようになる。そのあと、スピーキングは
場面ごとに必要な表現をイメージしていきながら、独り言や話す機会を作ることで上がっていくし、あとは、自分の興味のある英文を読んでノートに要約をする作業を続けていけば
英語を知的に話せるようになっていく。留学をしては英語力が付いてくるのは最後の作業を数多くこなしてくるからだ。)
それでも、読むたびに発見のある本であり、参照できるところは多い本だ。
本書を要約すると、
勉強の原則
1おもしろいことを勉強する
2全体から勉強する
3八割の原則
英語
分解法から、丸暗記法へ
数学
パラシュート勉強法
国語
3ラウンド読解法
文字の字数に応じて、文章を書いていく
記憶
類似と対比を意識する。
グループ分け
ストーリーを作る
etc
である。
Posted by ブクログ
高校生の時、父親にプレゼントされました。
この本を読んでから自分の中で勉強のスタイルが確立できた気がします。
要領がいいか悪いかは別として。
勉強の仕方が分からない方にお勧め。
Posted by ブクログ
学習方法指南の本は数あれど、わかりやすく説得力があってすぐに実践できそうな方法ばかりのコレは本当に役に立ちました。特に受験英語に関しては、「超英語法」よりもこちらの方が有用だと思います。
Posted by ブクログ
英語は丸暗記、数学はパラシュート式に行うべし。英語については江戸時代の武士が行った素読が想起される。
学生時代、読んでいると勉強した様な気分になれたが結局は不勉強だった。トピックスも読みやすいしモチベーションを上げるには良い本。
Posted by ブクログ
Eテレで放送されていた「欲望の経済史」に出演されていたので、ようやく自分の中で、顔と名前が一致した。頭の良い人は、自分のやっている勉強方法を俯瞰的に分析し、効率的かどうか検証しているのだなと感心した。やみくもに時間をかけて、自己満足の勉強方法では、効率が悪いことを改めてしらされた。でも、先生は20回も、音読すれば、頭に入るとおっしゃられるが、凡人はいくら読んでも頭に残らないのが悲しくなる。
Posted by ブクログ
子供の頃、勉強が好きではなかったし、勉強の仕方がわかっていなかったと思う。でも今は学ぶことが楽しいし、知識定着に有効な方法を知りたいと思う。今後のためにもと思い、勉強の方法について知識が欲しく読んでみる。
読んで、子供にはなんかしらのアドバイスをあげれそうだが、自分自身に対しては・・・どうかな。
【学】
基本三原則
・楽しいこと、興味の有ることを勉強しよう。知識が増えれば、興味も深まる。
・全体から理解せよ。部分の積み上げで理解するのではなく、まず全体の把握。それに基づき「鳥の目」で各部分を位置付ける
・八割まではやり遂げよ。
英語:ひたすら朗読。教科書を20回繰り返し読む
国語:わかりやすい文章を書け。3つのルール。
①1つの文で複数の内容を述べない。「が」を使わずに「しかし」を使う
②ねじれを無くす。主語を変えない、重複表現を避ける
数学:できるだけ早く全過程を見て、全体像をつかむ。受験数学は暗記
【更に読みたい】
続超整理法・時間
中山 親子で伸ばす学習戦略
多湖 小学生のうちにやっておきたい勉強のしつけ
浜田 楽勉のすすめ
Posted by ブクログ
基本になる勉強の方法について、もっといい方法はないものかと情報収集のために呼んでみた一冊。受験対策がメインで社会人が勉強することを想定して書かれていなかったので、参考になる部分は少なかったですが引き続き続ける勉強の効率をどう上げていくのかは考えていきたいと思いました。英語の、文章単位で覚えてしまう方が効率がいいっていうのは本当にその通り。単語は覚えてないけど歌詞とか10年経っても覚えてますもんね。
Posted by ブクログ
要約すると「細かい事をいちいち気にしてんなよ」という事、だと思う…。
いっつも些細な事で悩んで、落ち込んで、くよくよして、めそめそして、
腐っている身としては、得るものが多い本だった。
あ、勉強の話ですよ。人生じゃないって。
全体を把握して、重要な部分を見極め、その部分の理解に注力する。
これは「物事を理解する」こと全般において必要な事だと思う。
「英語」「数学」「国語」については特別講義が設けられているので、
それらを勉強する時がきたら、再読しよう。
ん、それっていつだ!?
Posted by ブクログ
極端なくらい合理的。こういうものに100%賛同するわけではありませんが、覚え方は自分もそういうものだと思ってやってきましたし、なにより効果は間違いなくあるでしょうね。
Posted by ブクログ
昔、といっても高校時代(十分、昔ですねw)に読んだことがあったのですが、ふとした機会に読んでみました。
当時、どんな風に感じたかすら忘れていました…。
で、読んでみたのですが、微妙ですね。
ほとんど共感できる部分がなかったです。
あと書き方もあまり好きではないですね。
なんか洗脳しようとしている様に受け取りまいした。
ただ一部、共感した部分は「人の名前を覚えるのは大事だ!」ってことです。
ホンマに大事ですよね。名前を覚えるだけでコミュニケーションの取り方がだいぶ変わってきますしね。
忘れると失礼になるんでね。
共感できた部分と言えばそれくらいです。
結局は、「学問に王道なし」ってやつですかね!?
Posted by ブクログ
勉強に対する心構えや、効率的に勉強を行うための方法を示した本。英国数に加え、暗記、受験に対する解説がある。
とりわけ高校生(1〜2年生)、ビジネスマン向けだが、そのほかの人にも応用できる内容。
言っている事は納得できるが、実践するのはなかなか大変。勉強に対するやる気はあるのに、どう手をつけていいかわからない人に薦めたい本。