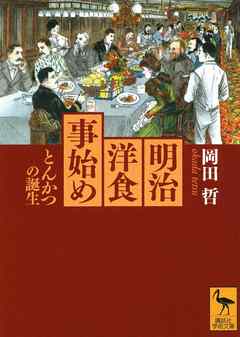あらすじ
明治維新は一二〇〇年におよぶ禁を破る「料理維新」でもあった。近代化の旗のもと推進される西洋料理奨励キャンペーン、一方で庶民は牛鍋・あんパン・ライスカレー・コロッケなどを生み出し、ついに「洋食の王者」とんかつが誕生する。日本が欧米の食文化を受容し、「洋食」が成立するまでの近代食卓六〇年の疾風怒濤を、豊富な資料をもとに活写する。(講談社学術文庫)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
とんかつの誕生として2000年に出版された本の文庫版である。牛肉、あんパン、とんかつ、について詳しい。カレーライスについてもちょっと最後の方で書いてある。挿絵も豊富であるが、店の名前も出てくるので、東京在住でない人にとっては地図が掲載してあれば便利である。学生が読むかどうかは不明だが、牛丼やカレーライスやハンバーグやラーメンについて書いてあれば学生も読むであろう。
Posted by ブクログ
「あんパン、ライスカレー、コロッケ、とんかつはどのようにして生まれたか」という副題にわくわくして、即購入。
めっちゃおもしろかった~!!
「これ読んでめっちゃ賢くなった」「すんごい知識増えた」という類の本ではないけど、これぞ読書の醍醐味。あまり知らなかった分野を知れた、それに伴って他分野を勉強してみたくなった・・・という好循環(^^)
明治天皇が肉食解禁してくれてよかった。
そしてとんかつが生まれてよかった。もちろんカレーもコロッケも。
あんパンの誕生秘話がいちばん興味そそられた。パンを作るということが、日本人にとっていかに大変だったかよくわかった。
日本人は、西洋文化・料理をうまく自分たちの文化に取り入れた。牛肉も、自分たちが食べやすいように煮込んで和風の味付けにしたことで、すき焼きが生まれた。
すばらしい!
あんパンが食べたい。とんかつ食べたい。昔の日本人に感謝したい。
歴史はおもしろいなーと初めて思えた本。
食べ物の歴史に照らし合わせると、苦手な歴史も楽しかった。
Posted by ブクログ
明治以降、日本に入ってきた”西洋料理”がどのようにローカライズされて”洋食”として広く普及していったか、さまざまな資料を基に活写されていて、とても興味深い。
”牛鍋(すきやき)”にはじまり、”あんぱん”や”とんかつ”など、それぞれが一つのドラマであり、プロジェクトXでもある。”カレーライス”と”コロッケ”の分量が少ないのが残念だが、トリビアも豊富で、この本を元にしてどこかテレビでやってくれないかなぁ…。私がプロデューサーなら絶対企画書作っているぞ。
Posted by ブクログ
文明開化のシンボルとして、明治天皇が進んで肉食を始めたという事実から話は始まる。西洋料理をそのまま導入する努力をしつつも、そこは日本人。コメを主食とするということを大前提に少しずつ工夫をこらす。おやつというアングルからあんパンを生み出し、コメに合う西洋料理としてとんかつという「洋食」を生みだした。
その背景にあるのは、今も昔も変わらない食に対する高い関心だ。肉食の導入こそお上からの思し召しだったのかもしれないが、それを自らの食の中に取り入れ、アレンジしたのは他でもない一般の庶民。こういう成り立ちを持つ文化の足腰は強い。四年前から料理教室に通い始めたワタシも「庶民の総力によって料理を作りつづける、世界でもまれな日本の食の文化」の一端の一端の欠片くらいを担わせていただこうかと、おこがましくも思っている。
明日の夕食は洋食にしよう。
Posted by ブクログ
明治維新は 食べ物維新。肉脂を忌避して米に固執する日本人がいかに西洋料理を受容したか。まず、西洋に対抗するには身体が小さい日本人に肉食を広める為、明治政府は天皇が肉食してみせ、鹿鳴館でパーティを連夜開き啓蒙。知識人や上流階級に広まる。庶民は江戸後期から広まっていた薬食いの料理方法で牛肉を醤油や味噌で煮た牛鍋やすき焼きにして食べた。さらにパンは主食にはなれず、あんパンなど菓子パンとして広まる。やがて本格的に西洋料理を学んだ人々が一般向けの店を開くが、マナーが難しく馴染みない味のフランス料理を代表とする西洋料理はあまり広まらなかった。その中で日本人合うように工夫された洋食が生まれる。大正時代になるまでに三大洋食コロッケ、カツレツ、カレーライスが生み出される。コロッケなどは油を大量に使うので家で作るのを主婦が嫌がり、肉屋の店頭販売を買うのが一般的だった。さらにカツレツから発展し、てんぷらの料理方法で柔らかく厚く安い豚ヒレ肉を使ったとんかつが生まれる。付け合わせはキャベツの千切り、箸で食べられるように予めカットされ、ご飯とみそ汁に合う、究極の洋食は大ヒットする。そば屋などは押され次々に潰れる。関東大震災の後、復興するなかでそば屋は洋食も出すようになり、現在のカツ丼などを提供するそば屋が生まれる。中華は戦後、大陸からの引き上げによるラーメン、餃子の普及を待たねばならない。
Posted by ブクログ
文明開化における食の西洋化に焦点を当て、とんかつの完成迄を追ったもの。学術文庫らしく、多くの資料から学問的根拠をもとに構成しているので、内容も信頼できる。この手の本は店の親父さんや、ライターの推論で勝手に決めつけて書かれている書物が多いが、この書物は良書である。
Posted by ブクログ
それじゃあお姉さん、洋食のはじめてを見に行こうか! 「クルクルバビンチョパペッピポヒヤヒヤドキッチョの、モーグタン♪」テ~レ~レ~レ~レ~...と、そんな声が(このネタが分かる方はきっと私と同年代でしょう)聞こえてきそうな「洋食はじめて物語」といった内容で、とんかつとあんぱんという2大発明を軸にして、日本の肉食と洋食誕生の歴史を紐解いていきます。楽しんで、また時には食欲を刺激され、おなかを鳴らして読みました。なじみの薄い「西洋料理」を「洋食」へと変えてしまった日本人の適応力とアレンジ力の高さには驚きです。
Posted by ブクログ
とにかく、『とんかつ』
『とんかつ』
『とんかつ』
大事なことなので何度でも言います(笑)・・・な感じ。
しかし、西洋から上陸した「西洋料理」が、米食に合う「洋食」という形で取り込まれ、庶民に広まるまでの過程がよくわかる。
エピローグは簡潔で良い。
そこに書かれていた、コムギ粉料理の歴史の方が自分的には興味深かったりして。
私を含める日本人が、なぜこんなに料理本が好きなのか、料理ブログが好きなのか、料理が出てくる小説が好きなのか・・・その理由は依然としてわからないけれど、明治維新までは獣の肉は穢れている、と食べられていなかったのに、たった100年そこらで劇的な食生活の変化を遂げたのは、やはり、並々ならぬ食に対する興味があったのだろう。
(日本人は)雑食性であり、食に対する主体性がない、とも書かれている。
Posted by ブクログ
明治期に流入した西洋料理がいかにして日本社会に取り入れられ、今日の洋食が生まれるに至ったかを書いた本。
洋食発生過程の人々の思惑・反応や、様々な紆余曲折・試行錯誤が詳しく書かれ非常に興味深い内容だった。とんかつやあんパンが登場するまでの数十年が実に濃密に感じられる。
Posted by ブクログ
開国して以来、日本は欧米諸国から劣等国として不平等条約を押し付けられていた。いち早く彼らに自らが文明国であることを証明し、不平等条約を撤廃させなくてはならない状況下におかれていた。
当時の外交はフランス料理が正餐であったため、西洋料理、特にフランス料理を取り入れる必要があった。また武力侵略され、植民地化されないようにするため、軍事力も身に付けなくてはならなかった。そこで体格向上の為、食肉をしなければならないというのが、至上命令となった。しかし室町時代以降、だいたい同じような食生活をしてきた日本人にとって、西洋料理は食べ付けない、美味しくない料理だったようだ。
明治以来日本人が、口に合わない肉やパンをどうにかこうにか加工して、日本人好みの料理に変化させていった過程を描いたのが本書である。
涙ぐましくもあり、滑稽でもあり、諦めなかったという意味では誇らしくもある長い努力の物語は、一読の価値があると思う。
Posted by ブクログ
◇目次
○第1章:明治五年正月、明治天皇獣肉を食す
○第2章:牛肉を食わぬ奴は文明人ではない
○第3章:珍妙な食べ物、奇妙なマナー
○第4章:あんパンが生まれた日
○第5章:洋食の王者、とんかつ
○第6章:洋食と日本人
本書は明治時代に本格的に入ってきた西洋料理が日本国内で受容・吸収されていき、日本ライズされた「洋食」の誕生まで辿る。
著者日く、受容・吸収の過程を三段階に分け、①西洋料理の崇拝期である明治初期、②西洋料理の吸収・同化期である明治中期、③和洋折衷料理「洋食」の台頭期である明治後期とした。「あんぱん」もこの①の段階で誕生し、普及した。
また、③の時期に出てきた「洋食」が大正期~昭和初期にかけて洗練され、庶民の家庭料理として普及していった。この段階で、現在の我々に馴染みのある「とんかつ」登場するとされる。
全体の明治「洋食」の歴史の流れは分かりやすいが、著者の具体的な事例が時系列通りでなく、行ったり来たりしたり、説明もちょくちょく重複があり、若干のくどさを感じてしまった。
そういう感想もあり、内容はさることながらやや低めの評価にしてしまった。