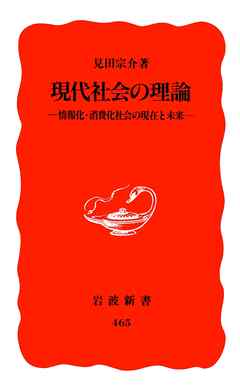あらすじ
「ゆたかな社会」のダイナミズムと魅力の根拠とは何か。同時に、この社会の現在ある形が生み出す、環境と資源の限界、「世界の半分」の貧困といった課題をどう克服するか。現代社会の「光」と「闇」を、一貫した理論の展開で把握しながら、情報と消費の概念の透徹を通して、〈自由な社会〉の可能性を開く。社会学最新の基本書。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
再読。現代が消費化/情報化社会であるとして、その欠陥点が〈消費〉の概念を社会全体が正しく捉えられていないこととして指摘、その解決を情報化と〈生の直接的な充溢と歓喜〉へと消費の概念を見詰め直すことに見出している。
以下、昔書いたまとめを。
------
<一章要点>
・資本主義という一つのシステムが、必ずしも軍事需要に依存するという事なしに、決定的な恐慌を回避し反映を持続する形式を見出したという事、この新しい形式として、「消費社会化」という現象をまず把握しておく事が出来るという事。
・自己否定、自己転回
・デザインと広告とクレジットを柱とする、ソフトなより包括的な戦略、「消費者の感情と動機と欲望に敏感な」システム
・消費社会としての資本制システムが存立する事の前提は、(この労働の自由な形式に加えて、)<欲望の自由な形式>である。
・<欲望の抽象化された形式>、<労働の抽象化された形式>
・古典的な資本制システムの矛盾——需要の有限性と供給能力の無限拡大する運動との間の矛盾、これが「恐慌」という形で顕在化する。
・上記の矛盾を、資本の基本システム自体による需要の無限の自己創出という仕方で解決し、乗り越えてしまう形式が<情報化/消費化社会>。
・自己の運動の自由を保証する空間としての市場自体を、自ら創出する資本主義。
・<情報化/消費社会化>こそ、初めての純粋な資本主義である。
・誘われたままでいる事を享受し、あるいは寧ろ、よく誘惑するものであるか否を、鋭敏な批判の基準として選択する対処の仕方は、1970年代以降の世代達にとっては、平常の基礎的な情報消費社会の内部を生きる事の技法となっている。
・<大衆が消費する事は、それが資本の増殖過程の一環をなすからといって、それが大衆自身の喜びである事に変わりない>
・この社会の固有の「楽しさ」と「魅力性」という経験の現象、それがこのシステムの存立の機制自体の不可欠の契機である
<二章要点>
・「自動的な廃滅化という現代の傾向」
・上記の様に呼ばれているのは、「モードの理論」と同じ戦略によるものである。つまり、<消費の為の消費>を通しての繁栄というシステムの基本の論理そのもの。
・根源的独占は、商品システムというものが、必要を充足する為の他の方法を排除してしまう事を通して、生活の仕方を選択する自由を否定する。それは、自然的な他の共同体的な選択肢を解体してしまう事を通して、商品システムへの依存を強制する。
・農村と都市の構造から家族の形態に至る、日本社会の基本的な構造が変容したのは、1960年代を中心とする、「高度経済成長期」である。日本に於ける「現代社会」の創成期である。
・現在の<情報化/消費化社会>が、自分で自分の無限定の成長と繁栄の為に設定する無限空間——人間達の現実的な必要を離陸する<欲望の抽象化された形式>、あるいは<欲望のデカルト空間>とは、このような<消費の為の消費>、<構造のテレオノミー的な転倒>の、純化され、洗練され、完成された形式である。
・生産の最初の始点と、消費の最後の末端で、この惑星とその気圏との、「自然」の資源と環境の与件に依存し、その許容する範囲に限定されてしか存立しえない。
・現代の情報化/消費化社会は、資本制システムの「自己準拠化」の形式として成立した。
・人間達の「必要」に制約されない無限定の消費に向かう欲望を、情報を通して自ら再生産する。
--------
<一章>
現代社会は資本主義社会である。世界恐慌等を経験し、決定的な恐慌を回避し持続的な繁栄を実現する為に<情報化/消費化>した。というのも、<情報化/消費化>は「消費者の感情と動機と欲望に敏感」になる事で、需要の無限の自己創出を可能にしたからである。そして、このシステムが成立するのは、<大衆が消費する事は、それが資本の増殖過程の一環をなすからといって、それが大衆自身の喜びである事に変わりない>事とこの社会の固有の「楽しさ」と「魅力性」という経験の現象によって裏付けられている。
<二章>
一章で先述されている、『需要の無限の自己創出』とは、必要を充足する為の他の方法を排除してしまう事を通して、生活の仕方を選択する自由を否定する根源的独占と、人間達の「必要」に制約されない無限定の消費に向かう欲望を、情報を通して自ら再生産する事で可能となった。また、先述の日本に於ける『現代社会化』は農村と都市の構造から家族の形態に至る、日本社会の基本的な構造が変容したのは、1960年代を中心とする、「高度経済成長期」に起こった。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
「ゆたかな社会」のダイナミズムと魅力の根拠とは何か。
同時に、この社会の現在ある形が生み出す、環境と資源の限界、「世界の半分」の貧困といった課題をどう克服するか。
現代社会の「光」と「闇」を、一貫した理論の展開で把握しながら、情報と消費の概念の透徹を通して、“自由な社会”の可能性を開く。
社会学最新の基本書。
[ 目次 ]
1 情報化/消費化社会の展開―自立システムの形成(新しい蜜蜂の寓話―管理システム/消費のシステム デザインと広告とモード―情報化としての消費化 ほか)
2 環境の臨界/資源の臨界―現代社会の「限界問題」1(『沈黙の春』 水俣 ほか)
3 南の貧困/北の貧困―現代社会の「限界問題」2(限界の転移。遠隔化/不可視化の機制 「豊かな社会」がつくりだす飢え ほか)
4 情報化/消費化社会の転回―自立システムの透徹(「それでも最も魅力的な社会」? 消費のコンセプトの二つの位相 ほか)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
学部生時代に手にして、途中まで読んでほっぽりだしてしまっていた。
部屋の整理をしたら久々に目にしたので、再読してみたら、当時とは違って読み終えられた。
少しは成長したのだろうか。
四(章?)の、情報のコンセプトの二つの位相という件がよくわからなかった。
何を言わんとしているのか、また寝かせた後に再読したほうがよさそうだ。
自分が成長していることを期待して。
全体を通して、ヴィジョンを提示するというスタンスではなく、軌跡をなるべくコンパクトに理論的にパッケージングするというスタンス。
初版1996年からもう15年程経過しているけれど、そこで語られていることは、今にも相当に当てはまる。
それだけ汎用性の高い理論化だったということの証左であり、かつそれだけ当時から現在に至るまでのわたしたちの社会がよくもわるくも変わっていないということの象徴でもあるのかもしれない。
とりわけ、ここで論じられている水俣病に関する件や、世界的な貧困に関する件は、今の日本社会が抱える「見切り発車であとはどうにかなるんじゃない」的な空気に符合する部分が多分にあるように感じられた。
津田大介氏がどこかで述べていた気がするが、古典と呼ばれるものは、現代にその思想を投影して読んでみることに意味がある(私の曲解かもしれないが)とのこと。
本書が「古典」と呼ばれるほどにtest of timeを経てきたかはわからないが、15年前の思想・理論を現代に援用して読み進められたのが、非常に好印象。