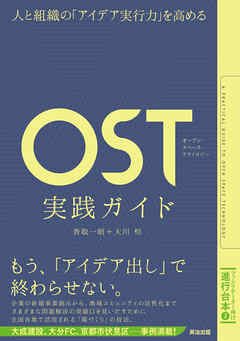あらすじ
もう「アイデア出し」で終わらせない。
企業の新規事業創出から、地域コミュニティの活性化まで
さまざまな問題解決の突破口を見いだすために
全国各地で活用される「場づくり」の技法。
【大成建設、大分FC×大分大学×富士通総研、京都市伏見区、edcamp Kamakura、田舎の宝カフェ……事例満載!】
◆「オープン・スペース・テクノロジー」とは?
実行したいアイデアや解決したい課題を参加者自身が提案し、
それに賛同する人たちが集まって話し合うことにより、
具体的なプロジェクトを生み出したり、
課題への理解を深めたりするためのワークショップ手法です。
「分科会同士の移動は自由」「ここにいる人が適任者なのだという意識をもつ」などの特徴的なルールがあり
参加者の自主性・自発性を最大限に引き出すことを目的としています。
組織開発コンサルタントであり、写真家でもあるハリソン・オーエンにより1985年に開発。
規模に成約はなく、数十人から数百人、数千人の事例もあり、
世界中で開催されるようになっています。
日本でも「ワールド・カフェ」をはじめとする「対話の場」が
盛んに開催されるようになっており、
それをさらに実践に落とし込む方法として、
OSTやそこから派生したプロアクションカフェ、アイデアソンなどの
イベントが続々と開催されるようになってきています。
本書の著者は、OSTファシリテーター養成講座を10年以上にわたって実施してきた第一人者。
日本各地の事例を取材し、実践のポイント、
ファシリテーターの心構え、
そして組織開発への示唆を盛り込んだのが本書です。
組織やコミュニティでの場づくりに関心ある方はもちろん、
リーダーシップ育成、組織開発に関心ある方にも
実践に生かせるヒントが詰まっています。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
情熱を注げる企画を探している折に見つけた書籍。最近のテーマは「企画立案と実行」。本書は、アイデア出しや企画立案のためのワークショップ技法であり、かつ、アイデア実行までをフォローする。多少なり、リーダーシップ論と絡めているところがある。
■著者が抱く課題と本書の意義
自分ですごい!と思うアイデアや前から持っていたアイデアがあったとしても、躊躇してしまい、実現に向けた一歩を踏み出せない人は多いのではないか。そんな人たちへ向けて実現までドライブしていくための方法論、OSTを紹介する。
■OSTとは
OSTは、実行したいアイデアや解決したい課題、探求したいテーマを参加者が提案し、それに賛同する人が集まって話し合うことにより、具体的なプロジェクトを生み出したり、議論するためのワークショップ手法。参加者には自発性と貢献性を要求する。
■ OST4つの原則
・ここにやってきた人は、誰もが適任者である
・何が起ころうと、それが起こるべき唯一のことである
・いつ始まろうと、始まった時が適切な時である
・いつ終わろうと、終わった時が終わりの時なのである
■ 移動性の法則
自分が参加したグループで、自分の貢献度が低いと感じた時には、いつでも他のグループに移動できる。自発性、貢献性で仕事を持つ
→社内でもこういう風に仕事をするといい。役職や立場で仕事が割り当てられる従来のやり方は、自発性や貢献性を引き出しにくい。
■OST2つの仮説
・人は自分が本当にやりたいと思ったことに取り組むとき、最大限の能力を発揮する
・参加者の内発的な動機から自発的に行動するためには、ファシリテーターはコントロールを手放して、参加者の行動上の自由度を高めなければならない
Posted by ブクログ
■Q1. OSTには、どのような効果があり、どのように運営されているのかを知る。
[効果]
OSTは、アイデアの実行力を高める場をつくることを目的とした手法である。
アイデアの実現や課題解決に向けて、様々な視点、立場、組織の人々と協同するという、新しいタイプのリーダーを生み出す効果がある。この理由は以下の通り。
①OSTでは自発性が尊重される
→強い意志と責任感を持って参加するリーダーを生み出す。
②集団の中でテーマ出し
→積極的に前に踏み出す勇気を示すリーダーを生み出す。
③OSTでは、どの検討会に参加するかは個人の自由(移動性の法則)であるため、メンバーの共感を引き出して自発的な参加を促すリーダーシップが必要となる。
→権限に頼らず、態度と姿勢でリーダーシップを発揮するリーダーを生み出す。
④OSTのテーマは答えが自明ではないため、他者の協力が不可欠であり、ダイアログが必須
→ディスカッションではなく、ダイアログで合意を形成するリーダーを生み出す。
※ダイアログとは:図1-2
※相手の発言の意図を「探求」することが重要:図1-3
⑤OSTのテーマは答えが自明ではないため、メンバーの能力を引き出せる必要がある。これには、専制君主的に振る舞うのではなく、部下を信じて任せることで、貢献している実感を持ってもらうことが重要である。
→メンバーが能力を発揮できる環境を整えるリーダーを生み出す。
※部下の能力を引き出すリーダー:図1-4
⑥これらにより、メンバー自身のリーダーシップが育まれる。
[アイデアの実行が促進される理由]
変化がゆっくりしていた時代には、ビジネス実行のための知識やスキル、ノウハウが安定していた。そのため、経験者や上位者の指示で動くことが効率的であった。
これに対して、VUCAの時代には、アイデア出しとアイデア実行には他者の協力が不可欠である。そのためには、個々の参加者が、テーマに情熱と責任を持って積極的に参加すること(=リーダーシップが醸成されていること)が必要となる。情熱が強くないと困難を乗り越えられないためである。OSTは、リスクを感じることなく自由に意見を述べることができ、行動が制限されない、安全で安心できるオープンな場を作り上げることで、リーダーシップの醸成とともにアイデアの実行を促進する。この際、ファシリテータの振る舞いが重要である。
[運営]
①オープニング
サークルになり、ファシリテータが目的、プロセス、グラウンドルールを説明する。
・グラウンドルール
・4つの原則
・ここにやってきた人は、誰もが適任者である。
・何が起ころうと、それが起こるべき唯一のことである。
・いつ始まろうと、始まった時が適切な時である。
・いつ終わろうと、終わった時が終わりの時なのである。
・移動性の法則:自分の意志でいつでも他の分科会に移動してよい
・蜂:ある分科会から別の分科会に移動する人
・蝶:どの分科会にも参加しない人
②テーマ出し
ファシリテータが提案を募集する。サークルの中心に出てテーマを提案する人が現れるのを、辛抱強く待つ。※全体ファシリテータの役割はここまで。あとは分科会ごとのファシリテータに任せる。
③マーケットプレイス
各自の意志に任せて、テーマごとにチームを分ける。
④分科会
自主的な運営が重要。移動性の法則、蜂、蝶を守って実践する。
⑤クロージング
サークルになり、感想を述べあう。
■Q2. 自身の業務に適用できるOSTの要素、および、期待できる効果を見つける。
OSTのファシリテータの態度や振る舞いから、組織マネジメントへの示唆(★印)が得られる。
①目的を共有して場を開く
参加者が貢献したい/貢献できる/貢献すべきと思える目的を設定することで、参加者に情熱や責任を持ってもらうことができ、能力を引き出すことができる。
★ミッション(何のために存在するのか)とビジョン(何を目指すのか)を共有すること。メンバーが情熱と関心を持てる共有ビジョンを、対話を重ねて決定することで、各自に貢献したいという自発的行動が生まれる。
②グラウンドルールを示す
グラウンドルールを示すことにより、安心、安全な場であると認識してもらう。これにより、主体的な行動や積極的な意見を引き出せる。
★バリュー(組織として何を大切にするか)や行動指針を共有すること。それを守れば何をしてもよいという安心、安全な場を作り、参加者の積極的な参加を促すため。
③フラットな関係の場を作る
フラットな関係の場を作ることにより、安心、安全な場であると認識してもらう。
※成功循環モデルにおける「関係性の質」が根底にある(図3-2)。いきなり成果を求めず、関係性の質を高めることから始めることが大切。
※キーパーソンやポジションの高い人には、事前に説明しておくことが重要。
※サークル状の椅子配置が大切。
④今ここに集中する
第一原則に従い、お互いを尊重して目の前のメンバーで最大限の成果を出そうとすること、および、第二原則に従い、むやみに意見を否定せず受け入れることで、主体性に目覚めることができる。そして、一歩前に踏み出しやすくなる。
★コントロールできることに集中する。それを日常的に発信し続けることが重要。
⑤内なるリズムで行動するように促す
積極的なリーダーが生まれることを期待できる。一方、つねに時間で管理され、誰かの指示によって使われていると、自発性が損なわれてしまう。また、多様性により創造性が生まれることを期待できる。
⑥コントロールを手放す
OSTのファシリテータに望まれることは、自己組織化が起こりやすい場づくりである。これにより、自主性や自律性が育まれる。そのためには、コントロールを手放して介入しないことが重要である。①目的の共有、②グラウンドルールの明示、③フラットな場づくりにより、コントロールを手放すことが可能となる。
※コントロールを手放したうえで、⑦場をホールドし、⑧混乱に耐える覚悟を持つこと。
★ミッション、ビジョン、バリューを共有し、安心、安全な場づくりを心掛けることにより、コントロールしないで信じて任せることが可能となる。
⑦場をホールド(保持)する
安心、安全で心地よい場を「確保」することが、リーダーが現れるための重要な条件である。そのためには、ファシリテータの行動ではなく態度が重要である。場に集中し、つねに「何のために、ここにいるのか」を自らに問い続けること。
⑧混乱に耐える覚悟でのぞむ
参加者を信じて自主性に任せる。クラエス・ヤンセンの混乱の部屋(図3-4)は、自発的な行動や創発的な協同のチャンスとなる「建設的な混乱」である。
■Q3. どのような問題を抱えている場合に、OSTの適用を考えるべきかを知る。
・Value Engineeringや基盤研究のネタ出しから、さらに実行においても有用ではないか。
Posted by ブクログ
OSTの考え方、How To、事例までくまなく載っているのでOSTについて知りたければ間違いなくこの1冊。運営としても参加者としても何度かOSTを体験していたので、すんなり内容も入ってきた。
個人的には特に第3章の「OSTのファシリテーションと組織マネジメントへの示唆」が面白かった。