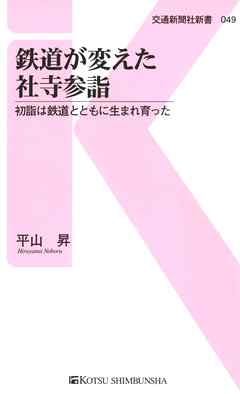あらすじ
日本人にとって最もメジャーかつ“伝統的”な年中行事「初詣」は、意外にも新しい行事だった……?! そしてその誕生の裏には、近代化のなかで変化する人々の生活スタイルと、鉄道の開業・発展、そして熾烈な集客競争があった――“社寺参詣のために敷設された鉄道は多い"という語り方で語られてきた「鉄道と社寺参詣」の関係に一石を投じ、綿密な資料調査をもとに通事的に解き明かす、鉄道史・民俗学を結ぶ画期的な一冊。
平山 昇(ひらやまのぼる)
1977年長崎県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。現在は同大学院学術研究員、立教大学経済学部兼任講師。主な論文に「明治期東京における『初詣』の形成過程」(『日本歴史』691号、2005年)、「明治・大正期の西宮神社十日戎」(『国立歴史民俗博物館研究報告』155集、2010年、第2回鉄道史学学会住田奨励賞受賞)などがある。
※電子書籍の仕様による紙版と異なる図版・表・写真の移動、本文中の参照指示の変更、ほか一部修正・訂正を行っている箇所があります。予めご了承ください。
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
恵方参りや初縁日と異なり、元日に寺社にお参りする「初詣」という習慣は、明治以降に鉄道ができてから、まだ珍しかった汽車に乗って郊外の寺社に出かけて散策を楽しむ行事として生まれたんだって。勉強になりました。
伊勢詣りの隆盛も、その裏に鉄道会社の競争あり。
明治30年代の官営の東海道線と関西鉄道(今のJR関西本線)との間での大阪-名古屋間のサービス競争の影響が起こり、関西鉄道が参宮鉄道(今のJR参宮線)との連携で伊勢詣りがPRされ参詣客が増え、さらに、昭和になり大阪電気軌道&参宮急行(今の近鉄)が参入し、国鉄とサービス競争を繰り広げたことで、さらに参詣客の増加に至った。そして、一生に一度の伊勢詣りが日帰り可能なレジャー化していったのだそうだ。
そして、個人的に一番興味をひかれたのは、阪神電鉄と西宮神社の十日戎をめぐる駆け引き。
明治5年の改暦により、西宮神社では新暦十日戎と旧暦十日戎が併存し、当初は新暦戎はさっぱりだったが、明治38年に開業した阪神電車が新暦戎に運賃割引サービスを展開し、新暦戎も賑わうようになっていった。
一方、西宮神社は(旧暦)9日夜に居籠り神事を行うため閉門するが、電車で来る都市部の参詣客は閉門後も神社に詰めかけることがありトラブルを生じていた。神社側は阪神電車に夜間閉門の周知徹底を求めたが、電車側は駅での掲示のみで最も効果のあった新聞広告での周知はしなかった。ようやく昭和9年になり新聞での広告を出したが、その時には神社側も閉門時間を1時間遅らせて12時にしたとのこと。
神事を守りたい神社と少しでも客を増やしたい電鉄側のせめぎあい、ここには全て書ききれませんが、興味深いです。
いやー、西宮戎に知られざる歴史ありですね。
身近な話だけに引き込まれて一気に読み切ってしまいました。
Posted by ブクログ
(130ページ)「初詣はもともと恵方だの初縁日だのといっや細かいことにこだわらずにお詣りするという、きわめてアバウトな行事として成立し、そのアバウトさに利用価値を見出した鉄道会社のPRによって社会に定着していったものなのである。それにもかかわらず、誕生からわずか100年あまりで、あたかも「初詣の正しい伝統」などといったものが古来からあるかのように説明する語り方が定着しているわけである。(中略)初詣の近代史を研究してきた筆者は、「『伝統』というものは、ずいぶんインスタントに定着するものなのだなぁ」という感想を抱いてしまう。」
「伝統」とか言い出したら眉唾モノだなと思った方が良いという思いを新たにした。