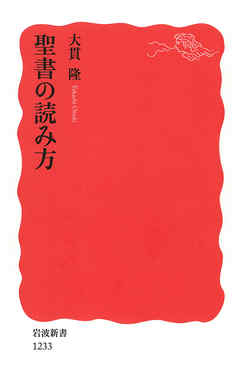あらすじ
「聖書は信仰をもつ人が読むものだ」。世界一のベストセラーとは聞いても、どこか近寄りがたさを感じてしまう書物『聖書』。本書はその聖書を、広く人びとに開かれた一冊の本として読む案内書である。特定の教派によらず、自主独立で読む。聖書学者である著者が、自身の経験と思索をもとに提案する「わかる読み方」。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
聖書入門は様々な形がある。聖書の概略を記したり、時代背景に焦点を当てたり、聖書の成立そのものを説くものもある。本書は聖書の有名な箇所を紹介して聖書の世界へと招く入門書とは一線を画す本である。むしろ本書が企図しているのは様々な形で聖書を読もうとしたけれども挫折したという経験がある人のための入門書である。しかし読み了わって気が付くことは本書が優れて聖書学的な見地に立って聖書への案内をしていることである。
教会で語られる聖書の内容から離れて、虚心坦懐に聖書に向き合おうとする読者にとって、何の手掛かりもなしに聖書を通読することは躓きの種である。その躓きの原因がどこにあるのかを本書は明らかにしている。聖書は様々な文章の集合体であり様々な書き手が様々な場面に応じて書き記したものが集められたものなのである。しかしそれぞれの文章にはまとまりがあるのでそのまとまりに注目して読み進めることが必要であることを本書は説いている。そのまとまりは旧約聖書に至っては数百年の歴史を扱うものでさえある。新約聖書ではそれぞれの記者の意図するところを読み解くことが重要になってくるのである。
著者の『イエスという経験』は聖書を学問的に読み解くことを通してその文字の奥に見出されるイエスの姿に肉迫しようとするものであり、聖書学研究の豊かな成果を生き生きと伝えてくれるものである。それに対して本書は聖書を読むときに抵抗があるとすればどこに抵抗があるのかに着目している。その叙述は時に聖書のことを知ろうと思って本書を手に取る読者を当惑させる記述もあるかもしれない。しかし聖書を読み進める中で感じる違和感の一つひとつに読者が本当に聖書を読み解くことへの招きがあることを知らせてくれる本なのである。聖書に対する過度な期待や思い込みを退けながらも、聖書の中に広がる豊かな世界を垣間見させてくれる一冊と言える。
『イエスという経験』で詳しく取り上げられることでもあるのだが、本書ではキリスト教の使徒信条が「基本文法」として取り上げられ、その「基本文法」を手掛かりに聖書を理解することが提案される。それぞれの文書が使徒信条のどの部分に焦点を当てた文書であるのかを意識することが、それぞれの文書の理解を深めさせてくれ、その成立の経緯やそれぞれの聖書記者の苦悩をさえ感じさせてくれるのではないかというのである。そのこと、つまり「基本文法」に照らして聖書を読むことが前著より簡潔にくっきりと提示されており、その意味で新約聖書学への案内ともなっているのである。本書の最後の部分の「聖書の読書案内」は外典をも含めた聖書の一つ一つの文書への案内となっており、それぞれの文書の要約に留まらず、生き生きとその内容を伝えてくれるものである。
本書は読者を選ぶかもしれない。『イエスという経験』を読んで本書を読む読者はそれほどの抵抗を覚えることはないと思う。しかし聖書を読んで躓いた人々の声を拾い上げてそれに答えようとする本書は、聖書を金科玉条のごとくに読む態度から離れて、書かれている内容への違和感を解きほぐすことを通して聖書のそれぞれの文書の書き手の想いを聞き分けることを促しているのである。
Posted by ブクログ
キリスト教、ユダヤ教、イスラム教などの、中近東の文化に触れていないと、
聖書を読んでも理解できないかもしれない。
日本人の多くが、聖書を読む前に、準備運動として読むと、理解するきっかけが生まれるかもしれない。
子どもの頃から、聖書は読んでいたが、本書は大人になって、聖書を読み直すきっかけになった。
Posted by ブクログ
読み応えのある本だった。私は子供の頃、教会に通ったこともあるし、近親者にキリスト教の信者もいる。信者ではないが、キリスト教は宗教として身近な存在であるであることは確かだ。クリスマスしかり。この本の中で、著者は「聖書」を「全て正しいことを書いてある本」として盲目的に受動的に読むのではなく、能動的に一つの書物として読むべきである、と主張している。中でも私が印象的であったのは、「声」それも「多声性(ポリフォニー)」ということについて書かれていたことだ。「多声性」が個々に十分に認識されることが「交響性(シュンフォニー)」となり、「一体性」となる、というくだりが一番心に残る。
Posted by ブクログ
聖書はなぜ読みにくいのか。そもそも通読を前提として作られていない。文書ごとに読んでいけばよい。特定の教派の読み方に縛られる必要はない。
聖書の基本事項が分かりやすくまとめられている。
Posted by ブクログ
宗教書というのは、仏典でも聖書でもそうですが、怪しい。って思いませんか?
科学万能の時代ですよ? どうしてもあら捜しの対象となったり、「あり得ない」奇跡の内容に、白けてしまったり、信者ってこれを100%信じているの?みたいに思ったりしませんか?
世界の約3割が信じるというキリスト教にあっても、「聖書の一字一句すべてが神の霊感によって書き表されています」とか言う人を見ると、あ、違う世界の人なんだ、いい人かもしれないけど、まあ分かり合えることはあるまい、とか、自分から扉を閉めたくもなります。
にもかかわらず、やっぱり気になります。
非現実的とか、話の筋に統一感がかけているとか、現代科学と矛盾しているとか。そういう齟齬は信者だってきっと感じているんではないのかな、と。実際の信者はどうやって聖典と現実を調停しているのか。
そうした疑問に答えてくれるのが本書。
そのものズバリのタイトルですが、どうやって聖書を読むか、という話です。
現実的な感覚でおかしい、あり得ない、的な部分をじっくり受け止めて答えを出してくれる本です。
・・・
構成は結構シンプルです。
第一章で、学生から集めたという聖書の分からなさ、不明点、読みづらいところを紹介し、聖書学者として解説しています。
第二章では、言わば聖書の解釈学ですが、どのように『読む』べきかを解説しており、これが非常に役に立ちました。セクションの見出しを紹介しますと、
1.キリスト教という電車
2.目次を無視して文章ごとに読む
3.異質なものを尊重し、その「心」を読む
4.当事者の労苦と経験に肉薄する
5.即答を求めない。真の経験は遅れてやってくる
とあります。
なかでも、1.にあった「基本文法」説は面白かった。これは新約の話なのですが、神の先在からキリストの受肉、・・・再臨・終末、とキリスト教のストーリの「流れ」を12に区分し、各福音書や文章がその一部を強調していたり、細部が異なる同類のストーリがやはり「基本文法」に沿っていることで、読者が統一感を感じられるというもの。
また4.も興味深かったです。これは言わば聖書の「行間を読む」ということを勧めているのかもしれません。聖書とは弟子たちの残した言行録であり、その直弟子たちの個別の経験と反省、あるいは歴史的背景があって書かれています。あるいはその筆者のバックグラウンドがあって書かれているとするものです。いつ頃書かれたのかとか、真の筆者の生きた時代などを大まかに特定することで聖書の記述の意味合いを浮き彫りにします。
そして最後の5も含蓄があり良かった。聖書の読みづらいところ、これを「躓き」ととらえ、そここそが読者にとって問題があるところ、という理解です。とくに新約は一般的な道徳倫理的な話も多いわけですが、個人的にいまいち納得しかねるところもあろうかと思います。そうした倫理がイエスによって叫ばれた理由・時代背景などを考えてみることは、新たな自己認識につながると思います。
・・・
そのほか、第三章で、外伝を含め、まとまりごとに概要をサマってくださっています。
この章は聖書そのものに格闘するときにきっと役に立つはずだと思います。
・・・
ということで聖書の読み方、という本でした。
聖書そのものに挑む前、挑んでいるとき、挑んだ後の再読、どのタイミングでも役に立つ書籍だと思います。
私も来月くらい、本書を頼りに、聖書そのものに挑んてみたいと思います。
Posted by ブクログ
聖書は読みにくい。
私は旧約聖書も新約聖書も頭から読もうとして、それぞれ出エジプトと使徒行伝で挫折しました。
別にキリスト教徒というわけではなく、文学理解の補助線として読んだので、何とか通読できた創世記や四福音書でさえ、かなり苦行だった覚えがあります。
本書の第一部では、学生アンケートをもとに聖書の読みにくさを整理しているのですが、共感すること頻りでした。
聖書を読むのに挫折した人が読めば、あるあるばかりでしょう。
第二部、第三部は、そもそも読み通せない聖書を読むための考え方や聖書の成立などについての解説。
キリスト教徒視点よりも研究者視点の方が強いので、信者でない人にとって神父や牧師の説教集よりは読みやすいと思います。
聖書は分かりにくい。だから分かりたいという人のための補助線としての本です。
読みにくい聖書が急に読みやすくなったりはしないので、悪しからず。
Posted by ブクログ
想像していた以上に良かった。
題名的に初心者向けに書いてある様に思ってしまうけれど、実際にはある程度聖書を読んで少なくとも聖書物語で筋が追える位でないとここに書かれている内容をしっかりと理解するには難しいと思う。
この本を読みながら思いを強くした。是非とも「聖書を読まずに聖書に強くなる講座」を開催したいと。
Posted by ブクログ
本書の主な対象者は,「聖書は読みづらい」というテーマに思うところがある,さらにいうなら聖書を読もうとして挫折した人々だと思う。Ⅱ章「聖書をどう読むか」からが本書の本領発揮で,ここでの解説はむしろ精読へのポイントというくらいには詳しい(なので読んだことがない人には厳しい)。
Posted by ブクログ
ヨハネによる福音書、五・六章入れ替えた方が自然
>W・イーザーの「行為としての読書――美的作用の理論」(田収訳、岩波書店、一九八二年)が大変参考になる。これは文学作品を著者がそれに仕組んでいる戦略の側面からと同時に、その作品を初めから終りに向かって読んでいく読者の読み行為の側面からも分析する研究である。
本文の前での新しい自己理解(P・リクール)
Posted by ブクログ
聖書はなぜ読みにくいのか、という問いを立て、答えていく。
第一に単独で通読して理解できるように作っていない。預言書は複数のテキストを貼り合わせたものだから時代の違う記述が途中で混ざってくる。長いものを先に、短いものを後に配列しているので、文脈が異なる。
第二に、神を主語にして書いてあるから、なじみのない人には意味がわからない。
第三に、キリスト教会の伝統的な読み方が一般の人にも影響しており、それ以外の読み方をするべきではないという規範になってしまっている。
聖書は自分本位に読むとよい。そうすることで、自己と世界を新しく了解することができよう。
「真の経験は遅れてやってくる。」
Posted by ブクログ
聖書に挑戦しようとする読者が疑問に思う点、躓く点と、その原因の分析から始まり、聖書への向き合い方を提示する一冊。
この本を読んで、聖書読破に挑戦してみたいと思った。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
聖書は信仰をもつ人だけが読むものなのか?本書は聖書を、広く人びとに開かれた書物として読むための入門書である。
特定の教派によらず、自主独立で読む。
聖書学者の著者が、自身の経験と思索をもとに提案する「わかる読み方」。
キリスト教に関心がある人はもちろん、西洋思想を学ぶ人にも格好の手引きとなる。
[ 目次 ]
1 聖書の読みづらさ―青年たちの声と私の経験(「正典」と「古典」であるがゆえの宿命;聖書そのものの文書配列の不自然;異質な古代的世界像;神の行動の不可解)
2 聖書をどう読むか―私の提案(キリスト教という名の電車―降りる勇気と乗る勇気;目次を無視して、文書ごとに読む;異質なものを尊重し、その「心」を読む;当事者の労苦と経験に肉薄する;即答を求めない。真の経験は遅れてやってくる)
3 聖書の読書案内(旧約聖書;新約聖書;グノーシス主義文書)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
世界最大のベストセラーである聖書。世界中のあらゆる言語で翻訳されている聖書。けれど、聖職者や研究者を除いて、この書物を通読したことのある人が、いったいどれだけいるでしょう?
本書は聖書の内容を解説したものではなく、聖書がなぜこれほどまでに読みにくいかということを解き明かし、そして、この読みにくい書物を読むには、どうすれば良いかという手ほどきを記したものです。聖書に関する本としては、ちょっと視点がかわっていて、とても興味深い内容でした。
Posted by ブクログ
聖書は「神が主語」である・・・がわかりやすい。
対してグノーシスは「人が主語」となる。
入門の入門書。最後の参考文献はいらないかも。全体としてもっと「読み方」についての量を増やしてほしかった。学生への「読みづらさ」調査もいらないかも。
Posted by ブクログ
「聖書の面白さを得々として謳う入門書や概説書は枚挙に暇がない。本書はそれとは逆の道を行く。聖書の読みづらさにすでにつまずいた経験のある人は、実は無数にいるに違いない。その読みづらさの理由をていねいに解きほぐすことこそ、これから初めて聖書を読もうとしている方々にとっても、もっとも親切な聖書入門になるはずである。」(「あとがき」 p. 208)
とある通り、よくある「入門書」とは違って、
読みにくく感じることが当然であって、
どうしてそう感じるのか、
どう考えれば、もっと読みやすくなるのか、
といった視点で書かれている。
この本でいう「読み方」というのは大部分、態度の話で、
実際の解釈の仕方という点では参考文献をあげるに留まっている。
全体的に、非クリスチャン向けに書かれているが、
クリスチャンの方にも読んで頂きたい。
内輪では当たり前となっていて、疑問すら抱かないことが、
外からはどう映るのか、また、そういった人たちと、
どう聖書を読んでいくべきなのか、という点で参考になると思う。
Posted by ブクログ
聖書を読む前の導入本みたいな本。
でも、聖書を全く読まない状態で見るんじゃなくて、ちょっと見てみた後「意味わかんない!」って思った後に読むのがいい。
いろいろ共感できて、おもしろかった。
聖書がよくわからなくて嫌いになった、大学のキリスト教学受講当時にこの本を読みたかった…。
Posted by ブクログ
聖書という大いなる山に挑んでるので、自分を鼓舞するために購入。冒頭のアンケートは面白おかしく読めるが、そこで示された疑問に回答しきれているかというとやや難しい。非信者でも納得のいく回答がもう少し欲しかった。
ただ3章の読書案内は有用で、各翻訳の特徴、有用な注釈書などが逐次書いてあるので是非とも利用したい。
読み方の本というより「聖書ってなんでこうなの?」に答える本なので、聖書読破に躓いてる人はこちらでなくてもいい気はする。それより自分自身が感じたツッコミ、疑問、解釈をAIに聞いた方がまだ聖書を読み進められると思う。
Posted by ブクログ
聖書の読み難さの分析から始まって、聖書が前提とする基本的な視点・視座の解説、実際に読むときの心構え、そして各書の簡単な解説。
もう少し具体的な基礎知識を解説したものかと思ったのだけど、それよりもう一歩前段階の内容が多い。
とはいえ内容が薄いわけではなく、聖書を読もうとする人が挫折しやすいところを丁寧に押さえている。
Posted by ブクログ
あるグループの中で語られる言葉は、そのグループで共有されている「基本文法」があってはじめて理解できるもの。
その基本文法は言い換えれば「自分なりの根拠」に過ぎない。
だから、誰かに自分の信じるものを理解してほしいなら、その誰かが「基本文法」を共有していないことを前提に、どう表現したら伝わるかを工夫しなければいけない。
本のメインテーマの聖書についてより、キリスト教徒がキリスト教徒でない人にキリスト教について話をする時の心構えが響いた。これってあらゆることに言えるよ。
Posted by ブクログ
聖書の初読者がつまずくことになるさまざまな原因を、著者の授業でおこなわれたアンケートの結果にもとづいて紹介し、聖書の読みづらさがなにに起因するのか、そして、読みづらさを乗り越えていくためにはどのような読みかたをすることが必要なのかといったテーマをあつかっている本です。
「聖書の読みづらさ」に正面から向きあうというスタンスで書かれた聖書の入門書であり、ねらいはたいへん興味深いと感じました。ただじっさいに読んでみると、聖書の読みづらさを克服していくための具体的な議論には乏しいという印象があります。それぞれの問題に対して専門家の立場からどのように答えられるのかということについてのあまり立ち入った説明はなされておらず、聖書を読むにあたって読者に求められる基本的なスタンスを簡潔に紹介することに終始しているように思えます。
立ち入った説明は他の聖書の入門書に譲るということなのかもしれませんが、個人的にはもうすこし内容に関する具体的な説明がほしかったように思います。
Posted by ブクログ
なぜ聖書は読みにくいのか、という問いに対して、聖書の構造を分析しながら解説している。特定の教派による偏った読み方ではなく、自主独立で読むためにはどうしたらよいか。目次順に通読しても難解だし、かといって拾い読みでは理解したことにならない。個々の文書の集合体である聖書は、目次を気にせず文書ごとに読むのが良い。聖書の内容の紹介ではなく、あくまでも“読み方”の手引きなので全くの初心者には不向きかも。自分も初心者だけど、先に読んだ日本文芸社『面白いほどよくわかる聖書のすべて』で得た知識がかなり役立った。
Posted by ブクログ
「人間は神によって造られたもの」というのは、「いのち」が人間の勝手になるものではない、ということを意味している。人間は自分の髪の毛一本でさえ、白くも黒くもできない。自分のいのちさえ自分にとって「他者」である。創造主である神は、その超越的な根拠、言わば「絶対他者」である。
Posted by ブクログ
学生たちが答えているアンケートの疑問とまったく同じように、聖書に対してどうも考え方になじめない。少しは読み方に対して理解はできたけど、どうしてもキリスト教や聖書に対して考え方が固いという印象をぬぐえない…
Posted by ブクログ
学生たちが聖書を読む際に抱く素朴な疑問を出発点として、なぜ聖書は読みづらいのかという考察を通し、聖書をどう読むか提示する本。目次通りにいけば。
Ⅰ部の学生の疑問については回答というよりはこういった疑問があげられているんですよーっと取り上げるだけにとどまり、Ⅱ部の提案についても散漫で聖書をどう読むかという提案の印象は薄く、さらに三部に詰め込まれた読書案内も相まってなんだかごちゃついた感じの本。
取り上げる質問の数や、提案の数を絞ってスッキリさせた方が、もっと伝わりやすかったんじゃないのかなーっつー。
簡単にいえば、聖書はもともとバラバラの文書のアンソロジー(しかもバージョンによって順番ちがう)だから通読するようにできてない。つーわけで読みたい文書ごとに読めばいいし、文書ごとに作者ちがうんだから違和感バリバリ当たり前。わかんねーとこあってもそのうちわかることもあるから無理に納得しようとせずそのままの気持ちを大事に。後、なんつっても何千年も前の外国の、しかも信仰の書だから、聖書学の研究も踏まえると捗るよ、ってなカンジ。
Posted by ブクログ
聖書を読む際の道標になる本。系統だてての解説は解りやすかった。宗教としての読む方ではなく、書物としての解釈の仕方は客観性に富み、納得のいくものだった。
Posted by ブクログ
なぜ聖書が読みにくいのか、という理由を、アンケート結果をもとに整理し、読みにくさの理由や克服の方法などを聖書学の見地から教えてくれる本。旧約聖書、新約聖書、グノーシス主義文書に含まれるそれぞれの文献の案内もある。
キリスト教の信者であるなしに関わらず、宗教的な記述をどのように「自己規制から解き放って、それぞれ自主的に聖書を読む(p.9)」か、ということがメインテーマで、聖書がどのような思考の枠組み、「基本文法」で書かれているかという点が解説されている。さらに、聖書だって神によって書かれたものではなく、人間の手で書かれたものであり、一般の書物と同じように読むことが大事であると説かれている。特に印象的な部分は、「人間は神によって造られたもの」という記述をどう解釈するか、という点で、創世記の創造神話やキリストの復活が非科学的であると退けてしまうことが、いかに稚拙なことか、という点に共感を覚えた。それに、「読者の常識に照らして違和感を呼び起こすところ、意味不明、異質で読みづらいと感じられるところ」こそ「本文の前での新しい自己了解」が得られる(p.149)、や「真の経験は遅れてやってくる」、「周縁ではなく中心に躓かない」といった部分がとても印象的で、他者理解の姿勢、読書の方法などにも役立つと思う。(10/06/12)
Posted by ブクログ
読むのが難しい聖書を、「どういう気構えで」読むか。ということを提案している本であって、聖書読破の詳細なガイド本というわけではない。
聖書の「読みにくさ」の原因を丁寧に解き明かすことにより、その部分に「いかなる気持ちで挑むか」、聖書に入る前段階からの下準備をさせてくれる。また、聖書の構造を丁寧に説明することで、そもそも聖書とはどういう書物なのかという基礎的な知識を教えてくれることは意味があると思う。
ただ、ではこの本を読めば一度は挫折した聖書がスラスラ読めるかというと、そういうわけではない。「この部分を記述した人々の苦難を理解し」「書き手の経験に踏み込む」といった読み方を提示しているが、具体的に該当の章が書かれた時代背景が詳細に説明されているわけではないから、読み手がそれを実行しようと思えば、結局は他の資料を当たって知識を仕入れるなりの努力が必要になるのではないか、と思う。
聖書が読みにくい理由については、頷けるものもあれば、個人的には首を傾げたくなるものもあるが、そうした点も含めて改めて読破に挑戦する際の心境の整理には役立つだろう。
聖書の一部分だけを取り上げ、聖書はこんなに面白い、だから読みましょうと安易に薦めるだけではなく、読みづらさを踏まえた上での視点は誠実であると思う。