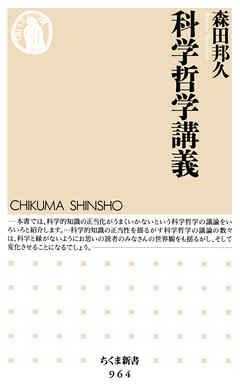あらすじ
「日はまた昇らない」──そんなはずはないと思われるでしょう。我々は毎朝「日は昇る」という知識を得て、日が昇ることを正当化しているからです。でもそんな推論がうまくいかないことを教えてくれるのが科学哲学。我々の見ている世界のあり方をがらりと変えてしまう科学哲学は、科学哲学者と科学者だけのものではないのです。科学的知識の確実性が問われているいま、科学の正しさを支えているものとは何か、真の科学的思考とは何かを根底から問い直す、哲学入門講義の決定版。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本屋で見かけて衝動買い。「分析哲学講義」といい、新書は哲学ブームなのでしょうか。科学哲学における幅広いテーマについて解説していき、最後に筆者の考える科学と疑似科学の線引き基準を解説しています。
これまで知っていた基準と違うので参考となりました。
Posted by ブクログ
科学的とは何か、を改めて考える良い機会になった。5章「研究プログラムの選択基準は発展性」と6章「科学と疑似科学の対比」が特に面白かった。ただ、構成に嫌らしいところがある。というのは前の方で述べた事柄について「あれは実は前提がおかしくて...」のように混ぜ返すことが度々あったので。理解を促進するための具体例も、簡単にしすぎたのか曖昧なのか、いまいちピンと来ないものが多かった(物理学の歴史に関する例は除く)。
Posted by ブクログ
科学と哲学って言葉の組合せって何かあわないような気が最初はしました。物理化学や生物物理なんて言葉の組み合わせとはちょっと違いますよね。でも読み終えると、スッと理解できた様な気がします。なるほどね、科学とそうじゃないものをキッチリと区別できるルールがあるんだ。
このルールを理解すると、誇大広告や詐欺、インチキ占い師に引っかからない、冷静でクールな人間になれたような気がします。
でも、好きな女の人の前では、すっかり忘れちゃうんでしょうね。
Posted by ブクログ
そもそも科学って何だっけというところからの出発。比較的平易に伝えようという著者の優しさは伝わってくるが、それでもところどころ議論が難しくてついていけない。が、それはこの本において特に大きな問題ではない。多かれ少なかれ難しい議論への理解には限界があるのであり、むしろそういうなかでどれだけ学べるかが重要なのだ。
という言い訳?を述べつつ、著者の言いたいことは第6章にまとめてあるので、何だか分かった気になれるのは嬉しいものです。
「科学的知識に正当性を与えるのは難しい」(第1~3章)。そしてその科学において実は「合理的な基準などなく、結局のところ、科学と他の知識体系の区別はできないのではないかという疑念」(第4、5章)が生まれた挙句、最後もやはり「科学的知識が正しいとする保証はありません」で締めるあたり、舌足らずだけど、何だかすごいなあという言葉しか出て来ない。
それでもやはり素人的に見て「科学」を大きく特徴づけているのは、というか科学への信頼を担保しているのは、その反証可能性にあるのだと思う。つまり、自分なりに解釈すれば、常にある命題(理論)が間違っているあるいは覆される可能性を確保しているところだ(その反証可能性主義にも批判があるというのだから哲学の議論は奥が深すぎてちょっとついていけない)。
ハイライトは第2章の因果関係の議論から始まり、第3章の量子力学の解釈あたり。原子の位置について、「現在の状態は、過去と未来の両方から決められている可能性がある」という解釈は、何ともロマンがある話だなあと思いました。勉強としての理科(物理)は何だか嫌いだったが、このように講義として聞く分には面白い。
Posted by ブクログ
野家氏による科学哲学入門書『科学哲学への招待』と比べるのはやや酷かもしれないが、凡庸という印象。トピックはある程度網羅されているし説明もわかりやすいのだが、上位互換の入門書があることだし…という感じ。新書なので安いのが利点。
Posted by ブクログ
科学的根拠とか科学的説明といったとき、それは客観的に正しい主張であるという意味が含まれていると思います。
物理を学んでいるうちに、物理学は「タダシイ」と思われているらしいけど、正しいってなんだ?と思いこの本を取りました。
僕らはある主張についてそれは科学的か非科学的か日々なんとなく判断しているわけなので、科学的な主張にはなんらかの構造、型があってそれを知っているはずです。するとそれらを具体的に知りたくなるわけです。
そういう期待で読んで、扱っている内容自体はこの期待に沿って書かれていました。
内容ですが、
法則性、因果性、道具主義、量子力学の解釈、パラダイム論等、多岐にわたって「ざっくり」書かれてあります。これだけたくさんの見解を一冊にまとめているわけですのでそれぞれの話題で説明に不満が残るのは当然でしょう。科学哲学の様々な見解を知るためには良い本です。
ある命題について、それが科学的である根拠と同時に科学的とはいえない根拠を提示し、結論としてどちらともいわずに終わる。という感じで繰り返して進んでいきます。読んでいていもやもや感が残る本ですね。
一番興味をそそったのは、エントロピーを切り口に僕達が未来についての記憶を持っていないことを説明を試みているところでした。
Posted by ブクログ
科学哲学入門ということだけど,ちょっと平凡すぎて退屈かも。初めて読むなら戸田山和久『科学哲学の冒険』,もっとじっくりなら内井惣七『科学哲学入門』,擬似科学との線引問題に興味があれば伊勢田哲治『疑似科学と科学の哲学』がおすすめ。
ただ,実在論vs非実在論のとことか,科学哲学って科学の側から見るとだいぶ周回遅れみたいなところがあって,このへんは好き嫌いが別れそう。何が科学で何が非科学か,という線引問題は素朴に面白いけれど,本書では分量の都合であまり深く論じられていないのが残念。
Posted by ブクログ
中身はともあれ,語り口でもっとわかりやすくなる気もする.
ただ,入門としてはいい本だと思う.
ここで出てくる哲学を更に深めていければ,科学に対する考えが深まるんじゃないかな.