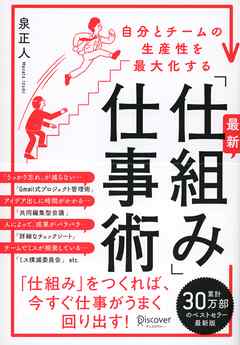あらすじ
威力抜群!明日からオフィスで使える「仕組み」の例が満載!
○「うっかり忘れ」が減らない→「Gmail式プロジェクト管理術」
○アイデア出しに時間がかかる→「共同編集型会議」
○人によって、成果がバラバラ→最強の「チェックシート」
○チームでミスが頻発している…→「ミス撲滅委員会」 etc.
最近、国を挙げて「働き方改革」の実現が目指されるようになっています。
これまで見られたような、多少残業をしてでも仕事を終わらせるべき、といった価値観ではなく、「いかに残業を減らし、生産性を上げられるか」が求められています。
しかし、気合いと根性だけで一時的な成果を上げることに成功したとしても、それだけでは長続きしません。逆にそれで身体を壊してしまっては、元も子もないでしょう。
では、どうすればいいか?――本書でおすすめするのは、「自分が働かなくてもいい仕事は、『仕組み』に働かせる」という考え方です。
仕事に「仕組み」を取り入れることで得られるもの
――それは、毎日定時に帰ることができ、自由な時間が増え、さらに年収も増えるといういいことずくめの世界です。
今こそ、増えつづける一方の仕事を見直し、「仕組み」を最大限に取り入れる「究極の仕事術」を身につけましょう!
「仕組み化」の5つのメリット
1. 時間が得られる
2. ミスがなくなる
3. 人に仕事をまかせられる
4. 最小の労力で最大の成果が出せる
5. 自分とチームが成長し続けられる
こんな方に、「仕組み」仕事術をおすすめします!
□ つねに作業に追われている
□ 同じミスを何度も繰り返してしまう
□ 仕事を人に振れず、いつも一人で抱え込んでいる
□ 効率が悪くても、いつものやり方でやってしまう
□ 自分もチームも、そろそろ次のステージに進みたい
□ 育児や介護などでフルタイムから時短勤務になった
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
これらの発想を取り入れるのは良さげと感じた。
・才能に頼らない
・STAGEフレームワークで強み可視化
・チェックシートどうやって作る?
・定型化して人に任せる
Posted by ブクログ
仕事メールが多いなど筆者と似た状況なので、受信トレイをToDoリスト化などは、ルールを決めて取り入れたい。マニュアルもよく作るけど、チェクシート(アイテムと詳細にわける)で一覧も分かりやすそう。強み発見シートも、スキルの見える化で、いいと思った。360度評価で作るのがよいかな。
Posted by ブクログ
どうやって自分にあったしくみを作るのか。同時に、組織にあったしくみをつくるのか。
Googleなのか、別のツールなのか、これからも考え続けたい。
Posted by ブクログ
仕組みの大切さを改めて実感できた本でした。
良いと思った点3つ
◎ 記憶に頼らない、全く初めてする人でもできるように考える、など普段から私が意識していることが書いてあり確証が持てた
◎ gmailや他のアプリなど普段使っているアプリで、まだまだ工夫できるところがあると知れて良かった
◎ 『自由を得るため』という作者さんのコンセプトに共感が持てた
Posted by ブクログ
旧版も読んでおり、ルーチンワークの朝処理やメールの即断即決などは実行していましたが、最新版ではgmailのスーパースター機能の活用等、手法がアップデートされていて参考になりました。
1番参考になったのは7×5のフレームワークについて。レベルを表す5段階は高校や大学で急速に普及するルーブリックにも似ており、若い社員にも理解しやすいのでは、と思いました。
一方、共同編集の活用は、教育現場の方が進んでいると思います(4年前の本だから比較するのがおかしい?)。jamboard等の共同編集では、誰が書いたかわかるよう加筆箇所の横に付箋で名前を貼る、人ごとに色を変える等の工夫が小学生でも行うようになっており,場面により本の手法とそうした工夫との併用が重要と感じました。
Posted by ブクログ
メールを活用してやることリストに。
launcherアプリを活用して効率化。
過去の成功体験を蓄積。
仕組みが機能する仕組みを作ろう。
メールアプリは使いこなそう。
使えるシステムは使う!
Posted by ブクログ
著者の本は10年以上前に読んだことがあり、それ以来、才能に頼らずに誰でも仕事を行えるよう仕組み化するよう取り組んできた。本書で目新しい内容は無かったが、要点を思い出させてくれた。
Posted by ブクログ
グーグルベース。ショートカットキー覚える。後で触るメールにはフラグを立てる。それ以外はボックスへ。返信時に件名を変えない。ラベルは変えるのかな。日付6桁。内容とゴールのわかる件名。タスクを行動レベルに分解。ルーチンワークは優先順位を考えない。メールサーチを使う???日時が確定したらカレンダーに記入、時間をブロックする必要があるかで決める。緊急度が低いものをToDoに。タブ設定はひらがな、ほかで使わない言葉にしておく。
共同編集を使った会議。その場で確定できる。
成功体験、場所、時間、ツール、人。ルーチン。記録する。うまくいっている人のまねをする。時給で判断する。外部圧力を使った仕組み。
Posted by ブクログ
自分はずっと意識してやっていることばかりだったので新しい発見はなかったが、
そうそう!と頷いて読んだ。
仕事の基本だと思うんだけど、
この仕組みづくりの大切さが分かってないダメ上司やダメ同僚によく読んで欲しいですね。
Posted by ブクログ
飛ばし読みで十分。
・仕組みとは再現可能なシステム。
・仕組み化は効率化だけでなく、ミスが減る。
・仕組みを作れば人に仕事を任せられる。
・仕組みは、いつ誰がやっても同じ成果が出るシステム。
・仕組み化の3つの黄金ルールは、才能に頼らない、意思に頼らない、記憶力に頼らない、の3つ。
・ザックリしたタスクは行動レベルに分解する。
・記憶せずに記録する。
Posted by ブクログ
Gmail活用事例多く,Redmineを仕事で利用していると一部対象外な内容か.
ただ,後輩に引き継ぐさいに,口頭で伝えるのはNG,次の世代での引き継ぎも口頭となり伝える側と伝えられる側に必ず二重に工数がかかるという内容は非常に納得.自分はできていない内容で,新人が読んでも理解できるようなマニュアルを作ったほうがマニュアル作成時はそこそこ工数がかかるが将来を見ると絶対こちらの方が工数削減できる.
Posted by ブクログ
自分とチームの生産性を最大化する 最新「仕組み」仕事術2017/4/20 著:泉 正人
仕事に「仕組み」を取り入れることで仕事量と労働時間を減らしつつも、安定した成果を上げることを提唱した前作の「仕組み仕事術」が刊行されたのは約10年前の2008年のこと。「仕組み」という言葉も市民権を得て、ビジネスシーンで当たり前のように使われるようになった。最近では「仕組み」という言葉は、「生産性」という言葉に置き換わり、世の中の関心を集めている。
生産性の向上は、労働人口が核に減る日本の至上命題となっている。「仕組み」を使って生産性を上げることは、仕事で成果を出すという前向きな理由だけではなく、自衛手段としてもその重要性が増している。
本書の構成は以下の6章から成る。
①なぜ仕事に「仕組み」が必要なのか
②時間をつくるための「仕組み」
③ミスをなくすための「仕組み」
④人に仕事をまかせるための「仕組み」
⑤最小の労力で最大の成果を出すための「仕組み」
⑥成長し続けるための「仕組み」
10年前の前作を読んで衝撃を受けた。
「仕組み」という言葉の印象は、効率的であり有用であるもどこか無機質で要領をかますというマイナスなイメージを受け取るものでもあった。しかし、十分に理解し、現状に合わせてつかうことでそれはどの概念よりも実務に活きるモノとなった。
全てを「仕組み化」することはできないし、するべきことではない。しかし、全体を把握し過去と現在、未来を意識してその考えを取り入れること。取り入れようとすることは大切である。
注意しないといけないのは、既存の仕組みが全て正しいと思い、タダ乗りを繰り返し、その意味を考えずロボットのように行うことなのかもしれない。仕組の先にあるものは、効率よく仕事を行い捻出した時間で「仕組み」ではできないような、人間本来の考えが必要な知識と知恵をフル活用した仕事に充てるためという側面を忘れてはいけない。
時代も変わり、既に仕組化されつつある自分たちの業務。
疑問を抱き、さらに良い仕組を模索し、そして次にいく。
そんな繰り返しで効率を学び、仕事力もレベルアップしていく。