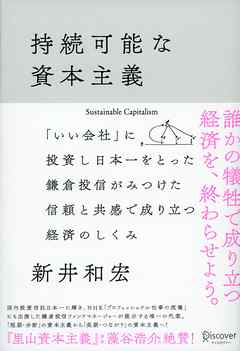あらすじ
誰かの犠牲で成り立つ経済を、終わらせよう。
「利益追求のため無限に効率だけを追求するいまの資本主義に永続性はない」
国内投資信託日本一に輝き、NHK「プロフェッショナル」にも出演した鎌倉投信ファンドマネージャーはそう断言する。
そして、その代案はすでに日本企業が示しているという。
カゴメ・ヤマト・サイボウズ・ツムラ・マザーハウス・ユーグレナ……全国の「いい会社」を直接訪ね、投資する鎌倉投信がみつけた、信頼と共感で成り立つ経済のしくみとは。
「短期・分断」の資本主義から「長期・つながり」の資本主義へ!
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
常に右肩上がりの成長を求めなくてもよい資本主義の在り方はないものなのかと漠然と考えることがあったところ、本書で述べられいる考え方がその解決の一つになり得そうだなと思えた。
効率化はステイクホルダーの分断をもたらし、リターンをお金だけで定義するとステイクホルダーの利益は相反してしまう。客観的基準ではわからない主観的評価をすることによって、地域、社会、国を含めた八方よしの「新日本的経営」を認め、応援することにより全ての関係者が利益を得ることが可能になるという。そんな新日本的経営を行う会社を応援したいなと思わせられる本。このような会社を評価して個人に紹介し、各個人がそれを応援できるような仕組みがもっと必要だと感じた。ふるさと納税の応用バージョンのような形でできないものだろうか。
Posted by ブクログ
二宮尊徳の「三方良し」を投資家目線で現代の日本企業をジャッジしてファンドビジネスするなら「八方良し」を目指す形となった、という内容。
実際に「鎌倉投信」を運営しているのでその信頼度はリアルタイムに結果に出るのでそちらでその都度確認するとして、そのジャッジの方法が「見えざる資産(社風、企業文化、社員力、社員のモチベーション、経営者の資質、社内外に気づかれた信頼、理念に対する共感など)」を「主観」によって独断で決めているというところ。
あと、フローの増加(短期売上)を四半期で追求する企業が増えるほどに社会基盤の破壊行為が横行し、究極的には戦争ビジネスに行き着くという考えに共感する。
破壊と再生のプロセスはストックで見ればプラマイゼロであっても、フローでは再生された分だけ増加する。しかもゼロからであれば伸び率の初速がハンパないわけだ。
そこで著者はこの短期志向へ向かいがちな資本主義に「長期的な最適化(社会基盤を毀損しない)」を念頭に置く「時間軸」を重視するよう主張している。
この辺りの主張は経済学者の宇沢弘文さんの「社会的共通資本」を連想した。SDGsが叫ばれる昨今、この問題意識はとても重要だ。
<八方良し>
①社員良し
②取引先・債権者良し
③株主良し
④顧客良し
⑤地域良し
⑥社会良し
⑦国良し
⑧経営者良し
Posted by ブクログ
印象に残ったところ
・資本主義の鉄則を会計学からみて、「フローの最大化」としている点がわかりやすかった。資本主義はBSとPLからみると、ROEなど一定期間の利益であるPLのフローを重視していることになる。
・フローの増加を目的にすると、「計画的陳腐化」のように、短期間しか持たないものを生産してしまう。破壊して再生するとストックはプラマイゼロ。フローだけ見ると生産高が増加しているため。
・「フローの増加の追求」は短期的最適化。「ストックの増加の追求」は長期的最適化といえる。
=>自分の働き方にも言えるかもしれない、短期的に利益の上がることを優先してやって、長期的にみて必要なスキル向上は後回し。
・CSRとCSV
CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)は、もともとヨーロッパで失業対策のために、起業が雇用を促進するためのものであった。しかしアメリカ輸入時に営利目的以外の寄付やボランティアと解釈されてその後日本に入ってきた。。
CSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)は、ボランティアではなく本業で社会貢献すること。「三方よし」につながる。
・日本の住宅は欧米に比べてサイクル年数が極めて短い。欧米は100年持つのに、日本は20~30年ぐらいでスクラップ&ビルド。
・用語
-貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう):BS(バランスシート)
-損益計算書:(PL:Profit and Loss statement)
-ROE(自己資本利益率:Return of Equity)
Posted by ブクログ
メモ
人の 生きる 世界 も 同じ です。 たとえば、 経営者 が 語る 理念 が どこ か 不自然 な 企業 が あっ た と し ます。 大義 を 掲げ ては いる ものの、 何 か とっ て つけ た よう な 印象が 残る。 そういう 企業 は、 しばらく 経つ と たいてい は 無くなっ て しまい ます。 いくら 壮大 な キャッチ コピー で 飾っ ても、 不自然 な 企業 は 長続き し ない の です。 逆 に、「 いい 会社」 は 理念 が 明確 で、 地 に 足 が 着い て い ます。 そういう 企業 は、 結果的 に 社内外 の 多く の 人 に 支え られ 長く 残っ て いく の でしょ う。
>結局、長期的な目線になれば、自社に関わっている人への提供価値をつきつめることになると思うし、もちろん偏りはあるけど、昔からそうだったと思う。
それを経営者として企業の本質に立ち返って、考えられるかが重要なのかもしれない。
あと、著者のお金の形成と社会の形成、心の形成が重要という考えは納得。
また、日本のNPOにもいいNPOとよくないNPOが出てきているという傾向の話があったが、
企業だけではなく、NPOも変化に晒される時代なので、
きちんと自分たちの事業で付加価値を生み出すことを意識しないと淘汰されてしまうのだろうなあと思った。