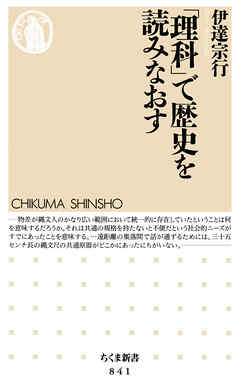あらすじ
歴史を動かしてきたのは、政治や経済だけではない。数学的知識、暦の作り方、冶金技術など広い意味での「理科力」こそ、人間を人間として進歩させてきたものなのだ。縄文時代の天文学、世界最高水準の技術で作られた奈良の大仏、古代日本人の数学的センスがかいまみえる万葉集。ギリシア以来の「アルス」のあり方……。人類の「これまで」と「これから」を理科の視点から眺望する。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
歴史に興味はあるけれど、教科書を読んでも頭になかなか入ってこなかった中高生の時に出会いたかった本。「数字」「鉄」といった具体的で普遍的な事象から歴史を眺めることは、歴史をイメージする手助けとなる。
「理科で歴史を読み直す」には、以下の二つの意味があると私は解釈した。
1.人々が数字や科学をどのように身につけ、利用してきたかをひもとくこと。(自然科学の歴史に焦点を当てる)
2.歴史を自然科学の知識から読み解くこと。(歴史を自然科学を用いて解明する)
もちろん両者は切っても切り離せないものだが、とくに後者のアプローチがこの本のユニークな点だと思った。
歴史研究の中心は文献史料の分析だが、当時のことを完全に理解しようと思えば「書かれていないこと」も知らなくてはならない。それを読み取るために、「理科」の知識はとても役に立つ。
たとえば、鉄が世界史に与えた影響は銅よりもはるかに大きく、火の発見に次ぐほどのものだという(p.77)。そのことを知るためには、鉄の特質を考えることが助けとなる(筆者によると鉄は「知的複合体」)。
昔の人々は、近代科学を持たなかった分、自然の法則を敏感に感じ取り、知識を得ていたはずである。「理科」的思考によって、史料には現れない、当時の人々の見えない行動基準について想いを馳せることも歴史の醍醐味なのだと思った。
Posted by ブクログ
歴史を動かしてきたのは、政治や経済だけではない。
数学的知識、暦の作り方、冶金技術など広い意味での「理科力」こそ、人間を人間として進歩させてきたものだ、という著者の主張です。
特に縄文時代の天文学の記述を知りたくてこの本を読みました。
結果として、世界最高水準の技術で作られた奈良の大仏のことなど、また、新しい情報を得ることができました。
途中、あまり興味がないところは飛ばし読みしてしまいました(笑)。
Posted by ブクログ
読後の感想は、「久々に読み応えのあるちゃんとした新書を読んだなぁ~」というもの。
私が大学生の頃、新書と言えば岩波新書、中公新書、講談社現代新書が御三家で、卒業する頃に集英社などからも出るようになったと思います。当時は今のように各出版社から多数の新書が出ている状況ではなく、一冊一冊がかなり重みのある作品が多く、一般教養書としてとても重宝しておりました。しかし今は粗製乱造というのか、本当に読んで良かったなぁと思う、かつてのような重みのある新書は少なくなった印象を持ちます。そんな印象が多い中、この『「理科」で歴史を読みなおす (ちくま新書)』は私の知的好奇心を心地よくくすぐり、そしてタイトル通り歴史の読み方に別の視点、「理科(=理系的な分析)」を与えてくれます。
縄文人が見ていた夜空の星と、現在の我々が見ている星空が異なるというお話しや、弥生文化との入れ替えなど、興味深いお話から始まり、現在のレア・アース問題もびっくりするような日本の金銀産出とその流出の歴史(全く今考えるともったいない話です・・・)、そして数の話など、とても興味深い話がたくさん出てきます。そしてまた文章も簡潔でわかりやすく、飽きのこない書き方で魅了してくれます。
中でも最終章の「アルスの世界-科学と芸術の接点」は、科学が如何に発展してきたか、そして芸術と科学がどのように分化していったかというところが、科学者としての著者の深い考察の中で示されています。
現在は様々な方面の分野に専門的に分化した時代。しかしかつてはそういった分化したものではなく、“アルス”という知的好奇心を満たす大きな未知の世界の探求があり、芸術的な分野と科学の間を行き来する知の巨人が数多くした時代。それゆえに芸術的とも、科学的ともいえる大きな発展や発明を担うことができたのでしょう。
ネット時代になって、情報が錯綜し、正負入り乱れる情報の海で難破する方も多く見うけられると思います。情報の海に溺れないためにも、ぶれない一つの視座がほしいところです。本当の“知”とはどんなものか、お時間のない方は最終章だけでも読むことを強くお薦めいたします。
Posted by ブクログ
日本語の数表現は多彩。「ひ」「ふ」「み」の和数詞と中国期限の現代数詞が混在する。その現代数詞もよく見ると呉音と漢音が混在する。数の歴史は日本の歴史でもあることに気づいて実に興味深い。
Posted by ブクログ
「理科」で読み直す、というより、「科学的思考」がどのように歴史的遺産等から読み取れるか、というマニアックな歴史読本。
科学的思考の一指標としての数詞に重きをおいている。
目から鱗の内容です。
Posted by ブクログ
著者の専門は物性物理なんだけど,歴史や文化にも造詣が深いらしく,「理科力」で日本史を見てみようという本。科学受容史といったところかな。でも網羅的でなく,話題は断片的。
天文,鉱物史,魔法陣などいろいろだが,著者は特に言語に興味があるらしい。中でも数詞について詳しい。縄文時代など,文字の記録が残っていないから推測になってしまうのだけど,想像をたくましくして当時の数のありかたを描いている。
著者の『極限の科学』が滅法おもしろかったので読んだのだが,さすが年長者だけあって博学。やはり門外漢なわけで,信憑性はいまひとつ。人生の総仕上げとしてざっくばらんに書いてみたという感じだろうか。戦国大名の伊達氏についても記述があったけど,別に祖先だとは言ってなかったな。
Posted by ブクログ
本書は過去の歴史のなかの個別課題を「理科」的視点から取り上げた論考であるが、興味深くおもしろいと感じた。
著者はどれの専門家ではないという。そういう場合、内容がしぼりきれずに拡散してしまう場合が多いのだが、本書では、おもしろくまとめていると感じた。著者の「伊達宗行氏」は仙台生まれで東北大学理学部卒というから、あの「伊達」の眷属なのだろうか。
「縄文の空の下で」の原人前後の内容は、すでに最新の知見ではないと感じたが、縄文や弥生時代についての論考はいろいろと多面的で興味深かった。その道の専門家でない著者の幅広い知識が伺えて、おもしろいと感じた。
「いち、に、さんではじまる現代数詞」についての論考もおもしろかった。数詞の読み方は漢音と呉音が混在しているというのだ。「漢字」というくらいだから、漢の時代のものと漠然と考えていたが、本書によると「仏教は呉音の世界」だそうである。本書はその理由について幅広く考察している。もとより推測なのだが、実におもしろく説得力があると感じた。
「金・銀・銅」についての考察もおもしろかった。「マルコポーロが13世紀に東方見聞録で黄金の国」と紹介したことは有名であるが、日本は歴史時代に黄金をとり尽して、その黄金は海外に流出したというのだ。当時の施政者の見識のなさを非難してもちょっと遅すぎるかとも思った。
ただ、「数遊びの東西」は、多分著者の趣味なのだろう。歴史的な「数遊び」にはあまり興味が持てないと感じた。
筆者は「異分野の交流」を主張している。まとまりがない結論になる場合も多いかとは思うが、本書のように興味深い論考にまとまる場合もあることを思うと、おもしろい提案であると感じた。
Posted by ブクログ
科学と歴史というのは以外に相性が良い。気候の変動や病原菌の突然変異、穀物類の植生等は、それだけで人類の歴史を大いに左右しうるわけで、そういった観点から歴史を読み直すのが、最近はやっているらしい。「銃・病原菌・鉄」など世界的な名著もある。
本書もその流れを汲んでおり、日本の歴史を「理科」的な視点から再構成してみようという試みは非常に立派。実際、それを本職の先生がやれば面白い本ができるのは間違いないと思うのだけれども、本書の場合は著者が物性物理学の先生なので、いわゆる「余技」に過ぎない。余技でも一級品に昇華できていれば良いのだが、いささか消化不良気味でした。