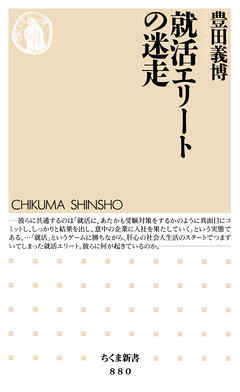あらすじ
エントリーシートを綿密に作りこむ。面接対策をぬかりなく講じる。まるで受験勉強に勤しむような努力をして、超優良企業へと入社していく「就活エリート」。新卒者の勝ち組たる彼らが、いま、多くの職場で、戦力外の烙印を押されている。「スター願望」ともいうべき偏狭なキャリア意識に自縄自縛となり、スタートラインでつまずいているからだ。採用試験では高い評価を得たはずの就活エリートが、なぜ、入社後に迷走するのか? リクルートで長年にわたって就職情報に携わり、採用現場の表と裏を熟知する著者が、就活のあり方と若者のメンタリティを分析する驚愕のレポート。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「求める人材、ってどの社も一緒じゃないか」「なんでキャリアの多様化がい有れている時代なのに、新卒採用は一括なの?卒業してから就活、っていう道がもっと広まるべきだ」
就活をしたことのある人なら、一度はこんな疑問を抱いたことがあると思う。
そんな疑問に、ここ数十年の時代背景の変化を踏まえて著者が分かりやすく解説している。
また「就活エリート」を、そのような疑問を産むことになった現在の就活をめぐる動きに飲み込まれた人として扱っている。
そしてその動きを良い方向に動かすために企業と大学は何ができるか、について述べている。
筆者が大学に課す要求は無茶なところがある(彼は、大学を学問をする場所とはあまり考えていないのだろう)ものの、企業への「採用時期・採用経路の多様化」「今の面接の『主観・非日常』を評価するスタイルへの過度な依存をあらためよ」という提案は的を射ている。
就活を始めたばっかりの人や就活に漠然とした不安のある大学1,2年生に是非読んでもらいたい本。
ちなみにこの本には、リクルート勤務の著者が就活に対して抱いていた想いも描かれている。それを読んでこの著者に好感を抱いた。
Posted by ブクログ
『就活』の問題点を社会学的なアプローチで分析してて、なかなか興味深く読めた。
企業側から出される過剰なエントリーシートや、それに対応するための深い自己分析により、
就活生たちは乏しい社会経験の中から「やりたいこと」を決め付けてしまい、
結果的に雇用のミスマッチ→早期退職といった会社側にデメリットをもたらすとは、なんとも皮肉なもんだ。
最終章にもある通り、就活でも何でも横並び、といった風潮を変えていったほうが、
世の中に多様性が生まれて楽しくなると思うんだけどな。
Posted by ブクログ
「就活の現状とそれに対応したのが就活エリート」
就活と言うゲームにハイスコアを出すのが就活エリート。しかし、あくまで就活だけ。各企業の面接に自分自身をチューニングして面接を勝ち抜いたため、入社してからは、会社と自分のズレが出ているという実態が書かれている。
企業に合わせて内定もらうのではなく、自分に合った企業に入りましょうということ。
就活に疑問を持ったときや、就活のヒントを掴むときに読む一冊。
Posted by ブクログ
就職活動でやりたいことを強く自己暗示することで就活というゲームに勝つことができたにも関わらず、就職した後にズレを感じて辞めてしまう就活エリートが増えている、という話。
空気を読んで相手に合わせるタイプが就活エリートになるらしいから私にはある意味関係ないけど、就活に違和感を感じている人は読んでみると良いと思います。
Posted by ブクログ
本書は硬直した就活における、就活生の現状や行動特性を描いている。
本書によると就活生はその場で面接官の人物を見抜き、その場で人格をつくりあげるという。(注:私はできませんが、何か?)
なぜ若者がこのような行動を取るか、取れるのかという若者論に近いところまで踏み込んで解説している。
また、会社説明会で就活生が涙するという現象も取り上げている。その原因説明会で流すVTRが感動するドラマになってりるためだ。これに対し、筆者はだめなところもきちんと伝えるべきだと主張している。この提案については(実行は難しいが)面白い提案である。
Posted by ブクログ
一言でいえば、何事もほどほどにということですね。就活というのもひとつのゲームと割り切って、ESや面接で言ったことにこだわらないことです。所詮はうそも方便と言うことで、うそをついた自分がだまされてはいけません。
Posted by ブクログ
就職活動における画一的・硬直的な採用制度のせいで一部のエリート(新入)社員は入社後に焦燥感を抱き、他方でエリートになれなかった(と感じ入る)諦観層も生み出している。
Posted by ブクログ
他の就活本と違った視点で、批判だけでもなく、極端に賛成するわけでもない中立的な書き方がよかった。就活する上で、あまりのめり込みすぎるのもよくないというふうに思えた。少し安心するような本だった。
Posted by ブクログ
エントリシートやグループディスカッション、集団面接に数ある個別面接を勝ち抜き、いくつもの内定と希望先企業の内定を確保して入社する「就活エリート」。しかし、彼らは、実際に企業に入ると「自分のやりたかった仕事ではない」「5年後、10年後の自分のキャリアが想像できない」などまさに迷走するという。「この会社であなたがやりたいことは何ですか?」に代表される選考上の質問、エントリーシートの影響とは?
シャインの有名な理論とは、ビジネススクール(大学院生)に対する指針。他にも、いくつかの参考になりそうな著書も示されている。
とはいえ、最後に示されている著者のいくつかの提言は、どれも実際には実現性が困難な事、即効性の難しい事を一番実感しているのもまた著者自身ではないか?とも感じた。
Posted by ブクログ
タイトルの「就活エリート」とは「就活というゲームに勝ちつつも社会人生活のスタートにつまづいてしまう学生」のことをいう。
就活というイベントを通して今までの人生をひとつのストーリーに仕立て上げ、やっとのことで見つけた「やりたいこと」をもって社会人となったこの「就活エリート」たちは、入社後の業務と自分のやりたいこととのギャップに気づき、早期退職をしてしまう、ということを問題としている。
この問題に対し、現在の「就活」の構造を明らかにした上で改善策を提案している。
日本社会の変革や求められる人間性を新卒雇用という観点から書いた面白い本。
Posted by ブクログ
自分もついこの間まで就活紛いのことをしていたので、関心を持って手にとりました。
就活をきちんとこなし、無事に第一志望の企業から内定をもらえたはずの「就活エリート」と呼ばれる大学生。
しかし、入社して間もないうちにその中の決して少なくない数の人が、第一志望だったはずのその会社をやめてしまう事案がおきている。
こうした問題の原因を、現代日本の就職活動の時期や内容から、大学生と企業それぞれの視点を踏まえて分析する。
自分が就活をしていたためか、一定の確信をもってその通りと頷ける内容が多かったように思います。
客観的・非日常の試験(ex.筆記試験)が重視される形式の採用日程だったためある程度の差異はあるものの、周りの人を見ていてもやはり大学生は就活をゲーム感覚でしている人が多いように感じます。
さらに、世代としての特徴分析が的を射ており、述べられている心理に心から共感できます。
就活真っ直中の人や、内定を経て職場勤務を待つ人が立ち止まって振り返る機会として最適な書籍だと思います。
Posted by ブクログ
就職活動において、自分(の物語)を創り上げることが要求されることが多い。
その物語は、過去を誇張して、未来を過剰に描くことで、自分そのままの「現在」と乖離していく。
以前は就職活動において、明確な未来の物語を求めることはなかった。
採用における一種の流行としてこれが始まって拡大・定着した。
この「創り上げる作業(ゲーム)」においてハイスコアを出す人が、内定を多く手に入れる「エリート」となる。
こうして現在・現実と物語は乖離し、「エリート」ならば「エリート」であるほど、
入社後のパフォーマンスは低くなってしまう。
うーむ。。自分は「エリート」ほどでは全然ありませんでしたが、なかなか、じわっと思い当たるものがあるよ。。
Posted by ブクログ
就職活動に特化した「就活エリート」の存在に切り込み、現代日本における「就活」の問題を指摘している。
現在の若者に見られる「スター願望」の問題、面接に偏重した採用活動など、分かりやすく分析されている。
著者の提案する日本のあるべき採用活動には同意する点が多い。
Posted by ブクログ
8年前、就職氷河期、僕は就活の真っ最中にいた。
その時から、今までのキャリアを見ると、
多くがこの本に共感できる部分がある。残念ながら。
ということで、ほんとは5☆だけど -1☆で4☆^^
就職って、結局お見合い方式でいいと言う筆者に僕は賛成。
就活学生必読の本。
Posted by ブクログ
リクルート出身の人でも良いこと言うんだね。
今の「就活」の問題点がよく分かる本でした。変なところだけ欧米式にする日本人の弊害です。教育、企業が一体となって変えなければ現状の問題点を解決するのは難しいと思います。
Posted by ブクログ
この本には大学生の頃に出会いたかった。今の日本の就活についてすごーくわかりやすく書いてくれています。今自分が抱える悩みも有る意味必然なんじゃないかと思います。
Posted by ブクログ
リクルートで長く就職・採用活動に携わってきた著者が、「やりたいことが明確にある」「就活エリート」のその後の迷走を見て、あるべき就職・採用活動について再考している。興味深いが、現在就活中の人は読まないほうがいいかも?(笑)。いやぁ、昔のほうが楽だったように思えてしまうなぁ
Posted by ブクログ
最後の就活改革への提言みたいのはとってつけたようで具体性などにとぼしかったので、そこら辺はページのムダかなとか思ったんだけど。
でも今の就活生やシステムの問題点の分析は鋭い。
Posted by ブクログ
すごい努力をしてせっかく入った会社でも、「思っていた仕事と違う」と感じ辞めてしまう原因が書かれた本。
一番の原因は面接やエントリーシートで必ず問われる「あなたのやりたいことは何ですか」という質問のとらえ方が企業と学生で違うこと。企業はこの質問をしてポテンシャルや目標を持って生きている人間かどうか見たいだけ。それに対して学生は「やりたいこと」を探し、見つけだし、それを面接でぶつけ、内定が出れば「やりたいこと」が実現できると思ってしまう。このズレは企業、学生、就職をサポートする学校職員などがしっかり認識しなければならないと思った。
Posted by ブクログ
是非、採用に関わる人に読んでいただきたい。
現実との乖離なしの実態が描かれていると思う。
「新卒」ブランドに疑問を覚える身としては現在の就活・採用活動システムに対しての提言は賛同できる。
自分の意見にこの本によって根拠づけができたイメージ。
就活生が悪いんじゃなくてシステムそのものに問題があるという論旨。
こっからは感想
まさしく自分は「就活エリート」です。
「就活」というゲームに勝った感覚。勝つというと語弊があるかもしれないけど。
この本に書いてあるように要領よく、自己分析してやりたいこと設定して面接にそなえ、面接でもコミュ力(空気読みつつ時に演じながら場を盛り上げる)を発揮して盛るところは盛って、内定をもらう。
もらえるだけもらってから選ぶというスタンス。
実際やりたいことなんですけどね。いざもらうとビビる。
ここに入って何したいんだっけ?ってある意味入ったことで達成された感がある。だからキャリアプランとか困る。っていうまさしくその状態。
ゴールが明確で入ってきた分、少しでもちがうと違和感っていうのは当てはまらないけど、失敗を恐れるのは多大に当てはまる。
でもまぁ長期的に考えてゴール意識は大切だと思うんだよね。
そのために逆算して今やるべきことを実直に取り組む。
それが自分の望む環境じゃなくてもやるべきことはやる。
環境のせいにしない、変えられる環境なら自分で変える。
環境に適応できるとは思うんだけど、長期的ゴールが果てしなすぎて見えないんだよなぁ。まったくもってブレイクダウンできていない。
もっと考えなきゃなぁ。アウトプットのためにいろいろインプットしよう。
モチベーション論理 p.38
(技能多様性+タスク完結性+タスク重要性)÷3×自分の裁量×フィードバック
どれかひとつの要素が0ならモチベは0
エントリーシートはソニーが発明した当時は画期的なシステムだったことが意外。今じゃスタンダード。
Posted by ブクログ
「みなさんご存知の通り「就活」ってなんかおかしいよねー、それはねー…」という解説本。真面目な人が会社入ってから違和感を感じるケースが多いのは、変に「やりたいこと」とか「キャリアプラン」なんかを考えちゃうからということのが著者の主張。
まあそんなことはさておき、リクルート出身の人が「リクルートがこういう風潮を作ったと言われるが、自分は違う!少なくともそんなつもりではなかった!」という弁解をするのは何かの流行りなんだろうか、というくらいよく見る。
Posted by ブクログ
内容は、自分の中で腑に落ちた言い方をすれば「たこつぼを獲得することが目的になってしまい、そこから抜け出せない学生」についての本だった。しかし起きている問題に対しる著者の提示する対策はあまりに「たこつぼ的」だった。
内容をきちんと言葉に言葉に落とそうとしたら、次のようになった。1997年に就職協定が廃止された。それにより就職活動の解禁日が無くなり学生と企業の就職・採用活動のあり方が折角多様化し始めたのに、2004年に経団連の倫理憲章に「学生生活中に面接等を実施するのはけしからん」という内容の一文が記載されたた。そのため就職活動が再び硬直化した。それによって「就活」という体系化された試練を乗り越えるために論理武装をした「就活エリート」という集団が誕生し、入社後さまざまな問題を起こしている、というものだった。それに対して様々なシステムを整備する必要があるという。
読んでいて、著者の問題に対する洞察力は鋭いと感じた(まぁ自分が鈍いだけの気もするんですが…笑)。
「あなたがしたいことは何ですか?」という質問に対する洞察は特にするどいと感じた。企業は学生のことを考える材料の一つとして数ある質問の中から「あなたがしたいことは何ですか?」と質問する。しかし学生はその質問に胸を張って答えられる=正義だと考える。よって学生は就活中に「自分のしたいこと」を作り上げる。しかし実際に企業に入ってやることは、質問された際に堂々と答えた「やりたいこと」ではないことがほとんどである。この「あなたがしたことは何ですか?」という質問に対する両者のスタンスに差がある、という洞察はそのとおりだな、と思った。
他にも、「学生の勉強に対するインセンティブ」と「企業の(すり合わせという意味での)長期インターンシップに対するインセンティブ」に関する話はそのとおりだな、と思った。
著者は著書の中で「多様化」という言葉を多用する。しかし彼の言う「多様化」とは何なのか、と思った。今あるゴールは据え置きにしてそこにたどるまでのゴールが多様化すれば、彼にとっては多様化したことになるのか、と思った。「多様化」という言葉を使うならゴールも多様化するべきではないのか、と感じた。
最後に印象に残った文章を載せる。
「(人間は)他者への同化を繰り返しながらbさまざまな「私」を無自覚に形成していく」 by豊田義博さん(著者)
Posted by ブクログ
なんとも評価の難しい。指摘している問題点はよくわかる。
日本の教育は働いて、生きていくためのものではないんだよね。日本の大学は、学府ではない。学びと働くこととの断絶、歪み。それが産む就活エリートの悲劇。
二社目になった今、やりたいことがないならやるなという人もいる出版という仕事でなにができるかとは考えてしまう。けど、学生のときから「やりたいことはなんですか?」って質問には、いつかやらせてくれんのかよってずっと思いながら受け答えしてた。はっきりとはわかりません、ってのが、答える側も、採る側も本音だと今なら思う。就活の違和感を説明してくれる本。