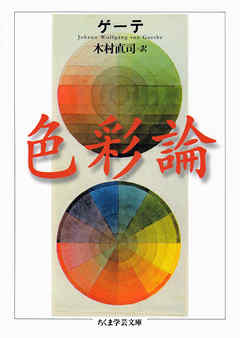あらすじ
文豪ゲーテは多くの貌をもつ。その文業とともに、終生情熱を傾けたのが、植物学・動物学・地質学・解剖学・気象学などに及ぶ広汎な自然研究であった。とりわけ形態学と色彩論はその白眉と言うべく、シュタイナーらの再評価を経て、現代的関心もきわめて高い。分析と還元を旨とする近代科学の方法に対して、綜合と全体化を目指すゲーテの理念の背景には、汎知学─ヘルメス学の伝統が控えている。『色彩論』の精髄たる「教示編」に加え、「科学方法論」を併載し、ゲーテ自然思想へのチチェローネとなす。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
Goetheの赤 -2009.03.09記
以下はゲーテ「色彩論」における<赤色>談義だ。
「青や黄を濃くしてゆくと、必ずそれとは別の現象が一緒に生じてくる。色彩というものは、最高に明るい状態でも暗い翳りをもつものである。したがって色彩が濃くなれば、ますます暗くなってゆくのは当然である。しかしながら、色彩が暗くなるにつれて、同時に色彩はある輝きを帯びてゆく。
この輝きをわれわれは「赤みを帯びた」という言葉であらわしている。この輝きがだんだん強まってゆき、高昇の最高段階に達すると、圧倒的な力を示す。強烈な光を見た場合には、網膜に真紅を感じる漸消現象が生じる。プリズム黄赤色は-朱色-は、黄色から生じたものだが、黄色を想起する人はほとんどいない。
赤という名称を用いる場合には、黄や青を少しでも感じさせるような赤は除外し、完全に純粋な赤を考えていただきたい。たとえば白磁の皿の上で乾かせた純正のカーマイン-紅色の絵具のような。古代人の言う真紅が青の側に近いものであったことはよく承知しているが、赤という色彩にはその高貴な威厳のために私はしばしば真紅という名をあたえてきた。
真紅が生れてくる課程をプリズム実験で見た人は、真紅には現実的にも可能的にも他のすべての色彩が含まれているとわれわれが主張しても、牽強付会の言とは思わないであろう。
黄と青の、この二つの極が赤に向かって高昇し、合一するところに、理想的充足と名づけてよいような真の平静さがあらわれると考えることができる。実際、物理的現象においては、それぞれ合一を目指して準備し、一歩一歩進む二つの相対する極がついに出会ったところで、赤という全色彩現象中で最高の現象が生じるのである。
この色彩は、その性質ばかりではなく、その作用も比類がない。この色彩は厳粛で威厳に満ちているというばかりでなく、慈愛と優美を併せ持っているという印象を与える。赤が暗く濃ければ厳粛で威厳があるものになり、明るく淡ければ慈愛と優美に満ちたものになる。このように老人の威厳と若者の感じの良さとが一つの色彩の中に包みこまれているのである。」
Posted by ブクログ
岩波文庫の「色彩論 色彩学の歴史」を解読してからのレビューであります。
ダンテの「神曲」のように詩韻に秘密があるのではないかと、行ごとに番号を付けながら解読して行きました。
また色彩論なので赤ならば赤、青なら青、黄色なら黄色、緑なら緑、白なら白、黒なら黒、灰色なら灰色、紫色なら紫色と色分けしながら、また、明るいもの、暗いものなども区別しながら解読しました。
その後、日本に正藍冷染(しょうあいひやぞめ)というものがあることを知りました。
なるほど、ゲーテの言う灰色を明るくしたり暗くしたり、緑が青になったりということと一致している。
また、ダンテの「新曲」の中でニュートンがプリズムに固執し過ぎていることも一致している。
さて、本題はここで始まる。
私にとってこの調和された本の解読がどのような意味を持つのか、また私にとっての調和とは何か、ゲーテが色彩という調和を見つけ示したように私にとってのそれを見つけたい。
Posted by ブクログ
ゲーテに色彩論があることを知りませんでした。
ルドルフ シュタイナーが、色彩の本質・色彩の秘密を書いていることも知りませんでした。
自分の好きな絵画について、本書を元に考察してみたいと思います。
理論は、現実を説明するための道具なのだから。
うまく現実と、自分の感想とが説明できれば、自分の道具になると思っています。
Posted by ブクログ
1810年に出した著書。教示篇(色彩に関する己の基礎理論)・論争篇(ニュートンの色彩論を批判)・歴史篇(古代ギリシアから18世紀後半までの色彩論の歴史)の三部構成だが,本書では教示篇のみ収録。
自然の観察に基づく思弁を主としており,今でいう心理学的な姿勢と言えるだろう。色彩科学の祖として,ゲーテの名がニュートンと共に挙げられるもの納得である。
Posted by ブクログ
「岩波文庫『色彩論』リベンジ」でもないけれど(?)、これも手に入れました。自然科学か否か、という分類はもはや気にならず、「文字にて書かれたもの」として対峙しようという構えにて臨みましたし、そういう意味では、岩波に接したときほどの敷居は感じませんでした。……で、私は、未だに(おそらくは生来)自然科学(の或る分野)には弱いんだなぁ、って、思い知りました。思い知ることができただけでも幸いです。プリズム分光器を作ったこともあるから、ちょっと自信あったんだけどな、その程度じゃダメか……。色々あれこれ「色ごと」は、大好きなのに。だから、これらゲーテの著作は大事にとっておきます。
Posted by ブクログ
ニュートンのような物理的な見地ではなく、ゲーテの色彩論はあくまで色彩を見る人の感覚を土台としている。どちらかというと文化論。
かなり読みやすい内容です。