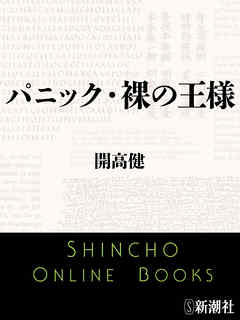あらすじ
とつじょ大繁殖して野に街にあふれでたネズミの大群がまき起す大恐慌を描く「パニック」。打算と偽善と虚栄に満ちた社会でほとんど圧殺されかかっている幼い生命の救出を描く芥川賞受賞作「裸の王様」。ほかに「巨人と玩具」「流亡記」。工業社会において人間の自律性をすべて咬み砕きつつ進む巨大なメカニズムが内蔵する物理的エネルギーのものすごさを、恐れと驚嘆と感動とで語る。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
〈裸の王様〉
作者の文壇登場を飾った短編4作の1編。
芥川賞受賞作。
カタカナで記された画材の数々…上流家庭の内情とは裏腹に瀟洒なその家屋の佇まい…それらが作品全体に洒落た雰囲気を醸していました。それが主題の重さを和らげていたと思いました。
主人公の功利主義への反発心が大人社会の歪形を受けた或る幼い少年との出会いからどう進展するのか?
驚くべきは焼け野原から復興日浅くして(12年程経過)これ程“完成した”閉塞感が確立していた事です。それは無数の功利主義の集積による皮肉な成果だったのでしょうか?
それに対して、主人公の絵画の指導を介しての“命の救出”は読前には非常にヒューマニズムに富んだ内容の展開かと思われたのですが読み進むうちに、この社会から受けた鬱屈を晴らす為の復仇の道具立てなのでは?と思われるフシが目立ち始めましたが、又別の方向性も見えました。『泥まみれでも垢だらけでもよいから環境と争えるだけの精神力をもった子供をつくりたいですね、』それは肥大化の一途を辿りつつあった現代機構の圧迫への著者のレジスタンスの立ち上げとも思いました。
総括として主人公は「歪形」からの解放者なのか?「社会順化」への妨害者なのか…サスペンスという言葉の原義に愚直に従うならば読後に果たして、そのどちらかしら?という宙ぶらりんな小さな不安感に襲われました。しかも、その評価はその時々の世相により変転するのではないか?という所に本作の深みを感じました。
戦前、戦中派の人々が漠然とした不安感としてだけしか捉えられなかった社会組織のなかの人間という現象を初めて言語化して文壇に提示したのがこれら4編です。これが世に出た事で著者は“現代作家”としての面目を躍如とさせました。
だが、これは昭和30年代時点での“現代作家”というだけでなく令和の今日でも引き続き「現代」作家であり続けていると思いました。
それは、これらどの寓話も発表当初の「もはや戦後ではない」時代から高度成長期…石油危機以降…ジャパン アズ ナンバーワン…更に21世紀に突入した今でも、これらの読後感は、そのまま、その時代その時代の社会潮流の水面下に投下した浮子の如く世相を推し量る物差しとしての役割も担えるかと思います。
こうした意味で開高健のこの一冊に対しての“現代の小説”という称賛は色褪せないでしょう。
以下に他3作品の感想を順に記します。
〈パニック〉の読後感は場面転換が鮮やかで映画を見た様な印象でした。短編という圧縮されたスタイルがその効果をさらに高めたかと思いました。
イタチの飼育室…ガラス張りの庁舎…晩秋の雑木林…忙中閑の夜の酒場のグラス…その間にも次第に巨大な集団と化してゆく鼠どもの不気味な予兆…このスリリングな展開の中で役所内で繰り広げられる上下左右の人間劇…やがて社会パニックへ…
感覚的な印象が薄らいだ後に更に感じたのは、人々が医療をはじめ様々な文明の恩恵に浴している環境で暮らしている世相と、逆にそれらが脅威に曝されている時とでは読み手の作品構成への着目点に差異が生じるのでは?という事でした。
すなわち前者の場合は作中の人間劇の方が主体となって鼠害の暗い影は後退し、後者の場合はその人間劇が長い暗く重い影で覆われるという具合です。世相、環境の違いで読後感に相違が生じるのではなかろうか?と思いました。
〈巨人と玩具〉は巨大企業とその下の人間群像が作品の柱ですが、ここにもう一つ『たまたまガラス壁のむこうの見物人のなかに』発見されて、たちまち作中のヒロインと化す一人のモデル『京子』の存在が目を引きました。読み始めは『巨人』と『玩具』の二極のイメージだったのが巨大組織とその宣伝課に所属する主人公の『私』らと『京子』の三者並立の構図を印象づけられました。自社商品の販売競争を取り巻く、この三者三様の呻吟が本作品の推進力ですが読後感がやや寂しい印象を受けました。標題と作品冒頭の印象からして結末はもっと、読者の固定観念を覆す様な陽性な読後感が欲しかったのですが、主人公の現実逃避的な印象が残念でした。
しかし本作を読んで驚いたのは、この発表が昭和32年…焼け野原の敗戦から僅か十二支のひと回りです。この前年の経済白書に「もはや戦後ではない」と意欲あふれる言葉が記された、その復興ぶりもさることながらその水面下にこれ程の構造の完成と“成熟”が存在していた事です。
〈流亡記〉は全4編の内の最後に読みました。他3編には我が国内の晴朗な日射し、現代建築の外観や人物の会話などにまだしもの救いがありましたが、ここは正に不毛の異郷に投げ込まれた様な衝撃を受けました。白か黒かの両極しか許されぬ非情さに貫かれ出口のない無間地獄
的な「閉塞」の世界を感じました。閉塞は他編にも感じましたが戦後の「島国」のそれとは異なる茫漠たる大地のそれは本作に圧倒的な迫力を付与しています。
主人公の生まれ故郷の町は『小さくて古』く『地平線上のかすかな土の芽』と喩えうる程、卑小な存在でした。町の外周には緑色の畑の描写が僅かにありますが、それは本作を読み進む中で色彩感覚として霧消しました。結末まで黒い諧謔に満ちた歌詞が連綿と続くカントリー音楽を背景とした黄土色のモノクロ映画を見せられた印象を持ちました。自ら見たのではなく受動的に見せられたと感じました。
舞台は始皇帝統治前後です。改行少なく連綿と続く独白体の文章に残念ながら眠気を催すこともありました…笑。これは他3編には無かった事でした。だが、それが作中の所々でハッと覚醒を強いられたのです。
それは作者の執筆時点での、現代という時代帯の将来を見通した予言めいた真実味に富んだ洞察力、先見性の為です。初出は1959年です。
或る箇所で、対ベトナム戦でその戦略的欠陥を露呈させた(68年以降)米国への風刺か?と思わされたからです。
作中、時は移り秦帝国の統一的統治が始まり治安による安寧の色彩が回復したかと思ったのも束の間、帝国の兵卒らに主人公は町の男達共々、長城構築の為、辺境へ連行されてしまう。その徴集された人員は全地方から膨大でした。
この巨大構築作業は外在する匈奴達をさらに遠く駆逐する為でしたが、彼は次第に帝国の巨大機構に心身を圧迫され、閉塞感もつのり、遂に、こともあろうに敵対する剽悍な匈奴に対し憧憬の心を抱くに至ります。
作中この辺りの描写には70年代中期以降顕在化した流れ作業や分業の欠陥をデフォルメした物か?と思わされ、更に大帝国の微に入る統治機構は今の電脳統治を彷彿とさせます。この古代の徹底した統治の前では現代のデジタル専制も、この古代の叫びに対する新しい谺での
返答にすぎぬのでは?とさえ思えてしまいます。
この独白劇は終幕へ向けて匈奴への憧憬がさらに増し自らも彼らに成りたいとまでに心は傾斜して行きます。彼らは長城の外にいます。彼らの元へ馳せるのは果たして「逃亡」か?新たに開拓地目指す「脱出」か?前者は受動的であり後者は積極的行為です。
著者のあまりの筆力に読後感を「逃げ場無き逃亡」を目指して…などという受動感覚で終息させたいのですが、これですと私にも許されぬ“未来”が待ち受けている気がして落ち着きません。それは私も作者開高健も主人公も『新鮮な上昇力に接し』て『蘇生』しなければ活路が無いからです。
この作品を敢えて「寓話」と呼ぶのであればー私には本作にどうしても不気味な既視感を覚え寓話と呼ぶに憚りが有りますーそこに主人公の心の傾斜の推移を読み取り、それをいかに短調的曲調から長調的かつ積極性に富んだ魂に変調させうるかという知的考察力だけが『蘇生』への「脱出」を助ける唯一の活路への第一歩につながる武器になるだろう…という事、又、そうしなければ救いは無いだろう…という事を結末感想にしたいと思います。
以上により〈流亡記〉は感想というよりは印象を、印象というよりは衝撃を受けた作品となりました。
Posted by ブクログ
表題にもなっている「パニック」と「裸の王様」がおもしろい。「パニック」は県庁が舞台で、鼠大量発生に困る話と分かった時からぐっと入りこんだ。社会派の話は普段はあまり読まないのだけれど、これはいい。鼠が集団でただまっすぐ走りつづけるという習性にとても象徴的なものを感じた。
「裸の王様」はそれまで権力のきたなさを各作品で感じてきているからこそ、ここに出てくる太郎が心を獲得していく過程にうんと感激した。最後の最後、審査会で大人をアッと言わせる場面はなくてもいいと思ったけれど。なんだか太郎の描いた裸の王様さえも利用されてしまった気がしたのだ。
Posted by ブクログ
こういう文章を書いてみたいと思わせるような文学性の高さは見せつつも、決して読みにくいということはなく終始読者フレンドリーで面白かった。
『パニック』は、著者が筆に託して描きたかったものは果たしてなんだったのかが、読み終わってからようやくわかる筋立ての作品だった。そのためか、組織内政治の描写をそんなに読み込む必要はなかったなと若干の徒労感がある。ただこの作品の勘所はそんな陳腐なテーマじゃない、なんてことは著者のレベルを考えればそもそも自明だった。
『流亡記』は、序盤にほぼ固有名詞が出てこないため、古代中国の城邑っぽい架空の時代と場所が用意された物語として読むこともできる、というか残虐性が高くてそう読むよう誘導される。そのなかに突然出てくる「咸陽」で、読者は秦初の中国のどこかにいることに気付かされる。これは、元々帰属する国など持たなかった主人公と城壁の街が、突然秦の統治機構に組み込まれて帝国民になり、時間意識を与えられたことに合致する。読者が主人公と同じタイミングで同じ情報を与えられるという技巧が面白い。
争いはなくなったが、かつてあった他者との連帯が厳格な法執行と管理のもとで失われていくという問題意識に新規性はないけれど、物語中のシステムに組み込まれて潰されていく人間の有様には真実味があった。
それでも一番面白かったのは『裸の王様』かもしれない。
Posted by ブクログ
過去にも読みましたが、実に20-30年ぶりくらいの再読。
いやあ、なかなかしびれました。
本作、4編の短編から構成された作品群ですが、強烈に感じたのが、通底するシニシズムでありました。お金、権力、偽善への痛烈な批判のようなものを感じました。
・・・
「パニック」では、若手公務員の視点で描かれます。
自らの属する官僚組織に巣食う汚職や腐敗、権力を毛嫌いしまた見切りつつ、120年に一度起こる恐慌(ネズミの巨大繁殖とその後の農作物大被害)について声高に対策を上程します。新人の戯言として無視されるも、これを「想定の範囲内のもの」としてあえて看過。のちにネズミ恐慌が起こった時の「それ見たことか」感。
この斜に構えた感が個人的には大分共感しました。まあ私は50歳手前で「それ見たことか」感出しながら仕事しているダメなおじさんですが笑。
・・・
「裸の王様」もまた、シニシズムを湛えた、こども絵画教室主宰の「ぼく」の視点からの作品。
やや理想主義ながら、こどもの絵をかく能力を「自由に」「制約なく」描かせることに腐心する主人公と、それを無意識に阻んでいる親や家庭環境、あるいは教育の現場。こどもに真正面から向き合わない親や教育現場を痛烈に批判します。
表面的な美徳に潜む腐臭、善意の顔をした商業主義のようなものを全力で揶揄しようとするかのような作品です。
・・・
「巨人と玩具」で感じたのはむしろ徒労感、でしょうか。
レッドオーシャンにあえぐ菓子メーカーのキャラメル部門をめぐる話。競合三社があの手この手でシェアを増やそうと努力しつつという中で、「私」が見た宣伝部でのイメージキャラクタの選定や景品の選定などをめぐる話。社会派の作品でありながら、すさんだ競争社会を揶揄しているような作品でもありました。
ある意味この昭和の営業現場の熱気は、今でいうベトナムやインドなどの熱気などに似ているかなあと感じました。徒労感という意味では、私が勤めていた証券会社での終わりのない営業ノルマを想起しました。
・・・
「流亡記」は中国は秦の始皇帝が始めた万里の長城構築をモチーフにした、用役人夫の視点からの作品。
人夫が用役に駆り出される前から物語は始まりますが、最終的にはこの人夫の達観がこれまた徒労感を呼び起こします。駆り出されたことは不幸といえば不幸。でもこれを駆り出す役人も、規定の人員を規定の日付まで送り届けなれば死刑。つまり管理する側される側は同じ土俵で死と向かい合う。人夫は将来の反乱も予想するも、長城の建設・辺境での戦い、王位に就くものの横暴等は続いていくものとの達観を得ます。
単調さの中に物語は終えますが、シニシズムが光る一作。
・・・
その他、全編にわたりとても密度の濃い書きぶりも気になりました。流麗な比喩や美辞とでもいおう表現が多数使用されています。
とてもライトな書きぶりとは言えないのですが、密度の濃い文章は味わい深い読み口であったと思います。
・・・
ということで開高氏の初期作品の再読でした。
本棚整理のための再読ですが、これは取っておくかどうか迷うところです。斜に構えた感じがとても私のツボでありました。他の作品も読みたくなりました。
Posted by ブクログ
『パニック』
一つの自然災害が火種となって、政治家の汚職や若者のデモに飛び火していく展開は、コロナ禍の今と重なるものがあるなと思った。
人間の文明や知略、そして生命までもを食い殺した鼠の群が、そんな事は全く無関係に湖に一直線に飛び込んで死んでいく光景がとても鮮烈。生命の不条理を感じた。
パニックは120年後にまた訪れる。鼠達の群れは湖の底でまたギロリと目を光らせるのだろう。そのようなパニックの中に置かれてこそ、人間の生命は生々しく輝きを放つのかもしれない。
Posted by ブクログ
ずっと気になっていた作者の、有名な小説を読んだ。
「パニック」「巨人と玩具」「裸の王様」「流亡記」の4編あり、僕はタイトルとなっているパニックと裸の王様が印象に残った。
流亡記はちょっと描写がグロかった。
パニックは、役人機構の腐敗をうまく表しているが、それがメインではなく、ネズミの群れがもはや一つの巨大な物体となり、台風のように人を襲い、それが湖へ消滅していく圧巻を描いている。
裸の王様は、審美眼を持った「大人」たちの目には映らない、というよりむしろいかに我々がなにも見ていないかを表している。
いや、知らんがな。感想が陳腐だ。これこそ裸の王様の家来になった人の感想だ。