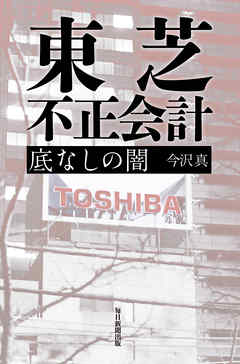あらすじ
暴かれる「名門」の正体。「チャレンジ」という魔の言葉で始まった粉飾。歴代トップと監査法人の責任は? 隠蔽された米原発子会社「減損」の意味は......。
リーマン・ショックと福島原発事故が直撃、チャレンジ=利益水増し強要、大リストラ、トップの激しい抗争、米原発子会社ウェスチングハウス1600億円減損、監査法人の節穴監査、赤字額5500億円の衝撃・・・・・・。あなたの会社は大丈夫か?
<目次>
序 発端
第一章 緊迫の株主総会
1 株価急落 /2 「役員は全員去れ! 」株主の怒りの声/3 「納得できず」株主あきれ顔/4 証券取引等監視委員会への内部告発?
第二章 「チャレンジ」魔の言葉
1 第三者委員会の報告書/2 たった3日で119億円利益水増し/3 過剰なまでの利益至上主義/4 「私は指示していない」田中社長の辞任会見
第三章 第三者委報告書が明かさなかった三つの謎
1 西田、佐々木両氏の激しい対立/2 ウェスチングハウスの経営問題/3 監査法人の責任問題
第四章 迷走をはじめた「室町体制」
1 財務制限条項/2 「消去法社長」室町氏/3 有価証券報告書の提出を再延長/4 2度目の株主総会
第五章 広報に丸投げした歴代社長提訴の説明
1 土曜午後の決算発表/2 苦しみに歪んだ広報担当者の表情/3 役員責任調査委員会の報告書
第六章 ウェスチングハウス1600億円減損の驚きと疑問
1 隠蔽された子会社の減損/2 東証の開示義務違反/3 社外取締役も知らなかった?子会社損失隠し/4 「原発46基受注」東芝バラ色の予測/5 海外では通用しない「二重基準」
第七章 残された困難な課題
1 監査法人の「節穴監査」を厳しく断罪/2 第三者委員会の報告書の「罪」
第八章 赤字額5500億円の衝撃
1 年末の株価急落/2 残されたアキレスけん/3 東芝の再生に向けて
あとがき
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
2015年の東芝不正会計のことを、数時間で読み終えて、その後、何が原因だったのだろうかと、深く考えさせられる…著者の追体験ができる素晴らしい内容です。 あれから10年、上場廃止しての今、何が明らかになったのか、続編が、ぜひ読みたくなりました
続編の副題は、底なしの闇 から 何になるのでしょうか…
私も東芝と関わりの深い会社で仕事をしており、この本に書かれてる内容を肌で感じ取ることができました。もう3年も前の出来事ですが未だにその時の事を思い出すことができます。本書は事実の羅列だけでなく、筆者の真相を追求しようという目線で書かれてるので大変興味深く読み進めることができます。東芝と関わりのある仕事をされてる方へ特にオススメの一冊です。
Posted by ブクログ
毎日新聞経済プレミアの編集長の本。
ちょっと、経済プレミアを宣伝しすぎの嫌いがあるが、
仕方がないか。現在の東芝を書くためにも、
そのポジションが必要かもしれない。
2015年5月8日東芝による「不適切会計」の発表があった。
何故、「粉飾」ではなく「不適切」なのか?
もしくは「不正会計」なのか?
どう考えても、「粉飾決算」なのであるが。東芝への遠慮?
西田厚聰、佐々木則夫、田中久雄の 三バカ社長が、
東芝を 毀損した。社長のクオリティが悪すぎる。
一番の真犯人は、西田厚聰かもしれないな。
それを、あばくことができない 社外取締役。
調査委員会、新日本監査監査法人。
まさに、日本と言うブランドの品質劣化。
リーマンショック、そして 福島原発事故によって、
東芝は、その向かうべき方向性を見失った。
ビジョンや理念もなく、闇の中に 落込んでいく。
何故、外部から プロの経営者を ハンティングできなかったのか?
日本の財界の 総本部まで 侵食する テイタラク。
読めば読むほど、あきれて、モノが言えない。
東芝は、上場廃止が 適切な処理なんでしょうね。
Posted by ブクログ
毎日新聞の記者の本。
東芝の決算延期、配当延期の記事、他の新聞は小さい記事でしか書いてないけど、毎日新聞は一面でデカデカと書いてたよね。といううさんくさい出だしだった。買っちゃったから読まないともったいない精神から、仕方なく続きを読むことに。
『チャレンジ』と『ウエスチングハウス』
チャレンジで、残り3日で120億円の利益水増しを求めた。
土光さんの使った言葉チャレンジが、時代が流れて『利益水増し』の意味で使うようになってしまった。
派閥争い、米ウエスチングハウス、新日本監査法人の責任。がポイント。
説明責任を果たさない役員。広報担当に丸投げ。
Posted by ブクログ
東芝の不正会計を同社の動向を追いながら、著者の見解とともに書いた一冊。
報道でなんとなく理解していた部分はありましたが、本書を読んでその時なにが起こっていたのかや同社の対応のずさんさを知ることができました。
西田、佐々木両氏の対立やウェスチングハウスののれん代を巡る経営の問題、新日本監査法人の監査体制などリーマンショックと東日本大震災という2つの出来事を契機に歯車の狂った日本を代表する大企業の迷走のなかでなにが起きていたのか?そして著者の見解から知る深い闇。
財務諸表などの会計書類から解説されている部分もあり、会計用語や仕組みに関しても解説されていました。
本書を読むことで報道で知ることのできない姿を知ることができました。
Posted by ブクログ
仕事で東芝の方とも商談をさせて頂くことがある。不正会計発覚後、会社が大変な状況になっているともお聞きした。
東芝のこの問題の真相を知りたいと思い読んだのだが、2016年1月時点では真相はまだまだ明らかになっていないようである。とはいえ、不正を主導した過去の経営陣(特に前3代社長)の責任は重い。個人の利益を追求したものではなかったにしろ、市場に対する責任を放棄したことは犯罪に値する。
今期の東芝がどうなるかを注視したい。
Posted by ブクログ
昨年(2015)新聞を見ていて、あの大企業の「東芝」の決算発表が延期されるということを思い出しました。延期となった原因は、不正会計を正すために時間が必要だったからのようですが、この本にはその経緯が書かれています。
原子炉会社の買収、その後に起きた東日本大震災、資産評価修正の必要性等、色々と原因があったようです。そのような状態にあっても、決算内容を良くしなければいけない、という圧力のもと、多くの人が意に反した行為をとらざるを得なかったことが偲ばれました。
戦争が終わった時には、殆どの大企業は生まれて間もないベンチャー企業だったと思います、それが成長して大きくなった今、どうしてこのようになってしまったのでしょうか。そろそろリセットすべき時期が来ているのかもしれません、と思いました。
以下は気になったポイントです。
・歴代三代社長は、「チャレンジ」と称する過剰な利益上積みを各自業部門に繰り返し要求していた。社長が出席する会議で「チャレンジ」という形で示された数値目標は必ず達成しなければならないものと位置付けられ、強い圧力が各事業部門にのしかかった。これが、東芝を組織ぐるみで不正に走らせたキーワードであった(p38)
・押し込み販売とは、液晶やメモリーなど、パソコンの主要部品を東芝が調達し、通常より高い価格で製造委託業者に売る。業者が製品にしたパソコンは東芝が買い戻して販売ルートに載せる(p42)
・08年から巨額の部品押し込みが行われた結果、パソコン事業の月別の損益は、一時、四半期末月の営業利益が売上を上回るほどの異常な状態となった(p46)
・東芝が業績でここまで窮地に追い詰められた原因である、子会社の米原子力大手ウェスティングハウスについて、まったく触れられていなかった(p56)
・最初の報告書に書かれていないこととして、1)西田氏と佐々木氏の激しい対立、2)子会社ウェスティンぐハウスの経営問題、3)東芝の決算を監査した新日本監査法人の責任問題、である(p58)
・将来、利益を上げることを前提に、資産として計上することが許されている項目として、「のれん」や「繰り延べ税金資産」がこれに当たる。何等かの事情で利益を上げられなくなったら、資産から外して損失として計上しなければならない、これが減損である(p72)
・東芝は買収時、20年までに世界の原子力需要は原子力発電所で約130基相当分拡大する、と見込みを明らかにしていた。当時の東芝の原子力事業規模は約1500億円、ウェスティングハウスを傘下に収めたことで、15年に約7000億円、20年には9000億円になると予想した(p74)
・高い利益を上げなければ、のれん、繰り延べ税金資産の減損に繋がりかねない状況であった。そうした中で、歴代3代社長が「チャレンジ」と称して過剰な利益を部下に求めた(p76)
・東芝は、旧三井財閥系の有力企業、三井不動産・三井物産といった三井グループの中核企業の親睦会「二木会」のメンバーである(p86)
・東芝の場合は、9月に不正会計問題で、「特設注意市場銘柄」に指定されている(p132)
・親会社の東芝の連結決算は、同業他社の市場評価との比較をせず、将来の収益予測だけで評価した。(p142)
2016年6月4日作成
Posted by ブクログ
『製造委託業者に部品を高く売った時点で、差額が一時的に東芝の利益となる。四半期ごとの決算期に合わせてその利益が積み上がるように仕組むのだ。』
西田社長時代にパソコン事業の赤字が拡大。利益水増しのため、製造委託業者に部品を高く売る「押し込み販売」を敢行。
営業時代は見込みの売上を埋蔵金と呼んでいた。いつの時代もなかなか見つからない。。。
Posted by ブクログ
過剰な利益至上主義による「押し込み販売」や「チャレンジ」を続け、事業に集中するのでもなく、鉛筆をなめつづけた東芝の不正会計(なぜ粉飾決算といわないのか)に関する著者の考察本。著者は、①西田、佐々木氏の対立②ウェスチングハウスの経営問題③新日本監査法人の責任の3つを謎として掲げている。正直①はどうでもよく、②及び③に個人的興味がある。本書では、③については金融庁における「公認会計士・監査審査会」により「運営が著しく不当であった」と詳らかにされているが、正直実態がどうなっていたのかは謎である東芝と蜜月でもあったのだろうか。いずれにせよプロとして仕事をしているのに加え免許制でもある仕事であるからにはしかるべき処罰を受けるべきであると感じている。また、②についても会計上の計算方法など米国と異なったりしており不明点が多い。これについても監査法人の体たらくなのではなかろうか。本書はなんだかんだ触り部分のことしか述べていないためより詳細な内容のものを読みたくなった。