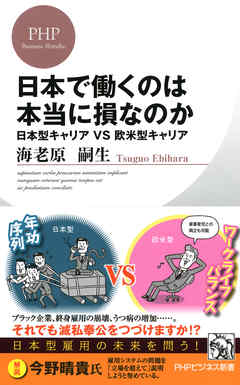あらすじ
ブラック企業、終身雇用の崩壊、うつ病の増加……。それでも滅私奉公を続けますか?なぜ日本人は、上司や会社の悪口を言うのか、なぜ日本人は、なかなか転職しないのか、なぜ日本では、女性活用が進まないのか―欧米型雇用と比較して日本型雇用の本質を鋭く分析し、まことしやかに信じられている常識を覆す。内容例を挙げると、日本には人事異動があるが、なぜ欧米にはないのか 欧米ではなぜ若者の雇用デモが頻発するのか? 日本の若者は大人しいのか? 日本では先輩が呑みに誘うのに、欧米では誘わないのか? 欧米と日本、どちらが学歴社会なのでしょうか 等々また日本型雇用問題への解決策も提示する。そして『ブラック企業』がベストセラーとなった今野晴貴氏が本書を解説―「雇用システムの問題を『立場を超えて』説明しようと務めている」学生から、管理職まで、企業の雇用問題を知る上で必読の一冊!
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
日本と欧米の働き方やキャリアに関する違いを論理的に述べている。日本の働き方はダメだから働き方改革しなきゃいけない!というような内容ではなく双方のメリットデメリットが書かれており非常に勉強になる。
Posted by ブクログ
日本と欧米の労働雇用の慣習について、これほど的確に違いを描き出している本ははじめてあった。日本では異動をつづけながら適材適所を探していくという特徴、それゆえに酒屋での会社の愚痴も日本と欧米で違ってくるというのは面白かった。間違いなく良書だと思う。
Posted by ブクログ
なぜ欧米でワーク・ライフ・バランスが実現できて、日本では難航している原因が分かった気がする。
欧米型キャリアはエリートコースとノンエリートコースがはっきり分かれており、1割のエリートが激務で超高給、その他ノンエリートはヒラからあまり昇進せず薄給ではあるが、残業なしで休暇も取りやすい。
日本型キャリアは基本全員エリートを目指すコースで、年功序列で全員ある程度昇進できて高給をもらえるが、全員に滅私奉公が求められる。
長年疑問に思っていたことに対して納得できる解が見つかったかもしれない。欧米型は本当にそうなのか、欧米で働いてる友達に聞いてみよう。
Posted by ブクログ
面白い。日本の雇用形態を、歴史的成り立ちから紐解き、海外の労働背景と比較し、長短双方の視点から紐解いている。
今後実現可能性がありそうで、道筋を示している。
年老いても、やりがいのある人生を送りたいものだ。
Posted by ブクログ
「雑学」カテゴリですが,「ビジネススキル」にも「就職活動」にもつながる部分がありそうです.実際にヨーロッパで生活をしながらこの本を読むと,非常に納得できる部分がたくさんあります.
個人的には,かなりお勧めの1冊です.
Posted by ブクログ
色々な専門家がいる中で、この人の意見が一番定量的かつ客観的であると感じる。
国の雇用慣行なんて、一括りに語ることができるほど、単純ではない。どの層、どの産業をを対象にした話なのかが重要。
欧米の良い部分がまるで全ての労働者がそうであるかに語られたりする中で、丁寧に解説している。
かつては欧米のような飛び抜けた人材を、徹底的に伸ばすというものに非常に共感を憶えたが、今は色々あって日本人のは日本式があってるのかもなと。
まぁ一長一短なんだけど。
Posted by ブクログ
日本と欧州、米国との雇用システムのメリットデメリットを分かりやすく整理。具体的な提言もあり、実用的。濱口さんの本と一緒に読めば更に理解がふかまるかと。
Posted by ブクログ
明快な論旨である。
ヨーロッパで一般的な就職時に数%のエリートと非エリートが分かれる就業形態:非エリートは昇給も(一定年齢以降は)転職も殆ど無い代わり、ワーク・ライフバランスが保てる。企業はベテランを安く使えるので、若年層の失業率が高い。エリートは、高学歴が必要、若くして早く昇給し、高い報酬を得ることができる。労働時間は長く、育児などはアウトソースする傾向。家庭生活への満足度は低い。
日本の誰でもエリートになれるシステム:2、3年で熟練するような単純作業が中心の業種を除き、誰でも頑張れば課長くらいまで昇進する可能性がある。若年層を大量採用するので、若年失業率は低い。全員が、頑張ることが期待されているため、ワーク・ライフバランスは壊れやすい。女性は出産・育児との両立が困難。
Posted by ブクログ
雇用の専門家による、日本と欧米の雇用システムについての研究書。年功序列型雇用や正規労働者への優遇が批判されているが、欧米のシステムと比較しての多くの批判に誤りの多いことを指摘している。説明が質問・回答方式となっておりわかりやすい。説明も丁寧である。ただ、素人でもわかるよう容易に理解できることに重点が置かれているため、データの提示や根拠となる他の研究の紹介が少なく、研究所としてはやや物足りなかった。
「統計データを見ると、かなり昔から、中卒は3年で7割、高卒なら3年で5割、大卒でもやはり3年で3割辞めるという状況が続いてきたのです」p6
「日本の雇用の特徴:1 給与は「仕事」ではなく「人」で決まる 2 正社員とは誰もが幹部候補であり、原則、出世していく」p8
「日本では、ポストがなくても能力アップすれば給料が上がる。だから、社内で地道に能力アップに励む。欧米だと、ポストがない限り、給料は上がらない。だからポストが埋まっていれば、それを求めて外に出る」p22
「最近は、役職者になれる割合は減っているといいますが、それでも、大学を卒業した人たちなら、そのほとんどが40歳代には係長になり、50歳くらいでは、6割以上が課長になっています。賃金構造基本統計調査の数字でも、この傾向は示せます」p116
「欧米型雇用の年代的な問題は「若年層に仕事がない」こと。日本型雇用の年代的問題は「働かない高給な熟年が多い」こと」p122
「(受け皿となっていた農・工・建設・自営業の縮小により)今の若者たちは、まず、対人コミュニケーションを要求されます。人付き合いが苦手という人には、極端に生きづらい環境になります」p136
「誰でも昇進昇格が当たり前、と考える日本人特有のキャリア観は、世界ではとても異端なのです。欧米では「階段を上る少数エリート」と「ヒラのままの大多数」の2層に分かれています」p158
「長期熟練を保つためには、長い修行に耐える見返りとして、年功昇給が用意されていなければならない」p176
Posted by ブクログ
読みやすく、簡潔に日本と欧米の雇用の差について書かれている。
欧米コンプレックスが打ち砕けるのでは?
案外日本は休みが多いと言いますし、メディアリテラシーが大切ですね
Posted by ブクログ
以前にBBTの番組で海老原さんのお話はお聞きしていたのですが、こうして本で読むとさらに理解が整理されます。
巷間「日本型雇用」と呼ばれているもの、特に欧米との比較によるそのマイナス面、遅れている面というような形で語られるそれの誤解と、どう理解するのが正しいかをQ&A形式で懇切丁寧に解きほぐしています。
氏の論は大筋私にはもともと同感、あるいは認識を新たにした部分についても大筋腹落ちします。日本で働く人、特にいわゆる「サラリーマン」として働く人は読んでおいて損はない本ではないかと。
Posted by ブクログ
欧米型雇用と日本型雇用。
昨今グローバル化(この表現も謎)が流行りだけど、その言語の根幹にある文化や社会制度と折り合っていけるか。
経営にとっていいとこどりの職務給では、下方異動の理由作りにしかならない。
日本型職務給の意味を考えさせられる。
Posted by ブクログ
雇用の現状・あり方を一問一答形式で考える。単なる欧米型の礼賛ではなく、丁寧にその背景や実情を読み解く。実際的な提言も含めて、本当によくまとまっている本。最近の働き方ブーム本の決着じゃないかと思います。
Posted by ブクログ
日欧米の働き方をどちらかを一方的に糾弾するでもなく、過度に賞賛するのでもなく、双方の特徴を描き出す。著者の態度としては、日本型雇用のメリットを礼賛はするが、その維持・継続が困難になった現代における就労環境の問題点を分析。ここ20年程度の求人状況のなかで大卒求人は実は減っておらず、急激に件数が減少しているのは高卒求人であること、日本の就労・就活事情の困難の原因がコミュニケーション重視の産業にシフトが移ってしまったことなど、その姿をデータを参照しながら提起していく。
日本型雇用の連続性として現れたブラック企業、出産・育児を両立する女性(と同時に男性)の労働市場参入という視点からも必要なエリート・ノンエリートの働き方の差別化という話も押さえていて、網羅的。
それでも、僕の印象としてはだいぶ日本型雇用贔屓に見える。日本型雇用のメリットである業務異動・調整は大企業しか享受できる仕組みになっていないし、日本型雇用最大のの欠陥である「企業の指揮命令権の巨大化」についてはほとんど触れていないし、フェアではない。でも雇用の仕組みについてはかなり勉強になった。