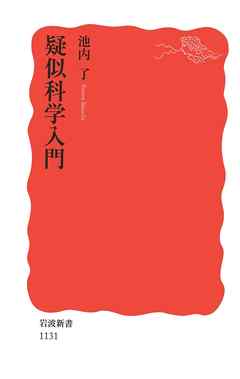あらすじ
占い、超能力、怪しい健康食品など、社会にまかり通る疑似科学。そのワナにはまらないためにどうしたらよいか。また地球温暖化問題など、「科学が苦手とする問題」で疑似科学に陥らないためにはどうしたらよいか。さまざまな手口と社会的背景を解き明かし、一人ひとりが自ら考えることの大切さを説く。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
虐待する母親の例
虐待する母親の実数の3分の2は実母で、継母は1しかいなかった。→実母のほうが危険
と書いた新聞記者がいた。※児相の数の比を参考
しかし、虐待してない母親の数を比べると圧倒的に実母のほうが多い。すると割合から言えば継母の方が虐待確率は高い。実数と割合を区別せず、事実を逆様に報道した。
こういった数字のマジックにひっかかってることは多々あるな、と反省させられた。
ひとつひとつの項目で具体例をだしてくれているのでとても納得しながら読み進められた。
正論につぐ正論が清々しいくらいだった。
科学という厳しい世界に身をおかれる筆者だからこその説得力である。
Posted by ブクログ
「疑似科学の社会学」としたかったとあるが、可笑しい。
博士が更新がなく、社会的地位が低く,報酬が少ないことが、
似非科学にかならずといっていいほど博士の裏書きがあることを説明すれば、社会学を名乗ってもいいかもしれない。
経済的な効果と頭の中の論理だけで成り立っているようなので、
社会学はない。
お金の話なら、似非科学の経済学が妥当かも。
「疑似科学入門」は、疑似科学を操れるようになる人を増やしそうで心配。
多くの疑似科学信奉者は、この本に書いてあるような分類は気にしていない。
気にするようになれば、ますます増長しないだろうか。
人の言ったことを信用するかどうかという水準で議論しているところで、科学を議論していないことにならないだろうか。
繰り返し起こることと、
一度しか起こらないこととをきちんと分離して議論しないと、
科学と歴史の区分がつかないかも。
Posted by ブクログ
フォトリーディング&高速リーディング。
まえがきにおいて著者は、えせ科学に人々が引きつけられる理由を「不合理なものを受け入れて、むしろ楽しむ傾向」と警戒している。考えることを他人任せにしているというのは考えさせられた。
地球環境問題やリサイクルに対しての賛否両論の極端を指摘している箇所(P148)は、私自身の考えが極端であったとの気付いた。
星四つ。
Posted by ブクログ
世にオカルト批判の書物は多いけれど、本書のように疑似科学の範疇として「複雑系」の問題を取り上げたものはあまりないのではないか?本書では「不都合な真実」も「環境問題はウソである」も公平に取り上げている印象を受ける。一つ一つの事柄は正しい・正しくないと判断できるのであって、どちらか一方の意見を妄信して他を無条件に退ける態度こそ「疑似科学」である、というわけで、視聴者の心に忍び込んでくるスピリチュアリストも、何でもかんでも温暖化のせいにする古舘伊知郎も等しく疑似科学である、という認識はきわめてまっとうだと思う。
Posted by ブクログ
知覚エラーや記憶エラーを論じる部分(30頁ー)は,伝聞証拠の議論を思いだす。
以下引用。
「最も憂えることは,自分の頭で考えるのではなく,(神仏や人からの)ご託宣を何の疑問も持たずに受け入れてしまう体質になることである。……自分で考え決断して選択するという生き方を忘れ,私たちが社会の主人公であるという本来の民主主義から離れていくからだ。「観客民主主義」に堕していくのだ。」(22頁ー)
Posted by ブクログ
現代は疑似科学のまさに百花繚乱の時代であり、知らないうちに私たちの生活に浸透してきている。その罠にはまらないためにできることはないか。どうすべきか。を論じています。
疑似科学というと、ゲーム脳や水伝(水からの伝言)などを連想するのですが、端から見ていると「こんなの引っかからねーよ」とは思うものの、いざ自分がこれまでにはないタイプのものに直面したとき、正常な判断を下せるか、というのがとても不安ではありました。常々思ってるのですが、テレビの情報やネットの情報はそのまま信用せず、まずは疑うことである、と再認識しました。
ただ、「おみくじや占いなど罪がないもの」とはしているものの、程度は同あれ、こういう人が疑似科学にハマるんだ、といわんばかりの論調がややひっかかりました。神社に初詣に行く人々も、著者にはこう映るんでしょうかねえ。まあ考えすぎでしょうが。
Posted by ブクログ
疑似科学、すなわちエセ科学。
著者は大きく3種類に分類している。
・占いなど、思い込みなどなどでどうにも変ってしまうもの
・健康食品など「いかにも」な感じを出しているもの
・正直よくわからないんだけど「○○現象だ」と言われて納得してしまっているもの
共通して述べられているのが、なんとなく納得した気になって深く追及することを避けてしまう風潮への警告。
自分自身がそのような傾向があるだけに、ぎくっとした。
自分一人に害がなければよいと思ってしまうところもあるけど、とくに環境問題などでは各人が「まあいっか」と思っていることが世の中の動きになってしまうことだってある。
対策としては、うのみにしないで、自分で一度疑ってみること。
疑った上で納得するのなら、それでいい。
受け入れることばかり教わってきた私たちにそれは難しいけど、身近なところから始めていけるとよいとのこと。