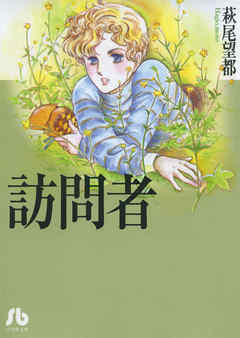あらすじ
オスカーの出生にまつわる秘密……。それが父母の愛を破局に導き、思いがけない悲劇を呼び寄せた。母を亡くしたオスカーと父グスタフのあてどもない旅が始まる。名作「トーマの心臓」番外篇表題作ほか、戦時下のパリで世界の汚れを背負った少年の聖なる怪物性を描いた「エッグ・スタンド」、翼ある天使への進化を夢想する「天使の擬態」など、問題作3篇を収録。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
名作中の名作
最後の場面でユリスモールの前で流すオスカーの涙。罪を犯した父に許しを与える存在になりたかったのに、父にとっては自分は裁きをくだす者だった。愛と絶望の描写が胸を締め付けられる。「エッグ・スタンド」も初めて読んだのははるか昔なのにいまだにセリフの一つ一つが心の中にしまわれている。進化論から、死んだ子どもへの罪の意識を漂わせる現代っ子の救いの物語。城を作るには、黒と白の石が両方必要だということを本当に納得できたのは十数年たってからだった。
Posted by ブクログ
他3編の短編もそりゃあ素晴らしいのですがオスカー厨なのであえて訪問者の感想です!
この話のなにが一番の救いって、あくまでトーマの心臓って物語が未来にあることを前提として訪問者って話が作られたことだと思います。親から与えられるべき当たり前の愛を得られなかったオスカーが、それでも自分以外の他人を許し受け入れ愛することができた、それがトーマの心臓におけるオスカーの姿なんだもんね…許される子供になれなかった子が一人の人間を許し愛せるようになったという…
最後のページのユーリの姿がたぶんオスカー視点なのだと思うけどあまりにも眩しくて…ユーリにとっての愛という救いをもたらした天使はトーマとエーリクだったのだろうけどオスカーにとってのその意味での天使は紛れもなくユーリだったのだなって…大丈夫、っていう何も知らない故の美しくて優しい言葉がどれだけそのときのオスカーの心に染み込んだことでしょうか
Posted by ブクログ
いろんな切り口の「訪問者」
自分がそこにいてもいいと思えることがどんなに重要で、切実な願いか。周りの人に愛してもらえることは勿論、「エッグ・スタンド」は政治的な存在自体の断罪まで言及される。
「愛も戦争も同じ」と語るラウル、生きている実感を伴うものがそのふたつだとしたら、愛そのものも恐ろしい。。「許している」ように見える彼らだって、所詮性的搾取者という地獄側面を持っており、まさに「すべてがきわどいところにある」。人間が人間を裁くことの限界を感じるけど、不条理でも誰かの許しが誰かの存在に間違いなくつながっていて、、涙
萩尾望都を読んでから「許し」についてよく考える。人間の持てる感情で一番すごいのは許しかもしれない
Posted by ブクログ
「トーマの心臓」の前日譚。9歳のオスカーのパパ、グスタフは売れない写真家でママ、ヘラとはケンカばかりだった。ある雪の日グスタフは夫婦喧嘩の末ヘラを射殺する。オスカーがグスタフの本当の子ではないと打ち明け離婚を切り出したからだ。真実を悟ったオスカーは警察に疑いの目を向けられるグスタフをかばい、グスタフはオスカーと犬のシュミットを連れて旅に出発する。グスタフの精神が不安定な中オスカーは必死で旅を続けるが、シュミットの死によりグスタフはオスカーの本当の父親が校長を務めるギムナジウムに彼を残し南米へ旅立つ。
「たとえあなたが裁きをおこなえる神様でも子どものいる家にきてはいけないんだよ」「ぼくは悪い子だったけど、どんな悪い子でも家にいていいんだって。」
他に「城」「エッグ・スタンド」「天使の擬態」を収録。第二次世界大戦下のパリを舞台に、ドイツからパリに逃げてきた不法移民のユダヤ娘ルイーズ、無垢な殺し屋の少年ラウル、ドイツ軍に抵抗するレジスタンスのマルシャンの3人を描く「エッグ・スタンド」は短編ながらも映画のように深い。
「戦争は人間の心の中にある欲望か何かの炎が狂ったように次つぎと人から人へ引火してとめどなくもえひろがる大火事だ」「大火事はすっかりもえつきないと消えないね」
「戦争はいちど始まったら終わりだ。平和!正義!そんなものじゃない。戦争は戦争。破壊だ。平和は平和の中にしかない」
Posted by ブクログ
「訪問者」
「トーマの心臓」に出てきたトーマの外伝。
母を殺してしまった父を庇う子の話。
逃避行の途上で体調を崩していく父の姿が悲しい。
「城」
寄宿学校に預けられたラドクリフが、優等生のアダムとギリシャ人の不良オシアンに影響される話。
「エッグ・スタンド」
ナチスドイツの侵略するフランス。
パリの踊り子ルイーズのもとに身を寄せる謎の少年ラウルを、
非合法活動に携わるマルシャンが、ふたりを愛しつつも調査する話。
「愛も殺人も同じなんじゃないの?」というラウルの存在が面白い。
「天使の擬態」
自殺未遂をこころみ、天使になることを夢想する大学生の次子が、
新任教師シロウと触れ合ううちに、本来の自分を取り戻す話。
次子がいったい何に絶望していたのか、が最後に明かされる。
どれもよい中篇・短編だった。
「訪問者」「エッグ・スタンド」は萩尾作品によくある設定だが、珍しく「天使の擬態」は日本が舞台で驚いた。
@@@@@
202109再読。
訪問者 小学館文庫(新版)1995.9.1
萩尾望都の70年代はデビューと同時に綺羅星のごとく輝いたが、
80年代もまた別の意味で冴えており、凄みを増す。
90年代の「残酷な神が支配する」で遺憾なく発揮される精神分析的関係性が、80年代ですでに。
心に深く潜るとはこういうことだと思う。
■訪問者100p
前に読んだときは「トーマの心臓」のオスカーだとあまり関連付けずに読んだせいかもしれないが、
「トーマの心臓」の直後に読んで見たら、ちょっと自分でもびっくりするくらい胸に響いてしまった。
単に感動とか泣いたとは言えない感じ。
胸郭が自分でも信じられないくらい広がった空間になって、そこに鐘だか銅鑼だかが鳴り響いて、これどうしたらいいんだろう、と。
父母の性を目撃という意味で、正しくフロイトのいう原光景が描かれる。
愛着と、捨て子と、そしてこの年になって父(というか……)の「弱さ」も他人事ではない。
ラスト3ページの光に溢れた風景と、独白が、依然とは全然違う響きを持って感じられた。
■城33p
心の中にお城を作る、その材料は? という箱庭療法を連想させる、やはり深層心理学的な話。
しかしまた、そういうラドクリフの文脈をゆうに軽々と乗り越えて自転車で駆け抜けていく女性もいて、ここが最もぎょっとするところ。
■エッグ・スタンド100p
パリ、ナチス、レジスタンス、男娼、ミステリ。
単なる雰囲気や要素だけでなく、吉田秋生「BANANA FISH」と通じるものがあると思う。
少年の胸の奥に開けた洞窟の大きさに慄く大人、という構図。
また卵の中の死んだ雛→押井守「天使のたまご」を連想。
実際萩尾望都は押井守作品では「天使のたまご」が好きなんだとか。
■天使の擬態50p
本書の中で唯一、少年少女ではない、青年男性と成熟直後の女性の話。@現代日本
萩尾望都もまた宮崎駿と同じく「雑学の人」で、生物学の雑学が詩情を増す方向で発揮されている。
■エッセイ―私のルーツ、萩尾まんが:折原みと(漫画家・小説家)
Posted by ブクログ
まるで純文学のような。
どっしりと骨太で何かが心に残る作品集でした。
あと、絵が綺麗。(樹なつみはもしかして作風が似ている?それとも時代性?)
解説が折原みとでした!
Posted by ブクログ
「トーマの心臓」も今作と合わせて読むとその背景・人間関係がより良く分かる。子どもにとったら出生の秘密なんて知りたくなかったよな…。でも手放す父の寂しさ・複雑な気持ちも子を持った今となってはズシンとくる。それでも子どもには自分を捨てて身軽になれて良かったねと皮肉を言われてしまうのだが。萩尾先生は心理描写が巧み。
Posted by ブクログ
親子ってものはなんでこう難しいのかね。
本当に血がつながってなくても、まあいい。
確かに自分は愛されている、そこに自分の
居場所があると、こどもが思うことができれば
それでいい。
でも、それが叶わなかった子って、たくさん
いるんだよね。不安定な気持ちのまま
育った子が。
そんな子はきっと、我慢して我慢して
いい子でいようとするでしょう。
自分の気持ちを隠して大人に合わせようと
するでしょう。愛されたくて。
だから、子どもの割に変に落ち着いてたり、
見方によってはどこか冷めてたりもする。
子どもが子どもらしくいられる。
みんながそうであったらいいのに。
オスカーみたいな子を増やしたくない。
ただ願うのは、オスカーがいつの日か
幸せな家庭を築いてくれること!
繰り返さないでほしい…