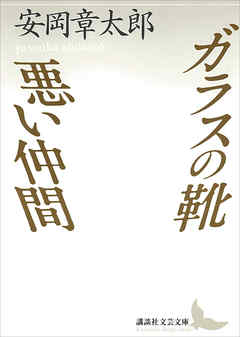あらすじ
初期作品世界デビュー作「ガラスの靴」芥川賞受賞「悪い仲間」「陰気な愉しみ」他、安岡文字一つの到達点「海辺の光景」への源流・自己形成の原点をしなやかに示す初期短篇集。幼少からの孤立感、“悪い仲間”との交遊、“やましさ”の自覚、父母との“関係”のまぎらわしさ、そして脊椎カリエス。様々な難問のさなかに居ながら、軽妙に立ち上る存在感。精妙な“文体”によって捉えられた、しなやかな魂の世界。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
1920年生まれの作者。
ある人から「サアカスの馬」を勧められて、それを読み、よかったので、短編集に手を出してみた。
夢中になって読んだ。
独特な、劣等感、罪悪感、諦めの感覚、自己嫌悪、自己憐憫、ユーモア感覚、文体、に中毒のようになってしまったのだ。
ひとまずは身辺雑記や私小説的な題材と言えるが、大きく見れば戦争の影響もあり、太宰同様見方次第でスケールが大きくなることもありそうだ。
再読するときは、あらすじありきではなく、細部の描写や小道具やユーモアに注目せよ>未来の自分へ。
■ガラスの靴★ 009 1951年=昭和26年=31歳。芥川賞候補。……春樹「ノルウェイの森」そっくり! ていうか、後に続く作品群とは一味違う、エバーグリーン。
■ジングルベル 035 ……うーん太宰治「トカトントン」を連想するなあ。戦後の象徴というか。
■宿題★ 051 1952年=昭和27年=32歳。芥川賞候補。……比較的長め。これはよい少年期もの。お母さんが「お前も死になさい。あたしも死ぬから」(おまえもしなさい、あたしもするからの聞き間違え)とか、小さい挿話が輝いている。……このお母さんが作品発表の数年後にああなってしまうとは(「海辺の光景」)と思うと感慨深い。
■愛玩★ 091 1952年=昭和27年=32歳。芥川賞候補。父への込み入った思い。
■蛾 109 題材は家族から少しだけ離れるが、しかし少し登場する父が、やはりいい味。一人称は私。
■ハウス・ガード 129 1953時事文学賞。戦後という状況を、糞真面目でも深刻でもなく描く、視点の置き方の面白さ。「あなた、ビフテキとなります」という台詞には、おかしみはあるが、恐怖もまた。
■陰気な愉しみ 149 1953=昭和28年=33歳、「悪い仲間」・「陰気な愉しみ」にて第29回芥川賞を受賞。1954結婚。一人称が私だが、やっぱり僕のほうがよい。この人の足取りにはどこか梶井基次郎「檸檬」が見えるなー、と思って検索してみたら、なんと、
(以下引用)
しかしどうしたことだろう、私の心を充たしていた幸福な感情はだんだん逃げて行った。(中略)以前にはあんなに私をひきつけた画本がどうしたことだろう。
(梶井基次郎「檸檬」)
いったいどうしたことだろう。お金のないときには、あんなに悠々と歩けた街が、いまはこんなに気おくれしなければならないとは。
(安岡章太郎「陰気な愉しみ」)
「あ、そうだそうだ」その時私は袂の中の檸檬を憶い出した。
(梶井基次郎「檸檬」)
「そうだ……」
そのとき突然、私は一人の婆さんを頭にうかべた。
(安岡章太郎「陰気な愉しみ」)
「檸檬」で檸檬が占めている位置に「婆さん」をはめ込むと「陰気な愉しみ」になる。「檸檬」の「私」は檸檬のおかげで気が晴れるが、「陰気な愉しみ」の「私」は「婆さん」のおかげで気が重くなる。「陰気な愉しみ」、ダウナー系の「檸檬」。
■悪い仲間★ 167 1953=昭和28年=33歳、「悪い仲間」・「陰気な愉しみ」にて第29回芥川賞を受賞。1954結婚。……比較的長め。「三者による鏡像関係」、というか、こういう関係性は奇矯なものではないが、ある時代にある社会背景(まあ戦争)が重なると、特別に見えてくる、という類いの作品だ。よい。手紙というメディアが増幅させる、というのも、SNSや一億総ナンシー関化を思い出させて、現代的。
■剣舞 203 ……父を巡るあれこれの記憶が、剣舞のラジオで甦る。プルースト効果だろうか。
■勲章 235 ……題をパイプとせずに勲章としたあたりに、読み甲斐がありそうな。蹂躙された側に視点を置く。
■築地小田原町 257 ……無理に自らに課した江戸趣味修行が、無駄に自分を苦しめる……風亭園倶楽部と同じものかしらん。
■吟遊詩人 277 ……戦後の男女立場入れ替わり。
■王様の耳 295 ……嘘をめぐる話だが、人の命がかかっているだけに、軽い小話にはなりえない。
Posted by ブクログ
話の筋も表現も「うまいなぁ」と、思った。大衆万人向けだなぁとも思った。生活という現実そのものを感じた。
そして、そういうまるまる現実そのものみたいな小説って案外ないよなぁと思った。(ただ私がそういうジャンルの小説を読まないだけかも知れないけど。)
絵でも小説でも美しく描きたくなったり、想像的なモチーフを描きたくなったりしてしまうものだと思うのに、安岡さんの物語にはそれがない。ただ人間が生きている。リアルな人間の生活がありありと在る。
どの短篇の人間も、流れるまま、主張せず、待ち、決定的な場面を避ける。
現実を生きる人間というのは、日常というのは、案外そういうものであると思う。
私が好んで読む本はどちらかというと形而上学的なものが多いから、安岡さんが新しく感じた。
とくに『宿題』という男の子が主人公となる話は強烈だった。終わり方にゾゾゾとした。
『陰気な愉しみ』の筋も主人公の感覚もそう描くのかと感心した。『悪い仲間』良かった。