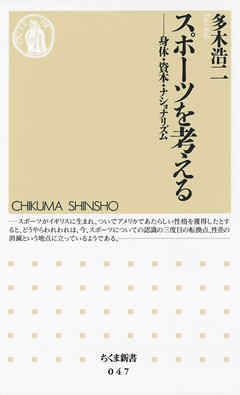あらすじ
イギリスで誕生し、アメリカで変容・拡大した近代スポーツは、いま大きな転換期を迎えている。現実には個々のネーションのなかでの「非暴力モデル」でしかなかったスポーツは、いまや国境を跳び越え、あたかも高度資本主義のモデルであるかのごとき様相を呈している。スポーツと現代社会の謎を解く異色の思想書。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
スポーツを本質的に理解できる書籍。主に感じたことは二つ。「スポーツの本質を理解できる唯一の本」と「それを書いた著者がスポーツの研究を主な活動にしていないこと」である。
スポーツを学ぶ人は必須の本。よって、ほとんどのスポーツに関わる研究者が推薦本としてあげている。
エリアスの記述やスポーツが民主主義のロジックをもっていること、研究はさすが。ここまではスポーツの勉強をしている人は周知の事実。大事なことはこの先。民主主義はプロテスタントの概念がふくんでいる。例えばキリスト教の予定説の考えだ。てことは宗教が不在であった日本は民主主義が完璧に確立できない。民主主義の概念をもつスポーツも確立できない??おそらくスポーツもプロテスタントの概念も関係しているはずなのであろう・・・・
二つ目に考えたことは「著者がスポーツの研究を主な活動にしていないこと」である。スポーツを研究している人は自覚が必要。はずかしく思うべき。ジャーナリストもね。ちなみに著者は思想家であり哲学や芸術の研究者。
Posted by ブクログ
近代化によってスポーツが誕生した歴史を振り返りながら、記号論を頼りにスポーツを捉え直す試みだと読んだ。
一部読み切れなかった部分(主に身体についての章)もあったが、大衆、性差、ナショナリズム、資本主義とスポーツの関係についてとても面白く読んだ。
ただ、多木があとがきで白状している通り、「問題提起以上に到達していない」と感じた。
しかし、多木浩二の形作った議論の枠組みは、刊行から30年ほど経過した現在でも驚くほどに陳腐化していない。
国家予算規模ともいえる選手の年俸の高騰、シティフットボールグループに代表される本来は街のクラブであったはずのサッカークラブの世界進出、SNSとスポーツ、女子スポーツのさらなる普及など、現在、スポーツは更に変化している。
本書での議論を引き継ぎ、スポーツは何かを考えさせる著作があれば読んでみたい。
Posted by ブクログ
スポーツというものは何か。その根本を考える上で大変役に立った。
オリンピック創成期、このころのジェンダー、目的や大切とされていたもの、そしてアリエスの金言など当時の歴史背景も考慮しつつ、
現代のスポーツ観に焦点を当て書かれている。
私のようなスポーツ学科生は一度読んでみると良いと思う。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
近代スポーツはなぜ誕生したのか?
スペクタクルの秘密は何か?
どうして高度資本主義のモデルになったのか?
スポーツと現代社会の謎を解く異色の思想書。
[ 目次 ]
序章 方法としてのスポーツ
第1章 近代スポーツはなぜイギリスで生じたか
第2章 近代オリンピックの政治学
第3章 スポーツのアメリカナイゼーション
第4章 スポーツの記号論
第5章 過剰な身体
第6章 三度目のスポーツ革命―女性の登場
第7章 スポーツの現在
終章 理想は遠くに
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
確か購入したのは東京オリンピックのあとで、さらにサッカーのワールドカップのあとだった記憶。
ずいぶん読みきるのに時間がかかってしまった。
とあるスポーツ(を見るの)にハマりかけてたので、スポーツ観戦ってなんだろう?特にナショナリズムとの関係が気になって電子で購入。
まさか30年近く前の本とは思わなかったw
想像より真面目な本で、哲学の知識なんかもあったらもっと腑に落ちたかもしれない。
私の持論で本とは関係ないんだけど、戦争するくらいならスポーツで競えばいいし、金儲けのために戦争をするくらいならスポーツ利権でえげつなく稼げばいい、と割と真面目に考えている。
もう一度ちゃんと読もう。