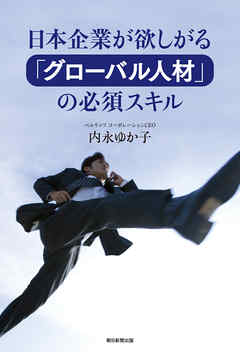あらすじ
今、どこの企業でも求められるのは「グローバル人材」だ。「ドメスティック人材」からどのような転身を図れば、就職・転職マーケットで有利に戦うことができるのか?外国人とのコミュニケーションに必要な思考法から、会議・プレゼン・交渉の場面で役立つフレーズ までノウハウが満載。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
グローバルに活躍するためのコミュニケーション技術をまとめた本。
日本人だけとのコミュニケーションの違いを、マインドから実践的な注意まで、コンパクトにまとめている良本だと思う。
そして、最も価値のある部分は、巻末にまとめてあるビジネス用語のフレーズ集であろうと思う。これらを習得すれば、ビジネスへの一助になる。
--------------
こういう本を、私は非常に嫌いで、今でも読んだことに対して不快感が俄かに胸中に残っている。然しながら、私のような凡人は、斯かるテクニックを覚えでもしないと、まともに人と話せないのかと思うと、止むを得ない。
Posted by ブクログ
国際化、グローバル化が進むなかで、社外だけでなく、社内でも国籍・価値観・文化を乗り越える普遍的コミニケーション・ツールが必要とされている。著者(元IBM==> ベルリッツ社長)はツールの土台となる6つの条件を提唱しています。
①論理力
②ゼロベース・コミニケーション(母国語、文化の違い集団に育った人間は言葉で全てを表現するしかない)
③「違い」を理解する力 (異なる文化に対して、その価値観を理解する)
④「そこそこの英語力」
➄自分を語る力 (外国人に対して自国文化等に訊かれた場合、それに対して回答する。)
⑥名刺なしでつきあえる人脈
しかし、著者の提唱の中で、最も印象深かったのは「ブレない"個"を作る。」という話でした。
大競争時代において「先に成功したプレーヤーの後を追いかけよう」という二番煎じでや、「他がやりだしたから」という横並びの姿勢では通用しません。リーダーの立場ではメンバーの意見を聞いて、「強く」「早く」決断しなければならない。自分が下した決断通りやりぬくという確信を支えるにはその結論に至ったまでの筋道です・「なぜ、そう考えたのか」がはっきりしていれば、逆境にあっても自分を納得させられるし他人も納得させられる。先が見えない時代に「強く」「早く」決断をするには、強固な「価値観」が不可欠だ。
ではブレない軸、決断のベースとなるものを養うにはどうすれば良いか ? それは「古典」と向き合うことだと著者は言います。「古典」とは、つまり「普遍的に変わらない価値観」のことです。何百年の風雪に耐えてきた古今東西の歴史、哲学、思想と「対話」することで、しっかりとした決断のベースを養うことができる。
Posted by ブクログ
最近読んだ『多文化時代のグローバル経営―トランスカルチュラル・
マネジメント』と重なる内容が多かったが、グローバルで活躍する
ビジネススキルとして、納得できる点が多い。
英語表現は、応用できる内容が多いので、活用していきたい。
Posted by ブクログ
日本IBMの取締役を経験した著者ならではのグローバルの厳しさがあらわされている。英語の表現について多くのページを割いていて若干ベルリッツの宣伝じみているところは残念だが、これから自分の役に立つかもしれないと感じた。
Posted by ブクログ
グローバル人材とは会社に依存しない人材のことだと思う。特に個人のスキルがものをいう世界で生きていくということ。
ぶれない軸を持ち、責任の所在を明らかにした上で行動力のある人物。
日本の古い企業には異端児として映るかもしれませんが、世の中の流れは明らかにこのような人材が路を作るんでしょうね。
Posted by ブクログ
人気英会話教室を展開する企業のCEOが語るグローバル時代を乗り越えるためのスキル。自分の志向を知ることは等、海外だけでなく日本の中でも必要なスキルが多い。場面別にすぐに使える英語フレーズが豊富に紹介されているのも良い
Posted by ブクログ
先に読んだ『採用基準』で語られている「これから必要とされる人材」とかなりの部分オーバーラップする。それだけ両書とも普遍的かつ本質をついているということだろう。
こちらは『採用基準』よりももう少し具体的な「実践編」的な内容にも触れられていて、結構参考になった。
Posted by ブクログ
メモ
•流暢な英語≦論理的な英語力を目指す
•国内にチャンスがない、→海外にチャンスがあるから、出て行く
•外国人と、あうんの呼吸は通じない。言葉で全てを表現する。しつこいほど
•自分の考えを、英語で話す練習
•日本以外は、ローコンテクスト=小さな事でも確認し、納得するコミュニケーション、これは不安がある為
•沈黙=悪、生産性0、3秒以内
•海外で、謙遜は禁止
Posted by ブクログ
グローバルな世界でいきのこるには英語・・よりも論理力がまず重要という、当たり前といえばそうですが、当社の上司を想像するに忘れられて?理解して?いなさそうなことだなあ・と
外資からの転職組とプロパーさん転籍組さんの区別がつきやすいのはこういうことだったのか、と
学生さんにオススメの内容
同調傾向の強い人間がコワいので
グローバル化は万歳ですが
自分がホされないようにしないと・ね
Posted by ブクログ
読まなくても良かった。いくら上司からの薦めでも、身内贔屓が過ぎると思う。
「フォーマットを整えよ」という意味で読めと言ったのなら、解る。
Posted by ブクログ
日本語というある種の曖昧さを美徳とする言語を使う日本人に対して、I thinkではなくI believeだと言える論理力を身に付ける事を教えてくれている。
論理力はグローバル人材限らず、多くの人材に必要な能力にも関わらず、軽視されている事も多いのではないか。
まずは目の前にいる人に自分の想いをしっかり伝えられる人材になろう。
Posted by ブクログ
著者の講演を聞く機会があり、その際にいただいたので読んだ本。「グローバル人材を目指す」自己啓発本と英語の例文集とがごっちゃになったような本で、どちらか一方にした方がいいんじゃないかと思った。とは言え、現職はベルリッツの CEO なので、多少は自分の会社の宣伝が入るのは止むを得ないか。
個人が「グローバルでも通用する人材」を目指すのは素晴しいことだし、また結構なことだと思うが、著者が「やっぱり企業もグローバルじゃなきゃ生き残れないよね」と言って展開する持論には正直賛同しかねる部分も多い。今の日本企業は、グローバル化の名のもとに国内の雇用をおろそかにし、それで日本人が物を買えなくなると、「国内では売れないから」と言って自国民ですらロクに買わないような商品を世界に売りに行き、「やっぱり売れない」と嘆いているだけのように見える。日本は昔から「日本人ですら満足する製品を国内で作り、それが自然と世界で評判を取る」という商売の仕方をしてきた。国内で売れないもので世界と競争しようと思っても、それは日本製品の強み(著者の言葉を借りるならアイデンティティ)を失なっている。