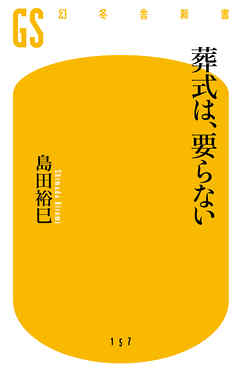あらすじ
日本人の葬儀費用は平均231万円。これはイギリスの12万円、韓国の37万円と比較して格段に高い。浪費の国アメリカでさえ44万円だ。実際、欧米の映画等で見る葬式はシンプルで、金をかけているように見えない。対して我が国といえば巨大な祭壇、生花そして高額の戒名だが、いつからかくも豪華になったのか。どんな意味があるのか。古代から現代に至る葬儀様式に鑑みて日本人の死生観の変遷をたどりつつ、いま激しく変わる最新事情から、葬式無用の効用までを考察。葬式に金をかけられない時代の画期的な1冊。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
戒名の仕組みについてが何より興味深かった。
葬式と仏教、神道、キリスト教など宗教との関わり、現在の葬式仏教の成り立ちなどが手軽に分かる。
たしかに200万300万かける葬式などしたくないし、されたくもないのだが、いざ身近な人間が亡くなった際に実行できるかどうか。。。地方の村社会にいる人やそこで育った世代に対して理解を求めるのは現実的には難しいそうだ。。
ただ当事者になる前にしっかり考えておくことが大事という意味で良い本だと思う。
Posted by ブクログ
勉強になった。
単なる葬式無用論ではなかった。
戒名の意味、葬儀がともすれば豪奢になってしまう理由、葬式仏教とならざるを得ない寺院の現状がよく理解できた。
自分の葬儀はできるだけ地味にとボンヤリと考えていたのですが、その根拠とすべき物を見出せた気がする。
Posted by ブクログ
葬式の是非についての記載に留まらず、日本を中心とした仏教史を古代から現代に至るまで、分かり易くかつ葬儀を民俗学、宗教学といった側面から、日本人の死生感と信教の関わりを紐解いた素晴らしい書籍。自分にとって葬式とはどの様な意味を持つのか?そもそも、本当に葬式が必用なのか?戒名の習慣と戒名料の疑問等、読み進むうちにお寺と権力者の繋がり、近代から今日までの庶民の見栄と欺瞞が見え隠れする。そもそも、私を含め一般の日本人の大半は、宗教に無関心であるのに、他国と比べ逸脱して葬式にお金を掛け贅沢に行うのか?こういった点からも疑問を持つべきだと思う。また、お坊さんの殆どが本来の仏教の戒律を破戒し、結婚や飲酒その他もろもろで出家も形だけでしかない。公務員で兼業の人もいる。なのに、出家の証の戒名を授ける。それもランク付けがあり、お金で高いランクが買える。それは何故か… 本文を読めばよく分かります。習慣に惑わされず、一つづつ検証し物事を選択する事の重要性を教えられた。☆5を軽く超えてる。
Posted by ブクログ
葬式と墓、コロナ禍後大きく変わってしまった。
11年前の父の葬儀は必要以上に費用をかけてしまった。立派な葬儀をすることが残された家族の努めだと思っていた。
コロナ禍の2020年の母の葬儀は、限られた身内だけで自宅で行なった。
今度は自分の番となり、葬儀と墓について考えざるを得ない。
この本は良い道標となりました
Posted by ブクログ
葬式の文化や背景を紐解きながら、データを交えていて見やすい構成でした。
本書を見て、自身が死んだ時も葬式は必要最低限にしようと決意できました。
Posted by ブクログ
仏教、儒教、葬式、檀家等の前提知識が必要でちょっと葬式初心者(?)には読みづらい点もあったけど戒名は自分でつけられる、とかそもそも戒名とは何かとかお金がどのくらいかかるのか、とか基本的なことを抑えてくれていて大変勉強になった。読みづらいけど。
Posted by ブクログ
法外な戒名料にお布施。
日本の葬式費用は優に
諸外国の十倍以上。
これを異常値と言わず
に何と言うのでしょう。
当事者たる日本人にも
葬式仏教を疑問に思う
人は少なくありません。
かく言う私もその一人
・・・
だった、というべきか
本書を読んで目から鱗。
多くの寺院は葬式以外
に収入源がない実情。
現代のこの状況を考え
れば葬式仏教化は必然。
そして住職は毎日本尊
の前で、
檀家の故人たちの冥福
を祈り読経しています。
そう、私たちは檀那寺
に対し御先祖様の供養
を委託しているのです。
私たちにはその自覚が
足りません。
足りないが故に高額の
戒名料やお布施に不満
を感じ批判する。
本当にそれでいいのか。
故人を偲ぶこと二の次。
世間体という見栄欲に
振り回され金額の多寡
にこだわる。
そんな葬式は要らない。
たしかにそう思います。
Posted by ブクログ
『世界のすごいお葬式』(ケイトリン・ドーティ)を読んで、
「自分の葬儀は簡素にしてほしい。面倒な手続きもいらない」と思ってた時に見つけた『葬式は、いらない』(島田裕巳)。
葬式の流れを読んで、「直葬でいいし、お墓はいらない。何なら散骨してほしい」という思いが強くなった。
自分のためにお金がかけられる事が馬鹿馬鹿しい。
Posted by ブクログ
いつになるかわからぬが、将来の自分の葬式を考えるに大変参考になった。遺された者に良かれと思う限り、宗教、形式まして費用にこだわる必要は全くないのだと。高額の戒名料に頼らざるを得ない葬式仏教寺院の背景や破戒僧が戒名を与えることの矛盾などは特に興味深く読んだ。
Posted by ブクログ
日本人が葬式にお金をどれくらいかけているのか、すごくわかりやすく説明されていました。また、"伝統"といいつつその歴史も浅いもの、という宗教的なこともせつめいされていてなるほどなと。
Posted by ブクログ
宗教学者 島田裕巳が日本の葬式について論じた2010年の著作。タイトルはセンセーショナルですが、海外の葬儀に比べて、非常に高額となる日本の葬儀について、宗教史を紐解きながら解説しています。内容はいたって論理的です。これからの葬式の在り方についても触れられています。誰もが必ず通る道だけど、全然知らないというか、知る機会がないお葬式について考える機会になるのは非常に有益だと思いました。
Posted by ブクログ
祖父の死をきっかけに、葬式について学んでみたいと思った。
本書は、葬式に関する根本的な意義を問い直す。
・葬式仏教
・直葬
・戒名のまやかし
・檀家の意味
・弔いは特権的
・寺の収入
・日本の僧侶の破戒
などについて。
第1章 葬式は贅沢である
第2章 急速に変わりつつある葬式
第3章 日本人の葬式はなぜ贅沢になったのか
第4章 世間体が葬式を贅沢にする
第5章 なぜ死後に戒名を授かるのか
第6章 見栄と名誉
第7章 檀家という贅沢
第8章 日本人の葬式はどこへ向かおうとしているのか
第9章 葬式をしないための方法
第10章 葬式の先にある理想的な死のあり方
Posted by ブクログ
葬式の段取りや節約に関する本は数あれど、葬式の歴史を遡り、そのあり方を具体的に書いた本はこれまでなかった。良書。
「生き方とその延長線上にある死に方が、自ずと葬式を無用なものにする。」
Posted by ブクログ
日本の葬式の多くは、仏教に結び付いてしまっているため、また、日本では世間体を気にする人が多いため、葬式の料金が非常に高額になっています。
そこを見直そう、ということを主張した本です。
決して、完全に葬式をなくそう、という主張の本ではありません。
が、葬式の簡略化が進んでいる現在の状況を考えると、いずれ、葬式はなくなるかもしれない、という予想には納得できるものがあります。
自分自身、身近なところで、すぐに葬式が行われる可能性は低いですが、とりあえず、このタイミングで読んでおいてよかった、と思っています。
Posted by ブクログ
自分用キーワード
墓埋法 エドガー・アラン・ポー『早すぎた埋葬』 白洲次郎(葬式無用、戒名不用) 自然葬 社葬(日本特有) 直葬 媒酌人(バブル前後まであった) 永代供養墓 友人葬(創価学会) 宇宙葬 奈良の古寺(葬式仏教ではなかった) 南都六宗 二十五三昧会 往生院 末法思想 エンバーミング 阿部謹也『「世間」とは何か』 寺請制度(危険視された宗教信者ではないと証明) 村の身分秩序 戒名のランク 柳田国男『先祖の話』 核家族化の影響 戒名のコンピュータソフト スタンフォード大学の設立由来 PL教団の花火大会の意味 式場で分かる人と人の繋がり(故人の人徳)
Posted by ブクログ
日本人の葬儀代は平均で231万円。葬儀そのものにかかる費用だけでなく、戒名や墓など、あれもこれもといろいろかかる。その後も檀家になると法要代でまたかかる。本書は、この仕組みには日本における仏教の歴史が反映されてていることを明らかにするととともに、現在、仏教の位置づけが大きく変容しつつあることを指摘しています。
核家族化が進み、都会に住む人が増えた現代において、葬儀はともかく、檀家のシステムは変化を余儀なくされることは自然な流れと感じます。
Posted by ブクログ
日本の葬式のあり方、そして今後について考える一冊。
葬式とは一体何のためにするのか。
葬式はそれほどにお金をかけなければいけないのか。
内容のメモ
日本の葬式は高い
葬式費用が高いのは式の費用と戒名が主
葬式は特権階級のもの。
豪華にすることで極楽浄土を現世に表そうとした(平等院鳳凰堂しかり)
僧侶が行っていた葬式を庶民で行うため修行中の僧の様式で葬儀を行ったため、戒名が必要になった。
寺領が上知令により取り上げられて、収入がなく、戒名等で寺を運営しなくてはならなくなった。
死んだら健康保険から埋葬料がもらえる。
豪華な葬式もいいけど、結局は遺族の気持ちの問題だということ。
Posted by ブクログ
生前葬っていいな、と思うがドラマのようにはいかないのだろう
子供は減り結婚すらしない人が増えて独居老人だらけになる日本の未来に新たな葬式の形はどんどん出てくるだろう
とりあえず、自分の戒名を考えてみたくなった
Posted by ブクログ
世間体、見栄、名誉などは気にしないようにして生きています。特に退職後は。死後についてはなおさらです。戒名不要、葬式不要、墓不要で、直葬、手元供養(自宅供養)か樹木葬でお願いしたいと思っています。10~20万円位で済ませて欲しいです。島田裕巳「葬式は、要らない」、2010.1発行。
Posted by ブクログ
一人の人間が生きたということは、さまざまな人間と関係を結んだということ。葬式には、その関係を再確認する機能がある。その機能が十分に発揮される葬式が、なによりも一番好ましい葬式なのかもしれない。
Posted by ブクログ
葬儀は、誰のためのもの?葬儀は、残された者が故人への感謝と気持ちを切り替えるためのもの。
父は90歳と高齢であったため、。告別式だけの1日葬(参列者11人の小さな家族葬)でした。葬儀は故人のためというよりも、残された者が故人への感謝と気持ちを切り替えるために必要な儀式なのだと思いました。
◆葬儀屋さんは、事前に決めておこう…
父の葬儀に際しては、スマフォで検索した!にわか仕込みの知識しかなくて、ほとんどの事を葬儀社の担当者に助けられながら決めたのですが、簡素にするにしても仏式で葬儀を行うのであれば、少なくともこの本に書かれていることぐらいは、知っておきたかったと思いました。
生前に何も聞いいなかったとは言え、先祖が世話になっていた菩提寺の宗派も知らないようでは、葬儀の読経を住職にお願いする時点で躓いてしまいます。『浄土真宗はなぜ日本でいちばん多いのか』も並行して読んでいるので、仏教の歴史についても概要を掴んでおきたいと思います。
◆葬儀には、いくらかかる?
財)日本消費者協会によるアンケート調査2007年によると、葬儀費用の全国平均は231万円で、諸外国と比較しても飛び抜けて高いそうです。
この本を乱暴に要約すると、明治に時代が変り、2度にわたる「上知令」で寺領が召し上げられ、神道と仏教の分離が推し進められたことによって、危機に瀕した仏教寺院が、生き残るために葬式仏教に傾いていったことと、高度経済成長における戒名のインフレ化などが要因だとしています。著者は、そのような背景から、葬式をしてほしいとは思わないと書いています。
◆葬儀の意味…
故人を知る人たちが集まり故人を忍ぶという機会になれば、とても大きな意味があると思います。家内の実家がお世話になっているお寺のご住職も、そのようなことを仰ってました。法要も本来は、そのような意味があるのではないかと思います。
◆何方に導師を依頼するか…
父の家系の菩提寺は、奈良県の天理にあり、千葉からお参りに行くのは厳しいため、供養していただき、父の代から近所の霊園にお墓を設けるつもりでおりましたが、著者はお墓も贅沢だと言います。
確かにすべての家系が個別に求めたら、日本中が墓地になってしまいますし、我が家のように子供が女の子だけだと、後継者が途絶え無縁仏になってしまう恐れもあります。我が家は、永代供養付きの墓地を選びましたが、難しい問題です。
◆お墓が無い人はどうするの?
私が契約した霊園では、長男が受け継がなければならない、という規則もなく、両親と私たち夫婦だけでなく、長女夫妻や、次女が結婚すれば次女夫妻も入れるようです。合理的ですね^^;
Posted by ブクログ
葬式をテーマにしてますが、最後はどのような人生を送るか、人生の延長線上に葬式がある、と人生観でまとめてます。
・葬式は贅沢
・墓も贅沢
・戒名はいらない。自分でつけることも可能。檀家関係なければ完全自由。
・戒の無い僧侶から戒名もらうのはおかしい
・最期をいかに生きるか
・故人の死により会葬者同士が久しぶりに再会することもある。それは故人の人徳。
Posted by ブクログ
お葬式の話というより、全体的には宗教の話ですね。お葬式を古代まで遡って論じています。戒名は本来生前受戒するもの、日本独自で他国には戒名は無いしその決め方も本山などから指導されているものではない、など仏教寺院にはばらされたくない話が多いです。檀家制度の解説や檀家になること自体が贅沢、など今まで考えたこともなかった目から鱗の話もあります。タイトルは過激ですが決してお葬式を批判しているわけではなく、お葬式とは、戒名とは、檀家制度とは、をもう一度考えさせる本でした。
Posted by ブクログ
なかなか過激なタイトルでしたが、頭ごなしに否定するのではなく日本における葬式の歴史、文化の変遷、寺院の経済的背景を述べながら今の葬式形態に疑問を投げかけてきてますね。
歴史、民俗学、経済事情を述べながら(間違っていない)僧侶批難も交えつつ否定論を説いております。
わかりやすいといえばわかりやすいですが、それゆえ全体的に浅い気もしますし、一番大切な心の問題、信仰や先祖崇拝、先祖供養についてはほぼ触れられてないですね。
あと、宗教学者さん故か、即物的な意見だけで終わってしまいこれからの日本人の死生観や今後どうすべきかも書かれてないですし、結論は非常に曖昧でタイトルとは趣旨が異なってました。
ただ、僧俗問わず葬式について考える(考え直す)きっかけとしてはいいかもしれません。
Posted by ブクログ
今の日本のお葬式のルーツを、さらっと触ることができた一冊。祭壇が豪華であるのが、平安時代の極楽浄土の思想がルーツであることが知れたのが、私にとって一番の収穫だった。
Posted by ブクログ
島田さんのベストセラー?みたいなので読んでみたが、意外と「目からうろこ」度が低かった。本の裏の紹介文と目次で大体予想のつく内容。
葬式や死にまつわる経済的な側面、民族学や社会学的な側面、の話が中心で、心の問題はほとんど語られない。
戒名の付け方を教えてくれているのが面白かった。この著者は「戒名は自分でつける」というような書名の本も出していたと思うが、この部分を一冊分書いてるのか?それともこの本とほぼ同内容?
Posted by ブクログ
なぜこんなに日本の葬式にはお金がかかるのか、そのタネを明かした本です。
いかに、日本の葬式は、浪費であり贅沢であるかということを、
日本での仏教の変遷などとともに明らかにする、無理のない
葬式無用論といった本でした。
たくさんお金を取られる、死後に名づけられる「戒名」というものは、
実際は仏教の教義とは関係のない、葬式仏教として発展してしまった、
日本の仏教独自の慣習にすぎないことなのだなど、いろいろと、
葬式について知識のある人もない人も頷きながら理解を深められる内容になっています。
本の裏表紙にも書いてありますが、
日本の葬式の平均費用は231万円なんだそうです。
これが、お隣の韓国だと37万円。
イギリスだと、12万円。
お金も資源もパーっと使うアメリカでさえ、44万円だそうです。
そして、そんな、葬式へのお金の使い方を、「世間体」「見栄」「名誉」
などといった視点で説明しています。
また、お墓についても、「ヨーロッパではお墓参りはしない」など、
日本の慣習が真理ではないことを知らしめてくれます。
僕は毎年、墓参りに行くタイプではないのですが、
たとえば周囲が「俺は今年もちゃんと墓参りに行ったぞ」と胸を張る
ことに違和感を感じていたんですよねぇ。
そこらが、少しスッキリしたというか、味方ができたというか、
そんな安堵感を得たような気持ちになりました。
うちの親はこの本を読んで、自分の葬儀は費用のかからない葬式で
済ませるという持論に勢いを得たようで、「家族葬」にするとか
言っていました。戒名はどうするんだろうねぇ。
僕の場合だったら、無宗教式に、僕が好きだった音楽を流してもらって、
花でも添えてもらえればそれでいいかなと思っています。
迷うのは、墓ですね。墓参りをそれほどしない身で言うのもなんですが、
墓が無いのはちょっと心もとない感じがします。
それでも、無縁仏になって、きったない墓をさらすようになるくらいならば、
散骨とか、土に埋めてその上に植樹するとかそういった方法のほうが、
マシなのかなぁとも思いますねぇ。なんか、自分が死んだ後の、
抜け殻としての肉体って想像しがたくないですか。
なにはともあれ、この本はかなり売れているようですね。
それだけ、今までの絢爛豪華な葬式というものに、
みんな疑問符をつけているってことを象徴しているのかな。
葬式を頭から否定しているわけではなくて、亡くなった方とのお別れとしての
意味合い、けじめ、というものがあることをしっかりと肯定して、
かつ、高額の葬式について論じている本なので、偏った感じはそれほど
感じませんでした。興味のある方は読んでみてください。