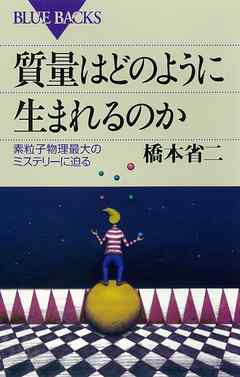あらすじ
ヒッグス粒子とは何かの鍵は真空にある。素粒子物理最大の謎に迫る。2009年、スイスのCERNで人類史上最大の加速器LHCが動き出した。そこでは質量が生まれる仕組みの鍵を握るヒッグス粒子の発見が期待される。しかし、それが見つかれば質量の起源の問題はすべて解決されるのか?質量が生まれる仕組みの理解には、特殊相対性理論や量子力学はもちろん、自発的対称性の破れなど現在の素粒子理論の基本的な考え方が総動員。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
12年夏のヒっグス(と思われる)粒子発見で興奮して、ヒッグス機構を調べようと苦戦している時に手に入れた本。質量について、全体像が見えてくる本。南部陽一郎が偉大だということも分かった。クォークの質量が生まれるメカニズム、計算シミュレーションでの質量スペクトル検証など、全く知らなかったことを分かりやすく説明してくれる。肝心のヒッグス機構だが、最後の章に簡単に説明されているが、少し物足りない。もの凄く苦労して分かるように書いてあると思う。それでも読み返しても納得できない部分もあるが、それはこれから調べていく燃料となる。
Posted by ブクログ
「神の粒子」ヒッグス粒子って何なのさ、ということで何冊か読んでいたのだが、やっと詳しく書いてある本に出会えて、へーそうだったのかと思いつつ読めた。
曰く、ゲージ対称性を破る張本人、ということで、まあ、なんとなく、そういうことだったのか、と理解はできたが、その正体については、まだ新しい粒子だか理論だかがありそうで、まだ続くんかいと思わざるを得なかった。
300ページとそこそこボリュームはありながら、素粒子物理の幕開けから2010年の近況まで超特急で飛ばしてる感はあったが、ブルーバックスらしく?危険なところには踏み込まないで助けられた面も多々あり、なかなか良いバランスの本だなと思った。
Posted by ブクログ
ちょうど、LHCの実験でHiggs粒子が見つかったとのニュースがあったので、思わず衝動買いしてしまった。著者はちょうど脂がのった所の素粒子論研究者、これ一冊で素粒子論の大部分を一望出来るというと言い過ぎだろうか。
本書は素粒子が質量を獲得する過程をテーマとしているが、著者も述べている通り、自発的対称性の破れやQCD、それらのもとになっている相対論や量子力学の知識が必要となり、結局内容は多岐にわたってしまうようで、本書も様々な内容から構成されている。
これだけの内容を専門家でない人々に分かりやすく解説するのは大変な苦労だと思うが、専門的な内容で多少「そういうものとする」的なことになるのは仕方ないにしても、話が発散することもなくまとまっていて概要はつかめた様に思う。特にHiggs粒子が関わる質量の話については、ニュースのせいもあってか自分も誤解していることが分かった。
時折盛り込まれる日常でのエピソードや、御大にサインをもらいそこねた、初めての海外で英語が出来なくて困ったなどの話は、研究者である著者に親しみを感じる文章で面白かった。
関連してあとがきに南部先生らがノーベル賞を受賞した時に出版されていたら...という話があったが、本書はHiggs粒子発見のニュースが出た今、タイムリーな内容ではないだろうか。専門家でない素粒子物理に興味がある人にとっては、メディアで報道される内容で誤解しないためにもおすすめである。
Posted by ブクログ
まさに知りたいことが次々と提示される本。真空におけるカイラル対称性の自発的破れがクォークに質量を生み出すあたりの記述がクライマックス。読んでいて胸が高鳴る。
数学、物理に詳しくなくても、センスさえあれば理解できると思う。南部先生の「クォーク」でもやもやしていた部分がかなりはっきりする。SU群の性質もこの本で概要理解した。
私も質量をもたらすのはヒッグス粒子という単純な認識はなかったが、それは質量の2%に過ぎないという。
・弱い力は左巻きの粒子だけに働く。
・カイラル対象な粒子は、右巻き左巻きを完全に区別できる。したがって光速で走る。
・粒子と反粒子のペアが凝縮した真空の中で、粒子がある種の抵抗を感じて思うように進めなくなり、それが質量の源になっている。
・起こりうることはすべて起こる。これが量子力学の基本原則。これを応用したのがファインマンの経路積分。
Posted by ブクログ
発行当時、スイスでの超大型の粒子加速器「LHC」の稼動が話題になっていたためか(偶発的にブラックホールが発生する可能性もある、などと騒がれました)、帯や背表紙では「ヒッグス粒子」が宣伝文句として用いられていますが、本書の要旨は題名どおり物質(素粒子)が質量を持つに至った原因を、ノーベル物理学賞受賞者の南部陽一郎氏の理論を主軸としながら解説することにあり、ヒッグス粒子やヒッグス場についての言及は多くありません。
非専門家向け解説書にしては比較的数式が容赦なく使われており、ド文系の私はそういった部分は表面だけなぞって深追いしませんでした。
ちなみに、パウリの排他律の解説(p170)で、筆者が「私も…いくら読んでもわかった気がしなかったものだ。白状しておくと、今になっても本当にちゃんと理解できたかどうか怪しいかも知れない」と記してくれたのは大変励みになりました。専門家ですらそうなんだと思うと、とたんに難解な部分を斜め読みするのが苦でなくなりました。
面白かったのはまさに粒子の質量獲得を解説した第3章から第6章にかけて(というか、それ以降、特に9~10章はあまり理解できませんでした)。以下、理解したと(自分では)思っていることのメモ。
・電子などの粒子はそれ自体磁場を生み出していることから、自転(スピン)していると考えられる。このスピンには右回りと左回りがある。
・この右回りと左回りのスピンをもつ粒子は、その素粒子が光速で運動しているのでない限り区別できない(カイラル対称性)。
・しかし、中性子・陽子・電子・ニュートリノに作用する「弱い力」はなぜか左巻き粒子のみ区別して作用する(パリティ対称性の破れ)。
・ということは、粒子は元来光速で運動できた(=質量を持っていなかった)のだが、何らかの理由で質量を持つに至ったと考えられる。
・そこで真空を考える。真空は何もない空間ではなく、エネルギーが最低レベルに落ち込んだ状態。そこでは、粒子がペアを作って空間をぎっしり埋め尽くしながら全体として均質な最低エネルギー状態を生み出すことがある(ボース・アインシュタイン凝縮)。
・そこに光速で(=質量を持たない)粒子が飛び込むと、粒子ペアにぶつかり次々に連鎖反応を起こし、結果として光速より速度が落ちた状態になる(=質量を獲得する)。
Posted by ブクログ
質量の起源をテーマに,量子論・素粒子論の概要をやさしく解説。この手の本,よく読むのだが,導入から基本事項の確認までは快調に読んでても,後半ついていけなくなるお決まりのパターン…。無念。
でもなんとなく雰囲気は分かってきたような気がする。要するに質量の起源は,98%が量子色力学の真空に,2%がヒッグス機構による,ということらしい。素粒子論では真空が重要で,素粒子が沈澱(凝縮)する真空における,自発的対称性の破れが質量をもたらすというのが南部理論。
収穫だったのが,今まで何だかよくわからなかったスピンについて。シュレディンガー方程式を,特殊相対論を考慮して修正したのがクラインーゴルドン方程式だがこれはうまくいかない。さらに時間と空間の対称性を考慮して時間微分も空間微分も一階にした方程式がディラック方程式。ディラック方程式から陽電子が予言され,後に確認されたことは知ってたのだが,パウリが(根拠なしに)導入したスピンも,この方程式に出現していた。すでに知られていたシュレディンガー方程式を相対論と矛盾なく書き換えることで,天下りで導入されてたスピンに理論的根拠が与えられたのか!
ちょっと気になったこと。快調に読んでた前半部分なのだが,特殊相対論の説明で「走っている人が測ると、同じ長さのものでも伸びて見える。」(p.67)と言うのだが,これは「縮んで見える」の間違いでしょう。走っている人にとっては測るものが動いてるんだから。それが相対性。
実は本当にどう見えるかは単純でない。p.67では,上記に続けて「逆に言うと、丸いボールを高速に近い速さで飛ばすと、地上でそのボールを見る人は進行方向にぺったんこにつぶれた空飛ぶお好み焼きを見ることになるだろう。」と書いてあるが,丸いボールは,確か丸いまま見えるんじゃなかった?ガモフも間違えたとか。
丸いボールが光速に近い速さで横切るのを見ると,形は丸いまま見えるのだが,見えるはずのない裏側が見える。立方体とか,球ではない形だと,さらに歪んで見える。視点と物体の各点の距離が違うから,光が届く時間も異なり,その間に物体は動くのでそういう見え方になる。
Posted by ブクログ
この手のタイトルの本にはいつも惹かれる。それが根源的な内容を扱うほど。
本書はまさに質量の起源という世界の根本的なところに迫るものだ。
科学者、物理学者が究極の統一理論に迫ろうとする欲求も、そういったある種哲学的な問題の引力に惹かれる質量なのかもしれない。
世界の根源がシンプルで美しくあって欲しい、そうあるべきだという思いは世界共通だろう。しかし、本書を読んで分かるように、迫れば迫るほど、新たな事実が生まれ複雑に絡み合おうとする。
質量の起源に迫るために、素粒子論の先端を駆け抜け、クォーク、量子色力学、ゲージ理論、場の量子化、などなど次々に難しい概念が出てくる。
それらを科学者でない我々が理解するには、あまりに壁が大きく、見通しが悪い。
しかし、本書は、歴史的な流れを辿りつつ、1つずつ説明がなされていく。どういう流れでその理論が生まれたのか、それで何を説明したくて、それが質量の起源にどう繋がっていくのか。
専門的な話抜きに語ることができないところは、大胆に切り捨て、でも説明を諦めるわけではないところが良い。途中、話がいろいろな方向に飛び出していきまとまりがないようにも感じられるが、
逆にそのおかげで、教科書的な説明ではなく、科学者たちが遭遇してきた発見とその驚きに共感を持てる。
内容的には本当に高度なものも扱っているが、それでも最後まで読み通す気にさせてくれる科学本を書けるということはすごい。
Posted by ブクログ
最後の方は難しく、飛ばし読みで言葉のイメージの理解にとどまった。それにしても、ミクロの世界は不思議というか、本当に我々の目の前でそういうことが展開されているのかと思うと、素粒子物理学者の夢の一端を共有できた気持ちになる。
真空とは何か、質量はどこから来るのか、このような科学的であり哲学的な問いは、これからも私の好奇心をそそると思う。
Posted by ブクログ
「なんで空は青いのだろうか?」と疑問をもって自ら調べるような人でも、「なんで綿菓子はボールより軽いのだろうか?」とは調べない。誰もが重さについてわかっている気になっていて、質量が重力を持っていることなんて教わらなければ気付くはずもないだろう。
なぜ地球は縄もなく月を引っ張れるのか、どうやって自分の体重はわずかながらも地球を引っ張っているのか。質量がどのようにして生まれるのかが分かれば、その答えに近づけるかと思い本書を手にとったが、ますますわからなくなった。もう何度こうして素粒子物理学の壁に阻まれたことだろうか。
クォークまではなんとか理解できた気になった次の瞬間に、『質量ゼロだったクォークが、真空中の凝縮体にぶつかることで質量を持つことになる。』と置き去りにされ、さらにそれをわからない量子色力学で説明されて、知っていたはずだった"真空"の概念さえもわからなくされる。そしてその説明にしても、定義をしっかり語られず、説明しきる前に次の話題に流れていくので、素人が読む解説本としての出来は良くない。
素粒子物理学に明るくない自分がなんとか読み解けた部分としては、光速と質量とエネルギーの関係性については以前より一歩進めた気はするし、『素粒子は波であり粒子である』という事をわかっていたつもりなのに、ついイメージする際は粒子の形で考えていたということには気付けた。
わかった気になったりまたわからなくなったりして楽しめるのもこの分野以外にないだろう。趣味として、惑わされながら学んでいきたい。
Posted by ブクログ
数式を使わないでの説明は理解するのがやはり難しかった。結局主題の質量はどのようにして生まれるのかは煙に巻かれたような気がする。ただこの最先端の課題で科学者らが何をしようとしているのかは少しわかった気がする。
Posted by ブクログ
いや、スピンが1/2とか、カラー、とか、ストレンジとかよくわからないですよねみなさん。この本はかなりこのあたりのことをうまくわかった気にさせることに成功してる。最先端の学問は、分かっていないことに深入りすると特に素人には全くわからないし聞きたくもないということになるのでサイエンスライターはどこまでを書くかを決めるかが勝負なんだと思うんだけど、南部さんの受賞ともつながってうまくそこら辺までは読みやすくなってる。最後の方で、まあわからないことだらけなので尻切れトンボとなるのだが、たぶんこれは現在まで書きすぎちゃったのでそうなったのかと思う。自分の生きている間には誰も解明しそうにない仕組みが世の中にあるっていうことを知るのはいいね。さて、どこまで超巨大な加速器を人類は作れるのでしょう。