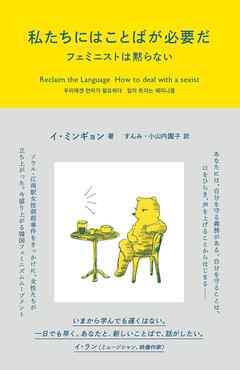あらすじ
韓国社会で可視化され始めた性差別の問題。本書は差別問題て苦しむ女性たちのための日常会話のマニュアル書です。なせ差別が存在するのか、男性のことばにカチンとするのか。実際の 体験から問題を読み解き、自分たちのことばで対策を提案、「なにもかも女性嫌悪!」「セクシストにダメ出しする」など力強く痛快な表現で、フェミニスムを提言しています。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
小・中学生の時にこの本に出会っていればよかった。
いろんな差別、刷り込み、嫌がらせから身を守れたし、怖いおもいをしなくてよかったと思う。
護身術ならぬ、護心術としてこの本を所持しておくこともよいと思う。
女性嫌悪という考え、言葉さえしらなかったので、その言葉があることで自分の経験が無かったことにされない安心感を持つことができた。言葉にする。態度で示す。屈しない。って、大事だ。
Posted by ブクログ
性差別・性暴力を受けたことがある人なら味わざるをえないこの社会、そしてのうのうと生きる人間に対する絶望感、疎外感。そんな気持ちを自分の内に閉じ込めていた人は、この本を読んだら、きっと、性差別・性暴力に対して、いい意味でイライラして殴りたくなるほどの力が湧いてくるのを感じるだろう。
どうしたら次は戦えるか。というかそもそも、セクシストを相手にする必要なんてない。話す時間がもったいない。自分が大事。幸せに生きなければ。そう思わせてくれる本。一家に一冊。
Posted by ブクログ
高校の時に読もうとしたときには、差別の構造も知らなかったし筆者の主張が強すぎる・偏っていると感じて途中で読むのをやめた。だが今回読んでいると納得する部分が多くて、そこに対する共感は女性差別だけでなく他の差別・抑圧の事例に触れたからなのか。
女性差別だけでなく、様々な場合において適応できる会話法だと感じ、参考になる部分が多かった。
人と話している中で、相手の意図がはっきり見えなくて、それにより知らないうちに自分の心が疲弊している場合がある。そういうことを防ぐための解決にもこの本は役立つ。
自分が弱い立場にいる場合に他の人とどう話すか、という視点で書かれていて、もちろんその面で勉強になる部分も多かったが、同時に、自分が弱い立場にいる人と話す際にどういったことに気を付けるべきか、本を読む前よりも見えるようになった。
Posted by ブクログ
著者の書き方が優しくて胸が張り裂けそうな想いで読みました。女性やその他のマイノリティの属性がある方には共感できることが多いと思います。
委員長は男、副委員長は女 と決められている時代に生まれたので、これは当たり前と思って生きて知らないうちに諦めていたんだなと気付きました。
なんか失礼だけど指摘するほどでもないかとうんざりしていたことがハッキリする本です。たぶんこの文章をキツいと思う人はまだ時代に取り残されていますね……
全ての女性のためにももう少しだけ強気で生きていこうかなと思います。優しい人だけ大事にしろよな!!!!!!!!!!!
心が強くなりますし、お薦めですよ フェミニズム初心者は読むべし
Posted by ブクログ
フェミニズムについて書かれた本で、わたしが最初に手にした一冊。出会えてよかった。
傷付いては笑ってごまかしてきた日々に塗りこむ軟膏のようでもあり、ワクチンのようでもある。自分を守るための「ことば」たち。
Posted by ブクログ
本書を読んだら、話が噛み合わない男友達との会話が、掲載されているセクシストとの会話例にそのまま当てはまり、ショックだった。
ここに書かれているような返しを咄嗟にできなかったことは悔やまれるが、話を中断するという選択をとらざるを得なかった過去を自分の中で少し許せた気がした。
女性差別的振る舞いを正す責任は、そもそも女性ではなく、真摯に学ぼうとしない男性本人にある。
Posted by ブクログ
すべてを丁寧に、わかるように、わかってもらえるように、優しく、説明してあげる必要はない。
相手に知ろうとする気がないからそもそも噛み合わないのだ。
当たり前と言えば当たり前なことを気づかせてもらい、なんだかラクになった。
Posted by ブクログ
フェミニストを自称する人でも、そうでない人でも、一読して欲しい。
特に女性は、セクハラや痴漢について男性と会話する時の"噛み合っていない感覚"や"何となく不快に感じる"理由をこの本から見つけられると思う。
説明が不十分だったからでも不出来だったからでもなく、そもそも相手に理解する気がなかったのかもしれない。
そう思えるだけど救われる過去の自分が沢山いた。
Posted by ブクログ
まず、議論することはしてもしなくても良い、私が説明したくないと思ったらしなくても良いと書いてあって、楽になった。理解できない人には一生理解できないのだから、私がわざわざ説明してあげることもないか、と思った。攻撃された時に返せるような言葉をいくつかもっておきたいとも思う。
本当に私たちには言葉が必要だ。言葉があるのに何で建設的に議論ができないんだろう。
Posted by ブクログ
女性専用車両や東北大学女性教員採用促進は男性差別!という言説に対し、そもそもそういう謎な思考の持ち主と、私では視点が違いすぎるので、会話できないな?と思っていましたが、この本があればいけるかも!これはセクシストが失礼・不勉強・差別構造を温存したくてコメントしてきた場合に特化した、かなり実践的な本です。
ま、でもこれもこの本にあるように、セクシストを説得する義務もないので、相手が”無関心でいられる立場を悪用したい”場合以外は、無視しておこう…
Posted by ブクログ
フェミニズム。
過激な言葉を使っているフェミニストを少し怖いな、と思っていた。
この本を読むのもずっと躊躇っていた。
けれど、今が読むタイミングだなと思って読み始めたら、なぜ過激に見えるのか、いや過激に見えるのは自分がフェミニズムについて何も知らなかったからなのだと思った。
自分は女性だけれど、自分の中にも潜在的にあった女性嫌悪。気付かされたとき、自分でも意識しないまま行動してしまったこと、なんとなく感じていた違和感。燃えるような感情になった。
もっとはやく知っていたら、あんな行動しなくてすんだのに。自分ばかりが悪いと思っていたけれど、実はそうではなかったのでは?
一度読んだだけでは理解が追いつかない部分がある。
けれど、フェミニズムってこれからを生きる誰にとっても必要な知識だと思った。
差別は中々無くならないけれど、無くそうと意識することが大切だと思わされる。
Posted by ブクログ
タイトルに反して、自分を尊重しない・理解する気がない相手との対話は打ち切ってもなんの問題もない、というのがメインの内容。
「理解」とはするものであり、現状において権力を持つ側が弱者に差別について説明させて理解させてもらうという態度であるのは思い違い。
ミラーリングにだけ関心を持ち怒り出す女性嫌悪者たちは日本でも多い。
権力構造上、男性嫌悪ミラーリングは女性嫌悪のパロディとしての力しか持たない(誰の命も脅かさない)のだが、解像度が低いせいで低レベルのやり方にしか反応できない。
Posted by ブクログ
フェミニズムを説明する本ではなく、性差別に傷ついてきた女性に護身術を伝える本です。
よって、性差別を受けたことがない男性はピンとこなかったり、内容にイラつくと思います。それこそが、加害者である権力者側にいる証拠です。お前たちのせいで我々は傷ついてる!と言われたら、心穏やかではいられないですよね。
私はつい、そんな男性にも女性差別の現状がわかるように受け入れやすいように、更には気分を害さないように言葉を選んで心を配って説明しようとしてしまいます。
しかし著者は、わかってもらう必要はない。説明する義務はない。相手が教えてほしいと言ってきた時だけ相手してやればよい。と断言しています。
もう、力を尽くして説明してもわかってもらえなくて余計に傷つかなくてもいいのだと、肩の荷が降りた気分です。
私はこれまで、「男性だって大変」とか「女性の人生にもいいことはある」、といった言葉に惑わされて確信が持てなかったのですが、この本を読んで、女性差別はある、と断言する勇気をもらいました。
Posted by ブクログ
中年の男性が多い職場でモヤモヤすることが増えて買った本。
答えない選択肢があるということを意識するだけでもだいぶ救われた。
小さいことでも声をあげていいと思う。
当たり前に麻痺したくない。
Posted by ブクログ
韓国のフェミニズムの本。
友達が卒論書く時に読んでて、気になってたから読んだけど、
学校で学んでたことが事細かに書かれてて、
最近女性軽視発言を気にしなくなってた自分がいることに気づいてた。
人間って最初は疑問に思っても、あまりにもその状態が続くと麻痺して何も感じなくなるんだよな。
私は私らしく、違和感を得た時は声を上げなきゃ。
Posted by ブクログ
男性である自分が読んだ感想です。
まず、女性が声を上げることに対する反発に対する作者の大きな怒りを感じ、男性側が内容についてとやかく言ってはいけないとまず感じました。
文中に何度も出てくる、女性の話を遮り差別をなくす男性像は生々しく、自分も同じことをやっていたなと反省しかありません。
「なにが差別なのかは自分で決める」、「差別される側の経験を否定されると差別がなかったことにされる」といった言葉は重く、それを受けて自分を含めた男性側が変わらなければ社会が変わっていかないと感じました。
そう思った男性に対する処方箋も本書の中には用意されています。まずは、女性に教えを乞い、いままで見過ごしていた周囲の女性嫌悪的な発言を正すことで自分の周囲の差別だけでも減らすよう努力すべきというものです。できることは多くないですが、文中にあるとおりフェミニズムの主体は女性です。あまりでしゃばったり上から目線にならないよう注意深い行動が必要となることもわかりました。
以上、女性だけでなくジェンダー平等に興味のある男性でも読む価値のある本でした。
Posted by ブクログ
マジョリティには、マイノリティのことを学ぶ責任がある。学びもせずに検討外れな意見をしてくる連中など無視しよう。差別には怒りの声をあげよう。私たちはもう黙らない。
Posted by ブクログ
作中でも「そう見えるかもしれない」と幾度か出てきていたが、若干女性と男性の対立をベースにして書かれた本というふうに読めてしまった。
永遠に続いてきたかのような家父長制社会において女性を奮い立たせるため、言葉を口ごもらせず外に出させることを目的にして書かれた作品。そういう角度が必要なときもきっとある。
Posted by ブクログ
女性の味方になってくれるような本だと思った。
数字を示して論理を展開しているものではないし、読んだ後に自分の中にあった疑問が解決してすっきり、となるわけではない。だけど、女性であれば誰しもが感じたことがあるであろう、もやも体験が綺麗に言語化されていて、「やっぱりみんな同じく感じてたよね」と安心出来、大変だったら無理にわからない人に説明する必要はない、と言ってくれ、勇気を持って対話してみようと思う人向けには、そのための武器(言葉)を示してくれている。
筆者が各シチュエーションで提案している反論の際の言葉の選び方はとても的確で、痛快。もちろん論理の筋を通すことも大切だが、相手に正確に考えを伝えるために私に必要なのは、言語化の力を磨くことだな、と思った。
(筆者は言語が専門だということなので努力しても到底及ばないかもしれないけど笑)
Posted by ブクログ
フェミニズムについて男性と語るとき、なぜかこちらが説得しなきゃいけないような、言い訳めいた気持ちで話をすることが多かったけど、そもそもそれっておかしいことに気づけた。相手の態度が良かろうが悪かろうが、女性側に性差別を「知らない」相手に説明する義務なんて一切ないんだから、嫌なら話さなくていいということを強く主張し、いろいろな護"心"術を教えてくれる。
男性とフェミニズムについて話したことがあり、もやもやしたことがある人には読んでみてほしい。
Posted by ブクログ
理解する気もない人にわかってもらおうと言葉を尽くしてきたんじゃないか。わからないのはあなたの説明が悪いからじゃないよ。相手にわかる気が、ないんだよ。
めっちゃ、納得した。
Posted by ブクログ
ずっと読めてなかった本をようやく。
韓国だからなのか、発売された頃の空気なのか、それとも私が比較的恵まれた環境にいるからなのか、詳しくないので分からないが、セクシストとフェミニストが対立している構図が、今、女性である私自身が感じているものより酷く思った。
少し時間が経って、良い方向に向かっているのだと思いたいけれど、決して女性嫌悪がなくなったわけではない。未だに、この本に書かれているような言葉を投げかけられることはある。
その時に私は、性別による不平等はあるし、なくなるべきだというスタンスでやってきたし、これからもそうでいたい。だけど、話すかどうかは自分で選んでいい、話さない選択肢もとっていいということ、話す時のヒントを得られてよかった。
Posted by ブクログ
セクシスト的な人への対応の仕方マニュアル。
男性に対して丁寧に説明する中で古傷に塩が塗り込まれるような感覚になるから、一般の女性が、「それについては話したくない」という選択肢を当然持っていることに光を当てたのはよいと思う。
もし本当に社会を変えていくなら、女性全員がこの語り口でバサバサ斬っていくのはあまり得策ではない気がした。一般女性はこの書にあるような言葉で心身を守りつつ、活動家たちが男性やセクシスト向けに丁寧に説明していくことは必要だと思う。対立を深めるのではなくて、権力者側にいる男性の中に味方を作っていくことこそが社会を変える元になると思うので、その努力は必要。女の言うことは聞かなくても、同じ男から言われたら説得力も増す。
毅然とした態度を取ることと喧嘩腰になることは違う。私たちにはことばが必要、で、そのことばは平等と平和の礎になるべきものだ。その場で身を守るためのことばはこの本にたくさんあるが、本当に良い社会を築くためのことば、対話することばは別にある気がする。
ルサンチマン感が強い。
Posted by ブクログ
フェミニズムについて知りたくて読んだ。2冊目。なかなか読んでてしんどい箇所もあった。口喧嘩で勝つ方法のマニュアル書。
フェミニズムって呼ぶ理由とか、結局本人(私)がそう主張したいからそう主張する。他人(男)がどう思うかは関係ない。みたいな部分が大きいのかなと思った。
こんな男がいるんですよ〜に自分が重なることが多くて当事者意識が強かった、反省
Posted by ブクログ
正直な気持ちを書き記します。
今後、何度も読み返す必要があり
その時、どこまで自分が理解を深められたか
把握する為。
日本はまだまだ女性軽視が根深く存在しており、
女性自身が差別を受けているという認識を
持てていない‥、そういう方が多いと日々感じています。
私自身、女性差別を受けた経験があります。
残念ながら、その時に相手に対して
女性差別発言であると指摘することは出来ませんでした。
本書では相手から差別発言を受けた際の
対処方法が記されています。
ただ、全ての差別発言に対して反論、指摘しなければならないと言っている訳ではなく
見極めて相手にする必要がないと思ったなら
無視しても良い。
私達はその選択が出来るとも書かれてあります。
自分自身の気づきとして
女性自身が女性差別に加担している‥という記述を読み、確かにその通りだと思いました。
女性なのに‥
女性のくせに‥
こんな風に相手に対して思うことが
これまで何度もありました。
これ自体、女性差別的考え方だとあらためて気付かされました。
こういった考え方、発言は
幼い頃から、大人や社会から得たものです。
私達は無意識のうちに差別的言動を
周りの大人達やマスコミにより植え付けられており
自分で気づかなければ、そんなつもりもなく
同じ女性に対して差別的発言をし続けるのです。
これでは世界から女性差別を無くす事は
難しいでしょう。
私はまだフェミニズム、フェミニストの入口の扉ドアを開けただけに過ぎず、その本質への理解は足りていません。
ただ、長い間に癖付いてしまっている
差別的な考え方を変えて行きたいと思っています。
Posted by ブクログ
41.
「言葉の温度」ということばを今日たまたま見かけたのだけど、この本はかなりアツアツの温度で語られています。作者の方が今までぶつかってきた壁を想像してしまった。私もまだこの本をきちんと読むにはあまりにもアツくてちょっと難しかった。一方的な好意を寄せられた時の恐怖、相手が期待する対応をしなかった時の掌の返し方、そんな相手に私には拒絶する権利があるのだと言ってもらえて涙がでた。
まだアツアツの言葉をしっかり読むのがちょっとこわいけど、またいつか、今度はしっかりと読み返すことになる気がする。