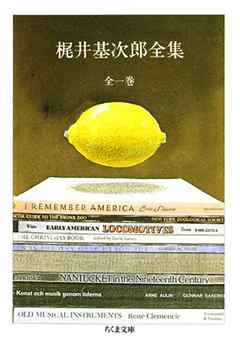あらすじ
ほとんど無名のうちに夭折しながらも後年、三島由紀夫をして「デカダンスの詩と古典の端正との結合、熱つぽい額と冷たい檸檬との絶妙な取り合はせであつて、その肉感的な理知の結晶ともいふべき作品は、いつまでも新鮮さを保ち、おそらく現代の粗雑な小説の中に置いたら、その新しさと高貴によつて、ほかの現代文学を忽ち古ぼけた情けないものに見せるであらう」と云わしめた梶井基次郎の全集。難解な語句には注を付し、すべての作品はもとよりの習作・遺稿までを網羅した全一巻。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
窓を覗く、檸檬を握る。私も彼と一緒のようなことを人生でやったことがある。でも彼のようには感じなかった。注視すべき一つの体験として自分のなかに刻まれなかった。ここに小説家とそれ以外の人間の差があるのかもしれないなと思った。
ひんやりとしたのものや清浄なものが熱病に冒されていた彼に与えた安らぎ。幼い頃、喘息を患っていた私にもわかるような気がした。
また本書とは関係ないのだが、寺田農氏による「檸檬」や「ある崖上の感情」の朗読が素晴らしいので、聞いてみてはいかがだろうか。
Posted by ブクログ
梶井基次郎という人は、結核という病を得て死について考え考え、考えぬいて生きたんだなというのがよくわかる。
世間と隔絶されてしまったかのような焦燥感、絶望感、最後は諦念と恐怖のなかにかすかに達観も見られ、どこか救われるような気持ちになったりもした。どれを読んでも胸にせまるものがある。
読みながら、自分自身の父のこと母のことを思い浮かべてなんともいえない切ない気持ちになった。
著者はこの文書を書きながら涙を流し、血を吐いているんだなと思った。
若くして亡くなったことを惜しむ声は多いけど、若くして亡くなることがわかっていたからこそ、ここまでの輝きを放った人だったのではとも思う。
Posted by ブクログ
美しい表現や文章に表すことができないような体験を文字として美しく羅列していると思う。
自分が今まで忘れていたようなことをこの人の文章を読んで思い出したことがある。
ただしまだまだスムーズに読むことができない話もたくさんあって、全部は読めていない。
年齢を重ねて、時が来たら読めるようになると思ってそれを待っている。
Posted by ブクログ
うつ病で一人部屋の隅にいた時にこの本を繰り返し読んでいた。この作者の作品群に共通して垣間見える孤独な感じが自分の心を癒してくれるような気がした。でも、少し幸せになった今は本棚から取り出す事がめっきり減った。
そんな作品。
Posted by ブクログ
自分の影と対話するような面と、母親や友人との、やりきれなさや苛立ちを抱えつつ、それでもどこか縋るような透明な関係性に共感して引きつけられる。
「檸檬」(角川文庫)になかった初読の作品では「路上」、習作の「卑怯者」「彷徨」が特に印象的だった。
「路上」では崖の道をあえて滑ってみたり、「冬の蝿」では病を抱えているのに山奥に置き去りにしてもらって遠くの温泉地まで夜中に一人歩く話が出てくるんだけど、実際の梶井さんも重症の肺結核で友人の前で川に飛び込んで泳いでみたりしたというから、病んでる人の持つ反転したエネルギーの凄さよ…。
ちなみに宇野千代さんの寄稿では、梶井さんの行動は彼女を心配させることを目的としたものだったとされてて、私的にはそういう次元に留まらないんじゃないかなと思ったりも。梶井さんが宇野さんに「死ぬときは手を握っていてくれますか」と生前言っていたのに実現しなかったエピソードは良かった。
Posted by ブクログ
この「ちくま文庫」が個人全集刊行を始めた、わりあい早い時期のものだったはず。「全集全1巻」なら、私も「梶井、読んだよ」なんて言えるなあ、と、そういう浅はかな思いが過ったことを告白します。檸檬と丸善があまりにも有名で、だからなんとなく知ったような気になっていた夭折の梶井基次郎、習作や遺稿や解説も含めたものを文庫で手にすることができるなんて、と欣喜したことも憶えています。ちょうどそのころ、梶井基次郎を偏愛していて「あんた、檸檬以外を知らないの?」と言う先輩がいたので、ともかくも、との意地もあって手に入れたフシもあり。ただしそれだけではなくて、「断片の迫力」に気圧されたことは鮮明です。断片だから、「……」から唐突に始まっているものあり、「、……(欠)」で終わっているものあり。「夭折」に関して、不可抗力であれなんであれ、「そーゆーことなんだなー」と、通り一遍の感慨しか持ち得なかった当時の私が、これで打ちのめされたのでした。優劣とか是非を云々するのではなく、「全集全1巻」の、その重さ。
Posted by ブクログ
文章うまいし短編ばかりだし読む価値あり。
「早逝したのは残念だがあれが絶頂期だった」と知り合いが言っていたが、個人的にはまだまだこれから伸びていく人だったなと思う。
一人称の作品が多いので、もっと三人称を描けるようになる梶井さんを見たかった。
心理描写もさることながら、会話文が一番好きです。
Posted by ブクログ
習作、遺稿を含めたすべての作品が収録されている。そのため、作品のいくつかは話が似ており、梶井基次郎が作品を完成させるまでの過程と苦労がわかる。また本書の末尾に、実際に梶井基次郎と親交があった宇野千代の文章も収録されており、宇野から見た梶井の人物像を垣間見える。それによると、人と話すのが好きでしかも話が面白かったという。その反面、自身の話については語ることは少なく、病気を患ったこと(それにもかかわらず激流の川の中に飛び込んだ)についても周囲に打ち明けなかったらしい。さらに解説によると、梶井は青春や病気に捉われたことで、日ざしや雲などといった世界を発見して、それが感情や感覚となって揺れ動いた自己を発見したのではないかと考えられる。
Posted by ブクログ
理不尽な病に生涯に渡って苦しめられるその惨めさこそ小説の本質であり、自分の運命と必死に格闘した梶井にとっては小説を書くしか生きる道がなかったのだと思う。
Posted by ブクログ
梶井基次郎作品集は他にもあるが、このちくま文庫版の安野光雅の表紙カバーのが一番好きだ。
開高健のエッセイから梶井のことを知った。
「檸檬」は、繰り返し読んでも飽きない。
昭和一桁の年代に書かれたものだから、古風な感じは拭えないが、暗いけど明るさがある。
Posted by ブクログ
高校だか中学だかの国語の教科書に、『檸檬』が載っていたことは覚えているが、しかし、こんな美しい文章だったことは記憶になかった。
大人になって読み返してみると、実に豊かな描写で感銘を受ける。
Posted by ブクログ
書きかけの小説とか断片だけ残っているものとか戯曲とかも含めてまるごと入った全集。初稿から改稿の過程なんかも載ってて面白い。改稿ってちょいちょい修正を入れるとかじゃなくてほとんどまるきり書きなおすのかよ~~~~~とか思ってびびった
面白いのはいくつかあったけど、やっぱり『檸檬』とか『櫻の樹の下には』が良かった気がしてしまう。まあ、すでに何度か読んだことがあるからかもしれないが。他のだと冬の蝿の話が好きでした。
読み飛ばしたけど、また今度気が向いたら断片だけの小説とかも読んでみるかもしれない
Posted by ブクログ
春なので、久しぶりに再読。
「櫻の樹の下には」は春になって桜が咲くと、つい読みたくなってしまう作品です。
「Kの昇天」「冬の日」「ある崖上の感情」もお気に入りです。
Posted by ブクログ
桜の樹の下には、
屍がうまっている。はずだ。
そうでなければあの美しさの説明がつかない。
生と死
美と醜というような対比なのか?
命という尊さがないと美しいものを生み出せないということなのか?
Posted by ブクログ
読み終わったばかりの時は感動も薄かったけど、数カ月たっている今も少し覚えているということは、何かココロに残っているのかな。
でもはやはり、私にはすっきりしないものが多かったような気がする...
Posted by ブクログ
最初の出会いは教科書。年齢バレるかな? 別にいいけど。
まったく興味が湧かなかったことだけは憶えている。“授業のテキスト”じゃ無理もないだろう。
思い返せば、中島敦も三好達治も教科書が最初だ。教科書、意外と侮れない。
その後どういった経緯で再び梶井作品に触れることになったのか、もはや思い出すことは困難だ。新潮社版の奥付には、昭和六十二年五月二十五日 第四十一刷とあるから、えぇと…………いつ?(笑)
とにかく今から20年以上前ってことだ。そのくらいに、梶井と三好達治に、分からんけど何かハマった。
三好達治のことはここでは置いておいて(梶井と三好は同人仲間)、梶井作品については、私自身若かったこともあって、透明というか、脆くて儚げで神経質なイメージに強い憧れを抱いたものだった。
もちろん、著者が「肺病持ちの物書き」ゆえ、「サナトリウム文学」とも謂われる一連の作品群が、若輩が抱くステロタイプな幻想に合致しただけなのは解っていた。
あれから20年以上経って、あらためてちくま文庫の全集という形で梶井作品に触れてみると、さすがにそういった上辺のイメージは払拭した模様。
代わりに終始まとわりついてきたのは、「すぐそこまで来ている死=不可避な現実=絶望」を内に抱えてなお書き続けた著者は、書きながら何を思っていたのかーーというような醒めた思考だった。
『檸檬』発表時病状はかなり悪化していたらしい。『Kの昇天』『ある崖上の感情』『冬の蠅』といった、若い頃読んで好きだった作品はもちろん、新潮版未収録の習作群を読むと、「死のなかに生きる人間」の悲痛さが浮き彫りになってくる。
ぼんやりと生きながらえている身だからこそ感じる痛みか……
最後に収録されている同人仲間との手紙のやり取りが印象深い。
歳月がもたらす変化はなかなか興味深く、同じ作品を読み返してみるのも悪くないと思った。(解説で群ようこ氏がすべてを台無しにしてくれるのをのぞけばw)
Posted by ブクログ
きれーな心の人。わからない方がいいことだってきっとある。頭のいい中学生の書いたものを読んでいるような、ププッと済ませたい夢見がちな作風。このテイストで子どもが迫ってきたら、大概のものは買ってあげるでしょう(笑)。
Posted by ブクログ
音楽会の最中の静けさに孤独を思う「器楽的幻覚」
猫の耳を切符切りでぱちんとしたい、猫の爪を切ってしまいたい、
そう想像しながら猫の前足を瞼に乗せる「愛撫」
桜の神秘的なほどの美しさの理由を見出す「桜の樹の下には」
影の中に別の人格を見ていたK君が溺死した「Kの昇天」
崖の上から期待を持って開いた窓を見つめる「ある崖の上の感情」
新任の先生につけたあだ名が勝手に広まるのを恐れ出す「大蒜」
なかなか帰ってこない小学生の弟2人を嫌々探しに行く「夕凪橋の狸」
土手の上から眺めた雲の恐怖を覚える「蒼穹」
ほか全27編に梶井の手紙を加えた全集。
装丁:安野光雅
本人も病を患っているからか病気の人物が多く、
彼らが見る世界の美しさやそこに感じる畏れが描かれています。
あまりにも有名な「檸檬」は色彩が本当に鮮やか。
Posted by ブクログ
『Kの昇天』―Kという青年が海で溺死したと手紙で知らされた語り手は、手紙の差出人に彼の死の謎について語ります...
ソログープの『光と影』と共通するものがあるみたいなことを書かれていたのを見たのがこれを読むきっかけになったと思う。どちらも美しい話です。シーンと静まり返って時間が止まったようなひんやりした夜中に読むと素敵だと思います。