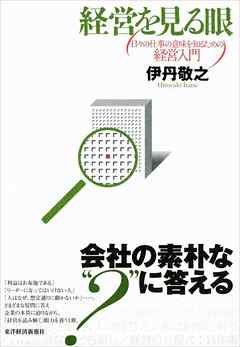あらすじ
斯界の第1人者が送る初の入門。「上司にどう対処するか」「経営ってそもそも何?」「ヒト・モノ・カネの関係」など経営に関する基本的内容を解説。経営を学んだ後に読んでも役立つ。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
経営とは何か?について総括的に解説した本。個からはじまってリーダーシップ、会社全体と徐々に視点高度をあげて解説している。総括的に知るには良書。
・会社の側から見れば、マネジメントの一つの本質は富と情報と権力と名誉の適切な分配にある、と言ってもいいだろう。それを分配される個人の側から見れば、会社は彼らの人生にとって大切なこれら四つのものの分配を決めてしまう存在なのである。
・契約社員は会社にとって、銀行借り入れと似ている。満期が来たら関係がいったん終わること、そして更新があり得ることを事前に想定している点が似ているのである。その点、正社員は株主と似ていなくも無い。
・(人の)流動性が高いということは組織というチームを安定的に組めないということを意味する。メンバーが流動的に替わるからである。それでは、ノウハウの蓄積やチームスピリットの醸成などに、マイナスであろう。そして、いずれ放り出されると働く人が思えば、企業へのコミットメントは小さくなり、カネをもらった分だけ働くという態度になるであろう。それでは、企業としての発展に必要な知恵やエネルギーを従業員が出してくれなくなる。
・リストラが必要な状況になってしまった責任は働く人々にはないのがふつうである。したがって経営者は3つのことをやらなければならないだろう。1.経営者による陳謝と感謝、2.去る人々への「過分なほどの」補償、3.会社に残る人々も賃下げや厳しい人事制度改革などで痛みを分かち合うこと。
・(株式の)売買差益というリターンの面白いところは、リターンを株主に与えているのが、新しく株主になる人だ、ということである。
・「利益とは社会から頂いているお布施だ」という考え方が花王では伝統的にある。利益が社会へのお役立ち料であり、社会からのお布施であると考えれば、赤字を出すということは社会に対してお役に立っていないということを意味する。つまり、赤字はその意味で社会的な罪悪なのである。
・リーダーのあり方を考える上で、教育と経営の類似性を考えることの意義は大きい。名経営者は必ず名教育者だ、と思うからである。なぜか。もちろん、人を育てることが経営者として重要だという意味で経営と教育は関係が深いのだが、それよりも本質的に、教育するということの要諦と経営するということの要諦が同じなのである。したがって、経営者あるいはリーダーはあたかも教育者のようにものを考えると、経営がうまくいく、ということになる。経営とは、他人を通して事をなすことだと再三述べている。他人が仕事をしてくれるのである。つまり、他人が「自ら事を行うように仕向ける」のが、経営なのである。それは、教育の本質と同じである。教育のプロセスがうまくいくとは、学ぶ本人が自ら学ぶことがうまくいくことである。教育の本質は自学であり、自育なのである。
・The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires. 凡庸な教師は、命令する。いい教師は、説明する。優れた教師は、範となる。偉大な教師は、心に火をつける。(アメリカの教育者ウィリアム・ウォードの言葉)
・リーダーになってはいけない人。1.私心が強い、2.人の心の襞がわからない、3.責任を回避する。
・リーダーの内への仕事のうち一番中心になるプロセスマネジメントについて、リーダーとしての基本行動は何だろうか。それは、部下たちを「刺激すること」と「束ねること」である。束ねとしてもっとも大切なのは「方向性を説得的に示す」ということであろう。リーダーが示した方向性に向かって、多くの人が努力すれば、それが自然に束ねになっている。ここでは出される方向性の納得性とリーダーの説得能力がカギとなる。
・最近、考えられないミスが現場で起こるという話をよく聞く。直接の原因は合理化しすぎて現場をぶらぶらと見回って何くれとなく細かいところに気をつけている年配者がいなくなったことだそうだ。それは結局、マネジメントする側の立場の人間に現場の想像力が足らなくなったから起きた現象なのではないか。そういう一見ヒマに見える役回りの人がいないと、現場で細かな刺激と束ねが少なくなってしまうのではないか、という想像力である。
・任して任さず、という一見、矛盾するような言葉がある。松下幸之助さんが好んだ言葉の一つだそうだ。リーダーが自分でやるべきことと他人に任せるべきことの間の線引きの微妙な消息を伝える言葉である。
・上司のマネジメントをきちんとできるリーダーに、部下は信頼してついてくる。1つには、上司のマネジメントの状況が、そのリーダーの人格の表れる、一種の正念場だからである。上司に言うべきことをきちんと言えるかどうか、たんなるゴマスリでないことをしているかどうか。その人の人格が表れる。その人格が、リーダーの背中を通して、部下にはわかるのである。もう1つの理由は、リーダーがきちんと自己をもち、自分の組織内の立ち位置とチームの進むべき方向性について深い理解や核心をもっていないと、上司のマネジメントはできないからである。上司を説得するにせよ、誤りを正すにせよ、それは何かの基準に照らしているはずのことである。その基準がない人には、上司に従うことはできても、上司のマネジメントなどできないであろう。
・(企業戦略と事業戦略の)2つの戦略は、その内容やカギがかなり違う。企業戦略は事業間の資源配分がカギ、事業戦略は市場対応行動のプランがカギとなる。だから、事業戦略をただ集めれば企業戦略になるわけではない。しかし、そんな現実例が多すぎる。それは、事業責任者をやれる人は案外いるけれど社長が務まる人が少ない、という経営陣の人材的偏りとつながっている。
・人間はやっかいなものである。現実を知りすぎれば、拘泥する。しかし、現実を知らなさすぎれば、実行可能な戦略はできない。そのバランスをどう取るか。戦略の大きな設計図はトップの責任でつくり、その詳細設計は現場に任せる。基本的にはこれしかない。
・競争優位の戦略は、しばしば戦略の焦点(たとえばターゲット市場)の絞り込みと資源の集中を必要とする。絞り込んで、その狭いところに資源を集中するから、その集中のおかげで集中の結果で生み出される武器が有効となり、差別化が可能となるのである。「一兎を徹底して追うものは結果的に二兎を得る」というのが、多くの成功した戦略のパターンになっている。
・差別化の武器をきちんとつくる必要がある、と書くと誰しも納得する。では、差別化の武器を挙げてくれと多くの企業の方に問いかけてみると、最初は、自分たちはこれだけのことが「できる」というものが武器として挙がってくる。しかし、本当に競争相手と明らかに差があるものは何か、と突き詰めて問いかけると、あまり多くの武器が残らないことがしばしばである。「できる」と「優位」は違うのである。なぜその違いに気がつきにくいかを考えると、3つの理由がありそうだ。1.「明らかな」差がなければ、顧客の目を大きく自社の方へ向けることはできないということを忘れがちである、2.優位かどうかの最終判断者が顧客であることを、つい忘れている、3.競争優位を考えるあまりに競争相手の動きにばかり注意を払い、肝心の顧客のことを忘れてしまうことである。
・顧客を終着点とするとは、本当に顧客が製品を使う時点が最後の審判のときであるということである。吉野家の例で言えば、顧客が牛丼を口に入れるその時点である。顧客が実際に食べる時点で、うまい、安い、早い、と感じてもらわなければ、差別化の意図は実現できていない。吉野家がそういうキャッチフレーズをつくれれば、顧客がそう思ってくれるわけではない。吉野家の意図を実現できるように実際の仕事がきちんとなされなければならない。そのための仕事の仕組みの基本設計図が、ビジネスシステムである。
・ビジネスシステムの設計とは、基本的には次の3つの事柄の決定である。1.どんな業務を自分が行うか、何を他人に任せるか(他者との分業のあり方)、2.自分で行うことを、どのように行うか(企業内の仕事の細かな仕組みシステム)、3.他人に任せることを、どうコントロールするか(分業した業務のコントロール)
・戦略のカギを考える際に大切なのは、見えざる資産である。それは、技術、ノウハウ、信用、ブランド、システム力、などさまざまな目に見えない資産である。見えざる資産が戦略の背後できわめて重要である理由は2つある。1つには、見えざる資産が競走上の優位性の真の源泉だからである。見えざる資産は、カネを出しておいそれと買うわけにはいかない。自分で育てる必要がある。そして、自分で蓄積するには時間と手間がかかるものが圧倒的に多い。その時間と手間の部分が、競争相手との差をつくる源になっている。第二の理由はそれが変化対応力の源泉だからである。変化とは、既存事業での競争条件や需要の変化もあるし、産業構造の変化もある。それらの変化へ対応して既存事業を革新しあるいは新事業を開拓していくために、見えざる資産が使われる。見えざる資産は、見える人には見えて、見えない人には見えない。だからやっかいなのだが、そのやっかいさが戦略の優劣の大きな原因の一つになっている。
・ケンカのさせ方が大切とは、組織構造を設計するときに、どんな構造をつくっても組織の内部にコンフリクト(対立)が発生することを覚悟したほうがよく、むしろどんなケンカのさせ方が建設的かを考えた方がいい、ということである。しばしば起きる誤りは、対立が生じないような構造を懸命に考えるという誤りである。しかしそれは間違いで、むしろ、必要な対立が表面化して、建設的な解決策への議論へと進むことを狙うほうがいい。(例えば、銀行の審査部門を、営業とは独立の本社機構の主要部門と位置づけるか、複数の営業部門それぞれに審査部門をもたせるか)建設的なコンフリクトの吹き出させ方とは、そのコンフリクトが吹き出して顕在化することによって、重要な問題の存在をきちんと多くの人に知らせるような吹き出させ方、あるいはそのコンフリクトを解消しようとして多くの人が前向きの努力をするようになる、そういった吹き出させ方である。
・組織構造は人を動かすためにある。しかし、人は組織構造の下で育つものである。
・影響行動とは、部下の行動がより適切になるように間接的に影響を与えたいという行動である。たとえば、インセンティブを与えて部下の行動を導く、目標設定を部下と行う、部下が目標の達成状況がわかるよう期中に業績情報を提供する、などがその例である。直接介入は文字通り介入で、任せることの一時的中断である。
・当たり前スタンダードは私の造語である。一時期グローバル・スタンダードという和製英語が流行ったことがある。韓国と日本でしか通用しない英語だと聞いた。その頃、グローバル・スタンダード流行に違和感を感じて、グローバル・スタンダードより当たり前スタンダードを守るべき、と言いたくなったのである。当たり前スタンダードとは、文字通り、誰が考えても当たり前の標準、という意味である。例えば、1.顧客の満足度を本当に考えた行動を組織のあちこちでする。2.若いエネルギーを大いに活用して、スピードある組織活力を保つ。3.社長は大きなビジョンを掲げて、しかし責任を取るべきときはきちんと取る。4.資本の効率をきちんと維持する。
・松下幸之助さんの言葉に、「経営者の仕事は大きな事を考えることと、小さな事に目を配ることだ」という言葉がある。細部に注目して経営を見るようにすると、案外ものが見えてくる理由は3つある。第一に「現場こそすべて」だからである。いくら社長が立派な理念をもっていても、実際の仕事をするのは現場の人々である。彼らの細かな行動がきちんとしていなければ、組織としての業績は長期的によくはならない。その現場は、細部である。その細部まで経営の意思がどう伝わり、どう実行されているか。それが、経営のよし悪しを最終的には決めるのである。第二に「一事が万事」だからである。現場の細部にその組織全体の傾向を象徴するようなことが表れることが多い。だから、一つの細部を見ることで、全体の様子の想像ができる。一事が万事とは、一つの現象が実は氷山の一角であることを意味し、また一つの行動がその直接の対象にだけでなく多面的な波及効果をもつということである。つまり、細部は全体の象徴なのである。第三の理由は、細部が「蟻の一穴」だからである。立派に見える堤防も、そこに蟻の穴が一つあると、そして「不運にも」その穴から水が漏れ始めると、堤防の決壊につながることがある。細部と見えることが、大事をもたらす小さな出発点になってしまう。だから、そうした小さな穴を早期発見、早期解決できるかどうかで、経営の成否はかなり決まる。経営を見るとき、そんな眼で細部をあえて見てみるといい。
・(経営の論理に関して)私は次の3つの論理が大切だと思っている。1.カネの論理(経済の論理)、2.情報の論理(みえざる資産の論理)、3.感情の論理(人間力学の論理) それは仕事をする人間が三面性を持っているから。カネを必要とし、カネのことを気にする経済的存在・物理的存在としてのヒト。情報をつかみ、学習し、他人に情報を伝える、情報的存在としてのヒト。そして、感情をもち、他人の動きや言葉に感情的に反応しあう、心理的存在としてのヒト。三つの面すべてを、一人の人間がもってしまっている。分かちがたい。したがって、どのような経営判断、経営のあり方の決定も、必ずカネ・情報・感情の三つの流れに影響を及ぼす。その影響を通して、現場の人々の行動が左右されてくる。だから、この三つの流れがどうなるかの論理が、経営を考える際の三つの基本論理となる。