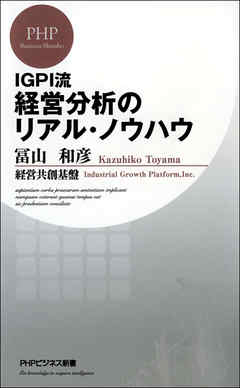あらすじ
経営分析、財務分析の本は山ほどある。ただ、「机上の空論」で終わるものも少なくない。「数字のウラ側を読み解く技術」を身につけられる本書は、それらとは一線を画す。会社が生きるか死ぬかの修羅場で真剣勝負し、成功を収めてきた企業再生のプロフェッショナル・冨山和彦氏。氏が率いる会社・経営共創基盤(IGPI)のコンサルタントとともに、独自の「実践テクニック37」を初公開!メーカー、小売・卸、通信、飲食ビジネスなど、具体的なエピソードが満載で、物語を読むような感覚で理解できる。勤めている会社は大丈夫か、取引先は……。日々、状況把握を求められ、「診断ミス」が許されない営業のリーダーに、必ず役立つ一冊。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
当たり前に思える部分もなくはないが、本質的な分析およびリアルな勘所を押さえた話は参考になる。
<メモ>
規模の経済が働く世界、働かない世界。
範囲の経済性、資源の有効活用。相乗り。
密度の経済 ドミナント戦略
ネットワーク外部性
スイッチングコスト
相場観を身につける。いろんな商品・サービスの価格が浮かぶようにしておく。スーパーなどでも価格をみて、原価・商流を意識する。
事業が本来持つ事業サイクルを意識して判断をくだすこと。
Posted by ブクログ
画一的な経営分析では、経営の舵取りはできないことを示唆した本。
1.隠れた病気を発見し、今後の治療と将来の予防に役立てるのがリアルな経営分析であって、過去を評価するためのものではない。目線は常に未来に向いている
2.リアルな経営分析では企業ごとの実態の違いに目を向けなければいけない。全てを一括りで扱う投資家向けの財務分析の世界とは違い、りんごとみかんを一律指標で分析・比較してはならない。
3.経営分析はナマの事業モデルをつかまえることからスタートする。みかんとオレンジは、よくよく見ないと区別がつかない。
4.細かい業界専門知識を持つことは、必ずしも経営分析力に直結しない。「結局どうなのか」を知るには、売上インパクト、コストインパクトの大きな部分に目を向ける必要がある。
5.同じビジネスでも、業界ポジション、成長ステージやスピード、経営者の資質と組織との関係性などによって、企業を見るための「ものさし」を変えなければいけない。
6.経営分析はまず数字から。数字をもとに背後にある企業実態を想像する。出てきた仮説を現場に足を運んで検証して企業の実像に迫る。その繰り返しで分析の質を高める。
7.PLを突破口に木々用実態を思い描き、BSで確認し、最後はウソのないCSでチェックする。
8.簿記は必ずやっておくべき。現場で使える経営分析の能力は、しっかりした簿記の土台の上に築かれる。
9.世の中は教科書通りには運ばない。本当の観察力、想像力は経験を積むことでしか培われない。そして、その学習スピードは、数字と人間の両方に対する「好奇心」次第。
10.戦争に勝つのはより多くの情報を持っている者。経営改革という戦争の勝者になりたかったら、経営分析力を磨け。
11.当事者意識を持たずにいくら決算書を眺めても、付け焼き刃の知識しか身につかない。経営の修羅場、ガチンコ勝負に飛び込め。
12.たかが会計、されど会計。せっかくの人類空前の発明品は都合よく使いこなすべし。
13.経営分析の目的は、まずは勝つためのルール(儲けの仕組み)を理解すること。経済原則、特にコストを支配する法則が何かは必ず押さえるべし。
14.事業の経済メカニズムについて、世の中は誤解だらけ。安易に「規模が効く」と思い込むな。まずはありのまま現実を凝視し本質を洞察せよ。
15.単純に規模を拡大しても、その効果が得られる業種は、実は驚くほど少ない。共有コストが薄い場合、むしろ規模の不経済が働き、勝敗を決めるポイントは拡散する。
16.優勝劣敗の構図が本当に変わるのは、経済構造が変わったとき。そこで当該事業が消えゆく運命なのかを見定めるのも、経営分析の大事な仕事である。
17.経済の本質のひとつは、人間心理である。人間音痴では、正しい経営分析はできない。
18.世の中の多くのビジネスを支配しているのは、実は「密度の経済性」。単純な「規模」だけでなく、「密度」の持つ意味にも着目せよ。
19.同じ事業のように見えても、購買行動、立地、業態などによって経済構造は異なり、重要な経済指標も違ってくる。「違いのわかる」分析者になれ。
20.普及するほど利用価値が高まるネットワーク型の商品・サービスの場合、リスクをとって全速力でシェアを取りに行くことが正しい行動となる。先手必勝!
21.イノベーションなどによって、市場の創造〜成長〜成熟は繰り返される。分岐点における競争ポジションによって個別企業のとるべき戦略も変わる。経営分析でもそのダイナミズムを見極めないとならない。
22.顧客が他社製品に乗り換えるスイッチングコストを高めることは、提供「価値」を「適正価格」として実現する基本中の基本戦略。顧客サイドの経済性を分析せよ。
23.見た目は同じ工場でも、系列取引の割合を見極めないと、経営の実態に近づくことはできない。B to Bビジネスでは、このような産業構造的な視点からの経営分析を忘れるな。
24.インダストリー・バリューチェーン全体の成熟度合いとイノベーション、その中での位置付け(より多くの価値配分を勝ち取れるポジションにいるか)の両方に目を配らないと、企業の将来の競争優位性は掴めない
25.大競争時代の勝ち抜きの決定版は、スモール・バット・グローバルナンバーワン・モデルで、価値(価格実現力)とコスト(規模の経済)の両取りを狙うこと。スモールセグメントでのシェアとコスト、そしてスイッチングコストに着目せよ。
26.儲かっているビジネスこそ要注意。運と実力を冷徹に見極めよ。
27.経済メカニズムの視点を各種分析枠組み(3C分析や5Forces分析)にしっかりと入れることで、個別企業のあるべき姿と、その裏返すでその企業が直面する問題点や課題がよりクリアに見えて来る。事業経済性で本質に迫れ。
28.単価と数量を掛け合わせれば売り上げがわかる。売り上げを1日、1店舗、一人あたりに細分化すれば具体的な姿が見えて来る。
29.PL全体でのストーリーをつかみ、BSでそれを確認する。どんなヒト、モノ、カネ、業務プロセスが絡んでいるかを、PLとBSからイメージ化できると「勘」が働き出す。
30.ある数字を見て異常に気づくためには、相場観が欠かせない。特に値段のリアル感に敏感になることは、あらゆるビジネスの基本である。あなたは今日のトマトの値段を知っているか?
31.単品管理を徹底すれば、どんぶり勘定の余地がなくなる。大抵の問題はそれで解決できるはず。
32.お約束通りにやる財務会計は出発点。分析者の経営センス、オリジナリティーが問われる管理会計こそがゴール。
33.売り上げを増やすのに、どのようなコストがかかっていくのか、どのような売り上げの伸ばし方が、コスト効率が高いのか、という「コストドライバー」の視点で勝ちパターンを見極めていくことが重要。
34.数字の分析を徹底的に突き詰め、壁にぶち当たり、悩み、苦しむことで、その会社の組織サイド、人間サイドの本質的な問題も浮かび上がってくる。
35.月次、四半期、年度決算がその事業のサイクルと一致しているとは限らない。当てる定規の長さによって、業績の評価や予測は大きく変わることは少なくない。
36.取引先や競合他社を見るときも、財務データ、経営データを分析することで、従来とは違った見方を手に入れることができる。プロが本気で分析するのは、その会社と事業の経済性(儲けを決めるメカニズムとその堅固性)と、財務の健全性(いざというときの生存能力)。この2点について、数字と業務実態がコインの表裏のように整合的に納得できるまで、徹底的に分析せよ!