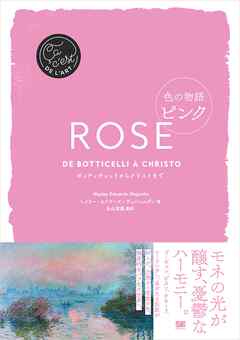あらすじ
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】
なぜこの色に魅了されるのか? アートにおける“薔薇色”の物語
◆華やかさの裏側にあるものとは
好評既刊「色の物語」シリーズ、第二弾。仏語で「ROSE」はピンク色・薔薇色を指します。小さな女の子の色というステレオタイプで扱われてきたこの色は、過去には権力者の色だった時代もありました。皇帝ヘリオガバルスによる凶悪な薔薇の逸話を知っていますか?
◆美の理想から、誘惑の色へ
ボッティチェッリによる美の理想・ヴィーナスや、ロココの時代に多数描かれた官能的な肉体。モネやピカソといった巨匠はこの色をどのように使ったのでしょうか。現代では、モードやポップカルチャーと結びつき、力強い存在感を放ちます。本書ではピンク色に彩られた著名な美術作品のビジュアルを多数掲載。色と美術作品の知られざる関係を、気鋭のフランス人美術史研究家が解説します。
◆構成(抜粋)
アートにおけるピンク/ピンクの世界地図/ピンクのヴァリエーション/ヴィーナスの誕生(ボッティチェッリ)/櫛(喜多川歌麿)/ラヴァクールのセーヌ川に沈む夕陽、冬の効果(モネ)/タヒチの女たち(ゴーギャン)/アヴィニョンの娘たち(ピカソ)/An Homage to Monopink 1960 A (村上隆)/ピンクのコートを着たグールゴー男爵夫人の肖像(ローランサン)/ピンクの貝から(オキーフ)ほか
【「色の物語」シリーズ】
その色はどこから来て、どこへ向かうのか。古今東西文明のなかで、さまざまな意図で使われてきた「色」の歴史とストーリー、影響力を、名だたるアート作品の美しいビジュアルでたどる。地図や図解、年表等のグラフィックも豊富に盛り込み、多彩な角度からの解説が特徴。第一弾「青」好評発売中。続編「黒」「赤」「ゴールド」刊行予定。
【著者】
ヘイリー・エドワーズ=デュジャルダン
美術史・モード史研究家。エコール・デュ・ルーヴル、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション卒業。キュレーター、フリーランスのライターとして、ヴィクトリア・アンド・アルヴァート美術館の調査事業や展覧会に協力するほか、個人コレクター向けのコンサルタントとしても活躍する。ギ・ラロッシュのメゾンのアーカイブ部門の設立を手がけた。パリでモード史、ファッション理論の教鞭をとる。
【翻訳者】
丸山有美 Ami MARUYAMA
フランス語翻訳者・編集者。フランスで日本語講師を経験後、日本で芸術家秘書、シナリオライターや日仏2か国語podcastの制作・出演などを経て、2008年から2016年までフランス語学習とフランス語圏文化に関する唯一の月刊誌「ふらんす」(白水社)の編集長。2016年よりフリーランス。ローカライズやブランディングまで含めた各種フランス語文書の翻訳、インタビュー、イベント企画、イラスト制作などを行なう。
※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
BLEU「青」に続き、今回はROSE「ピンク」の系譜を辿っていく。
著者曰く、ピンクのフランス語は”rose”「薔薇色」で、薔薇の花が持つ豊かな色合いを意味する。(あくまで個人の感覚だが)ブルーと違ってピンクは濃淡の幅が広く、場合によっては電灯の色に溶け込んでしまう。
本書では≪ヴィーナスの誕生≫(P.18)etc...といったアート作品に、幅広いピンクのイメージが散りばめられている。そのためなるべく外が明るいうちに、自然光が降り注ぐ場所で読んでいただくことをお勧めしたい。
最近は疑問視する声もあるが、少し前までは「ブルー=男性」「ピンク=女性」の色と(いつの間にか)定められていた。
しかし女性の色であると決めつける以前に、ピンクは古来より様々な場面で重宝されている。何ならフランス革命以前は男性王族・貴族の衣服にも用いられており、豊かさの象徴であった。(著者がフランス人でその基準なのは仕方がないにしても、世界的にはどうなのだろう)
≪軍神マルスに扮したアンリ4世≫(P.22)は初めて見たけど衝撃的!ピンクの鎧を纏うアンリ4世。
現代人目線だと、誇らしげであろう笑みがチャーミングに映ると同時に、猛々しい印象のマルスがある意味塗り替えられたような感触を覚えてしまう…。
他に驚かされたのが肌の色。
ピンクは肌の色に抑揚を与えるといい、 本書でも≪アヴィニョンの娘たち≫(P.46)や≪6人の踊り子≫(P.90)等、ピンク肌を強調した絵が多数取り上げられている。肌に注目しながら鑑賞していくと、ピンクの採用率が高いことに驚くだろう。「ローズ・ドゥ・ナンフ」(妖精の肌を思わせる色)なんて種類もあるほど、ピンクと肌は切り離せないようだ。
ふと、昔通っていた英会話クラスの教材を思い出す。塗り絵を通して色を学んでいく章で、白人男女の肌から矢印が引っ張られた先には”pink”と書いてあった。ピンク色の肌を持つ人がいるとは信じられずにいたが(イギリス人教師は”pink”と言って聞かなかった)、これでようやく合点がいった。
時代や文化によってピンクの持つ意味が変わってくるのも興味深い。
前述のフランスでは豊かさの象徴であった傍ら、イギリスでは「堕落」を意味する。古代ローマ皇帝が大量の薔薇で招待客を窒息死させるという事件を描いた≪ヘリオガバルスの薔薇≫(P.40)は、植民地で栄華を誇っていたヴィクトリア朝を皮肉っているという。
同ヴィクトリア朝時代の作品≪ポプリ≫(P.86)にも大量の薔薇が描かれているが、かたやこちらは堕落というよりも憂いが浮き彫りになっている。ポプリ作りをする女性の儚げな後ろ姿。赤髪も相まって、映画「タイタニック」のヒロイン ローズ(奇しくも!)を彷彿とさせた。
どちらの作品も、「薔薇色」が決して喜び一色を表すものではないことを教えてくれる。「絵」は口ほどにものを言うってか。
陽気で余裕があって、時に浮いてしまうピンク。
その種類同様、幅広い層から受け入れてもらえると良いな。
Posted by ブクログ
中世・ルネサンスまでは、いわゆるピンクは淡い赤と認識されていた。ピンクが意識的に使われるようになったのがロココ。ピンクそのものがひとつの色として言及されたのが1837年。
昔から、絵画においては、いわゆるピンクは絵画の中での効果をちゃんと意識して使われていたのであろう。信仰、喜び、権威、美を表すものとして。ロココはもちろんエロスでしょう。でもねえ、こうやってこの画集でピンクが目立つ形で使われている絵画を見ていくと、はっきり言って違和感の方が多いなあ。ロココやドガが女性を表現するのに使っているのはそうでもないのは、ピンクは女性的な色という固定観念があるのかなあ。ローレンス・アルマ・タデマの「ヘリオガバルスの薔薇」のピンクは主役の異常性を表すのにはふさわしいと感じる。オキーフのピンクもなんかエロチックだ。こういうちょっと特異な絵にはふさわしいと思ってしまう。