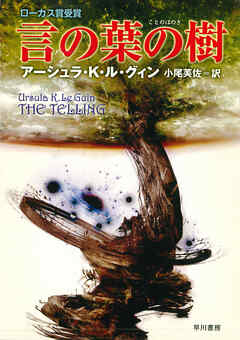あらすじ
古い象形文字で書かれた、詩や小説、歴史書、哲学書など、過去のあらゆる本が焚書にされる惑星アカ。科学技術の進んだ大宇宙連合―エクーメンと接触後、圧政がしかれているアカは、伝統的な文化を捨て去り、新たな道を進みはじめていた。そんな世界に観察員として、地球から派遣された若き女性サティが知った伝統文化“語り”とは……『闇の左手』と同じ“ハイニッシュ・ユニヴァース”を舞台に描いたローカス賞受賞作。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
読みにくいが、最後にはホロリとさせられる
表紙 6点小阪 淳 小尾 芙佐訳
展開 6点2000年著作
文章 5点
内容 750点
合計 767点
Posted by ブクログ
ゲド戦記から入った私はこれがル=グウィンの初SF体験でした。
SFはほとんど読まないので、ストーリーに入るのに少し時間がかかりましたが、読み進めていくとやはりル=グウィンらしさがあり、だんだんとのめり込みました。言葉を大切にするところやフェミニズムをしっかり入れてくるところなどゲド戦記に通じるものがありました。
SFは私にとってはやや読みにくいのですが、これをきっかけにル=グウィンのものから読んでみようかとも思いました。
Posted by ブクログ
「闇の左手」と同じく<ハイニッシュ・ユニバース>シリーズのこの作品。
今度の主人公はテラ(地球)出身の女性、サティ。宗教を初めとした文化を一元化しようとした「ユニシス」が支配していたテラでは、キリスト教以外の宗教・考え・芸術全てが弾圧の対象になっていた時代があった。そんな時代に生まれたサティが、エクーメンの観察者として同じようなことが行われているアカという惑星にいるところから始まる。
ル・グインはその舞台となる惑星を見てきたかのように、風景や人物や文化を鮮やかに描き出す。
今回のテーマは「異文化との接触」。どうやってその異文化を受け入れ、拒否し、解釈するか。そんなことが丁寧な文体で書かれていく。
サティが旅をする山「シロング」の景色は厳しくも暖かい。旅の友となっているアカの人たちも弾圧されて隠されていた「語り」をサティに教えつつ、自分達の存在をまとめようとしているように思える。
「闇の左手」が男性ふたりの強烈な友情を軸に、激しくまとめられたものだとしたら、この作品は出てくる人物みんなが優しい視線で相手を見ているためか、非常に穏やかな作風になっている。
個人的には「闇の左手」ほどの感動はなかったが、さすがとうなる筆のうまさの作品。
Posted by ブクログ
極端に抑制を効かせた文章が、最後の3行で恐ろしく詩的になって、言いようのない高揚感に包まれたところでストンと終わるという、半ば途絶したような印象さえ与える結末も、このドラマが「ハイニッシュ・ユニバース」という大きな枠組み、その中でおそらくは無数に形成されている社会の、ごく一端でしかないことを示唆していて、他の社会で生み出されるドラマへの興味をそそられずにはいられない。
Posted by ブクログ
アーシュラ・K・ル=グインの言の葉の樹を読みました。闇の左手と同じ世界設定の中で語られる、原題はTELLING(語り)というSF物語でした。アカと呼ばれる世界では伝統的な文化を捨て去り、継承者を迫害し本や記録を破壊する圧政がしかれていた。そこに地球から派遣された文化人類学者の女性サティは地方にはまだその伝統を継承している人たちが残っているはずと考えて、風前の灯火である伝統的な文化を守ろうとするのだが...ちなみにサティはインドの女神でシヴァの妃です。これも、この物語の隠し味になっています。この物語を読みながら、つらつら考えたのは、文化というのはその担い手がその文化の中で生活していくからこその文化であり、絶滅した動物の剥製のようなものは文化ではないということでした。例えば方言なども一つの文化ですが、その言葉を使って生活している人たちがいるからこその文化なのであって、その基盤が壊れてしまえば後は衰退するだけだと思います。そして、いったん壊れてしまった文化は元に戻すことはできないんだろうなあ、ということです。ヨーロッパの人たちがネイティブアメリカンや南米の文明を破壊してしまった後では、その文化を復元することはもうできないのだから。
Posted by ブクログ
外交使節でもある文化人類学者が、とある異国で失われつつある前近代の文化風習を再発見するための旅をする物語。
と、まとめてしまうと物語の骨格はSFでもなんでもないのですが、その「SFらしくなさ」が正にル・グィンらしさでもあります。
彼女が紡ぎだす「ハイニッシュ・ユニバース」の一端を成す作品。高度の発展を遂げた「ハイン人」が銀河規模で潘種し、地球人類もその一環として生まれた世界。その後、潘種された種族は衰退して星間の交流がなくなり、各惑星上で独自の進化・発展を遂げていく。やがて星間交流が復活し、星間連合「エクーメン」となって、未だ宇宙への再進出を果たしていないかつての同胞を教化・指導する立場となっていく。
そんな舞台設定を背景としているため、この作品をはじめとする「ハイニッシュ・ユニバース」シリーズに登場する異星人は全て地球人類と基本的に同種の生き物です。似たような文明を築き、似たような政治体制を変遷し、初対面でも最低限のコミュニケーションが取れますし同衾すらも可能です。
それは即ち、人間の現実社会をそのまま描いている、ということに他なりません。ル・グィンの作品は、SFというフォーマットを借りた「社会的寓話」とも言えるでしょう。
この作品は、特に、近代化の波に突如曝された前近代的文明(「前近代的」という言葉自体が非常に相対的な価値観を孕むため、鴨はあまり使いたくないのですが、他に適当なワーディングを思いつかなかったためこう表現させてもらいます)が自己の胎内に抱え込む相克を詩情豊かに描き出して余りあり、様々な観点から読み込むことが可能な作品だと鴨は思います。
ただし、これもル・グィン作品の特徴ではあるのですが、あたかも社会学のレポートと古代の叙事詩を足して2で割ったような独特のゆったりとした筆致で物語が進むため、一般的なSFにありがちな爽快感や驚き、手に汗握る面白さと入ったものはまず感じられません。特に物語の中盤は読み進めるのにかなりの忍耐力を要するレベル。読む人を相当選ぶ作品だと思います。