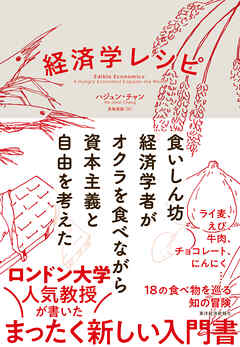あらすじ
牛肉、ライ麦、チョコレート、にんにく、えび……18の食べ物を巡る知の冒険
ロンドン大学人気教授が書いたまったく新しい入門書
コカ・コーラで「新自由主義政策」、鶏肉で「不平等」、いちごで「オートメーション」……
知っておきたい経済学の知識が身につく!
【推薦の言葉】
「名著だ。チャンは20年にわたり、ネオリベラリズムに代わるものを提供しようと精魂を傾けてきた。今、彼は研究人生の絶頂期を迎えている」――ダン・デイビース(英『ガーディアン』紙)
「チャンは複雑なことをわかりやすく説明するのが、ほんとうにうまい。料理でも、経済学でも、チャンの手にかかると、すこぶるおもしろい話になる」――ビー・ウィルソン(英『サンデー・タイムズ』紙)
「経済学の本を読んで、こんなに笑ったり、よだれが垂れそうになったり、反省させられたりしたのは初めてだ。楽しくて、深くて、食欲をそそる本だ」――ブライアン・イーノ
「素朴なネオリベラル料理だけで政策立案者たちは生きていけるという通念への見事な反駁の書。まさにご馳走のような一冊だ。世界各国の料理にまつわる機知に富んだ話とともに、経済の代案がずらりと並ぶ。ハジュン・チャンは本書によってあらためて、世界でも指折りのエキサイティングな経済学者であることを証明した」――オーウェン・ジョーンズ
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
1980年以降、経済学は新古典派だけになってしまった。イノベーションや行動経済学も組み込まれた付け足しでしかない。
アメリカでは奴隷は財産であり、貸付対象、担保にもなった。
1791年ハイチ革命で、フランスに反乱を起こし1804年に独立国となった。ルイ14世はルイジアナから撤退し、アメリカがこれを購入して領土が広がった。ハイチ革命がなかったら、ルイジアナはフランス領のまま。
資本主義と自由との関係は複雑、ときに両立しない。
労働参加率は貧しい国の方が高い。タンザニアが87%、ドイツは60%。児童の労働率が高い。
生産性の高さは環境によるもの。富裕国に移り住めば生産性が高まる。生産設備、高いインフラなどによる。貧しい国は、個人後からではどうしようもない問題で貧しい。真面目に働かないから、欠点があるから、ではない。
ペルーは、ペルー沖の片口いわしを食べた海鳥の糞による肥料や火薬製造によって潤った。ハーバーボッシュ法まで。一次産品は、たやすく他国に奪われる。ゴムやコーヒーの例。化学産品はそれとは違う富の奪い方をする。オランダは技術力で(温室)農地を増やし、水耕栽培で垂直方向に農地を増やした。高い生産水準のためには技術力が欠かせない。
幼稚産業保護論。日本が重化学工業を保護しようとした政策は批判があった。繊維産業に特化した方が競争風位があるのではないか、と。
英国と米国は、自由貿易発祥のイメージがあるが、世界一の保護主義の国だった。自国の産業が強くなってから切り替えた。しかし、安易にやると大人になり損ねる。
現代グループは、もともと建設業。自動車はフォードとの合弁産業。いろいろな要素、優秀な人材と政府の力で伸びた。三菱は海運会社としてスタート。発展は、個人の才能、企業努力、内部相互補助、政府の支援、消費者の犠牲、のおかげで成長した。
アメリカ国防省の防衛研究がなければ、IBMもインテルもアップルもなかっただろう。
自由主義社会での成功は個人主義ではなく総合力が必要。
ゴールデンライスは遺伝子組み換え問題で、軌道に乗っていない。
特許が絡まり合った状態で、技術的な進歩ができない。特許プールで共有する方法がある。そのほかにすべての特許を短くする方法、報奨制度で初期費用をまかなう、方法もある。
缶詰の技術は懸賞金によって発明された。
ウルグアイはサッカー王国でもあり、牛肉王国でもある。コーンは、もともと粒の意味。コーンビーフは塩漬けのための塩の粒から来ている。
穀物法は、産業と、貿易に課された政府の帰省とのと戦い。最終的には撤廃することで産業側の勝利となった。自由貿易の起源とされる。が、世界で最初に自由貿易を強いられたのは南米。不平等条約のせい。日本も同様だったが、城郭改正後は30%乘関税を掛けた。WTOでは現地調達率規制は禁止されている=富裕国に有利。
貿易の自由化は敬愛援助の条件となっている。
世界貿易は、力の不均衡により自由をいう名前で不公平な貿易を強いられている。
バナナは品種改良の結果、自分では子孫を残せない。バナナ企業は巨大になり、中南米の経済を支配した。現地に対しては功罪がある。新技術の導入に役立つこともある。外資導入策が成功する国もある。フィリピンは飛び地経済の被害国でもある。安価な労働力だけを使われて技術移転しない。合弁を義務づける、雇用の制限などが必要。規制を課してノウハウを手に入れようとする努力が必要。と同時に支援策で誘致する。
コカコーラの名称はコカの葉とコーラの実に由来する。ボリビアのモラレス大統領は、ワシントンコンセンサスに反して、主要産業、公益事業を国有化、社会保障費を増やした。経済学的には後退だが、所得格差が減少し、経済は成長した。アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、ウルグアイ、ベネズエラが続いた。ピンクの潮流という。ベネズエラの失政以外は。
発展途上国では、新自由主義が惨憺たる結果を招いている。
ドイツのビスマルクは、ライ麦生産者に関税の導入を認めさせて、重工業を発展させた。社会保障制度、公的年金を導入しt。社会主義運動の弱体化を狙った施策。そのため、社会保障制度は当初、社会主義者に反対された。労働者を買収する手段と映った。
福祉給付はただではない。全員が対価を払っている。スケールメリットがあること。そのために全員が安価で済んでいる。医療保険がないアメリカの医療費と比べると一目瞭然。細分化されてる医療保険ではスケールメリットを活かせない。
自由主義派は競争の結果を受け入れるべきと考える。しかし機会の平等を徹底できるか。男女差、人種差、教育差、など。ニーズや能力の違いをどうするか。
結果の平等を促進するためには市場の規制のほかに、社会保障制度による再配分がある。
GDPには、家事労働や無償労働を計算に入れていない。ワーキングマザーという呼び方は、主婦は働いていないかのように映る.ケア労働は無償であっても欠かせないもの。GDPでは過小評価されている。
壊血病の克服のため、英海軍ではライムがラム酒に混ぜる形で配られた。ライミーズといえば英国人を指す言葉。
船乗りにライムを摂らせるように、市場の問題には政府の介入が必要。
有限責任の会社はスパイス探しの大冒険を可能にした。スミスは、他人の金でギャンブルをするもの、と批判したが、資本主義の原動力になった。
行き過ぎた金融化で、株主還元割合が90%以上に高まった。長期的な投資ができない状態。議決権を保有期間で決める方法、株主以外のステークホルダーの力を強める、株主の選択肢を制限する。経済の進歩の妨げになっている。
機械化は、雇用を失わせるのはいつの時代でも同じ。AIが特筆されるのは、それを訴えている階級に危機が迫っているから。その技能が無用の長物になりかねない恐怖。
自動織機のおかげで、織工は4倍に増えた=安くなって需要が増えた。政策を通じて雇用を維持できる。コロナで明らかになった。
理屈では、学び直しによって新しい仕事に就ける。現実には教育以外の支援が必要。学び直しがなければ、高い技能を必要としない職にしかつけない。積極的労働市場制度が必要。
いちごはベリーではないのに、ベリーの代表格になっている。
スイスは工業国。ミルクチョコレートはスイス人の発明。後のネスレ。
脱工業化論の罠。製造業は人件費の安い中国のような国で行われ、富裕国は金融やIT、コンサルなどサービス業にシフトすると言われた。しかし、サービス産業化のお手本といわれるスイスとシンガポールは世界1位2位の工業国。
脱工業化の原動力は生産性の変化。需要の変化ではない。機械化で人では減っているので従事者は減る。しかし製造高は増えている。サービスの価格が相対的に工業品より高くなっているだけ。製造業は技術革新の源泉。企業内から外注化されているので、売り上げがシフトしているように見えるだけ。製造業の衰退は、脱工業化の印ではない。製造業がなくて他の産業だけが成り立つことはない。
経済学はいろいろな味方で見るべきである。経済学の分析は、材料のでどころがどこか、を調べるべき。