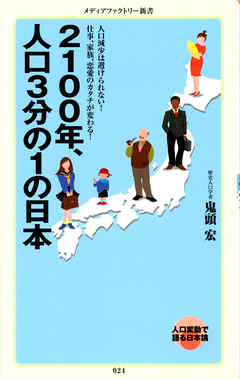あらすじ
現在の1億3000万人が、50年後に9000万人、100年後は4000万人にまで減ると予想される日本人口。この変動が政治経済や労働環境、家族関係など社会全体を激変させる。「過疎化」するニッポンの行方とは?歴史人口学者がデータを駆使して描き出す、渾身の未来予想図。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
【読書その175】増田元岩手県知事等の有識者から構成される日本創世会議の報告書が話題を呼んでいる。我が国において、人口減少への取組は大きなイシュー。そこで、NHKにも出演した、上智大学経済学部教授鬼頭宏氏の人口問題を扱った本。近代からの人口推移の議論は興味深い。
Posted by ブクログ
・日本人口が増えるのは、例外なく外部の文明を取り込んでいった時代。
・「年齢構成」と「地理的分布」の変化による不均衡の拡大。
・一人暮らしの老人が劇的に増え、2030年には700万人に達する。
・日本政府は1974年に「出生を抑制すべき」と明言していた。
・同質化した社会を変え、外に出よう。
・今後、食糧需要を補うための農業開発には常に環境問題がセットになる。
・地球が支えられる人口は多くて100億人。
・21世紀中に世界中で人口増加が止まると予想されているが、問題はそれまでに人口が膨大な数に膨れあがること。
・結婚した夫婦の出生行動は、ほとんど変わっていない、本当に大事なのは、未婚者への政策では?
Posted by ブクログ
こうやって見ると歴史と未来予測はつながっているのだなあ。211pの資源循環型再生可能エネルギー中心の人口分散型スローライフ高齢化社会の話は詰めるのが大変そうだが一理あるようにも思える。
Posted by ブクログ
日本の人口は、晩婚化・非正規労働者の増加(所得減)など子供が増えにくい状況になっていることを分析。実は政府が1974年に人口減を提言していたことはびっくり。対策としては、高齢者の活用、女性の社会進出、移民の受け入れ等の大体は予想していた内容。この状況を乗り越えるには結局は社会システムの大きな変革が必要と言うことか。
Posted by ブクログ
遠いようでそう遠くない2100年の日本。
人口が3分の1になった日本。
今とはかなり違った日本になるようだ。
悲観しているばかりではしょうがない。
人口は増えればそれでよいということではない。
社会を営む上で必要な人口を維持することが大切。
これからの日本社会はどうあるべきなのか。
日本の衰退ばかりをいう内容ではなく
人口減少をきっかけとした新しい国作りを提言するような内容だったので良かった。
でも問題はやはり深刻なようだ。
Posted by ブクログ
先日も大きく報道された人口減少問題を、日本だけでなく2100年の世界まで広げて論じた内容。
著しく減少していく地方に暮らして、弘前市でも経営計画のメインを人口減少対策にしているだけに、もっと考えていかなくてはならないテーマです。
Posted by ブクログ
人口統計調査ではもしこのまま何の対策も打たなければ、日本の人口は2100年に今の3分の一にまで減少する。これはそうなった場合どうなるのか、そのための対策を記載している。現状を踏まえた上で楽観的に今後の行く末を見ることができた。歴史人口学的にもこれまでの日本の人口推移などが分かって興味深い
Posted by ブクログ
今から出生率が奇跡的に上がっても、既に一億人を切る事は決定的な事実。労働人口を上げなくてはいけないから、女性の掘り起こしか、外国人受け入れしかない、という話。
個人的には大賛成で、ぜひ動くべき。今の人口ベースの日本で、年金や社会制度、増税を議論すべきじゃないし、無理がある。
Posted by ブクログ
歴史人口学者による、これからの少子高齢化社会の日本の姿。予測では、2100年には四千万人になると…。確かに、どれだけ出生率を増加させようとしても、すぐに変わるものではないしなあ。さらに2055年には国民の40%が高齢者に。
ただ、この本はいたずらに不安を煽るのではなく、希望のある未来のために現実を正しく受け入れそのためにこうしていこう、という提言がある。
そのために、日本だけでなく、世界の人口がどうなるか、経済はどうなるのか、労働環境はどうなるのか、俯瞰して将来の姿が見えるように細かく書かれている。
そもそも文化に伴い人口は比例するものではなく、少子高齢化は日本特有の問題ではない。日本がいち早く迎える少子高齢化は世界の問題を解決するコンテンツになる可能性さえあるのだ。
Posted by ブクログ
とりあえずのメモ。
少子化対策と移民政策を同時進行するのはダブスタではない。少子化対策の効果がでるには長い時間がかかり、其の間減少しつづける労働人口を補う必要があれば移民はあり。ただ経済規模が縮小してもいいなら移民政策はとらんでもいい。移民せず経済規模維持するならかなりの効率化が必要。
Posted by ブクログ
津波のように日本社会の在り方―経済成長から地域コミュニティー、国民意識までを変えてしまう。それが人口減少の持つ力の大きさである。本書では現在の出生率が続けば2050年には日本の人口は8900万人と1億人を切り、2100年には4000万人を切ってしまうという恐るべき推計が示されている。現状のままでは確実にこれらの推計は現実のものとなろう。
その時、日本の経済、国土形成、家族には大きな変化が訪れる。倍増する現役世代の社会保障負担、縮小する一方の市場規模、次々と消えていく地方の集落と増え続ける老人世帯・・・。
もはやこれらは従来の公共概念を超えた問題だ。筆者は海外との交流を通して新たな文明を構築していこうと述べているが、私は保守を基軸としたい。すなわち、歴史、哲学、文化、自然と向き合い、日本の依って立つ基盤を理解したうえで、勇気をもって変革していく。それこそが、今の漂流から脱出する鍵なのだ。
Posted by ブクログ
高齢化社会と人口減少社会。
今後の日本の形を語る時に大きな問題点として認識しているこの問題。
文章の中で論理的に無理な飛躍が、無く非常にわかりやすい構成。
以下に私が特に気になった箇所をご紹介。
(1)1974年発布された「人口白書」の中で、「人口を抑制するべき」と明言していた事実。つまり当時の計画通りの状況になっているという事実に驚き。
→変化する外的要因に対応して、方針を変化させてこなかったの?
(2)世界の人口問題も2050年までは発展途上国を中心に急激に増加するがそれ以降は人口停滞期にはいるという予測
→今は中国・インドの人口爆発。その後はアフリカ。と人口が増え続けるんだという間違った世界観が修正されました。
Posted by ブクログ
~内容~
経済学者や経済通ではなく、歴史人口学者が書いた人口減少社会に関する本
~感想~
経済学者や経済通の書いた本だと、人口減少→経済への影響について語ってる本が多い。
この本でもそのような内容は扱っているのだが、この本が他と違うのは、世界および日本では人口が減少した時期があって、それがどうやって引き起こされていたのかを書いている部分が新鮮だった。
Posted by ブクログ
「デフレの正体」と似た感じで、日本の人口変動について書かれた本。
本書の中に、人口を維持するために、移民受け入れの必要性が訴えられている。
自分は移民受け入れに賛成。だけど、なにも用意しないで移民を受け入れて、使い捨てにしたら、大変なことになると思う。理由は、移民の子の暴動の危険性でしょうね。
だから、移民を受け入れるなら、移民の子の教育システムが本当に大事だと思う。移民の子でも、ちゃんと日本社会で伸し上がっていけるシステムを作るのがベスト。もう、日本を好きになってもらって、日本人にするのが目標を持つのが大事だと思われる。
Posted by ブクログ
【きっかけ】
ちきりんさんのブログで発売を知った。
以前この著者の本を読んだことがあり、縄文時代から現代に至る人口の推移が印象に残っており、本書を購入する大きな動機となった。
【感想】
2100年の日本は人口が4000万人まで減ってしまう。では、衰退するしかないのか?
日本が過去にも人口減少期を経験していること。人口が少ないからといって
【気になった言葉】
ガストアルバイター:中学か高校の社会の時間で習って以来、久しぶりに聞いた言葉だった。ドイツにおけるトルコ人労働者の総称。
Posted by ブクログ
2011年に既にこの本が出ていたとは。
早くからこの予想を知ることはできたのだな。
最近は人口減についての本はたくさん出ているが、顕在化していくこれからは、さらに増えていくに違いない。
Posted by ブクログ
2007年の日本総人口1億2777万人から2055年には8993万人、2105年には4459万人。
世界で人口爆発が問題化していたこともあり、1970年代の日本は出生率を抑えこもうという機運があった。出生率低下は多産多死→多産少死→少産少死に移行する。その要因は1.乳幼児死亡率の低下(不必要に多産でなくてもよくなった)、2.結婚と出産の不必要化(農業社会→工業社会への転換)、3.現代文明への不安感。
人口増加は、食料生産、さらに言えば土地の面積に依存する。生産が追いつかないため、人口増加は確実にストップする(マルサス)。産業革命で人口支持力(収容力)は格段に増加したものの、結局人口過剰による受胎調節が始まり、少産少死に移行した。環境と鉱物資源の限界は避けられない。
農耕技術は、人口密度が高まったときにイノベーションが起こる(ニーズ発生により)。また、過去の日本は技術が成熟した際に4回(4回めはいま)人口減少が発生した。新技術の到来で増加した。
2050年には先進国がだいたい人口減少に陥る。新興国は、中国インドの増加ベクトルは逓減する。日本が人口減少に陥る中で、これまでと同等の経済成長を確保するためには、一人あたりGDPを4.9倍程度まで引き上げなければならなく、厳しい。経済維持がやっとである。2055年には生産年齢人口=従属人口(年少人口+老年人口)になる。その対策として求められるのは、1.労働従事者の増加、2.移民の受け入れで、1に関してはⅠ.高齢者の労働参加とⅡ.女性の社会進出がある。
明治初期は女性も労働(農業)に従事していたが、サラリーマン化とともに分化が進み(M字カーブの形成)、その後バブル崩壊を機に労働力率向上が進む。一見、出生率と労働力率は相反し合うように思えるが、官民一体となれば不可能ではない(ヨーロッパの事例)。日本では、男性による家事・育児の参加が求められている。
日本の成熟過程(人口減少局面)では都市集中が緩和され、中央の文化が都心に拡散したが、今回はそうでもなく、むしろ人口集中が加速すると思われる(首都圏の老年人口の増加による社会保障費の増加から、それを逆に捉える説もある)。今後は地方の自然死が加速するだろう。これまで人口増加とともに住む所が増えてきたのだから、減るのも必然。むしろ、都市の集約化を進めたほうが、相互扶助による内的発展に寄与するだろう。今後は、マクロ環境や自然環境と対立せず、人間関係の形成を前提とした形で過疎対策に取り組めばよいのではないだろうか。
1920~50年の世帯の規模は平均5名だったが、2012年には2.46人になっている。これは少子化と住み込みで働く人の減少と一人暮らし増加と核家族化による。核家族化は農業→工業シフトに伴う都心集中などに関係している。ちなみに、東北は血縁関係が強く、西日本は地縁が強い(気候か?)。今後は(死に別れも含め)高齢者の一人暮らし世帯が増えていくだろう。
離婚の意味合いが異なるとはいえ、1900年初等の離婚割合は今より高かった。ただ、近年の熟年離婚の多さは注目に値する。
今後の生産年齢人口縮小を補うために、海外から移民を入れるという方法もある。人口を維持するためには2050年までにあと1714万人(全体で2250万人。人口の18%)、生産年齢人口維持のためにはあと3233人(4600万人,30.5%)が必要。現在が216万であることを考えると、大胆な政策になる。かつては0.8%だったところ、プラザ合意(1985)後のバブルとともに人口増加。現在1.7%。しかし欧米諸国は軒並み5%以上、アメリカは12%。
GDPに対する輸出は16.1%、輸入は15.6%。ドイツは40/33、韓国は45/47。貿易依存度は170国中164位。仮に鎖国したら、石油も入ってこなくなるため、生産性は低下する。日本の歴史を見ても、他国との関係悪化or鎖国時代は低成長だった。ただ、外国人が増えると、文化の違い(騒音)や日本語を話せない子供の問題などが起きる
今後、全世界で人口が拡大していくが、そのとき食料も資源も水も足りなくなる。食糧問題を変えようとすると、環境問題に直面する
Posted by ブクログ
1970年台には人口減少が望まれていた?なんてうまいこと興味を引いてきます。人口減少・高齢化社会が経済的にどうなるかという話はよく聞きますが、4章で述べられる人間関係の話なんかは新しい視点を与えてくれるものでした。
Posted by ブクログ
自分用メモ
・2055年に8993万人、2100年に4459万人
・1974年『人口白書』で「静止人口をめざして」と題し、増加し続ける人口を停止させ増えも減りもしない静止人口への実現を目指した。
→出生率を2程度に抑える。その後シンポジウム等で「子供は2人まで」という宣言がなされる
・出生率低下の原因 ①乳幼児死亡率の低下 ②子供を産んで子孫を残すことを必ずしも必要としなくなった、当たり前でなくなった ③現代文明の行き詰まりを予想させるような不安感
・従属人口=経済的・社会的に「支えられる側」0~14、65歳~
・生産年齢人口=「支える側」15~64歳
・生産年齢人口が従属人口の数の2倍を上回る現象=「人口ボーナス」
・従属人口が生産年齢人口を上回る現象=「人口オーナス」
・どのようにして生産年齢人口を上げるか?
→定年の引き上げ、女性労働者の増加
・「補充移民」=人口減少を大量の移民受け入れによって解決する際に必要となる労働移民のこと
Posted by ブクログ
日本の人口は、現在の1億3千万人が50年後に9千万人に、100年後には4千万人にまで減ると予想されている。本書では、4千万人にまで人口が減った時、経済・労働環境・家庭環境などがどうなっていくのかと予想されています。その予想は現実味があります。2100年の日本はどうなっているのでしょう。
Posted by ブクログ
士農工商の世襲時代は家族の規模が大きいので出産育児に対する家族のサポートが手厚かった。女性は出産や育児に専念できたので子沢山になれた。
戦後、都市化工業化が進み働き手は都市に集まった。(核家族の始まり)→女性の育児負担が増えた。
不況によって共働きが増えた。女性の時間は益々減少し、こどもを持てない家庭が増えた。
3分の1外国人時代
Posted by ブクログ
日本の少子化に対して、どのように考えていくかを説いた本。
なんか読んだことがあるかと思ったら、1-2ヶ月ほど前に読んだ「人口から読む日本の歴史」と同じ作者だった・・・
文明の成熟と共に、少子化が起きることはやむをえないこと。
そのため、少子化にあった環境を作っていかなければならないこと
という主張を訴えている
Posted by ブクログ
藤本(2011.11)
2100年には日本の人口が今の1/3になるという予測が統計的に出ているようです。そうなったとき、都市や経済はどう変わるのかを、過去のデータを紐解きながら解説してあります。今後のビジネスを考える上で参考になります。
Posted by ブクログ
今までは内需が多く、内需中心の産業政策でよかったけれど、全体の人口が減る上に、労働可能人口の割合が減るので、方針を変えなければならない。
しかし、これは文明社会の当然の流れであって、日本特有の問題ではない。
問題は、その速度、タイミングに大きなばらつきがあること。
同じく、国内でも地方によってばらつきは大きい。
都会のほうが今後は独居老人の問題が大きくなるだろう。コミュニティを維持する方向を探るべき
Posted by ブクログ
・日本政府は1974年に出産を抑制すべきと明言
→その後人口減に対する対策をしてこなかったために今の少子化がある
・日本では多くの高齢者が高い労働意欲を持っている
→本当?
・外国人人口は増える.
→社会システムはそれに適合して変わっていく.
・途上国を中心に世界のGDPも増える.
・結局はどのような社会を築きたいかというデザインが大事.
Posted by ブクログ
・1974年、政府主導で少子化が始まった。ベビーブーム世代が新卒者として労働市場に登場する。時代の転換期に特有の労働力過剰という雇用問題を避けるために、出生を抑制する必要があったのである。「人口白書」では、「合理的な生活設計を背景とした正しい家族計画の普及」を推進させることが、国民的課題とされた。
・2055年には国民の40.5%が高齢者になるのである。
・人口は減少を続けて2100年には3分の1、4,000万人近くまで減ることは避けられない。世界の人口ランキングで日本の順位が下がることに、本質的な意味はない。日本人からみて豊かな暮らしを実現させているヨーロッパの各国には、日本以上の人口大国は存在しないのだから。人口が縮小する日本が目指すものーそれは高度な労働生産性と適切なワークライフバランスを保った、豊かさを実感できる社会に他ならない。
・2050年に日本の人口順位は世界17位まで後退し、世界の経済情勢は大きく変わる。
・のんびりと年金生活を営むフランス人と違い、日本では多くの高齢者が高い労働意欲をもっている。労働力の担い手を増やすため、高齢者の定義が引き上げられるかもしれない。
・日本の技術力をいかした「モノづくり」こそ伸ばしていくべきだと語られるが、それだけでは不十分だ。技術は陳腐化するし、模倣されるものだから。常に新しいものをつくり続けていく競争力は必要だけれど、それだけでは日本にクラス人々の幸せには繋がらないのではないだろうか。一人ひとりが幸せを実感するために欠かせないのは、美しい自然環境に囲まれた居心地のいい都市、そこで築く豊かな人間関係である。そのためにも、国を挙げて国土の大掃除を行い、枯れた葉をよみがえらせること。その上で、ある程度の食糧自給率を保ち、かつ最新技術も開発できるような国づくりを目指したい。日常生活を快適にすごすことができ、財政的にも効率がよく、環境負荷の小さな居住―そんな理想的な将来像のデザインを描くことがいま、求められている。
・結婚に適齢期はなくなり、子どもづくりを目的としない新しい結婚文化が生まれる。
・国内労働力をいじするためには外国人の労働力を大量に取り入れる必要がある。
・減る分の労働力をすべて移民で補うと、2050年には人口3分の1が外国人になる。
・日本の貿易依存度は世界でも最低レベル。諸外国との分業的な連携が必須
・食糧自給率100%も夢ではないが、その場合は国民の大半が農民になる
・東京の大久保、群馬県の大泉町のような外国人街が各地に増えていく
・アジアを中心に、外国人と結婚する人も増えていく
・食糧と同じく資源やエネルギー不足が深刻になる
・地球が支えられる人口は多くて100億人。すでに限界が近付いている
・世界に先駆けて人口減少が始まった日本には、イノベーションを率先する役目がある
Posted by ブクログ
● 1974年6月には、戦後2回目の『人口白書』として『日本人口の動向』が発表されている。その副題は「静止人口をめざして」。少しでも早く人口増加を停止させ、増えも減りもしない「静止人口」を実現するため、政府は出生抑制をいっそう強化すべきだと明言したのである。
● 人口は幾何級数(等比数列)的、つまりペースを数倍していく勢いで増大し続け、食料生産は等差級数(等差数列)的に漸増する。マルサスは、やがて人口増加に食料供給が追いつかなくなると想定したのである。
● 問題がここまで大きくなった最大の理由は、人口がほとんど政府の予測どおりに推移してきたのにもかかわらず、出生率の低下にブレーキをかけて人口静止へと舵を切るのを忘れていたこと、あるいはタイミングが遅すぎたことである。
Posted by ブクログ
本書では人口減少社会の中で顕在化する問題とその解決を考慮して目指すべき方向性を提示している。人口という観点から近年の時事的な話題(震災、無縁社会、TPP、グローバル化など)にも触れているので頭の整理に役立つだろう。グローバル化、農業問題、コミュニティなどのいくつかのトピックにおける方向性や議論はやや既視感がぬぐえないところもあったが、個人的には過疎地域からの積極撤退という考え方が面白かった。国民的な理解、議論が必要な分野であり、広く読まれて欲しい内容だと思う。著者は歴史人口学者というだけあって人口に関する統計データ群は興味深かかった。