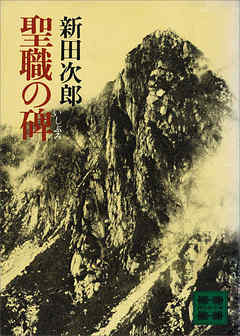あらすじ
伊那駒ケ岳稜線上に聳え立つ遭難記念碑は何を語るか……大正2年8月26日、伊那駒ケ岳登山中の中箕輪尋常高等小学校生徒ら37名は、突如襲った台風に遭難、11名の死者を出した。信濃教育界に台頭する理想主義教育と実践主義教育との狭間に、深い哀しみと問題を残した惨劇の実相を著者自ら登攀取材した長篇小説。
...続きを読む感情タグBEST3
登山の参考に
当時の登山がいかに過酷であったのかが良く分かる作品です。木曽駒ヶ岳に何度も登っていたので以前より興味がありました。読了して当時の状況が現況と照らし合わせることができ、とてもリアルに伝わってきました。
Posted by ブクログ
私の地元では中学生になると行事で登山をします。
登山が怖かったので先に読みました←
余計怖かったけど、読まないほうがさらに怖いので…
山の事故は怖いですね
Posted by ブクログ
大正時代に駒ヶ岳で起きた中学校修学旅行の遭難事故(11人死亡)を題材とした小説.自然相手の活動を行う際,どんなに事前準備をしても,自然の急変等により事故が起きる可能性がある.このことは常に肝に銘じるべし.事故後の教育会(今でいう教育委員会?)の対応も示唆的.現在ではこのような対応は難しいかも.
Posted by ブクログ
大正三年におきた中箕輪尋常高等小学校の修学登山事故を洗い直し、新田次郎の手によってドキュメンタリー風に書き出された山岳小説である。
初版は昭和五十一年。構成は三部立てとなっており、第一章は登山という行事がどのような教育理念の下に行われるのかを当時の状況を以って示し、第二章で事故のあらましがドキュメント風に描かれる。最後の第三章では、事故後の人々の対応と、現代まで登山行事が長野で行われる理由が明かされている。
本書にあるように、私の母校も戦後から毎年修学登山を行っており、私自身も経験していたが、まさかこのような背景があるとは知らず、もっと早く知っておけばよかったと思った。
山国である信州において、山の体験を学習の場と考えるのは赤羽校長のみならず、現在の教育現場も同様であるように思える。彼らの理念を引き継ぎ、どの学校もいまだに実行し続けていることはすばらしいと思う。しかし、その志は果たして子どもたちに伝わっているだろうか。(私自身はしんどいとしか思わなかった。)
さらに言えば、この理念を貫いた結果、誰が幸せになっただろう。長い目で見れば、という声はもちろんあるだろう。だが、赤羽校長や清水・有賀先生等の意思に感動する方があれば問いたい。教育者の妻として責任を問われ続けた赤羽つぎの道を、自分の妻に歩ませる神経を持ち合わせているか。唐沢可作の枷をはずす手立てはあるのか。
私には、そんな覚悟はない。
Posted by ブクログ
読みたい
登山好き、新田次郎好きの友達に借りた。八甲田山もこの人に借りた。
教育者なら絶対読むべき二冊のうちの一冊だと。もう一冊は「エミール」だって。そうなんですか?
2011/10/11
読み終わった
Posted by ブクログ
新田次郎の本は、講談社からも出ていたんですね。読んでみました。
この本は、尋常小学校の校長、生徒が修学旅行で駒ヶ岳を目指し、死傷者を出してしまった悲しい事故が元になっている。しかし、当時の聖職者たちの考え、立ち振る舞いに明治の日本人を見ることができる。
いまは、教職員の犯罪も毎日のようにニュースに流れる。聖職ということを自覚して欲しいものだ。また、実践教育は学校の場だけではなく、家庭でも取り組んでいくべきものだと思う。いまは、教育は学校がやってくれるものと考えている大人が多すぎる。教員にお薦めの一冊です。(2009/07/11)
Posted by ブクログ
教育としての登山、今ほど管理されていない山に登る危険、起きてしまった事故。遭難事故が主題じゃなくて、事故後、それぞれの立場で主張し進んでいく。凄い人間ドラマ。
後書きが取材譚で、まあまあの長さ、これも含めて一冊の小説だった。
Posted by ブクログ
涼しくなる1冊。冬に読んではいけない。
ひたひたと近づいてくる寒さ。
小学校の遠足登山(とはいっても戦前)で、集団遭難。
遭難する前から、押し寄せてくる嫌な予感の連続攻撃で、寒いことこのうえなしです。子供がたくさん遭難しちゃうので、涙もろい人はご用心を。
題名だけだと、すばらしい教師の話のようなんだけど、それは個人、一場面のレベル。遭難しないように準備することがもっとあったんじゃないの?と突っ込みどころも満載なお話。
そんなに数読んでないんですが、山岳小説は夏に読むのがいいのかな。
寒くなれる山岳小説あれば教えてください。
よく覚えてないのですが『八甲田山死の彷徨』も、かなり寒かった記憶があります。これもまた、新田次郎。