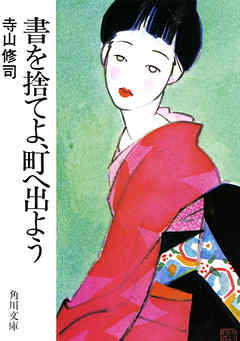あらすじ
あなたの人生は退屈ですか? どこか遠くに行きたいと思いますか? あなたに必要なのは見栄えのよい仕事でも、自慢できる彼や彼女でも、おしゃれな服でもない。必要なのは想像力! 家出の方法、ハイティーン詩集、競馬、ヤクザになる方法、自殺学入門……。時代とともに駆け抜けた、天才アジテーターによる100%クールな挑発の書。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
初めて手にした寺山さんの著書。
一読二読してみて、本書のタイトルの意味を理解できたかどうかが、この本(ひいては寺山さん)が自分に向いているかどうか、分かれるでしょう。
途中途中に詩や歌謡曲の歌詞を織り交ぜてくれる事で、つい感傷に浸ってしまいました。心に残る、ついメモを取りたくなる言葉が多いです。
売ったり手放したりせずに一冊、いつでも読めるところに置いておきたい本。人生の指南書の一つですね。
この本の中で一番好きな章は自殺学入門ですね
自殺とは死への純粋な憧れからの行動であり、何か生きてる上で足りないものがちょっとでもあればそれは他殺や病死になってしまうので自殺ではなくなる・・・とは、とても納得。今まで言いたいけど語彙力とイマジンが足りなくて手が届かなかった所に、やっと届いたという感じ。
この自殺論を理解したところで、「女がよく口にする”死にたい”はバカンスに行きたいと同義」という言葉を見たときの納得感にも説明がつきました。
大半が生の様々な苦しみから逃避したいというだけのものであり、実際に自殺したいという意味ではなく、ただ逃避したいという意味しか持たない、という風に。
何かからの逃げは他殺や病死と等しいのですね。”自殺”とは尊くあるべきものなのだと、そういう死生観がとても私のそれと重なり、快感のような物を覚えました。
丁度読む直前にTwitterで「スイスで70万円で安楽死させてくれる」という話を知り、安楽死が金で買える時代になったとは、人類は進歩したものだなあ…と思ったところで、検索から飛んできた人から「70万円は高すぎる」と絡まれ、私は「リーズナブルな安楽死というのはあまりにチープすぎる考え方ではないだろうか、死に価値を見出す人間ならば、ある意味金銭というそれなりの努力がひとつのハードルであっても良いことなののでは」と返したのですが、私の考え方は死の尊厳を重んじた正しい”自殺”の手段としてのものであり、向こうは社会的弱者に対する国家的サポート…という考え方をしていたので、話が噛み合いませんでしたね。
まあそれはそれとして、現段階では実際我が国においての倫理感の展望が初めの一歩すら踏めていない状況なので、数段も先の話なのではなかろうか…ということで話をまとめてしまいましたが…
長くなりましたが、そんなやり取りの直後に自殺学入門の頁を読んだので、より感動を呼びましたね。
さて、心に残ったさまざまなお話や言葉をメモがてらコメントがてら、続けていきます。
●「その時代の少年犯罪こそが、その時代の国家犯罪の反映だと思われる」
ーーー学校教育への造反、あらゆる既成概念への造反がやがて国家という概念への疑いにたどりつく……とのこと。
酒鬼薔薇事件や、LINEリンチ事件など、ちょっと考えさせられました。
●「印刷機械は実は詩人に猿ぐつわをはめるためのものだったのである。」
ーーー目から鱗です。もっと詩人はもっと様々な表現手段のある「肉声」で、受け取り手との「対話」があるべきなのだということです。
詩人だけでなく、インターネット、携帯端末が発達して何をするにも肉声である必要が無くなって来ている現代においては、我々にも当てはまる事でしょう。
●「親は本来的には、子を所有しようとするエゴイズムと幸福観とを重複させ、正当化する理念しか持っていない場合が多い。親の思想というのは、いわば「子守唄の思想」であって、醒めようとする子供を、家庭の和という眠りにおとしこもうとする考えに貫かれている場合が多いのである。家庭だけを核として考えると、「親と話しあう時間」の量が問題になるかも知れないが、彼らは「仲間と話しあう時間」を十分に持っていた。むしろ重要なのはそのことではなかったろうか。なぜなら、従来の模範少年たちは親とばかり話しあっていて、仲間と話しあう時間が少なすぎたために「親の作りたいような型」にスッポリはまった成長のしかたしかできなかった……と考えられていたからである。」
―ーーここまで(本書の終盤でした)読んで、現状の自分を反省し、やっと本書のタイトルの意味がわかってきたところでした。
寺山さんは一点豪華主義の視点からロックの考え方(退屈や模範や教育から抜け出す反骨精神)を持つ人であると私は理解しています。
現状への満足、平均化、停滞、「あした何が起こるかわかっている、何のために生きているかわからなくなってしまう」状況に落ち込むこと、新鮮さを感じられない感受性しか持たないでいることはダメなのだ……ということを学びました。
そして、カレー人間とラーメン人間の例え話から始まる、自宅カレー人間は家庭の味だから現状維持型の保守派、ラーメン人間は街の味だから欲求不満型の革新派が多く、カレーは家庭の幸福のシンボルでホワイトカラーの典型であり、ラーメン人間は何時も少し貧しく階級的な不満が付き纏う……しかし、ハングリー精神を持ち合わせているという話。
この、2つの価値観と幸福論を照らし合わせて総括するとつまりは、「現状に満足する人間に想像力の創造などはできない」。
本書終盤の「子守唄の思想」もそうでした。そこまで「ウウム・・・」と色々と考えさせられながら読んでみて、現状の自分と照らし合わせて実感として理解したとき、カレー人間とラーメン人間の話の終わりに唐突に降ってきた言葉「幸福とは幸福をさがすことである(ジュール・ルナアル)」の言葉に帰ってくるのか、と、感動しました。
●「歌謡曲人間は、つよい人間である。すぐ消えてなくなる歌の文句を拠りどころにして、にっこり笑って七人の敵に立ち向かっているような男でなければ、時代の変革への参与など、とてもできるものではない。だからこそ、わたしは日本人一億総「歌謡曲人間化」をすすめたいと思うのである。」
ーーー本書の一番最後の言葉です。そう言うだけありやはりこの本でも、歌謡曲の歌詞が随所で散りばめられています。
中でも私は「人に好かれていい子になって 落ちて行くときゃ一人じゃないか(畠山みどり 出世街道)」、「どうせあたしをだますなら 死ぬまでだましてほしかった(西田佐知子)」・・・が好きです。
現代であれば、口ずさむだけでなく、ブログやツイッターに歌詞を呟く事も「歌謡曲人間」に含まれるのでしょう。
瞬間瞬間に歌の文句を心の拠り所にしている人間は強い。この考え方には目から鱗でした。そういえば、心当たりがあるような気もしますし。私も歌詞に頼っているところがありますので…
本書の裏表紙に「あなたの人生は退屈ですか。どこか遠くに行きたいと思いますか。あなたの人生に必要なものは想像力だ。一点豪華主義的なイマジネーションこそが現実を覆す。書を捨てよ、町へ出よう」
というような事が書いてありますが、そのとおりだ・・・と、このレビューを書きながら思いました。笑
つい、長くなってしまいましたが。そういう本です。
さよならだけが人生ならば また来る春は何だろう。
はるかなるかな地の果てに 咲いてる花は何だろう
Posted by ブクログ
出版社の夏の100選とかにいつもエントリーされていて、気になっていた一冊。
タイトルも捻りが聞いていて、どんな内容なんだろうとワクワクして読んだけど、、、。
色々と期待と大幅に違った(汗)
なぜ母と寝てはいけないかを考えてみたり、母にお金を要求する手紙と、馴染みの女へのラブレターの中身を間違えて送って怒られたとか、母の立場からすると腹しか立たないんですけど(笑)
大学生くらいに読んでもらって、評価するかどうか討論してみて欲しい。
巻末に現代だと違反にあたったり、差別的な用語があるが、時代背景を正確に表現するために敢えて残してあると注釈が付いてた。
小学生とかも手に取るおすすめ100選に選ぶなら、これ巻末じゃなくて巻頭に載せた方がいいと思うよ角川さん。
○えー…と感じた所
話の内容の7割が競馬かパチンコか、風俗の話。しかも45年前の話で単語の意味がわからなかった。トルコ風呂とかうっかりググってしまった。あと、わかっちゃいたけど、女性蔑視の気がある。蔑視というか下の生き物と思っているというか…。生きてたら80~90歳代の人かな?
もちろん全員こうじゃないってわかってるけど、この考え方が当たり前の時代がおじいちゃん世代なんだから、親世帯との同居もすんなり上手く行くわけないよね。
あと、海外のを含め、詩や他の(おそらく哲学書)著書の引用が多く、馴染みがない分とっつきにくかった。
※引用だときちんと書いていることは評価する
○ほぅ!と思ったところ
・月光仮面(これもググった(笑))やタイガーマスクは国際問題に介入できないという話
これから正義の話をしようの著書の内容を思い出した。鬼滅の刃も鬼側の視点も面白いと評価されている。
特に国際問題は双方の正義がぶつかるので、絶対的な悪が見つけにくい。だから正義のヒーローは国際紛争には絶対登場できないという記述があって、ちょっと納得した。
ただ、最近のヒーローは地球を守ってるから、宇宙人と交流が発生するまで、まだまだ戦えそうだなとも思った。(笑)
Posted by ブクログ
そういえば最近読んだのだった、と書き忘れていたのを追加。寺山修司である。
僕が読んだのは緑色のカバーに朱色で印字されたシンプルなやつ。最近デザインが変わったらしい。
タイトルが好きで、いつか読みたいとずっと思っていたのだけど、折よく機会に巡り合うことができた。表題作、君もヤクザになれる、ハイティーン詩集、不良少年入門の四章構成で、さらにそれぞれ細かく中身が分かれているので、時間のないときでもちょこちょこ読み進められる。内容は、まあ面白いかな、という感じ。残念ながら寺山修司は僕を虜にするには至らなかった。読めば文学少年ぶれるかな、と軽い気持ちで読みだしたのだけど、ふたを開けてみれば詩集でも戯曲集でもなく、虚実入り混じった持論とエッセイのごった煮だった。八割は女と博打の話で占められているし。現実なんてこんなものだ。
でも、収穫がなかったわけではない。僕はまだニワカなので、彼の文章がどうとか細かい分析なんて望むべくもないけれど、三章「ハイティーン詩集」に収められた「一本の木のなかにも流れている血はある」から始まる短い詩は味わい深く思えたし、四章「不良少年入門」は面白く読んだ。後者はプレイボーイならざる「ブレイボーイ」になるべきだなどと、難しく考えずとも、肩の力を抜いて楽しめる文章だったので、是非一読を勧める。
また、読んでいて寺山修司の教養の豊かさに唸らされることも多々あった。非常に様々な分野への造詣が深い人物だったのだなぁ、などと感心しながら僕は読んでいた。氏が有しただろう、演劇や詩にまつわる知見がつまびらかにされることはほとんどなかったけれど。