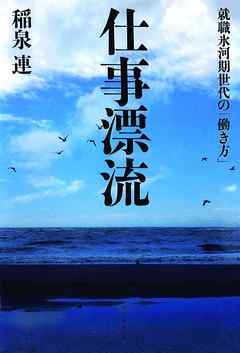あらすじ
第一章 長い長いトンネルの中にいるような気がした(元都市銀行33歳) 第二章 私の「できること」っていったいなんだろう(元菓子メーカー30歳) 第三章 「理想の上司」に会って会社を辞めました(元中堅IT企業30歳) 第四章 現状維持では時代と一緒に「右肩下がり」になる(元大手電気会社32歳) 第五章 その仕事が自分にあってるかなんてどうでもいい(元中堅広告代理店29歳) 第六章 「結婚して、子供が生まれ、マンション買って、終わり」はいやだ(元大手総合商社29歳) 第七章 選択肢がどんどん消えていくのが怖かった(元経済産業省32歳) 第八章 常に不安だからこそ、走り続けるしかない(元外資系コンサルティング会社33歳)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
1990年代中頃~2000年代前半の就職氷河期に大卒・総合職で就職活動を行い,その後転職という道を選んだ8人の若者についてのノンフィクション.いわゆるロストジェネレーションの人たち.新卒としての採用から転職に至るまでの経緯,および転職してからの現状について赤裸々に語られている.
就活を始める前の大学生から入社後数年の経験を経た若手社会人におすすめ.転職したいかどうかは置いといて,自分の仕事観・キャリアプランを形成する一助となるだろう.転職を推奨するものではない.
自分も就職氷河期に入社した者として共感する部分が大いにあった.
・右肩下がりの時代では,現状維持では時代と一緒に落ちて行ってしまう
・自分に自信が持てないからこそ走り続けざるを得ない
終身雇用の時代が終わったと言っても,日本の法制度のもとではいきなり解雇されることはそうそうない.しかし雇用が保証されているとは言え,おもしろくも無い仕事を延々と続けられるだろうか.登場人物の何人かが抱いている危機感は,同じ会社に留まり続けることで市場価値の成長率が低下すること.
健全な危機感を持って仕事に取り組んでいこう.
Posted by ブクログ
転職にまつわる氷河期世代8人のルポルタージュ。これには強いリアリティがある。ルポだからリアルなのは当然だが、その書き手の表現の仕方だろうか、描かれている気持ちがよく伝わってくるし、状況も非常に同時代を生きた者としては「あるある」と言った感じだろう。
起業に失敗する者、なんとなくで入社したが仕事を好きになれない者、あこがれの業界に入ったもののイメージとは異なり悩む者、どのシチュエーションも実に身近にあるものだ。
氷河期世代以降の学生は大企業の倒産を見ているので、大企業が安泰とは限らないことを肌感覚で知っている。だからこそ、手にスキルをつけたいとか、資格が欲しいとか、起業をして自分でコントロールいたいとか、何かしらの目標を掲げてそこに到達しようという動きが生まれた。
「何かをしなくては」という焦燥感に駆り立てられ、自分にできそうなことがあれば「きっとこれがやりたいことなんだ」と自分に言い聞かせることになる。結果、努力主義が人に過負荷をかけたり、夢を叶えてもこんなものか、と脱力したり、達成できないことに常にイライラを感じることになる。
努力や夢の行き先に絶望することで、キャリアアップって何?という疑問が浮かぶだろう。多くの人は無条件に上昇志向を良いものとして受け入れている。それまで経済成長とともに線型的に昇進を当然としていた人事制度、いや社会の在り方自体が上昇志向の中にあった。しかしすでに高度成長の時代は終焉を迎えていて、制度も価値観も時代遅れのものとなってしまった。
あとがきにも書かれているが、もはや一つのモデルに対応する一つの制度では対応できないほど、社会は多様化している。ひとつのものさしからはみ出した者がすべてにおいて否定されるようなことはあってはならない。願わくば大きな内需の創出と労働市場の流動化か進んでほしいものである。
Posted by ブクログ
2011年8月
転職を切り口にした8人の社会人のキャリア。
仕事選択、転職への決断、キャリア展望。
就職氷河期に就職した若者がどのような判断をしてきたのかがよくわかる。
働き方などやってみないとわからない。働きながら探す物なのかもしれない。
企業にとらわれない生き方を見つけるための転職か。転職の意味を捉えなおしました。
Posted by ブクログ
止め処もなくリアル。
働くということに対しての、人それぞれの価値観を垣間見ることで、自分を見つめなおすことができた。
僕も数年後、氷河期世代ということで同じようなことを悩むことがあるのだろうか。
Posted by ブクログ
こんなに「うんうん」と頷きながら読んだドキュメンタリーはない。睡眠時間削って読んだ本。弟が就活前だったら絶対に贈っていたと思う。金融、食品、石炭、広告、研究開発と様々な職種で社会に飛び込んだ当時の学生とその後について書かれているけど、どのエピソードにも思い当たる部分があって、恥ずかしくなったり励みになったり。仕事でどどーんと煮詰まったら読んでみて下さい。どの業界、どの職種、どの会社にも形を変えて遣る瀬なさは存在する、ことを思い出させてくれます。同じ風景も年月が経てば違って見える、それは必ずしも「流された」「染まった」「諦めた」で形容できるだけのものではない。
Posted by ブクログ
77年から81年生まれの8人の転職経験者の仕事観が語られる。著者は4年間くらいのスパンで彼らに複数回の追跡取材をしている。さらっとした文体のルポだが、それなりに元手はかかっている。
同時代の空気を映し出していると思う。私自身は彼らより半回りくらい年長だが、まさに自分のこととして読める。先の見えない下積みへの苛立ち、自分の社会での価値に対する不安、実際の仕事の手触りから得られる満足。
こうしてもがく人がいる一方で、最近の草食化は時代の変化なのか、それとも2極化の両極なのか。(おじさんは、このあたりけっこうステレオタイプに見ています)
Posted by ブクログ
就職氷河期というのはいつだったか、
いまやアベノミクスの好景気ということもあり、
明らかに新卒採用の人数は違うようだ。
そんななかで就職活動を経験して数年を経た人たちが、
それぞれに悩みを抱え、それぞれに新たな道を選んだりする様が描かれる。
その中身は個別具体的で生々しい。
同じ悩みを抱える人たちには共感を呼ぶと思う。
Posted by ブクログ
所謂就職氷河期に就職をした8名の転職を軸としたノンフィクション作品。
我々も就職氷河期(物語よりおよそ10年後)といわれた世代として、興味深く読み進めることが出来た。
共感できない考え方もあったが、仕事への葛藤・心情描写が非常にリアルで(ノンフィクションなので当たり前かも知れないが)面白かった。
色々な道があるよなぁ…と。
Posted by ブクログ
キャリアについて考える年ごろなので
最近この手の本をよく読みます。
内容はちょうど自分とほぼ同級生が転職に至るまでを
数人の例をあげて書いています。
共通点は全員就職氷河期ってことです。
びっくりするぐらい転職に至る動機が共感できます
自分も含めてこの世代はバブル崩壊のリストラや
その後の就職活動で痛めつけらているので
組織をあまり信用していないなーっという感じがします。
それに伴う年功序列の歪みもかなりでてきているのでしょう。
転職を考えているようなひとはもちろん
今の学生にも就職で人生全ては決まらない
ってことを知ってほしいので読んでほしい本ですね。
Posted by ブクログ
8人の働く若者のノンフィクション。
仕事とは、何を求めて生きているか、自分にも考えさせられる。
自分のやりたいことがあって、でも迷っている人にはすごく勇気づけられるだろう。
Posted by ブクログ
「漂流」という言葉とは裏腹に、自分の道を見つけて転職をする若者の姿を描く。インフォーマントの生い立ちから就活、仕事への姿勢、考え方などうまくまとめられていて読みやすい。
転職は、珍しいものではなくなっているのに、いまだに「いい大学」→「いい会社に入って終身雇用」幻想が広く浸透してしまっている。その齟齬によって少しずつ弊害が出てきている。
キャリアアップや本当に大切にしたいことのために転職という道を選んだ方々が取り上げられているので、将来を考える学生にはオススメかなー。
ただ、現実はもっと厳しいんだけど。
Posted by ブクログ
一度は就職したものの、会社に疑問を抱き、転職した人の体験談を語っている。登場する人物は優秀な大学を出て、良い企業に入った人が多いので、ニートに共感は得られない本だと思う。
Posted by ブクログ
自分がタイトルの状況にあった時に読んだ本。
取り上げられた人達の思考は理解しやすく、物語としても面白く読ませてもらえた。
作者の思想や解釈を無理に押し出していないところも好感が持てた。
正解がない中、同じ仕事人として悩み進む姿を身近に感じて勇気付けられた。
Posted by ブクログ
一流大学を卒業し、一流企業に入ったけど、転職をした8人に焦点を当てたノンフィクション。
キャリアアップという言葉に、アタフタさせられ、浮き足立たされる。その感覚は凄くわかる。
ノンフィクションなので、転職で何もかも得られるわけじゃないが、それなりの満足感を得ているといった、リアルな内容なのは良いですね。むやみに煽るわけでもない。
Posted by ブクログ
「選択肢が増えても成功の確率が低い時代、選択肢が少なくても成功の可能性が高かった時代」
「仕事漂流」とはこれだと言う仕事が見つからないということで、決して仕事にあぶれているということではない。ここに登場する人たちは、1990年後半から2000年前半の就職氷河期に就職できた勝ち組と言われる人々。 人としても魅力的で頭だっていい勝ち組であっても自分の生き方や選択に悩んでいる。(生活への不安は語られないし書かれていない)悩んでいるとはいえ、そこはやっぱ優秀で勝ち組になったのも納得。そしてそういう人はやはり大企業に入る。
30歳までの時期は大企業で働き、柔らかい頭に一流を詰め込み、それから中小企業やベンチャーに流れて、全体が見えるような仕事をする。おそらくこれが理想的なキャリアパスで、長い停滞に入る前は一般的な人材の流れだったと思う。均一で高品質な社会人の製造工場という面があるから、政府も便宜を図っていた。しかし、大企業が足並みを揃えて新卒採用を控えたころから、このキャリアパスが崩れてしまい、だから「世の中には魅力的で優秀な中小企業がいっぱいあります」から「そっちに入ってください」というキャンペーンにつながったと思っている。
中小企業は社会にカチッと噛み合う歯車を作るという役目を押し付けられたけれど、教育に投資するような資金的余裕ををもたない中小企業じゃ社会人のタマゴを育てることはできないと思う。OJTとは何とも都合のいい言葉。
この大企業→中小企業という人材の流れと、リクナビのような一括応募のモデルはとても合っていたと思う。新卒サイトの収益モデルでは、どうしても大企業を優遇するインセンティブがはたらいしてしまうけれど、それで良かったのだ。中小企業は大企業で教育された人をう譲り受けるだけでよかったんだから。もしかすると、中小企業のホンネは今もそうで、リクナビとかにクレームをつけてるのは、使い捨てにできる若い労働力を欲しがっているベンチャー企業なのかもしれない。
これから、大企業が社会人を生産してそれを中小企業に流すというキャリアモデルが崩れたらホントどうなるんでしょうか。