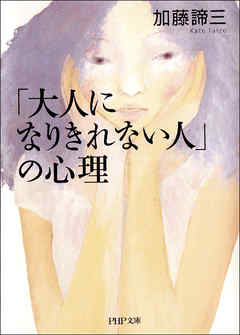あらすじ
五歳の子どもに、三十歳のビジネスマンのような生き方はできない。しかし「五歳児の大人」は、何の責任も負うことなくチヤホヤされていたいと願いながらも、「大人として」生きなければならないのだ。大人になりきれない人にとって、自信もなく、人を許せず、軽蔑を恐れながら過ごす日常は辛い。それに振り回されるまわりの人もまた、辛いはずだ。本書は、大人のフリに疲れた人の困った言動とその原因を分析し、今より心豊かに、人に優しく、満足感をもって生きるための方法を、自身も「五歳児の大人だった」という著者が説き明かす。彼らを上司や同僚、家族や友人に持ってしまった人たちにも役立つ心理学。「最近の日本の親は五歳児の大人が多い」「五歳児の大人を救う3つの条件」「幼稚さを認める勇気を持とう」など、現代社会の問題点や問題解決のための具体的アドバイスを満載した人生論。『「五歳児の大人」とそのまわりの人のための心理学』を改題。
...続きを読む感情タグBEST3
生きるのが辛かった。
大学3年生男子です。
大学生になってから“自分は中身が空っぽだ”と違和感を持ってから、何度か悩み続け、時には大学も行けないほど、バイトも休んでしまうほど悩み続けました。この本はそんな悩みの原因を解決してくれました(すべてかどうかは分かりませんが)。
とにかく気づくこと、知ることが大事とこの本では書いてありました。確かに、自分の内面のことなので、知ることで改善の余地ができるのかなと思います。
中略
まず、一日をちゃんと生きる。 僕は、やるべきことをちゃんとやろう、ということだと解釈しました。22歳の責任を辛いけども、しょっていこう、ということだと。
次に、憎しみを取り去ってもらうよう祈る。自分は「母なるもの」を持つことが出来なかったかもしれない。でも、今まで胸にこびりついていた憎しみに気づけました。これからは憎しみを貯めるのではなく、ぬぐっていかなきゃいけない。手がない状態で生まれた人は、手がある人をいつまでも恨まないだろう。「母なるもの」を持つことが出来なかったのなら、それを自然に、音楽に、スポーツに、敬愛する人に、最愛の人に、求めよう。
そして、人に期待をしない。自分の才と興味を生かして、一日に満足しよう。と思いました。人に期待する、人に母なるものを求めてはいけないということを漸く気づけました。しかし生きていかなくてはいけない。自分の才、興味に従って、一日を満足して生きる。自分を丁寧に扱おう。
Posted by ブクログ
小さな幸せで満足できず、満たされず周りを羨み、自分の不幸を呪う。不幸の原因を周りに求める。
そんな大人になりきれない感情の根底には、さまざまな憎しみがあり、それを消さない限り幸せを感じることは出来ない。
そしてそれを消すのは、やり返すことでも、追い越して優越感を持つことでもなく、「許し」しかない。
自分と向き合い、憎しみの根源を探し、許す。
そうして生まれてから積み上げた憎しみを消しさり、幸せに気づいていく。
簡単なようでものすごく難しい。
内容はひたすら同じことを繰り返しなのだが、いちいち当てはまるので読み飛ばせない。。。
Posted by ブクログ
はじめに私の背景について書く。自分の生育環境の普通でなさに25歳になってようやく気付いた。25歳になるまで焦燥感を感じながら必死に生にしがみついている感覚があり、気付いたらうつ病になっていた。自分の満たされなさはどこから来るのだろうかと日々思い悩んでいた。なんとなく、自分は他の人と比べて子供っぽい考え方をしているなと感じていて、そこが引っかかっていた。よくよく考えてみると今までの自分は甘えが満たされないまま成長してしまったんじゃなかろうか、それが現在の満たされなさに繋がっているんじゃないかと考えるようになった。
そこでこの本に出会った。
少し冗長なところはあるが、私の言いたいことをうまく代弁してくれているいい本だった。
私のように漠然とした満たされなさを感じて生きている人、愛情を受け取った記憶がない人にとってはこの本が生まれて初めての理解者になるかもしれない。
自分が昨今知名度が高まりつつあるアダルトチルドレンに該当するのではないかと考えたことがある人にはぜひ一度読んでほしい本である。
Posted by ブクログ
著者の育った環境も壮絶なものがあったようだ。それを乗り越えて来たからこと、大いに示唆の富む内容となっており、お勧めしたい。
自分に全く劣等感を持たない人はいるのだろうか。
幼少時代に満たされるべき各種欲求が満たされないまま大人になってしまった場合、大人になってもその欲求を消化出来ないまま社会と接する事の悲劇を訴える。
自分には意識すらしていない自分でも気づいていない(認めていない?)満たされなかった欲求があるのかも知れない。
「仕事が好きなふりをしてしまった。周囲の人を好きなふりをしてしまった。そして、仕事熱心な自分を演じてしまった。この自分を偽る努力は報われない。」P158
ではどうすればいいのか。「自らの幼稚さを認めるのだ」と。
同じような話題が繰り返し続くのは、その思いの深さからだろうと思う。
Posted by ブクログ
3年くらい前にある人を理解するために読み始め、その人と関わらなくなったので、途中で寝かせていました。今度は最後まで読もうとしたものの、読むのが辛いと感じました。それは、自分が五歳児の大人だからだと分かったのは終盤になってから。過去に釘付けされていたことは知っていました。その原因も。ただどうすることも出来なかったので、どうしたらよいかを文字で語りかけるように教えてもらえて本当によかった、ありがとうございます。
Posted by ブクログ
今までずっと、原因不明のイライラに苛まれてきた。
この本を読んで、その理由がわかった。
私はこの本にある、五歳児の大人だったのだ。
本を読んでいる最中は、自分について当てはまることがイヤと言うほど書かれていて、読み進めるのが苦痛だったが、
読み終わると、自分の頭の周りを覆っていた原因不明の靄は消え、すっきりとした気持ちになっていた。
これから少しずつ、周りの見方や感じ方を変え、本当の大人になっていきたいと思った。
Posted by ブクログ
五歳児の大人、まさに自分がそれだと思いました。
自分が我慢してるから、我慢せず適当にしている人間を許せない。
この本には特に解決策は書かれていませんが、自分がそうであると気づくことがまず大事なんだと思います。
自分が五歳児の大人だと気づき、今は自分と他人を比べないように、自分は自分のやるべきことをしっかりやっていこうと思っています。
Posted by ブクログ
小さいころにやるべきことをやらずに五歳児の子どものまま社会的責任を持って生活しなければいけない人々について。
今の自分に非常に当てはまることが多い。
原因…
小さいころしたくないことを強制的にやらされてきた。
したいことをしてきてない
症状…
初めて挫折したときに生きる気力をなくす。
自分で考え自分で行動できないで対処能力に欠けている。
自分を信じることが出来ない。
真面目で憎しみを持っている。
人から好意を得るために真面目に生きている
自己実現が出来ていない
協調性がない
言うことは正しいが多数はになれない、人望がない、→憎しみがあるから
威張っているだけで周囲にやってもらう
自分の話をすると喜ぶ、
自分の人生に困難がないと思っている
与えることが出来るまでに成熟してない人
人を愛することが出来ない
自分が何者かを理解できていない
これから…
責任を取る強さと人を愛する能力が持つ
自分が相手を理解する。
アイデンティーを持つ
間違った選択をしても自分で選択することが大切。
今自分のしていることが十年後どうなっているかを考える
今日一日をきちんと生きる趣味を持つ
孤独を覚悟する
自分の愚かさを反省する
自分にマイナスな人からはなれる
人生を楽しんでる人の生活を見習う
自信を持つ
自分を支えられるような自我を持つ
人にないものを考えるのではなく自分にあるものを考える
過去の自分にとらわれ続けて今の自分を犠牲にしない
自分に目的を持つ。
Posted by ブクログ
フロムの話を定期的に出していて、ちょうどフロムの本を読んだ後だったから入ってきやすかった。
愛着障害かも?アダルトチルドレンかも?と思った人は1度読んでみると解像度が上がるのと、分かりやすく言語化されているから良いかも◎
目次の「愛する人がいれば、戦うことができる」がワードとしてお気に入り◎
Posted by ブクログ
正直、自分のことを理解してもらうにはこれを読んでもらうのがいいんじゃないかというくらいに当てはまることが多くて驚きました。
親の育て方がどうこうとかではなく、自分の気質と周囲の環境とかそういう問題もあるのかなと思いますが、子供のころに年相応の経験とか感情の表出とか、そういうのができなかったというのはちょっとあるのかも、と思いました。いわゆる「いい子」でいないとという気持ちが大きくて、とにかく言うことを聞く、自己主張をしない、我慢する、そういう癖がついてしまっている気がします。それを強制されたわけではないんだけど、それが自然なことになってしまった。だからかわからないけど、よく大人っぽいよねとか落ち着いてるよねとか言われるし、多くの人の私に対する評価は「真面目」なんじゃないかなと思います。
「真面目」というのもこの本の中では信用できない部分もあるという風に書かれているし、自分でもそう思う節はあります。真面目なのかもしれないけどそれはあくまでそうじゃない部分を抑え込むためというか、根っからの真面目ではなくて周囲の目を気にしてそうしている部分は大きいし、でもむしろ今ではそれがデフォルトで普通のことになってしまっている。自分を見せたいように見せることができていると言えばそうなんだけど、本当の自分を知ってほしいという気持ちも持っているから厄介。
頑張るエネルギーが恐怖から来ているというのもその通り。どうやったらそんなに頑張れるのと聞かれることもありますが、頑張ってないと不安で仕方ないから頑張るしかないという感覚かもしれません。
そうして耐えて頑張って努力してきた人だから、五歳児の大人は頑張らない、我慢しない子を許せない、とこの本では書かれています。本当はそうなのかもしれないけど、そういう「許せない自分」も嫌で寛容な自分を演じるうちに、許せるようにはなったんじゃないかなと思う。けど、一方でそれは頑張ってきた自分の人生を無意識に否定することにもなっていたのかもしれない、それが無気力感につながっているのかもしれないとこの本を読んで思いました。
積極的に、主体的に何かをしなければいけない、自分で決断しなければいけない、責任を取らなければいけない、そういうことを極度に嫌うのも、この本に書いてある通り。だから「後輩」という立場では、責任はあまりない状態で、純粋に認められたい、褒められたい、役に立ちたいとか言う気持ちから頑張れるけど、引っ張っていかなきゃいけない立場になったとたんにやりたくなくなる。
目的が定まっていないというのもそうかも。だから人生をかけられる何かを持っている人を見ると羨ましいし妬ましく思っちゃう。
こんな風に、自分でコンプレックスに思っている部分が網羅されている本だだなと思いました。人生のそれぞれの段階で、それ相応の経験をすることがいかに大事か、変に大人ぶったりせずに各段階を経験し健全に卒業するということがいかにその後の人生に影響を及ぼすのかということを痛感した内容でした。
Posted by ブクログ
自分の家庭環境はそこまで悪くないとは思いながらも、5歳児の大人に当てはまることが結構あった。
今を生きること。最後の文がシンプルではあるがとてもスッと心に入った。
Posted by ブクログ
加藤先生はその著作の中で、幾度となくご自身も「5歳児の大人」であったことを認めていて、この本でもそれが出発点になっている。だから、他の著作よりも主張がより明確に伝わってくるように感じた。折に触れて読み返していくようにしたい。
Posted by ブクログ
『周囲の人を見て、今日すべき事をひとつひとつしていく』
『大切なのは、自分が相手にしてあげたことも、相手からしてもらった事も覚えていること』との事。
私、してあげた事結構忘れてます…それって結局自己満足なんじゃないかと思っていて、私がしたいからしている。したくない事は極力しない。よって、お礼を言われても何のことか思い出せない。
子供の頃、周りにこんな大人はいなかったが、今はいる。
皆んなが幸せなら、それが嬉しい。昔から変わらず思っている私は大丈夫かな?
思い当たる所は改善していきたい。
Posted by ブクログ
体は成人でも精神は5歳児の男女がこの世の中に紛れ込んでいる。その5歳児に振り回されて不幸になってしまう人がなんと多い事か。精神の成長が5歳で止まってしまった原因の殆どは、幼少期の環境に有ると言う事がこの本の主旨だ。私の周囲にも思い当たる節が有り、「あるある」と納得しながら読ませて貰った。
Posted by ブクログ
私はまず、5歳児であることを認めなくてはいけないと思う。というか、今回この本を読んで、改めて心理的に大人ではないんだなって思った。
今までは、いい子でいなくてはいけないという強迫観念とありのままの自分でいてはみんなに受けいれてもらえないっていう思いがあった。それに、みんなから嫌われたくないと思って、我慢したり言いたいことを言えずに過ごしてることが多かった。
周りの人たちからは、いい子だよね、優しいよねって言われることが多かったけど、自分の中ではみんなが評価してくれる優しいって言葉にすごい違和感があったし、そんなに立派な人間じゃないよって思いながら過ごしてた。
今回、この本を読んで私が言われてきた優しいっていうのは本当の優しさではなくて、他人の評価を気にしてるが故の偽りの優しさだったんだなって納得したし、心の余裕を持って人の優しさに気づいて、自分も本物の優しさを提供できる人になりたいなって思った。
できないことを認めたり、自分のダメだと思ってる部分を曝け出すことは今の自分にとってはとても怖いことに感じる。でも、それをちょっとずつでもさらけ出して、助けてくれる人を見つけたり、自分のかけてる部分を分析して周りの人を観察していくことで何年後でもいいから、情緒的に成熟した大人になれたらいいなって思う。
Posted by ブクログ
「大人になりきれない人」を今の言葉で分かりやすくいうと「生きづらい人」。
そのような自覚があったので読んでみた。
作者に言わせれば自覚しているだけで「5歳児の大人」を抜け出すための大きな一歩は踏み出せているという。
自分が感じている生きづらさの正体が分からず苦しんだまま死んでいく人が少なくないことを考えたら私は恵まれている方なのだと感じた。
「5歳児の大人」とは肉体的・社会的には大人であることが求められる年齢にも関わらず、精神的には5歳児の段階で成長が止まってしまっている状態の人を指す。
その肉体的・社会的年齢と精神的な年齢のギャップで生きづらさが生まれるのだという。
一般的に精神年齢が低いと聞くと好き勝手に生きてきたろくでもない人というイメージを持つだろうが、実際は幼少期に「母なるもの」と接することができずに満足できなかった、そのために精神的には成長の段階を踏めずに止まってしまった不遇の人なのだ。
決して本人のせいではない。
子供の頃に子供らしい無責任な一方的に無償の愛を求めるような生き方ができずに大人になってもそれらを求め続けている。
そして子供らしい生き方をさせてくれなかった親や環境に深い深い憎しみを持って生きているのが「5歳児の大人」。
大人であることが求められるから憎しみを撒き散らすわけにもいかず抑圧する。
そして生きづらさの原因が分からないまま苦しんで生きている。
健康な精神を持った大人になるにはその憎しみをなくさなければいけない。
自分を傷つけた人々を許さなければいけない。
心の奥底に抑圧した憎しみがあるままでは全てのものがマイナスにしか感じられず、何をしてもストレスを受け続ける人生になってしまう。
疲れて疲れて仕方がない。
子供の頃、本当は愛してくれるはずの親に傷つけられた。
自分は何も悪くないのに精神的に大きなハンデを背負って生きなければいけなかった。
でもそれは過去のこととして割り切って許すことで憎しみから開放されて生きづらさが消えていくだろう。
実際にこれらを頭で理解しても簡単に憎しみを捨てるなんてことはできるものではないし、体で理解するためには色々な人と触れ合って迷惑をかけながらも精神の成長の段階を確実に一歩一歩のぼっていくことが必要だろう。
精神の健康を手に入れるまでには人生の大半を使うのかもしれないというのが当事者である私の実感。
様々な「母なるもの」に触れていきながら少しずつ成長できればいいなと思った。
Posted by ブクログ
くどく無ければ星5の出来だと思う。
今の大人になりきれてない宙ぶらりんな自分に刺さる内容が書かれている。
優しい人とはどういうものか、成熟した大人とはどういうものか、そういった心の成長という観点に対して定義付けをしてくれている。
人に与えることに喜びを見出せるようにならなければ、与える側、背負える側にならなければ、家庭を築いたり、人の上に立つべきではないのかもしれない。
大人になるためというか、人生を進めていく中で必ず遭遇する、別れ道・困難・問題点に対してのレスポンスとして、他人頼りの選択は確かに楽だしスピーディーに物事を解決することに長けるが、自己解決能力の成長や、選択の失敗の教訓を得られないのである。
まさに自分の悪いところが浮き彫りだなと、反省させられた。
また、自分の身の回りの大人たちの中で、強く逞しく頼りがいのある人とそうでない人とでどのような差があったのか、今までモヤモヤしていた疑問が解け、視界がスッキリ晴れたような心地がした。
余談ではあるが、シン・エヴァを見た時期が重なったことで、心の成長・大人になるための落とし前という観点に重ね合わせて作品を楽しむことができたと思う。
Posted by ブクログ
「せっかく生を受けたのだ、最後まできちんと生きよう」と決断する。他人まかせではなく自分で考えて選び取る。奇抜な格好もゲームも、やりたいことをやれば満足して卒業していくもの。
「大人になりきれない人」が大人になるためのステップを書いた自己啓発本が読みたいかも。
Posted by ブクログ
自分は甘えているな、と思ってどうしたら克服できるのか読みました。
・自分には何が欠けているのか知る
・「母なるもの」を持たない母親のもとに生まれた人として生きて行く覚悟を決める
・生きることを楽しんでいる人の生活を見習う
・周囲の人から好意を期待しない
・スタート地点が違うのに、今まで立派に生きてきたんだから、自分は素晴らしいと自信を持っていい!
・恨みを消すために、「今日は人から何をしてもらったか」の日記をつける
・自分の恵まれない過去にとらわれ続けて今を犠牲にしてはいけない!今を生きること
加藤先生はやさしい。
わたしは、すぐに否定されたと思い込む癖があるので、なおしたい。
*わたしに欠けているもの*
話を聞いてもらうこと 関心を持ってもらうこと ありのままを認めてもらうこと 失敗を許してもらうこと 気持ちを汲み取ってもらうこと 安心できる場所 自分の気持ちをぶつけることができる人
Posted by ブクログ
「五歳児の大人」
本書はひたすら、それについて述べている。
内容的には同じことを繰り返し繰り返し説明しているだけで、要約するとそれこそ数行で済みそうだが、それだけ繰り返し同じことを説明されると、頭に残って忘れない。
極端な五歳児の大人は、そうそういないとは思うが、自分も含め世間の大人たちは本当に年相応に成熟した大人になりきれているのか考えさせられる。
Posted by ブクログ
人に「与えられる」ことだけに幸せを求め、またそれでしか幸せを感じる事ができない。そして、人に「与える」ことで幸せを得ることを知らずに人生を過ごす。それが、「五歳児の大人」である。人を愛せない人は、人から愛されないということだ。
Posted by ブクログ
大人社会で生きづらさを感じている人たちへ贈る本。
読んで痛切に感じた。自分は筆者が嫌っていた、大人になりきれずに世間を恨んでいた父親そのものだと。そして、ひたすらに愛への渇望を叫んでいた若き日の筆者であると。
筆者はその原因を子供時代の境遇にたどり、認識することで変わることができると説くが、認識しても抜け出せないから生きるのがつらい。わかっていても変えられないから苦しくて仕方がない。
安易な解決策などはなく、結局はその人自身の力で抜け出すしかない。ただ、認識することはすべての始まり。自分に問いかけるきっかけとしてこの本は役に立つだろう。
Posted by ブクログ
大人になりきれない大人、著者曰く「五歳児大人」についての本。前半はこれでもか!というほど「五歳児の大人」をコケにします。ほんとに、読んでて腹が立つほど!笑
しかし、最終章では改善というか、「ではどうするか?」についての言及もあります。自分に置き換えながら、考えながら読むべき本だと感じました。
Posted by ブクログ
加藤先生の本は同じことを何度も何度も繰り返し書かれていることが多い。
ACのことを「五歳児の大人」と表現している。
すごい叱られている感覚になる。ぐさっとくるというか、その通り過ぎて。
けれどもその根底に加藤先生の諦めそうになりながらもあきらめたくない愛情を感じられて、何とか抜け出してほしいと思ってくれているんだな、と伝わる。
こうやって自分に対して興味を持ってくれる人も、
叱ってくれる人もいなかった人にとっては、加藤先生のような存在は大きいのだろうな。
怒りで溢れていれば、それすらも気が付かないかもしれないが。
読みにくいし、対処法がたくさん記載されているわけではないが、
読んで良かったとは言える本。
【引用メモ】
・人は、心が満足するからやさしくできる
・五歳児の大人は、社会的には適応しているが、毎日が不満である。面白くない、楽しくない。そうなれば「他人にやさしくなれ」と言っても無理
・鉛筆をイヤイヤ削らされた子は、鉛筆を削るのを忘れた子どもに鉛筆を貸さない。自分がそれだけ嫌なことに耐えさせられたのに、他の子どもがそれをしないということが許せないのである。礼儀正しくしたくないのに礼儀正しくした人は、礼儀正しくない人を許さない
➡ACあるある。
・五歳児の大人の特徴は、「生きるのが辛い」ということと同時に、他人に厳しいということ
・人は、自分がしたいことをした時に、他人のわがままを許す。しかし、それを我慢させられた人は、他人のわがままを許さない
・五歳児の大人が「こんな自分がたまらなく嫌だ」と思うようになれば、もう出口は見えている
・人は、自分がその年齢ですることをきちんとすることで、次の人生を生きる土台を築くことができる。その土台がないままに次の時代に行くから、生きるのが辛くなるのである。五歳児の大人とは、生きる土台のない人々のことでもある
➡愛着理論
・人生にはそれぞれの時期にそれぞれ解決すべき課題があると書いた。そのほかに、人生にはそれぞれの時期にそれぞれ満足すべき欲求がある。五歳児の大人はそれが満たされていない。だから他人に対して厳しい
・多くの日本の親は五歳児の大人である。
日本の親は、我慢ばかりしている人が、アメリカに比べて多い。
だからわがままな子どもを許さない。子どもにやさしくなれない。
それ以外の親は、自信がないから子どもを放任にして
・人から好意を得るために真面目にしている人は、何かあるとまったく人が変わる。人から受け入れてもらうために真面目にしている人は、道徳的でも何でもない。彼らは認めてもらうために倫理的に振る舞っているだけで、もし分からなければ普通の人よりもはるかに反倫理的なことを平気でする
・五歳児の大人は、生き方そのものが「楽しむ」ということに重点が置かれていない
一方、心理的に健康な人は、どちらかというと楽しむことに重点が置かれて生きてき
・五歳児の大人の性格的特徴の第二は、他人の弱点を許せないで、協調性がないということで
辛い思いに耐えて生きてきた人々が、安易さに流されて努力しない人を認めたら、自分の今までの生き方、自分の価値、自分の存在そのものを否定することになる。
何よりも、辛い努力をしないで安易に生きてきた人が嫌い
➡わかる。この人はこれまでどうやって生きてきたんだろう、って思う。
でもそもそもACとACでない人の生きている世界(見えている世界)は違うから。
仕方のないこと。でも理解できないし、許せないんだよね。
・安易さに流されてわがまま放題の人々に、どのくらい激しい敵意を抱くかということは、その人がどのくらい辛い思いをさせられながら生きてきたか、ということに比例する
小さい頃、どのくらい大人の言う通りに嫌なことを従順にしながら生きてきたか、によるのである。辛い思いに耐えて従順に生きてくればくるほど、嫌なことをしないで、安易に流される人間を認められない
➡納得。これは他の本には書かれていないことだった。
怒りの度合いの違いだね。
・多数派になれない人々がいる。人望がない人がいる。言っていることもしていることも正しいが、みんながトップとしての 器 と見なさない。それは、今述べた憎しみを乗り越えていないから
人望のなさとは、人柄の問題
・自分の裸一貫からの努力を社会は考慮しない、それでも貧しい人にやさしい気持ちになれる人が、人の上に立つ器なのである
・心のゆとり」が、人の上に立てる器量である。
そういう人に、人は安心感と信頼感を持つのである。
どんなに正しい理屈を言っても、それだけで人は、その人に安心感を持つわけではない。その人を信頼できるわけではない。
➡なるほどなぁ、、
・本当のやさしさとは、自分がやさしさを感じて、自ら他人にもやさしくできることである。やさしさを強制するのは教育ではない。
無理にやさしくさせられたのは、やさしさではない。
しかしこれを、五歳児の大人は小さい頃からやられている。
だから、立派だけれども心がやさしくないのである。
➡その通りだと思った。自分が優しくされていないのに、人に優しくすることをずっと求められてきた。
人に優しくを常に考えながら生きてきたけど、
自分は本当は心が優しくない、とずっと思ってきた。
・いかなる時にも自分の辛さを 切々 と訴える人がいる。「私はこんなに辛いの」と涙ながらに訴える。これが五歳児の大人
同情されると機嫌がよくなる。
「僕をちやほやしてほしい」が五歳児の大人である。
五歳児は、「僕をちやほやしてほしい」のだから、五歳児の大人も同じことである。五歳児の大人は、義務と罰で育てられている。甘えの欲求が満たされていない
➡確かに、ちやほやされたい。
・ロジャースは、子どもは積極的に関心を持たれることを必要としている
・関心を持たれて育った人にしてみれば、
子どもに限らず相手に関心を持つことは自然なことである。
別に努力をして関心を持つわけではない。自然と関心を抱くのだ。
・五歳児の大人は、生まれてから死ぬまで自分の自然を許されないで生きるのが、当たり前のように周囲から期待された人々である。つまり、人間として生まれ、人間でありながら、人間でないことが当たり前のように周囲から期待された人々である。
➡つらいね、、
・愛されて育った人は、周囲に感謝するのを当たり前だと思う。
しかし、愛されないで育った人に、そのことを期待するのは残酷で
・人間にとって本質的な不満とは、要するに幼児的願望が満たされないという不満
・同じ体験が、ある人には苦痛になり、別の人には喜びとなる。
人間の幸せにとって重大なのは、何を体験するかということと同時に、
その体験をその人がどう感じるかということ
・トラブルは、決してあなたの価値を下げるものではない
色々なトラブルに巻き込まれる。そこで「自分はダメな人間だ」などと決して思ってはならない。自分は、よくここまで頑張ってきた人間なのである。どんなトラブルを抱えようが自分は素晴しい、という確信を持ち続けることである。
自分を責めてもいけない。しかし、立派だと信じていた自分たちの家庭に問題があった、ということを認めることである。次に、そのつけを黙々と払い続けること
・この世の中は弱肉強食ではない。少なくとも倫理的にそれは否定されている。実際に暴力が使われたとしても、暴力はいけないという倫理はある。しかし、心理的な世界では、間違いなく弱肉強食である。どんなに五歳児の大人が一生懸命しても、その努力の誠意は認められない。 必死で歩いているよちよち歩きの幼児を、「どうしてそんなに遅いんだ」と殴る人はいないだろう。しかし心理的世界においては、そうしたことは日常的に行われているのだ。心理的には、そうしたよちよち歩きの「大人」は、必死になって努力しても、その努力したことを認めてもらえずに、 怠け者と批判され、自分はダメな人間だ、冷たい人間だ、豊かな感情に恵まれなかった人間だと、自分を 蔑んで死にたくなる。だから、五歳児の大人は「生きるのが辛い」
・自分が悩んだ時には、常に客観的にこれだけ悩む原因があるわけではなく、自分の気質が自分を悩ませている面もあるのだということを心に留めておくべき
これまでの生き方の違いや、生まれた環境の違いがある
・「フロイトは、幼児期の母親に対する愛着――一般にはほとんど完全に消えることのない愛着――には異常に大きなエネルギーが内包されている
・「幼児期の母親に対する愛着」とは、母親に触れたいという欲求である。
人はみな安らぎを求めているのである。
人の安らぎを求めるエネルギーは、巨大である。
人はなんとしても安らぎが欲しいのである。
そのために、人はさまざまなことをする。これが満たされなくて、その満足を求めて、人は悪口を言ったり、長い悩みの手紙を書いたりする
この手紙を書くエネルギーをどうして前向きの生き方のために使わないのだろ
どうして問題の解決のために使わないのだろう、と不思議に思う
読んでいて吐き気がするほど自分勝手なのである。
その、独りよがりの他人を無視したエネルギーに、吐き気がする
この巨大なエネルギーこそ「幼児期の母親に対する愛着」のエネルギー
そのしがみつきのエネルギーは巨大である。 一旦 しがみつかれると、しがみつかれた人がノイローゼになる。それほどものすごいエネルギーでしがみついてくる
・深刻に悩んでいる人は、会う人みなに「母なるもの」を求める。
そしてそれが与えられないので、その人に幻滅する
➡自分で与えられる、自分でしか与えられない、ということを、納得してもらう必要がある。
そうでないと、相手は母親からの愛をカウンセラーや他人に求めることになる
・愛着人物がいない時には「良い子」であり、
愛着人物がいる時には手のかかる子になるということで
➡HSPの親しい人には思っていることを言える(=わがままを言える)のに近い気がする。
・燃え尽きる人は、嫌いな人にさえ愛されたい
・「幸せになる能力」とは、ほかならぬ「自分を尊敬すること」であり「愛する能力」のこと
・生きるのが辛い、辛いと騒いでいる人は、多くの場合、周囲の人が嫌いなのである。そして、嫌いな人のために働いている
まず第一に、孤独を覚悟することである。
周囲の人から好意を期待しないことである。
周囲の人の好意を期待して何かをしないことである。
一人になること、そのほうがいい。そうすれば自分にやさしくできる
●周囲の人から好意を期待している限り、あなたはますます周囲の人が嫌いになる。あなたの期待したようには周囲は動かない。
その結果、また周囲への憎しみを増すことになる。
そうした体験の積み重ねの結果、ますます生きることが辛くなる。
地獄とは、「人が嫌い」ということであり、天国とは「人が好き」ということ
➡納得。
・「誰も私の気持ちを分かってくれない」などと言うのは、甘えている証拠
・子どもに甘えないとはどういうことか。
子どもに自分の気持ちを 汲み取ってもらうことを 諦めるということである。
「親の苦労も少しは分かってくれ」と思わないこと
・自殺していった人は、みな自分の挫折を受け入れられなかった
・「母なるもの」を持たない母親のもとに生まれた人として生きていく覚悟を決めることである。
最後まで地獄で生きてしまうのは、自分が分からないからである。
自分が分からないとは、自分には何が欠けているかが理解できないということである。
生き方を間違ってしまうのは、自分には何が欠けているかが理解できないからである。そういう人は、人生の目的も間違える。
・自分は「母なるもの」を持たない母親のもとに生まれたのだと理解した時に、人々への恨みも消えていく。
それは自分の運命を受け入れた時である
・今日まで立派に生きてきた。あなたは今、生きていることに自信を持っていい。どのような心の状態であろうと、自分は素晴らしいのだと自信を持っ
・人間というのは、お互いに相手は自分と同じだと思っているし、何をしていても同じことをしていると思っている。しかし事実としては同じことをしていても、実は心理的にはお互いに違ったことをしている
・五歳児の大人は「母なるもの」に接することなく成長している。その結果、心の底に憎しみを持っ
この憎しみの感情を処理することが、五歳児の大人の最大の課題
欠けていることに注意がいくから不満になるのではない。
不満だから欠けているところに注意がいってしまうのである。
人は不満だと、どうしても欠けているところに注意がいってしまう
他人と自分を比較するから劣等感を持つのではなく、
劣等感があるから他人と自分を比較するようなもの
不満な人に満足した人と同じ物の見方をしろと言っても無理なのである。満足すれば、自然と満足した人の物の見方になる
自分を傷つけた人といつまでも心理的に 拘わっていれば、
人は心理的に成長できない。
いつまでも憎んでいては、どんなに努力しても人は変わらない。
・傷ついている自分をそのままにして、どうして心やさしい人間になれるだろう
何度も「今に生きる」と書くのだ。自分が納得するまで「今に生きる」と書くのだ。自分の恵まれない過去に囚われ続けて、今を犠牲にしてはいけない
・恨みを消すためには「今日は人から何をしてもらったか」の日記をつけることである。五歳児の大人は、自分が相手にしてあげたことは覚えているが、相手からしてもらったことはまったく忘れてしまっている。
また人からやられたことはいつまでも覚えているが、自分が相手を傷つけたことは意識してい
・本当は自分のわがままを通そうとしているのだが、わがままとは思われたくない。そこで表面は立派なことを言っている。当然、生きるのは辛くなる。そしてわがままが通らないと周囲の人を責める。 そうした責任転嫁をしていても、生きることはいつになっても楽にならない。むしろ、自分はわがままを通そうとしているのだと分かることが幸せに通じる道なので
・自分が子どもに好かれる母親を演じながら、自分の望みを遂げようとする。子どもに嫌われないで、自分の思うように子どもを動かそうと
・人が幸せを感じるのは、求めるものが分かっている時でもある。
それなのに五歳児の大人は、自分が何を求めているか分かっていない。
今、五歳児の大人に大切なことは、自分は何を求めているかを知ること
Posted by ブクログ
読んでいて悲しくなった。
今を生きるということが何よりも大事、これだけ思っていたい。
世間体とか捨ててしまえ...楽しく生きたもん勝ちや...
Posted by ブクログ
固着を起こすと心理的に大人になりきれないのに身体的・社会的次のステップに進まされるので負荷が重すぎて潰れてしまうとのこと.負荷が重すぎというのはなるほどと思う一方,各年齢の過ごし方は「こうあるべき」という全称的べき論を規定しているのは微妙かと.
Posted by ブクログ
同じような文章の繰り返しが多くて読みづらかったです。しかし、納得できる部分も多々ありました。
これからを担う若者にぜひ読んでもらいたいと思いました。
Posted by ブクログ
ACの本かと思い購入したが、この本にACという概念は出てこない。似たようなものだと思うけれど。
サラリーマンのおっちゃん、子育てに苦しむママさんなど、何で彼ら彼女らはストレス溜めまくりで欲求不満なのか、すっきり分かった。でも、同じことを違う言い回しで何度も言い過ぎな節もあって、最後の方はちょっとうんざり。
Posted by ブクログ
順調に年を取って社会的な責任がどんどん増しているのに、精神は5歳児のまま一向に成長しない「5歳児の大人」が増えていると著者は指摘する。心理学的に言うと、こういう大人は、幼児期における母親からの愛情が足りていない、ということになるらしいが、その主張はイマイチよく分からなかった。ただ、下記の引用にはドキッとしたのでメモしておく。私自身も、今のようにまっとうな職について、社会人として仕事をして、人並み以上の給料を貰っていることは「奇跡」だと思っているので…。(小学生~大学生の頃の知り合いは、みんな「あのアンタが、よく普通にサラリーマンになれたね」って反応だもん。私はどれだけ社会不適合者だと思われているんだ!?)