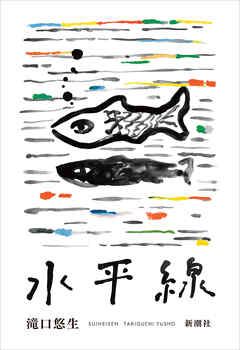あらすじ
祖父母の故郷・硫黄島を墓参で訪れたことがある妹に、見知らぬ男から電話がかかってきた頃、兄は不思議なメールに導かれ船に乗った。戦争による疎開で島を出た祖父母たちの人生と、激戦地となった島に残された人々の運命。もういない彼らの言葉が、今も隆起し続ける島から、波に乗ってやってくルルル――時を超えた魂の交流を描く。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
過去も未来も繋がっていルルル。
本にしかできないことがつまっていル。散らかる文章の先にわたしを待っているものがあル。過去でもあり未来でもあル。
Posted by ブクログ
時系列と語り手が移り変わるので、最初は戸惑うが、惹き込まれて読んだ。硫黄島、父島の戦中戦後の家族の物語。現代を生きる孫世代との謎の交信が不自然でなく描かれ、謎への興味に引っ張られて読めた。
硫黄島に米軍が上陸して戦場となっていたことを初めて知ったし、そもそも島の存在を知らなかった。内地に引揚げる家族と別れ、島に残らなければいけなかった人達の悲惨な運命。描写は淡々としていながら、それぞれの人物が語り手として登場することで飾りのない心情が伝わる。終わっていない終わり方も良い。
Posted by ブクログ
夏の季節に読めて良かったです。複数の本を同時並行で読み進める癖があるから、読み終わるのに1ヶ月くらいかかってしまったけど。
たとえば長い一日などで感じた、日常の中の些細なことの自分・他者の拡がりや、茄子の輝きで感じた、過去の自分の記憶の漂いみたいな、滝口さんの哲学たちが、時間軸や物理的にも拡張された壮大なスケールで展開されてゆきます。
壮大なスケールと言っても、SFみたいなあり得ない世界というわけではなく、まぁ見方によってはそうかもしれないけど、なんだか本当にあるような、ファンタジーとかって分類する意味がないような、日常のものとして語られていく。その語りが、悲哀に満ちた劇的な最期ではなく、硫黄島で死んでいった人たちの生活そのものを私たちの生活の地続きとして感じさせます。
過去の遠い出来事として薄れつつある戦争も実際にはあって、私たちと変わらない、語られない、残らない人たちが、それぞれあっけなく簡単に死んでいったということを実感として持っておきたい。
ただ目の前のことを受け入れる、理解しようとせず、疑おうとせず、そのまま受け入れる自分を受け入れたい。なにせ、確かなものなど、本当の一つもないのだから、と思いました。
もっといろいろなことを考え、想ったのだけど、すぐどこかへいってしまう。けど、そんなもんだよな、人の感情や記憶なんて。どこかにいってるだけで、確かにあって、確かに想ったことだけおぼえていれば、そのうち何かのきっかけでふわっと思い出すでしょう。
Posted by ブクログ
好きな滝口悠生さんの長編小説。文章がいい。「これは対話と呼ぶに足ル、と重ルは思っていル。」 ここ好き。
いつもの軽妙で誠実な語り口から広がる世界。過去と今、未来。現実と空想、縦横無尽。
硫黄島で生活していた人たちは私の頭の中にいるし私の頭の中からどこかへ呼びかけている。
Posted by ブクログ
とても読みでのある小説だった。読書好きの人には勧めたい本。
長いし、わりと時間はかかるのだが、どんどんページをめくっていきたくなる小説。
時空を超えたり、死者が語ったりするのはどちらかというと苦手なのだが、全く違和感なく、そんなこともあるだろうよみたいな感じで読めた。
硫黄島に人が住んでいたのは、映画「硫黄島からの手紙」等で知っていたし、その人たちが大変な思いをしたというのもなんとなくはわかっていた。そして戦後戻れないままであったことも理解していた。でもそこまでだった。この小説を読んで、生き生きとして暮らしていた人たちの様子、そこを去らなければいけなくなった悲しみ、家族との別離、新しい土地での苦労、島に残された青年たちの悲惨なその後など、知ることができた。
現代のパートはわりと楽しく読めた。こちらは自分も生きているのでリアリティがあり、それはそれで考えさせられるのだが、ちょっと息抜きもできた。硫黄島のパートも、別にずっと悲惨なわけではない。普通に暮らす日常があった。それを断ち切られてしまった、戦争のせいで。
「島」は大変だ。今現在も沖縄の島が将来犠牲にならないですむのかと心配になるような出来事が続いている。本島に住むものたちより先に犠牲になるようなことは絶対に避けなくてはならない。そんなことは一言も書いてないけど、そのことを改めて強く感じさせられた。
滝口悠生さんの小説は新刊が出るたびに「読みたい」と思うものの、読んだことがなく芥川賞受賞作以来だ。今回はしっかり手に取ることができてよかった。
"そこにはたしかに、よろこびもあった。(略)でもそんなのは作業に没頭している束の間の幻想だ。真剣さは毒だ。真剣になっているうちに、自分じゃなく誰かべつの者のよろこびが自分のよろこびであるかのように思ってしまう。他人のよろこびを俺がよらこぶのは俺の自由だが、他人から、そいつのよろこびが自分のよろこびであるかのように惑わされて騙くらかされるのは御免だ。だから俺はあれからずっと自分の真剣さを疑っている。なるべくふざけていたい。大事な話や、大事なものについて考えるときほど、真剣さに呑み込まれてしまわないように。" 308ページ
"いまは小さな濠のなかにいた。(略)生まれてこの方二十年以上も暮らした小さな島のなかなのに、いまいる場所がよくわからない。重ルには、そのことが違和とか焦りとかよりもまず悲しみとして感じられた。少し不思議だが、この悲しみはいったいどういう悲しみなのかと考えを追う気にならない。子どもの頃、意のままにならず泣いてみせるときみたいな、わからなさのなかで弱くなるような気持ちだった。" 317ページ
"いっけん規律に厳しい軍の仕事も、よく見ればあちこちにぼろがあって、いい加減さが露見しそうになれば無理くり封じ込めようとする。ないものもあるし、あるものもないことになる" 329ページ
Posted by ブクログ
太平洋戦争末期と現代。
物語は時空を行き来しながら進む。
70年以上の時間を隔てた人物から届く電話、メール。
今を生きる若者が導かれるように縁ある地に足を運ぶ。
不思議な物語。だが、この構成だからこそ強く伝わるメッセージが確かにある。
これまでの滝口作品とは一線を画す作品。
傑作。
Posted by ブクログ
読み終わるまでに時間もかかかったけど、読み終えてからもあれはなんだったんだって考える時間もあったりといい読後感だった。
最終章を読んでいた時、この部分を読むためにずっと漂っていたのかもしれないとも思った。思っていル。
「海はあらゆる時間にもつながっているんだ、海を見てれば誰だってそのうちそう気づいて気づいたときには遠い時間が波にのって寄せてくる」
硫黄島にはかつてそこで暮らし死んでいった人々がいた。民宿「水平線」の2階の部屋にはかつてそこで海の向こうを眺めていた家族がいた。そして今を生きる人がいる。そうやって繋がってきたものが時間を超えて混じり合う。海や釣りを介して。
現代パートでは横多の生きている世界では2020年に東京五輪が開催されているけど、妹の世界線では五輪延期しているのに兄(横多)の言っている五輪はなんだったんだろうという場面がある。この世界線の違いはなんだったんだろうと考えてもわからなかった。なので、そういうもんなのかと思いながら読み進めた。
Posted by ブクログ
硫黄島の島民の記録を軸に,敗戦前に疎開した人々とその家族を少しオカルト交えて描いている.そして軍隊に徴用された人々が全員死んだ事実には,改めて胸が塞がれる思いがする.硫黄島からの疎開者の孫である来未に死んだはずの祖父の弟忍からかかってくる電話と横多兄に行方不明の祖母の妹からのメール.夢ではなく現実に過去が混ざり合ったような場の異空間の表現が自然で,読みながらも受け入れていて,でもそれはおかしな事.
硫黄島といえば,戦争の激しさばかりが強調され兵隊さんたちの悲劇がクローズアップされるけれど,島中犠牲になった人々のことを思うと,どこかサバサバと綴られた物語の中に深い哀しみを感じました.
Posted by ブクログ
クリント・イーストウッドの映画で有名になった硫黄島。戦前は住民がいたなんて知らなかった。
硫黄島に残り亡くなった家族、そして本土に疎開して生き残った家族とその子孫の物語。リアリズム小説なら並行世界的に描かれるところだが、この小説では超常現象的に両者が交わり、そしてそれはとても自然に書かれる。またリアルに表現されているはずの現代パートも微妙にズレて両立する。
最初はその荒唐無稽な内容に違和感を覚えるんだけど、だんだんその世界に馴染んできて、世代的に遠く離れた人々が身近に、逆にリアルに感じられるようになる。不思議な話だ。
硫黄島の砂糖工場で使われる牛フジに最も共感を覚えるというのは、自分としてどうか。
「真剣さは毒だ。真剣になっているうちに、自分じゃなく誰かべつの者のよろこびが自分のよろこびであるかのように思ってしまう。他人のよろこびを俺がよろこぶのは俺の自由だが、他人から、そいつのよろこびが自分のよろこびであるかのように惑わされて騙くらかさせるのは御免だ。だから俺はあれからずっと自分の真剣さを疑っている。なるべくふざけていたい。大事な話や、大事なものについて考えるときほど、真剣さに呑みこまれてしまわないように。」
Posted by ブクログ
なかなかの力作!
うん?誰のパートだ?と最初は戸惑うが、人物像がはっきりしてくるとすぐに自分の頭も切り替わる。こんなファンタジーもありだと思う。知り得ぬ世界のことに思いを馳せて心を通わせていくところが良い。秋山くんと西武の秋山の話をするくだりがほのぼのしていて好き。
Posted by ブクログ
1982年生まれの作家が、生まれる40年近く前の戦争を描くには、相当な覚悟も根性も要ったのではないか。2020年の感染症が広がりオリンピックがどうかという現代に生きる来未たちと、その60年前を生きる忍ら。
中上健次を思い出すようでもあり、『想像ラジオ』や『フィールド・オブ・ドリームス』を思い出すようでもあり。たまにクスリと笑ってしまうような地味なユーモアも。
死者と生者が繋がるということが、たぶん時にはあるんだと思うよ。
Posted by ブクログ
親が離婚したことにより苗字の異なる兄妹である横多平と三森来未。平には祖母の妹から、来未には祖父の弟から、すでに亡くなったはずの人からなぜかメールや電話がくる。さらには平がいる2020年はコロナがなく東京オリンピックが開催されているが、来未のいる2020年はコロナが蔓延していてオリンピックも延期された。
海の水平線の向こうには見えなくても島や大陸が確かに存在しており、ということはすでに亡くなっいて目には見えなくてもその人の思いが残っていたり会話したりもできるのでは…というのが著者の言いたいことだったのかな?
皆子が突然失踪した理由が最後まで明かされず、平が大島まで行ったがそこに皆子が住んでいたのかどうかもわからずじまいで消化不良な読後感だった。