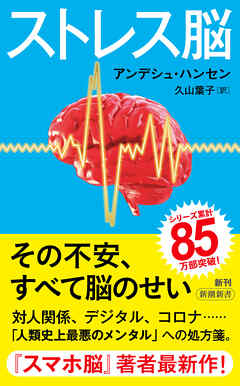あらすじ
病気や飢餓などのリスクを克服し、人類はかつてないほど快適に生きられるようになった。だが、うつや不安障害は増加の一途……孤独にデジタル社会が拍車をかけて、現代人のメンタルは今や史上最悪と言っていい。なぜ、いまだに人は「不安」から逃れられないのか? 幸福感を感じるには? 精神科医である著者が最新研究から明らかにする心と脳の仕組み、強い味方にもなる「ストレス」と付き合うための「脳の処方箋」。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
昨今はポジティブ思考、引き寄せ、強く願えば叶うなどの自己啓発の言葉を聞かなくなった気がします。そんな私も、このような類の書籍を読んで、色々と実践してきましたが、いつも目指すゴールに辿り着くどころか、反対に惨めな気分になる自分がいました。それは努力が足りないからだと自分を責め、ここ数年ほどは自己啓発本からは遠のいていました。
そんな折、YouTubeで樺沢紫苑先生がこちらの書籍を勧めていたのと、サイエンスライターの鈴木祐さんが私たちの脳について興味深い話をされていたのが本書を読むきっかけとなりました。
本書を通して、なぜ自分が幸せを感じられないのか、でもそれは間違ったことでもなく、そしてどこに目を向けて行動すればいいのかを知ることができました。
私たちはこんなにも便利なものに囲まれて、何の不自由もなく生活しているのに、精神的に病んでいる人の数は増加しています。筆者の言う幸せの定義は、常に最高の気分でいることや、最高の気分に持っていくことではなく、長期的に人生に意義を感じていられるかということです。
また、自分の脳も当てにならないことがわかったので、気分的にもかなり楽になりました。
Posted by ブクログ
技術・娯楽が発達し豊かになったはずの現代で、人々のメンタルは史上最悪と言われている。うつ病をはじめとする精神疾患はなぜ起きてしまうのか。その謎を脳の仕組みと人間の歴史から解明していこうとする新書。
なにがメンタルにとってリスクになるのか、それをどう防いでいくのか。各所で行われた実験を基にしているので、とても勉強になり面白かったです。
この本で印象に残っていること
・幸せは追い求めるものではなく、意義を感じられることに没頭した先に生まれる副産物。
・常に幸せである必要はない。
Posted by ブクログ
サバンナで生き残った人間達とほぼ同じ脳を私達は持っている、という考え方がいままでに無く、本の内容はこの筆者の本だと大体似た内容ですがそれでもやはり面白かったです。
自分に対しても他人に対してもなぜこういうことをするのかのメカニズムがこの本を読んでから大体こういうことかな?と考えることが増えました。
章のまとめもあってわかりやすく、ロマンチスト以外はお勧めできる本です。
Posted by ブクログ
・私たちの4人に1人が人生において精神的な不調を経験する
・回復さえできれば、たいていのストレスには勝つことができる
・孤独を絶対に感じないのは、不安を絶対に感じないのと同じくらい非現実的なことなのだ
・週に2〜6時間心拍数の上がる運動をするのが最も効果的。一方週に6時間以上運動しても、それ以上の防御効果はない
・脳の最重要任務は私たちを危険な世界で生き延びさせること
・自分は何が得意で、それをどんなふうに自分そして他人のために使えるのかを理解すること=幸せ
・エンドルフィン…鎮痛作用、強い幸福感を与えてくれる物質
・エンドルフィンの放出→親密な関係生まれる…グルーミングと呼ぶ
・ずっと幸せでいるなんてことはありえない
Posted by ブクログ
ストレスからくる不安やうつについて、その仕組みと背景を解説している本。科学的な面からはもちろん、人類学的な観点から、なぜ人間には不安やストレスを感じる機能が備わっているのか、ということを分かりやすく教えてくれる。人類の進化の歴史の中で言えば、私たちの脳はまだサバンナにいると勘違いしているのだ、という話は興味深かった。現代文明の急激な進歩に付随するひずみのようなものが、私たちのストレスや不安という形で表れているのかもしれない。筆者はそういった諸々への対処法として運動を進めている。これも科学的な見地からの提案になっているので、とても納得感があった。運動がいいとは聞いていたが、この本を読むことでようやく腹落ちした感じ。ストレスに悩まされていたり、現在休職中で不安に苛まれている人は、体調が良いときに一度読んでみてほしい良書。「疲れていて活字を読むのは辛い…」という方には、筆者の『メンタル脳』がおすすめ。本書の内容をもとに、中高生向けにまとめ直されたものダイジェスト版なのでとても読みやすい。
Posted by ブクログ
「スマホ脳」に引き続き、こちらの著書も拝読。ストレスにより脳がどのように変化するかに焦点を置いて様々な研究や検証を行い、著者の考えが述べられていた。
人間は進化しているようで進化していないので、健康的な生活を送りたければ今の生活を見直すことからが第一歩だと思った。
Posted by ブクログ
幸せとは長期的に人生に意義を感じ続けていられる状態! 人類が生き延びるために心身に、気づきを与えている事が今の我々に現れている。恐れず、利他の心で仲間のため、自分のために存在意義を見出し日々を味わって生きろと。そう受け取って少し勇気を68歳、いただきました。アンデシュ・ハンセンさんの本二冊目! あと三冊持ってるので、さらに深く味わいたいと思ってます。
Posted by ブクログ
とても良書だと思う。科学的根拠に基づいて書かれていて、わかりやすい。
印象に残ったこと
記憶は取り出した際に変化する。(語る、紙に書く)
脳の目的は、生き延びさせること。
トラウマの記憶を封じ込めるのは良くない(変化しないから)
孤独になると、交感神経優位になる、睡眠浅くなる、
人間は、集団で生き延びてきたから。
社会的な関係を維持したい欲求は、食欲と同じくらい欲求。
皮膚は軽く触られた時に、反応する受容体がある。
セロトニンは、ヒエラルキーや地位、情動
SNS等で他人と比較すると、セロトニン下がる→鬱
運動は、精神疾患のリスク下げる。
Posted by ブクログ
第1章 私たちはサバイバルの生き残りだ
第2章 なぜ人間には感情があるのか
第3章 なぜ人は不安やパニックを感じるのか
第4章 人はなぜうつになるのか
第5章 なぜ孤独はリスクなのか
第6章 なぜ運動でリスクを下げられるのか
第7章 人類の歴史上、一番精神状態が悪いのは今なのか?
第8章 なぜ「宿命本能」に振り回されてしまうのか?
第9章 幸せの罠
について、体の中の生理現象(特に脳からの分泌成分)を使って非常に分かりやすく解説し、やっぱりね!と納得させられた本。これがベースとなって青少年向けに先日読んだ『メンタル脳』を書いている。
Posted by ブクログ
スマホ脳に引き続き読破。
スマホ脳の内容を掘り下げた内容となっている。
結論にある「人間は不安を感じて当然」「幸せでありたいと思わない」は、なんとも切ないが、不安や幸せという目に見えないものを追い求めるほどさらに苦しくなっていくのだろう。
広告や動画、文章の虚無なメッセージに振り回されない(目をつぶる)ようにしよう。
また前作スマホ脳に続き、運動の重要性が解かれている。
週に1時間以上の散歩をしただけでもうつへの防御になるのだそうだ。
また、週に2~6時間心拍数の上がる運動をするのが最も効率的だそう。
とにかく毎日少しでも体を動かすようにしたい。
Posted by ブクログ
「それは最良の時代であり、最悪の時代でもあった」チャールズ・ディケンズ 『二都物語』より
まさに現代のメンタル環境は、そうらしい。SNSには功罪がありすぎる、人と繋がれる手軽さの功罪。著者は何人かの親友が居れば良いと言っている、私も賛同する。都会には人が多すぎる、私も落ち着いたら田舎ほど行かないが程よく利便性が効く程度の所で充分。
Posted by ブクログ
研究結果や論文をもとに、脳がどんな影響を私たちに与えているのかを分かりやすく説明してくれる。
孤独のリスクや運動の効果を知れてとてもありがたい。
第9章「幸せの罠」では、当たり前なのに忘れてしまっている事を気付かせてくれる文が何度も出てくる。
この本を手に取って良かった。
・幸せの感情は消えていくものだ。そうでなければ感情の最も重要な任務、つまり私たちに何かをしたくさせるという役割を果たせない。
・恒常的な幸福感など人間にとって自然な状態ではないというのに。
この2文は、当たり前の事なのに凄いパワーがあると思う。
そして私はいま、ステッパーを踏みながらこの感想を書いている。
Posted by ブクログ
人間の脳は今もサバンナで狩猟生活をしているのであれば、食うに困らない現代は夢の世界のはずなのに私たちはうつになったり眠れない夜に悩まされたりする。身体を動かすこと、孤独にならないよう人と直接会い話すこと。そして『あらゆる体験を自分の期待と照らし合わせるように進化したからこそ、幸せを追い求めるのをやめる』ことが良いとのこと。人は幸せになるために生まれてきたと思っていたが、なぜだかこの世に生まれて来たのなら生き延びるのが最優先。幸せじゃないと思った時、宿命を感じた時、孤独を感じる時、手元に置いて読み返したい。
Posted by ブクログ
私たちは生物。
絶滅するのが原則であり、生き延びるほうが例外である。
自分の恐怖の種類も、すべては生き延びるため。
そもそも幸せでいるようにはできていない。
辛い記憶を思い出すのは、脳が同じことが起きないように守ろうとしている。
ストレスは感染リスクが高まった合図。
遺伝子レベルだから、仕方ないと思おう。
運動と仲間と一緒に過ごすこと、大切にしよう。
Posted by ブクログ
人が不安やストレスを感じる理由を、脳の仕組み、人類の進化の過程との関係などから説明した本。
これだけ技術が進展しても、脳には狩猟時代に生き残るために人類が選んできた優先順位が刻まれている。だから、空腹ではなくても、食べ物があれば食べてしまうし、集団から外されるなど孤独を恐れる、という説明は納得感がある。
また、狩猟時代は生きるために運動量が多いのが普通であったことから、ヒトは運動をしないと不調になる。だから、運動はうつや不安からヒトを守ってくれる。
一方で、幸せを追い求めるのは非現実的で辛いだけ。1度の食事での満足感が長く続くようでは、生き延びられないのだから。
読みやすく、納得てきることも多かった。
Posted by ブクログ
「うつ」は脳の正常な反応、という点については、すごく納得できました。
その背後に、「ヒトは、幸せになるのではなく、生き延びるようプログラムされている」という点も、すごく納得できました。
ただ、本書で何度も出てくる「ヒトの脳はいまだにサバンナを生きている」のような表現には、個人的には違和感があります。
「ヒトの脳はいまだに、サバンナで生き延びることを前提(目的)にプログラムされている」のような表現であれば、しっくりきますが。
ただ、これについては、著者の問題ではなく、訳者の問題かもしれませんが。
個人的に、進化論の視点は、本書に限らず、生きていく上で多くの場面で使える視点だと思っているのですが、本書を読み進める上では、必須の視点かもしれません。
その視点があるかないかで、本書に対する納得度に、大きな差が出るような気がします。
Posted by ブクログ
わかりやすく、かといって安易に断言せずに今の学説と調査に照らし合わせて真摯に書かれていると思う。
自分がうつ病になった時も救ってくれたのは病院(合わなくて何件かかかったけれど)、散歩、ネット上ではあったけれど人との関わりだったので納得。人と比べることで幸福度が下がるのはブータンの例でわかっているし、女性が年をとると楽になるのはモテを捨てるからといわれるより他者と比べることをやめるからといわれるほうが腑に落ちる。
Posted by ブクログ
・人間が現代社会についていけてない(進化できてない)。
・心配性の遺伝子だけが命をつないできた。
・ストレスを物理的攻撃だと感じるので、身を守るために引きこもる(うつになる)
・一つ一つのストレスが気にしなくていいものは気にしなくていいと認知をさせる必要がある
・運動をすれば脳が安全であると錯覚する
など
よく言われてきた、ストレスに対しては「よく寝ろ」「運動しろ」「友達や家族と仲良くしろ」の理由を科学的に解説された本です。
Posted by ブクログ
スマホ脳から2冊目なので内容は被るがその分読みやすく納得できた。
うつの予防に運動は大切なんだなぁ!
私がダイエットうまくいかないのも遺伝子レベルにカロリーを消費するなーって脳が言ってるからなのか!笑
遺伝子になんか負けずに今日も走って、ストレスへの態勢を作りたいと思った今日この頃。
日常生活で不安を抱えている人が読めば、自分の性格じゃなくて脳の正しい反応なんだと少し心が和らぐのでは?
忘れた頃に最後の10箇条は読み返したい。
Posted by ブクログ
書籍末尾にある「10の最も重要な気づき」
①あなたはサバイバルを生き延びた人の子孫だ。健康や幸せのためではなく、生き延び、子孫を残すために進化した。だから常に精神的に元気でいるのは非現実的な目標だ。
②感情はあなたに行動させるために存在し、すなわち変化していくもの。脳があなたの周囲と体の中で起きていることをまとめたものが感情であり、体内の状態は思っている以上に重要。
③不安と鬱は大抵の場合、防御メカニズム。どちらも人間の本質として正常で、あなたが壊れているとか病気だとか言うことではない。何より絶対にあなたの性格ではない。
④記憶とは変化するもの、そうあるべき。トラウマになった記憶は安心できる。環境下で語ることで変化し、脅威を減らすことができる。
⑤睡眠不足、長期的なストレス、じっと座っていることなどで、脳が「自分は危険な世界にいる」「自分は自分ではない」と言うシグナルを受け取る危険性がある。脳はそれに対して、あなたを引き困らせなければと思い、精神状態を悪くしてしまう。
⑥運動はうつや不安からあなたを守ってくれる。あなたは運動するようにできていて、今の時代は運動量が少なすぎる。一方で、ダラダラしたいと思うのも正常な反応。
⑦孤独はいくつもの病気に影響するが、小さな努力が大きな違いを生む。健康の見地からは、親しい友人が数人の方が、浅い知人が多くいるよりも良い。
⑧遺伝子の影響もあるが、たいていは環境の方が重要。遺伝子的にそうだからといってうつや不安を防げないわけではない。あなたの生き方が脳の機能に影響する。
⑨幸せなんか無視しよう!常に幸せでやりたいと思うのは非現実的で辛いだけ。しかも逆効果。
⑩最も大事なのは、精神状態が悪いなら受診すること。医学があなたを助けてくれるし、あなたは1人ではない。
Posted by ブクログ
本書を読み、ストレスや不安の原因や捉え方を知ることが出来て少し楽になりました。
また、翻訳本は難しく感じることがありますが、本書は非常に読みやすいと思えました。
•人体はここ数十年の進歩について来れておらず、狩猟採集時代のままでいること
•不安やストレスは生き延びるために必要な本能であること。むしろ、それらを感じない方が異常である
•孤独はタバコと同じくらい健康に悪い。健康に歳を重ねるには良好な人間関係は欠かせない
•運動はうつや不安に効果があることは様々な実験で認められている
不安やストレスを生き延びるための本能として認識し、悪物と決めつけないことが必要だと思います。また、孤独対策や運動に対しても取り組んでみたいと思わせてくれる内容です。
また、幸せに対する考え方も目から鱗の発想でした。
ストレスや不安に悩んでいる方は是非本書を読んでみましょう。
Posted by ブクログ
出会ってよかったと思える1冊。
私は定期的に不眠を感じることがあり、精神的に緊張状態が続いてリラックスができないことに長年悩んできました。
時折、心療内科を受診し薬を処方してもらうと、一時的には回復するものの、しばらく行かないとまた再発する。ストレスを感じなくするのは無理だし、どうしたものかと縋るように何冊か、関連書籍を購入しました。
その中で、ストレスを感じる状態、不安や恐怖を察している状態こそは、長い脳の歴史の中で至って普通なのであると教えてくれたのがこの本。
そこに気がつけただけでも大きな一歩でした。
常に幸福でいることなど到底不可能だからこそ、心穏やかに過ごせる時間をいかに多く作れるかが大事で、そのための手法に『運動』があること。
睡眠や食事の質などに気をつける事、どつやってストレスを発散するかなどを懸命に考えてきたけれど、これからはいかに運動を日常に取り入れるかを考え過ごしてみたいと思います。
脳の本来のシンプルな存在意義
脳は人を生かせるためだけに、機能している。
2000年前から、ほぼ進化していない〜変わったのは、人を取り巻く生活環境。
脳が生物学的には進化していないため、その変化に順応しないのは、ごく当たり前の事。
幸福感がかつてからほとんど向上していないのも、ごく当たり前の事。
その現実を受け止めて、生きていくことが今の人々には必要な事だという事が、よく分かりました。
Posted by ブクログ
なんとなく想定していた内容でしたが、P.144に記載されている「そのエンドルフィンが物理的に体を触られた時に出るということは、私たちの社交欲求には物理的に接触する必要性があるという強い示唆になる。」というくだりは初見でした。
いま、リモートワークからだんだん出社の方向になってきていますが、そのあたりの事情からも納得感がある話だと思います。
Posted by ブクログ
81冊目『ストレス脳』(アンデシュ・ハンセン 著、久山葉子 訳、2022年7月、新潮社)
歴史上最も豊かで快適に暮らせるはずの現代において、何故これほどまで精神的な不調を訴える人が多いのかを、進化の見地から解き明かしてゆく新書。
平易かつ実践的な内容のため、気楽に読むことが出来る。メンタルに興味があれば、その入り口としては最適。ただ著者の過去作『スマホ脳』と重なる部分が多い点は少々気になった。
〈幸せとは幸せについて考えることをやめ、意義を感じられることに没頭した時に生まれる副産物なのだ〉
Posted by ブクログ
私たち人類は、歴史上かつてないほどに豊かで快適に暮らせるようになった。それなのに、なぜ精神的な不調を抱えている人がこんなにも多いのか。その答えを探るのが本書の目的。
人類の脳はとてつもなく賢いはずだ。なのに、なぜ持ち主の気分を常に良い状態に保つことができないのか。また、なぜいつも感情面で持ち主の足を引っ張ろうとするのか。
これらの謎を解く鍵は、自分たちが「今どこにいるか」ではなく、「過去にどこにいたのか」に目を向けること。
まず言えることは、私たちは死亡率が異常に高かった古代人たちの生き残りの子孫だということ。祖先のうちの誰一人として、子どもをもうける前にライオンに食われたり、崖から落ちたり、飢え死にしなかった。
適者生存とは、行きている環境にフィットするということ。私たちは生き延びて子孫を残すために進化したといえる。決して健康に幸せに長生きするために進化したのではない。
進化には途方もない時間がかかるため、現代人の身体と脳は今でも自分は狩猟採集民だと信じている。
私たちが慣れ親しんでいるライフスタイルは人類の歴史から見れば一瞬のようなもので、まだ適応することができてない。
狩猟採集民の暮らしは一言で言えば地獄だ。平均寿命は30歳で、半数は10代になる前に死亡。出産時や感染症にかかって死亡することが多かった。
運良く成人しても、飢餓、かんばつ、動物の攻撃、感染症、事故、殺人が待っている。
1万年前に、狩猟採集から農耕へと人類の大変革が起きたが、もっと酷い地獄が待っていた。
多くの歴史家たちも「農耕への移行は人類最大の過ちだ」と主張している。
感情というのは、実はただの任務にすぎない。任務というのは、生き延びて子孫を残すこと。飢餓や感染症、不慮の死を驚くべき確率で避けてきた何万世代もの祖先たちからのささやき声が感情である。
不安、恐怖などの負の感情、幸福感が長く続かないことも全て、生き延びるための進化の産物である。
うつになると引きこもりたくなるのは、感染症や事故などあらゆる脅威から自分を守ろうとしている。
トラウマとなった恐ろしい記憶を何度も脳内で再生されるのも、同じことが起きないように脳が自分を守ろうとしている。
不安や、うつを遠ざけるためにできることは、何をさて置いても運動だというのが著者の考え。そして、呼吸を整えること。呼吸を整えるだけで心拍は落ち着く。
さらに大切なのは、孤独を避けること。どのような状態を孤独と感じるかは主観的な問題だが、数多くの研究で浅い友人が多数いるよりも、心安らげる深い友人(家族も含む)が少数いる方が幸福度は高い。
著者が出した幸福に対する結論は、「人類はあらゆる体験を自分の期待と照らし合わせるように進化したからこそ幸せを追い求めるのはやめたほうが良い」というもの。
あらゆるメディアは、「幸せは自分で選び掴み取るもの。あなたが幸せでないなら何かが足りない、何かがおかしい」と畳み掛けてくる。
それによって脳は、事実上達成不可能な目標と自分を照らし合わせてしまう。ずっと常に幸福で満ち足りた状態というのは、人類にとっては不自然な状態であるというのに。
ある国では、広告にお金をかければかけるほど、2年後に国民の満足度は下がっていたことが分かった。
幸せというのは追い求めるほどに指の間をすり抜けていってしまう。逆説的だが、幸せになるためにできることは、幸せを無視すること、考えないこと。
幸せというのは、ゴールなどの独立したものではなく、あくまでも状況の一部でしかない。
人類が地球上で最も優勢な生物になったのは、一番強かったからでも賢かったからでもなく、協力するのが一番得意だったから。
孤独を避け、ほど良い運動をし、呼吸を整え、誰かの役に立つ。そして、幸せになりたいと考えないこと。
これを繰り返すだけで、驚くほど精神状態は良い状態を保つことができる。
Posted by ブクログ
結論としては『運動脳』と一緒で、運動がうつやストレスに効果的であるということ。
狩猟採集民族や発展途上国よりも近代化社会の方が同じ時代に生きていてもストレス度合いが高いことがわかっている。私たちのライフスタイルは、「運動」と「仲間と一緒に過ごすこと」が欠けているのではないかと本著では考察している。コロナ禍にzoom飲みがあったけれど、やはり対面に勝るものはないんだなあと思う。対面とオンラインではグループに属している、誰かと繋がっているという初回欲求の満たしに大きな差が出ている。もちろん対面がより連帯感を生む。そして、都会より田舎の方が精神状態が良いことがわかっている。加えて、非喫煙、環境汚染もあまりない、加工食品を食べていない、労働時間も短い、格差の少ない社会であることも影響しているはずと。ソーシャルメディアは、他人との比較によって「自分には十分な価値がない」と思い込んでしまい、ネガティブに精神状態が悪くなるリスクが高まる。これは男子はスマホでもゲームに時間を、女子はSNSに時間を割きがちなため、女子の方が孤独を感じるリスク大。浅く広くよりも、親しい相手が数人いる方が大事。つねに社交で忙しくしているより、限られた数の一緒にいてリラックスできる人たちの存在が重要。
Posted by ブクログ
最近他の本で読んだことも合わせて、幸せに過ごすということがなんなのかついて改めて考えました。
「幸せとは幸せについて考えることをやめ、意義を感じられることに没頭した時に生まれる副産物なのだ。」
そして、幸せになろうと思っても幸せにならないので、
ーそのうちカーズは考えるのをやめた。