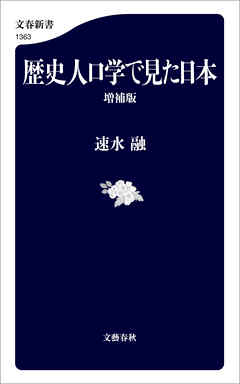あらすじ
「日本の多様性」を見事に明かした名著!
磯田道史氏「速水先生と出会わなかったら、私の学者人生はなかった」
エマニュエル・トッド氏「別格の素晴らしさ。この偉大な学者の“技”のすべてが詰まっている」
著者の速水融氏は、慶応義塾大学、国際日本文化研究センターなどで教育・研究に携わった経済史家で、「日本における歴史人口学のパイオニア」。仏歴史人口学者のエマニュエル・トッド氏も、「日本の歴史人口学の父」と称えている。
本書は、速水氏の長年にわたる仕事のエッセンスをコンパクトにまとめたもので、「歴史人口学」の最良の入門書。と同時に、「歴史人口学で見た新しい日本史」。速水氏が学士院の紀要に寄稿した論文を新たに加えた増補版。
※本書は2001年10月に刊行された文春新書『歴史人口学で見た日本』に、特別附録として「歴史人口学――成立・資料・課題」を加えた増補版です。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
歴史人口学がなぜ将来を見据えることのできる学問なのかを解き明かしてくれる素晴らしい書、あの巨人トッドとの関わりがあり、しかも影響を与えている❗️なぜか?考えると面白い。ミクロとマクロを見る、バランスも見る。また読んでみたい。
Posted by ブクログ
『自爆する若者たち』で、「ユース・バルジ(暴力年代)」がある一定以上に増えると、暴動・テロ等が起こるということを読んだが、そこから、「歴史人口学」についてもっと知りたいと思っていた。歴史人口学の創成期から、日本発のデータと論文を発信してきた、日本の歴史人口学の祖。
面白かったのは、濃尾の研究から出てきた「勤勉革命」。
ヨーロッパをはじめとする近代の産業革命や農業革命は、機械化が進むという資本集約・労働節約の方向に進んできたが、日本の近世では、家畜を使わなくなり、労働時間が増えるという、資本節約・労働集約の方向で、生産性が高まり、農民の生活水準が上がったという。
背景に、品種改良や肥料の改善という技術革新もあるのだろうが、この「勤勉を通して、生活がよくなる」という原体験が、21世紀の今まで続いているような気もする。
思想的には、山本七平の『勤勉の哲学』の石田梅岩にもつながるのだろうが、勤勉さをデータから復元するというのは、なかなか面白い。
Posted by ブクログ
日本における歴史人口学のパイオニアによる研究史。たいしたあてもなくヨーロッパ留学に出かけて歴史人口学に出会ったり、マイクロフィルム撮影機を車に積んで旧家をまわったり、時代のおおらかな空気と、未開拓の分野を切り開く興奮が伝わってきて楽しい読み物。
江戸時代の「勤勉革命」については、現代日本にまで及ぶ文化的な影響もあるのだろうか。かんがえてしまう。
Posted by ブクログ
<目次>
まえがき
第1章 歴史人口学との出会い
第2章 「宗門改帳」という宝庫
第3章 遠眼鏡で見た近世~マクロ史料からのアプローチ
第4章 虫眼鏡で見た近世~ミクロ史料からのアプローチ
第5章 明治以降の「人口」を読む
第6章 歴史人口学の「今」と「これから」
特別付録 歴史人口学~成立・資料・課題
<内容>
日本の歴史人口学の嚆矢で、第一人者だった速水氏の、歴史人口学の解説を、自分の人生に重ね合わせて説明したもの。1960年代からの地道な努力(根気なくして出来ない)を教えてくれる。その努力も、目的を逸しては何の価値もなく、各時代の人口から、人びとの生活や政治も見えてくる。コロナ禍において、こうした研究が役に立つことがよくわかる。