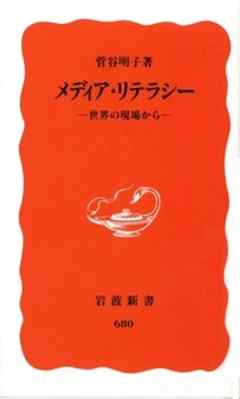あらすじ
人生の大半をメディアとともに過ごすとされる現代生活。報道の客観性や公正さ、暴力表現の影響などが議論になっている今、メディアのあり方を具体的に解読していくことの意味と可能性とは何か。各国で広がっている実践を丹念に取材し、教室での工夫や反応、メディアを監視する市民団体の活動などを報告、情報社会の今後を考える。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
2000年に出版されたのでやや古いが、内容は極めて新鮮な、文字通りメディア教育の観点からみた「メディアリテラシー」についての本。現場レポートというだけあって、イギリス、カナダ、アメリカのその当時の様子がつぶさにみてとれる。「教育論」の観点からは、ぜひとりあげるべき。
・メディアのコンテンツをとりあげ、分析、評価すること
・実際に制作する立場として、どう表現されたコンテンツが取捨選択されるかを見極めること
などが、初期的なポイントのようだ。
大前提としては、
・一つの真実などないこと
・多元的「現実」を製作側が一定の主観にもとづいて伝えていること
を踏まえてどうメディアに対処するかという視点が大切なのは、どこも変わらないようだ。
イギリス:根づくメディア教育
・メディエデュケーション
・国語の延長線上。中等教育で独立の科目
・大学研究者と英国映画協会主導
カナダ:ユニークな実践
・メディアリテラシー
・国語のカリキュラムにとりいれ
・トロント大学のマクルーハン「メディアはメッセージ」
・AML
アメリカ:草の根メディア活動
・こどもジャーナリスト
・RMMW
・PRウオッチ
・パーセプション・マネジメント
・CM分析番組
デジタル時代のマルチメディア・リテラシー
・ピクチャー・パワー
Posted by ブクログ
著者自らアメリカ、イギリス、カナダなど、いわゆるメディアリテラシー先進国に足を運び、各国のメディアに対する関心度、メディア教育への取り組みなどをまとめたものである。
1970年代、アメリカではこの頃からメディアリテラシーの重要性が語られ始めた。教育省は、子どもたちはメディアを積極的に読み解く力を養う必要があると感じて、メディア教育に重点を置いた教育プログラムを策定。これを教育機関を中心に配布。その結果、50州中46州がメディア教育を取り入れる結果となった。
しかし、世界で始めてメディア教育を体系的に取り入れたのは、カナダのある一つの州だった。1987年、オンタリオ州は、現在の日本で言う「国語」(母国語の理解、母国語を通した母国の文化理解を目的としたもの)の授業内に、メディア教育を取り入れ始めた。
それから1年後、イギリスは全国的にメディア教育に関するカリキュラムを制定。そこには、「母国の文化を正確に理解を理解するためにはメディアの学習が不可欠」といった一般的な声があった。非公式ではあるが、すでに70年以上にわたって、その礎は築かれていたのだ。
ここでおもしろいのが、各国におけるメディア教育発展の背景の違いである。
アメリカでは「メディアは悪影響、有害なもの」という考えが一般的で、それから子どもを守るためにメディア教育が盛んになっていった。
カナダはアメリカの隣国で、かつては敵対心が強く残っていたこともあり、アメリカメディアに対する挑戦の意味があった。そして、カナダ人としてのアイデンティティを強固にしようとする意図が隠れていた。
イギリスでのねらいは、当初は「大衆操作への危惧」が出発点であった。しかし時が経つにつれ、「目の肥えたユーザーを育てる」といったものへと変化していった。メディアへの対策、というよりも、メディアをいかに上手に利用するか、という意識の変化である。「メディアリテラシー」という言葉の発祥地らしい積極的な姿勢がうかがえる。
膨大な量の情報が行き交う現代社会。良し悪しはあるものの、メディアとの接触は私たちの生活から切っても切り離せない。これからの日本は、どのようにメディアというものを捉えていくべきか。そのためにも読んでおいて損はない一冊ではないだろうか。