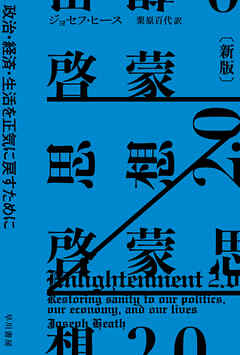あらすじ
世界はもはや右翼/左翼ではなく、狂気/正気に分断されている。保守主義や認知科学を動員した、新しい啓蒙思想。解説:宇野重規
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本書の中心的なテーマは、政治における右派(保守派)と左派(改革派)の根本的な非対称性
進歩的な社会変革は、複雑で達成しがたく、妥協、信頼、集団行動が求められ、膨大な量の「頭」を使わなければならない。それに対し、右派の運動は、直感的で感情に訴える方法で形成することができる。例えば、税金に関する政策に対して「皆さんが苦労して稼いだお金を政府は奪うんです!」といった直感的に誰もがイメージできる言説で大衆の賛同を得るような運動をイメージすればわかりやすいかもしれない。
本書は人間の脳がいかに合理的な思考を行うのが難しく時間がかかるか、従来の社会改革が人間の理性を過大評価してきたかを述べ、私たちの脳が得意なことと苦手なことを理解した上で、それでも人間は理性によって正気を取り戻すべきであるとし、理性を個人に求めるのではなく、人間の合理的な判断を促すような社会設計、制度設計が必要であると説く。
実際に政治家の発言やテレビのワイドショーなどは、インパクトのある扇動的な表現を繰り返し、多くの人の感情を揺さぶるように設計されているなと思った。本当は熟考型の議論こそが必要であるはずが、多くの人の心を動かし、政治的な票につなげるためには上記のようなやり方が最適解として実行され、SNSの浸透でその流れにさらに歯止めが効かなくなっているというのが昨今どこの先進国でも見られる現象であると感じた。
個人的には「学校とは、カリキュラムだけではなく、“社会環境”として機能している」という内容の箇所が印象に残った。著者は、学校は知識を得るための場所であると同時に、社会的な環境を提供する場所であり、 教室管理、読書課題、しめきり、テスト、成績評価は、集中力や計画性、目標達成に向けたセルフコントロールの不足を補うための外部足場であるとし、教室というリアルな場での対面の授業を評価している。オンラインによる授業スタイルが、コロナ禍を経て再び盛り上がりを見せているが、「授業を録画して配信することで、学校教育を届けることができる」というプロジェクトは、過去に完全に失敗しているとし、また独学者は、確証バイアスと陰謀論に陥りやすいということも述べている。これらは学校教育が子どもの理性的な思考の形成過程において必要な環境を提供する場であることの説明として説得力があると感じた。
Posted by ブクログ
人間の脳は構造的に弱点があり、そのため常に非合理的な考え方が優勢になる。この仕組みを克服するのではなく、よく理解して上手く使おうという提案書。そうすれば、世にはびこる非合理主義、反知性主義(例えばトランプ主義者。本人たちは思想だと思っている)に対抗できるぞ、と。それがアップデートした啓蒙「啓蒙思想2.0」。
端的に2.0とは、「政治は外部クルージ(人間の脳の弱点を有り合わせの応急措置で解決する)を利用していこう」「他者からの啓蒙(コントロール)をどんどん使っていこう」ということ。「個々の人間が理性を高めて社会を向上させる」というポストモダンで個人主義的な思想は武器にならなかった。実際効力が無い。個人では弱くて戦っていけない。いっぽうで、集団で協力して非合理を無効にするのはかなり有効。問題に直面したら、非当事者からの冷静な理性的助言に頼り正気を取り戻す。そして別の機会にはその立場が逆転する状況も起こるので、その時はこちらが理性的判断を代行してあげる。
偏見・男女差別・人種差別は人間のもって生まれた性質なのか。残念ながら、人間は、内には連帯感を求め、外には敵がい心を抱くという自集団中心バイアスは、変えられない性質は持っている。しかし幸運にもこれは固定されておらず、グループのくくりが固まれば性別、人種にかかわらずどのような集団にもなれる。「○○社員」「シカゴ・カブスファン」など。
そして人種に注意ができるだけ行かないようにすれば、差別感情は低下する。典型的なのはアメリカのぷろすぽーつチーム488
肥満問題では外部クルージ(クルージは、場当たり的な、いいかげんな解決策)の有効性が実証された。アメリカでは肥満問題解決のため外食のカロリー表示が義務付けられたが効果はなかった。しかしニューヨークのブルームバーグ市長は470ml以上のソーダ販売禁止の法律を作った。悪法とか、無意味な法制とかの声が高かったが、これが有効だった463
学校の授業以外、合理的理論を身につける場は、おどろくほど日常の中に存在しない。ディナーパーティーでたとえ10分間でも相手の話に真剣に耳を傾ける人はいない。ましてや説明に1時間を要する話など、聞く人はいない。但し例外がある。それは本だ458
インフレというのは、人間の脳の弱い部分をなだめて経済問題を解決できるように作られた政策。「給料が下がる(名目賃金が下がる)」と言われると弱い部分はひどく動揺する。しかし給料は上がるがそれを上回って物価が上がること(実質賃金が下がる)には反応が鈍い。このような脳の仕組みを取り入れた経済問題の解決法がインフレ。インフレ政策は典型的な政治における「外部クルージ」である450
リベラル本の結論によくある「よく考えて、批判的になって認知バイアスを克服するのが大切。さぁ読者の皆さんも実行しよう、」というのは、理論は正しいがほぼ無意味。非合理主義をこの戦略で覆せる楽観論に根拠は無い439
環境保護論者は地球環境問題を否定する論者(基本的に右派)を「科学的コンセンサスを無視する愚か者」と罵るが、いっぽうで自らは「ワクチンの否定」「農薬の否定」「ホメオパシーの推奨」を同じ口で言う。その時都合の良いことに、右派同様にしばしば陰謀論を持ち出す338
マルクーゼの思想が支持されると、新たな申し子が次々に生まれる。その典型的な一人が「フェミニズム」だ。当初は男女の対等な「理性の追及」を目指し、それが達成されなかった歴史は、「女性の教育機会の無さ」つまり理性のゲームに参加させてもらえなかったのが原因とされ、その克服を目指した(ウーマンリヴ)。しかし理性の正統性が失われる「解放と自由」の時代になると、フェミニズムは理性と直感の対比論争の中で、直感を支持したくなる誘惑に駆られた。理性と直感の対比は、そのまま男の流儀と女の流儀の対比と類比され、戦争を生む男の流儀(正統性の疑わしい「理性」の象徴)よりも、それに対抗する女の流儀(すなわち「理性に対抗」するのだから「直感」に類比される)のほうが正統性がある、と主張されることになる(ラディカルフェミニズム)331
理性の申し子「科学技術」はユートピアを生み出すはずであった。しかし2つの世界大戦は科学技術が善ではなく、多くの人々を殺戮するものだと認識させた。これに対し、ドイツからアメリカに戦時亡命したヘルベルト・マルクーゼは、解放と自由を重視した思想を生み出す。科学・管理と人間の対立を、解放された意識で超克することで、技術は「芸術」に進化する、と提唱した。この思想は60年代のニューエイジに支持された。これが現代まで生き残っている「リベラル側の反合理主義」に繋がる。そして、時が経つとこの思想は、新たな科学技術も、自然と折り合う方法も、理想の人間社会も生み出さないことが解った。327
成功した迷信や神話は「一点だけ期待から逸脱している」法則がある。全てが期待どおりだったり、期待が複数外れていたりするものは失敗する。例えば幽霊は「物質ではない」ので壁や窓をすり抜ける(『リング』ではモニターまでも)。しかし「床をすり抜ける」だけはしない(重力の法則にだけは従う)。本来、物質では無い法則期待があるなら床をもすり抜けるが、そうすると宇宙空間を高速で移動する地球から取り残され、出現後一瞬で「幽霊に遭遇した人」から置き去りにされる286
文化(非自然なもの)の伝播はウイルスと同じ法則。狡猾で、拡がりやすく、駆除しづらいもの、つまり人間の弱点につけ込むものが生存競争を勝ち抜く。SARSが治まったのは、潜伏期感の短さゆえに流行を失ったから。また、近年エイズの死亡率が低下しているのは、致死性の高いウイルス個体より低い個体が優位に進化したからだと言われる269
社会は人の問題解決ヒューリスティック(経験則に則した大まかな正解)をわざと混乱させ、誤解を与えるためにデザインされたものに溢れている。最も典型的なのは洗濯洗剤のキャップだ。必要以上に大きく、メモリは内側に小さく書かれ、何の説明もない。色はブルーがかった半透明でメモリは見にくい。「太いコップに入れると少なく見える」錯覚を利用した極太の径。不注意な利用者はキャップいっぱいの洗剤を毎回使う。これらは全て「洗剤を必要以上に使用させる」ためのデザイン。平均的に使用者は必要量の6倍の洗剤を使う。このことで衣服の劣化を早めてもいる258
マーガリンが市場に出回った時、酪農協会は「マーガリンを青く着色する法律」を実現しようと運動した(青色は人間の食欲をそぐため)。これは実らなかったか、マーガリンを不自然なオレンジ色に着色することはかなった255
2011年猛暑のテキサスでは州知事のリック・ペリーは対策として「三日間の雨乞い」を発令した。その間石油の採掘を続けた。そしてその後大統領選挙に出馬した247
多の霊長類には無く、人間だけに備わった本能として「利他的な懲罰」がある。これは直感に関連するものであり、人類学でも近年認められつつある。自分に不利益が被ることがあっても他者を攻撃する行為。227
キース・スタノヴィッチは、「911陰謀論」「高度な占いを勧める隣人」「オーガニックに取りつかれた人」に「合理性障害」という疾患を名付けた212
「直感(無意識)」を賞揚する研究者たちがいる。しかし直感の最大の欠点は、それがどんなメカニズムで働くかを何も説明出来ないことである。そもそも直感とは、「どうして機能してるか解らない」という事実自体が本質となってしまっているものだ。177
理想の社会は、国や地域、集団によってまったく異なる形式であり、各々の歴史的修正の累積によって作られてきた。しかし西洋生まれの思想は、「民主主義の形は決まっている」という立場で、それを他国に強要する。このことで様々な逆効果が生まれている。しかも西洋人の間でも「民主主義の形はこうだ」と合意できていないのに。まったく図々しい141
哲学の歴史では「本能」「欲望」「直感」などは、「理性(道徳)」に劣るものとされてきた。近年になると「道徳(理性)」という存在こそ幻想であり、こじつけのインチキだということになった(ここまでが啓蒙思想1.0)。それが最新の脳科学では「理性」が思想や哲学ではなく、言語を司る機能の一部であることがわかってきた103
啓蒙思想をアップデートするカギは、どうやら人間の理性である。理性はきわめて自然に「反した」ものだ。これは私たちを自然状態(動物)から解放する可能性があるいっぽうで、そのプロセスはかなり難しい。なぜなら理性を生み出す脳機能は、偶然に備わったきわめて未完成で不合理なものだと科学的に解ってきたから。93
フロイトは無意識を「内なる子供」と表現したが、現代の心理学者は「内なる火星人」と表現するほうが適切だと考える。人は人間の思考回路より、むしろコンピューターの思考回路のほうが理解出来る。73
Posted by ブクログ
科学的根拠のない言い放しの演説や、都市伝説のような噂話が世の中に溢れている。匿名の一般SNSユーザーの発言ではなく、一国のリーダーが、平気でこういったフェイクをばら撒き、指摘されても開き直り、訂正もせず、陰謀だと逆ギレる。著者はこういった世界的な風潮の分析し、人間の判断や知性の弱点を指摘し、熟慮、理性を取り戻すこと、スローポリティクスを提唱する。確かに、情報の奔流と、アプリの普及などで一瞬にして意思決定させられる状況が、こういった時代を引き起こしているのかもしれない。熟慮、大事だなあ。
Posted by ブクログ
心理学の見地から人間の合理的思考の脆さを一通り指摘し、その上で現在までの政治や経済活動における反合理的な風潮を見直す。個人的にはナッジ・パターナリズム(リバタリアン・パターナリズム)が権利の制約が最小限である、という点において魅力的に思った
Posted by ブクログ
二度の大戦以降、理性を信じきれなくなってしまった現代人に向けて教育とかルールとか、縛られるのも案外悪くないかもよ?理性信用してみようよって投げかける本。
文句はごもっともなんだけど、改善策がイマイチ出てこないなぁと。それは自分も同じなんだけど。