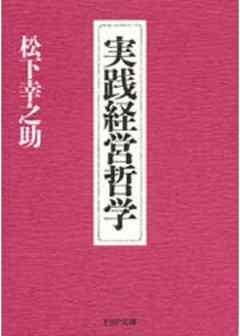あらすじ
松下幸之助「心得帖シリーズ」の五作目。本書では松下がささやかな形で始めた事業を、一代にして世界的企業に育て上げた要因を自ら分析して、二十項目にまとめたものである。経営に当たる者が、人間とはどういう特質をもった存在であるかを知らずに、正しい経営を行うことができるだろうか。使命感無きところには、為すべきを為す勇気も生まれてはこないだろう。そこに経営の失敗に通じる道を歩んでしまう危険性が生じてくるというわけだ。経営者はいうまでもなく、課の経営、部の経営に当たる人達にも是非一読を薦めたい一冊。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
心に響いた。
特に、後半の方が、ガツンときた。
前半は、経営者むけの話だが、後半は、より広範囲の人に届く話だった。
成功は運のせい、失敗は自分のせい
衆知を集める
素直な心を持つ
まずは、これらを意識したいと思う。
Posted by ブクログ
時代を超えて経営に必要なことを考えさせてくれる名著。半世紀以上も前に書かれたとは思えない程にリアリティがあり、筆者の思いが伝わる。VUCAの時代だから「パーパス経営」という以前に経営者たるべき者の「志」を問うてくれる。
Posted by ブクログ
古い本ではあるが今の世界にも通づる経営の原理原則。間違いなく今の日本を創ってきた一人である偉大な経営者でありながら謙虚な心で仕事にあたる。
自分の日々の仕事や振る舞いに見習いたいことばかり。
Posted by ブクログ
実践経営哲学 (PHP文庫)
著:松下 幸之助
本書は、著者の60年の事業体験を通じて培い、実践してきた経営についての基本の考え方、いわゆる経営理念、経営哲学をまとめたもの。
以下の20項目から成る。
①まず経営理念を確立すること
②ことごとく生成発展と考えること
③人間観をもつこと
④使命を正しく認識すること
⑤自然の理法に従うこと
⑥利益は報酬であること
⑦共存共栄に徹すること
⑧世間は正しいと考えること
⑨必ず成功すると考えること
⑩自主経営を心がけること
⑪ダム経営を実行すること
⑫適正経営を行うこと
⑬専業に徹すること
⑭人をつくること
⑮衆知を集めること
⑯対立しつつ調和すること
⑰経営は創造であること
⑱時代の変化に適応すること
⑲政治に関心をもつこと
⑳素直な心になること
昭和53年に記された本書。自分が生まれるより前に記され、その教えは古びれることなく、その時代や環境に合わせた新しい気づきや本質を提言してくれるような一冊。
経営の神様が惜しげもなく、実体験の証として考え抜かれた教えに触れることができることに幸せを感じる。上からではなく、共に考えるスタンス。素直な心を持ち学びながら成長をしてきた中で紡ぎだされる言葉。時代の変化に適応することを念頭に書かれたそれはしっかりと今の時代に適合している。そして、激動の変化の今だからこそ、心に染み入る考えが深く突き刺さる。
多くの書を残している著者。数々の作品に触れることでその一貫性から理解が深まる。一冊を深く読むこととさらに他作品に触れ続け、教えの片鱗を少しでも吸収し自己の人生に活かし続けたい。
Posted by ブクログ
60年間のみずからの体験から
経営哲学について書かれている。
この間 沢山の経営に関する本を読んだが、あらためて
松下幸之助の すごさに 驚いた。
そして、よんだ後にのこった 心に残ったものが
実に爽やかで、素直な気持ちに なれた。
疲れて、よごれたこころに 清涼飲料水をのんだような。
人の可能性をしんじる 姿勢が すごいのだね。
製品 をつくるまえに 人をつくる。
そして、うまくいかない原因は 我にあり。
そこから、すべてを見る ということです。
利益に対する考え方も 筋が通り
会社が 社会の公器 として 存続することを
あたりまえのように、さりげなく 書いている。
1978年に書かれている。
今から、40年ほど前とおもえぬ 新しさ。
経営哲学とは そういうものですね。
Posted by ブクログ
筆者が日々経営を実践する中で得た洞察をまとめた本.小手先の手法ではなく,シンプルに経営のあり方を説いている.
平易な言葉で書かれているため,ビジネスマンとしての経験を問わずに読める.ページ数も少ないため,2時間程度あれば十分読めるだろう.しかし書かれていることは非常に奥深く考えさせられる内容で,経験を積んでいくと感じ方も変化し新たな気づきを得られるのではないかと思う.節目節目に再読したい本.
Posted by ブクログ
全員経営、素直さ、カイゼンしていくこと。
ジョブスのシンプルさやアジャイルな精神に通じる。
-引用-
★
事業経営においては、技術力、販売力、資金力、人材といった、大切なものはいろいろあるが、一番根本になるのは、正しい経営理念である。それが根底にあってこそ、人も技術も資金もはじめて真に活かされてくるし、また一面それらはそうした正しい経営理念のあるところから生まれてきやすいとも言える。
★
経営に魂が入った瞬間に事業は急速に発展した。
★
事業は人なり
どんなに完備した組織をつくり、新しい手法を導入してみても、それを生かす人を得なければ、成果もあがらず、したがって企業の使命も果たしていく事ができない。企業が社会に貢献しつつ、みずからも隆々と発展していけるかどうかは、一にかかって人にあるとも言える。
この企業は何のためにあるのか、またどのように経営していくのか、という基本の考え方、正しい経営理念、使命感というものを持つ必要がある。これにもとづいた力強い指導もでき、メンバーもそれに従って是非の判断ができるから、人が育ちやすい。だから経営者として人を得たいと思うならば、まずみずからがしっかりした使命感、経営理念をもつことが先決である。
★
経営理念というものは、単に紙にかかれた文章であっては何にもならないのであって、それが一人ひとりの知肉となって、はじめて生かされてくるのである。だからあらゆる機会に繰り返し繰り返し訴えなければならない。
★
大切なのは形ではなく、心構えである。衆知を集めて経営をしていくことの大切さを知って、日頃からつとめて皆の声を聴き、また従業員が自由にものを言いやすい空気をつくっておくということである。そういうことが日常的にできていれば、事にあたって経営者が一人で判断しても、その判断の中にはすでに皆の衆知が生きていると言えよう。
Posted by ブクログ
『ハーバード流交渉術』の原理原則に基づくという話を読んで、7年ぶりに再読。入社前の課題図書でした。
人が見たら知れているレベルかもしれませんが、最近は判断に迷うことが多く、何が正しいのかということは非常に難しい。迷ったときはコレに立ち返る、やってみました。
まあ、これをどう生かすか、まだまだ自分には難しいと再認識したけど、とりあえず、共存共栄に、日に新た、改めて読むと胸が痛むことが多いわ。
また、素直な心の最終章には図らずも心を洗われました。
素直な心=とらわれない心、いかに私利私欲を捨てるか、平凡な人間も1万日=約30年やったら持てるらしい。
仮に今までできていてもまだ7年、そう、自分は私利私欲の塊ですわ。先は長いぜ。。。
Posted by ブクログ
松下幸之助の経営哲学。
カタカナがひとつもない希有な本。
経営理念をおもいいたったきっかけ。
商売の通念、社会の常識内で仕事をすることも立派だが、それ以上のもっと高い「生産者の使命」があるのではと考えた。(15)
使命感に燃えて仕事に取り組めるようになると経営に魂がはいる。16
経営理念は一つの人生観、社会観、世界観に根ざしてなければいけない。経営者は自らの人生観や社会観を常に涵養していくことが大切(21)
彼の根底にあるのは「ことごとく生成発展の理法」(24)
使命感を認識する。事業活動を通じて人々の共同生活の向上に貢献する。この使命を遂行するには利益は不可欠。事業経営は人々の共同生活に貢献すると考えると本質的には私事ではなく公事である。(41)
判断の際は私ではなく公の立場で人々の共同生活にどういう影響を及ぼすか?を考えること(42)
天地自然の理にかなった経営は、当然なすべきことをなす、につきる。経営はきわめて簡単(48)
利益とは社会に貢献した報酬である(52) 利益なき経営は社会に対する貢献が少なく本来の使命を果たせてない。また、企業の利益の半分は税金として社会に使われる。利益がなければこの観点からも社会へ貢献できていない
世間は基本的には神のごとく正しいと考える(74)
物事がうまくいったときは「これは運がよかった」と考えうまくいかなかったときは原因は自分にあると考える。(81)
業績の良否の原因を不況という外に求めるか?自らの経営のやりかたという内に求めるか?(86)
失敗の原因は我にあり87
経営のあらゆる面において自力を中心にやる自主経営を行うこと。そういう考えが基本にあって他力を活用することを考える。自力を中心にしていれば外部の信用も生まれ、求めずして他力が集まってくる。
ダム経営を実践する。あらゆる場所に10%程度の余力を持つ。無駄はだめ。見通しを的確にした上での10%の余力。
50人に通用する経営力と100人に通用する経営力。経営力の限界をこえたら組織を二つにわったほうがいい。(103)
一業に徹する。一品をもって世界に雄飛。(110)
人を作る。どうすれば?まずはこの企業は何のために存在するのか?という経営理念。それがないと部下指導に一貫性が生まれず時々の情勢や感情に押し流される指導になる。だから人が育たない。人を得たいと思うならば、自らがしっかりとした経営理念、使命感をもつこと。それを常に浸透させる努力をすること。血肉になるまでやること。(117)
企業は社会に貢献していく公器であり仕事も公事。公の立場からみて見過ごせない、許せないことは言うべきをいいしかるべきをしかる。使命感に基づく指導。何も言わない、しかられないというのは部下にとって一面、結構だし経営者にとっても楽だがそうした安易な姿勢では決して人は育たない(119)
経営とは芸術活動。無から有を創造する。単に物を作ってるだけかもしれないが、そのプロセスには経営者の精神が反映している。見る人を感嘆せしめる内容の経営もあれば、駄作といってもいような経営もある。ここにも芸術との類似性がある。経営の駄作は芸術の駄作よりも社会的な罪が大きい。つぶれたりするとほんとに迷惑。(145)
芸術家が一人前になるための修行はとても厳しい。骨身をけずって全身全霊で打ち込む。そうしてすばらしい芸術がうまれる。経営も同じ。
経営者が経営を行う上で大切な心構えは素直な心になること。とらわれない心。何かにとらわれてしまうと人の言葉が耳にはいらない。衆知が集まらない。しかし好き嫌いという感情は人間の生来のもの。だからとらわれない素直な心をもつことは言うわやすく行うは難し(164)
禅の修行は自分の心のとらわれをなくそうとするもの素直な心につうずるものがある。
1万回、碁をうてば初段になれる。毎日、素直な心になりたいと強く願い続ける。自分の言動を反省し少しでも素直な心を涵養しようとつとめる。そうして1万日(30年)すごせば、素直なこころの初段にはなれそうだ。167
素直な心こそ経営を成功させるための基本的な心のあり方なのだ。
Posted by ブクログ
タイトルほど、大それたものではなく、すら〜っと読めました。
哲学っちゃぁ哲学なんですが、それほど硬くないです。
マーケティング論とかの根本にあるんがこの考え方なんだなぁ〜と痛感。
・お客の欲しい物を作って売る
当たり前のことですが、難しいんですよね。
この本を良さは、僕がもっと「経営」っていうものに携わってからじゃないと分からないと思います。
他の経営理論とかの本は読んで分かった気になれますが、この本はそうはいきません。
(その反面、分かった気になるのはスゴク簡単だと思いますが…)
かなり「漠然」としたものなんで。
将来、迷った時に読み返したくなる本だと思います。
何より、この当たり前のことを実践して、これだけの会社にするってことは本当に素晴らしいですね。
この本から学んだことは、
当たり前の事を当たり前の様にしなさい!
う〜ん、難しい・・・
Posted by ブクログ
松下幸之助の実戦に即した経営哲学が本人の言葉で書かれている。
読むと当たり前のことが書いているのだが、ふと気づくと意識から抜け落ちてしまうことばかり。定期的に読み返して、自分を正す矯正器具として活用するのが良い。
誰からも学べる前提で素直にことにあたるべし。
Posted by ブクログ
元三井物産役員 佐伯基憲さん 課題図書
松下幸之助が素直で実直な人間であることが大変よくわかる本だった。「会社は何のために存在しているのか。この経営をどういう目的で、またどのようなやり方で行なっていくのか」当たり前のことであるが、何のためにやるのか意味や目的を明白にすることはその後、経営がうまくいっている時、うまくいっていない時、どちらも驕らず焦らずするべきことをすることができるという。これは人生にも置き換えられると述べている。
人生経営にもこの考え方はとても大切なことだと感じた。
また、印象的な言葉で、「芸術というものを一つの創造活動であると考えるならば、経営はまさしく創造活動そのものである」というように松下幸之助はビジネスとアートを掛け合わせたような考えをこの時代からすでに言ってることに驚いた。
経営理念は一定不変のものではない。
「〝日に新た〟でなくてはならない。この社会はあらゆる面で絶えず変化し、移り変わっていく。」
ミッションとビジョンは想いと社会の状況によって作り変えていくというような、ビジョンデザインのようなことについても触れている。
授業内で出てきた星野リゾートの経営についてもこのように初期のビジョンから今の時代に即したビジョンに変えていっていることと通ずるものがある。
この本は今でも時代感じさせない。
Posted by ブクログ
古い本ですが、現在でも十分通用すると思われる彼の哲学が学べます。さすがに偉人の言葉は、不朽。一例を挙げると、ダム経営。これはTOCで注目するボトルネックとほぼ同じで、やはりゴールドラットは、TOCを日本からぱくってます。
Posted by ブクログ
誰にでもわかる平易な言葉で書かれていて、非常に読みやすい本です。
書いてあることも、読めば納得のいいことばかり。
その分、「書かれていることを私たちの今のこの仕事に置き換えるとどうなる?」という段になると、解釈が分かれやすいだろうなと思います。
だからこそ、読んで終わりにしないで、
読んだ人同士でどう仕事に生かすのか議論するために使うことに向いている本だと思います。
例えば自主経営についての以下の部分。
「経営のやり方というものは無限にあるが、その一つの心構えとして自力経営、自主経営ということがきわめて大切である。つまり、資金であるとか、技術の開発その他経営の各面にわたって、自力を中心としてやっていくということである。」
この「自主経営」の単位を、「自分が所属する会社」ととらえるのか、「関連するグループ会社全体」ととらえるのかによって、何を是とするのかが大きく変わってきます。
また、例えば「理念」と「方策」の区別について。
松下さん自身も折に触れて書いているとおり、時代や環境が変わって変わらない「理念」と、時代や環境によって変化させていくべき「方策」は、しっかり区別する必要があります。
一方、この本の中にも「理念」の部分と「方策」を例示した部分が混在していて、「これは理念です」「これは方策です」ということが本の中で明示的に書かれているわけではない。
だから、ある人が「これは理念だ」と思った部分を他の人が「方策だ」と思えば、そこでもまた具体的な行動が変わってきます。
そんなわけで、企業研修とかで使うにはうってつけの本何だろうなーと思います。
私の会社でも、みんなでこれ読んで仕事の話とかしてみたい^^
Posted by ブクログ
語りかけられているようで大変読みやすかった。
世間は正しいと考えること。
衆知を集めること。
素直な心になること。
全ての関係先との共存共栄を考えること。
Posted by ブクログ
松下幸之助氏の著書。
自らの経験から学んだ経営哲学(経営理念)をわかりやすく書いてあります。
決して高みから見ているのではなく、謙虚に仕事に向き合っている姿勢には感銘を受けます。
20年ぶりに再読しましたが、
今の時代に松下幸之助氏が生きていたら、
どんな経営をしたのでしょうか?
非常に興味があります。
読んで傍らに置いておきたい一冊です。
Posted by ブクログ
松下幸之助の60年の経営体験から得た哲学をまとめたもの。まさに松下の真髄ここにありという内容。圧巻は、いきなり経営理念が大事というシンプルな答えに辿り着いていることだ。それに基づいて、方策や方針は時代や日毎に変わるべきと説く。そして、国家も同じで国家経営理念がすべてだと。企業も社会の公器であるとし、社会に貢献することが使命である。生成発展する企業のあり方は、不況を言い訳にせずに、失敗の原因は我にありという謙虚な心の持ちようが大事。自力経営でまずは自力を中心にやってゆき、その上で必要な他力を活用すべき。ダム経営で、余裕やゆとりを持っておく。これらは、経営の話をしていながら、結局ヒトの話をしているように感じる。事業は人なり。職業人としても社会人としても立派な人間を育てなければならない。それを素直な気持ちでやってゆきたい。
Posted by ブクログ
一時間くらいで簡単に読めるのでオススメ。
当たり前といえば当たり前だけし、誰でも出来ることな気がしますが、素直に実践して、継続して行くのは難しいんだろうなと思う。
正しいと思うことをまっすぐにやろう!って思った。
Posted by ブクログ
実践経営哲学という題名から受ける印象ほど難しくはない内容。
経営哲学を斬新な切り口で書いているのではなくてごく当たり前のこと実践することを分かり易く解説している。
パナソニックの会長である中村邦夫がアメリカ松下電器の時代からこの本を何度も読み返したそうだが、それほど当たり前のことを実践することは難しいということなのだろう。
Posted by ブクログ
「衆知を集める」のは部下に仕事を任せることでも成り立つ。
「雨が降れば傘をさす」ことが当たり前にできない。
「ダム経営」のゆとりの適正値は経験でしか学べないのか?
「成功は運が良かった、失敗は自責」
「共存共栄に徹する」ことで、取引先とのwin-winの関係を築く。競争はお互いの発展のために良いが、過当競争は業界自体を疲弊させてしまう。
企業の目的は利益の追求ではなく、事業を通じて共同生活の向上を図ること。その使命を遂行するために利益は大切である。
適正な利益は企業事態だけでなく、社会全体、国民全体の福祉向上のために必要不可欠である
Posted by ブクログ
言わずとも知れた経営の神様、松下幸之助の経営哲学をまとめた一冊。当たり前のことが多い一方で、幸之助の指す抽象的な言葉を自分なりに咀嚼して実践的に当てはめていくことの大切さを感じた。
①使命を正しく認識すること(p36)
企業の目的は利益の追求にあるように思われるが、その根本は事業を通じて共同生活の向上をはかることにある。利益はあくまでそのための“手段”であり、目的を見失ってはならない。
②利益は報酬であること(p51)
利益は会社で使われるだけでなく、税金となって国民の福祉のために用いられる。このように、利益を稼ぐことは社会を良くすることにつながっている。
だが、赤字を出すことは社会に還元する役割を果たさなくなることになるため、許されることではない。(幸之助は社会に還元する役割を“義務”と言っている。)今の松下電器ことパナソニックの現状はここから言えば義務を果たしていない。
③人をつくること(p114)
パナソニックが製品の前に人をつくっているというのは良く知られた話。では、その育てる人とはどのような人なのか。幸之助は、人を育てることを「経営の分かる人、どんな小さな仕事でも経営的感覚をもってできる人」を育てることとしている。事業部制を考えついたのもこのためだ。組織が大きくなったとしても、全体を見て仕事ができる。そういう経営感覚を一人ひとりが身につけることが、今の会社には足りていないのかもしれない。
Posted by ブクログ
【内容】
「六十年の事業体験を通じて培い、実践してきた経営についての基本の考え方、いわゆる経営理念、経営哲学をまとめた」もの
「すべての顧客に安価な物資を大量に」という松下電器創業時の著者の哲学は、昨今の「顧客をターゲティングして収益率をアップし、事業内容を絞って経営効率を上げる」といった経営手法と相反する。
【ポイント】
23/自然の摂理とか真理におもいをめぐらし、
なにが正しいかという人生観、社会観、世界観にたった経営理念をもって、
それを基礎において、経営を行っていくことが大事。
30/経営というものは、人間が相寄って、人間の幸せのために行う活動。人間観。
41/企業の存在意義。事業を通じて共同生活の向上をはかるのが使命。
これを遂行していく上で利益が大切。 利益の追求が目的ではない。
53/120円の価値のある製品をいろいろ努力して、90円の原価で作り、100円で供給する。
その努力・奉仕に対する報酬が10円の利益としてはいる。
57/適正な利益をあげ、それを国家、社会に還元することが企業にとっての社会てきな義務
であり、赤字であれば、企業の社会的義務を果たしていないことを認識せよ。
61/売上げ利益率10%が適正利益。
83/成功は運のせいだが、失敗は自分のせいだ。
87/日頃から、失敗の原因はわれにありと考え、自らの経営を厳しく吟味しつつ、為すべきを為していく。
93/技術に関する特許やノウハウは、開発したところが独占すべきでなく、すべて適正な価格で公開すべき。
96/「ダム経営」設備のダム、資金のダム、人員のダム、技術のダム、製品開発のダム、
余裕、ゆとりをもった経営 10% 安定的発展を保証する保険のようなもの
112/専業に徹する→全ての分野が独立経営体として成果をあげる
117/人を作る→人を得たいと思うのであれば、みずからしっかりとした使命感、経営理念を持つ
人を育てる→どんな小さな仕事でも経営的な感覚を持ってできる人を育てること。
仕事は思い切って任せること。
126/日頃から、みなの声を聞き、従業員が自由にモノを言いやすい空気を作る
127/できるだけ仕事を任せて部下の自主性を生かすようにすることも、衆智を生かす一つ
134/労働組合:対立と調和は、一つの自然の理法であり、社会のあるべき姿。
137/労使は車の両輪。同じ大きさでないとまっすぐ進まない。
139/経営は一つの芸術である。
147/経営は、生きた総合芸術である。という価値を認識し、それに値するよう努力すべき
150/立派な経営理念があっても、実際に適用していく方針、やり方にそぐわないものがある。
「日に新た」という、その時々のふさわしい方策、方針が必要。
158/今日の経営者は、自分の事業に懸命にとりくむと同時に、政治に強い関心を持ち、
適切な要望をよせていかねばならない。
170/同じ経営理念でも、具体的なやり方は無限。自分には、自分の持ち味にあった一番のやり方があるはず。
Posted by ブクログ
かなり昔の本ですが、今読んでも納得できることが多かった印象です。
経営についてももちろんですが、ほかの仕事の進め方についても参考になることもあるのではないかと思いました。
Posted by ブクログ
まあ良い本だと思う。
大事な心構えがいくつも記されている。
しかし、いまいち実感が湧かないし、
実際の仕事現場でどこまで徹することができるのか、
今のところまったく想像できない。
仕事に慣れてきた2~3年目に読むのが良さそう。
Posted by ブクログ
わずか三人で細々と始めた事業を、一代で世界的な企業にまで成長させた松下幸之助。その成功の要因を尋ねられたとき、松下は、「経営理念の大切さ」を説くことが多かった。本書は、松下が六十余年の事業体験を通じて培った、経営理念、経営哲学ともいうべきものの考え方を、二十項目にわたってまとめたものである。松下経営の真髄が説かれた、経営者必読の書である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
松下さんの本、これで4冊目になるのですけど、これが一番読みやすかったなぁ。
…薄さと文字量的に!笑
内容は「経営」と言われてイメージするものよりは、「気遣い」「善い考え方」とか、なんか説法に近い…というか観念的な事だと思った。
他の松下さんの本でも割と言ってたことが多かったので私としては物珍しい内容にはかんじなかったけど、むしろこれを一番最初によむべきだったか、というかんじ。
相手もやってける値引き……ってとこではっとさせられた。何かを安くして欲しいと思う時、相手がどうとか頭から抜け落ちて、とりあえず限界まで安くしてくれ!って思っちゃうけど、相手も経営していけるライン…でももしそれが適性価格に達してなかった場合達するよう協力して、値引きしてもらう…
そう最初から考えて経営してたとか凄すぎるよね。
あと、不景気でも売れるものは売れる!ってところで、そうだよなあと…
いま高い炊飯器が売れてるってよくやってるけど、不景気でもみんな欲しいものに対してお金使わないわけではないんだよね。そのお金が無い…ってわけでもいまの日本はない。
うーんすごいよねー
Posted by ブクログ
まず字がでかい。(笑)
非常に読みやすい。
書かれてあることを要訳すると「常に公正であれ」ということと理解しました。
響いた点は、企業は社会の公器であり、赤字を出すことは社会的にも許されない、ということ。
企業は利益を出して社会に還元してなんぼであり、赤字を出すような企業は社会的責任を果たしていない、
と述べられています。
ともすると赤字に対して同情的な視線を向けがち、あるいは自分らが赤字になると
同上してほしいという考えになりがちですが、黒字に比べて社会に何らの還元もなく、
存在悪とする視点は新鮮でした。
逆にいえば、利益は報酬であり、最近の日本における利益を忌み嫌う姿勢について、
やっぱりおかしいよな、と率直に感じた次第です。
利益追求のみに走る姿勢は正しくないと思いますが、
正しい行いをした結果として頂く報酬とそれに伴う利益は、やはり正しいのだな、と感じました。
また、仕入先に対しても、お客様に対しても、労働組合に対しても公正であれ、とのこと。
仕入先に単に値下げを要求するのではなく、相手の利益のことも考えて最善の策を考えたり、
お客様に言われるがままに値引きするのではなく、正当な対価を主張しないと過当競争になること、
労働組合を忌み嫌うのではなく、対立しつつも、車の両輪として互いに協調すること、
などが述べられており、徹底的なWIN-WIN思考なんだなぁ、と思いました。
2時間でさらりと読めますので、お暇なときにどうぞ。