無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
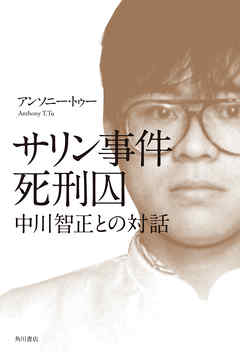
松本サリン事件・東京地下鉄サリン事件では日本の警察に協力し、事件解明のきっかけを作った世界的毒物学者。
彼は事件の中心人物で、2018年7月に死刑となった中川智正と15回に及ぶ面会を重ね、その事件の全容を明らかにした。
中川氏との約束に基づき、このたび緊急刊行。
第1章 サリン事件解決に協力する
第2章 オウムのテロへの道のり
第3章 中川死刑囚との面会
第4章 中川死刑囚の獄中での生活
第5章 オウムの生物兵器の責任者、遠藤誠一
第6章 オウムの化学兵器の中心人物、土谷正実
第7章 麻原の主治医、中川智正
第8章 3人の逃走犯
第9章 中川死刑囚が語るオウム信者の人物像
第10章 上九一色村とサリン被害者の現在
第11章 オウム事件から学ぶ、将来への備え
第12章 中川氏最後のアクティビティ
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。